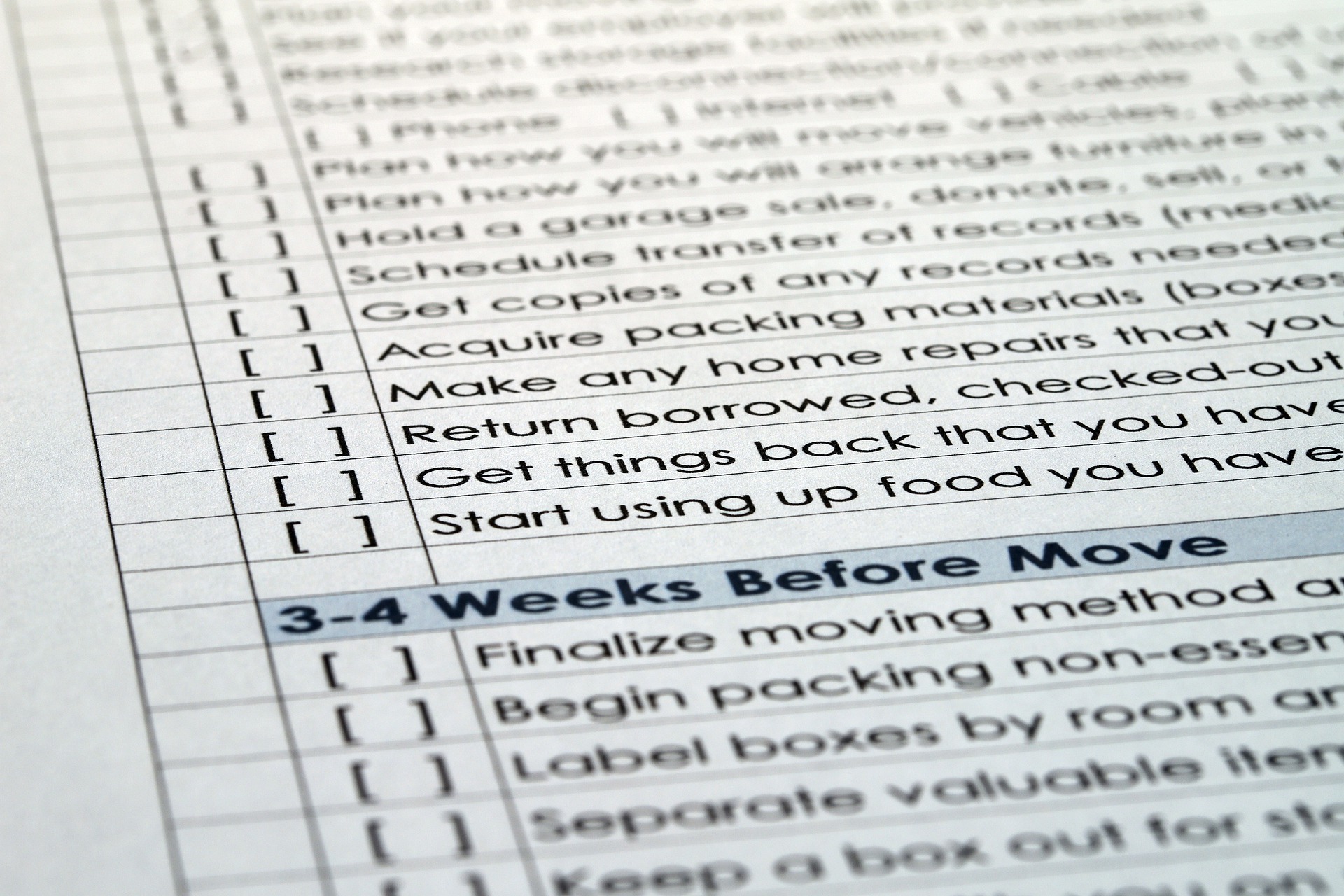今回は、犯罪収益移転防止法ということで、取引記録の記録事項について見てみたいと思います。
特定事業者は、特定業務に係る取引を行った場合、少額の取引などを除き、直ちに取引記録を作成し、7年間保存しなければならない(法7条)とされており、これを取引記録の作成・保存義務といいますが、その取引記録に何を記録するのか、という話です。
ではさっそく。なお、引用部分の太字、下線、改行などは管理人によるものです。
メモ
このカテゴリーでは、インハウスとしての法務経験からピックアップした、管理人の独学や経験の記録を綴っています。
ネット上の読み物としてざっくばらんに書いており、感覚的な理解を掴むことを目指していますが、書籍などを理解する際の一助になれば幸いです。
取引記録の記録事項(規則24条)
取引記録に何を記録するのか(=記録事項)は、規則24条各号に定められています。
▽犯収法規則24条
(取引記録等の記録事項)
第二十四条 法第七条第一項及び第二項に規定する主務省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。
一~九 (略)
記録事項は1号~9号までと数が多いですが、法7条1項で
顧客等の確認記録を検索するための事項、当該取引の期日及び内容その他の主務省令で定める事項
とされており、概ねそのようにグルーピングすることができます。
そうして、主な記録事項を簡略化して並べると、
- 確認記録を検索するための事項【1号】
- 取引の日付【2号】
- 取引の種類【3号】
- 取引の価額【4号】
- 財産の移転元・移転先の名義【5号】
のようになっています。(※6~9号は金融機関等プロパー)
以下、順に見てみます。
なお、特定事業者のうち士業者に関する部分については本記事では割愛します。また、条文中でも、その部分は薄くグレーアウトさせています
確認記録を検索するための事項(1号)
一 口座番号その他の顧客等の確認記録を検索するための事項(確認記録がない場合にあっては、氏名その他の顧客等又は取引若しくは特定受任行為の代理等を特定するに足りる事項)
「顧客等の確認記録を検索するための事項」というのは、先ほど見たように、法7条1項でも規定されている文言そのままです。
これは、取引記録等と本人確認記録が相互に連関して検索可能にするための措置を確保するためのものであり、データベースでいえばキーナンバーにあたります。具体的には、口座番号のほか、顧客管理番号等の本人確認記録を検索するための事項で足りる、とされています。
(「逐条解説 犯罪収益移転防止法」(犯罪収益移転防止制度研究会)232頁)
なお、括弧書きの「確認記録がない場合にあっては…」というのは、取引時確認義務はないが取引記録の作成・保存義務がある場合のための定めになります。
取引の日付(2号)
二 取引又は特定受任行為の代理等の日付
これは見たままで、取引の日付です。
取引の種類(3号)
三 取引又は特定受任行為の代理等の種類
これも見たままで、取引の種類です。
取引の価額(4号)
四 取引又は特定受任行為の代理等に係る財産の価額
これも見たままで、取引の価額です。
財産の移転元・移転先の名義(5号)
五 財産移転(令第十五条第一項第一号に規定する財産移転をいう。)を伴う取引又は特定受任行為の代理等にあっては、当該取引又は特定受任行為の代理等及び当該財産移転に係る移転元又は移転先(当該特定事業者が行う取引又は特定受任行為の代理等が当該財産移転に係る取引、行為又は手続の一部分である場合は、それを行った際に知り得た限度において最初の移転元又は最後の移転先をいう。以下この条において同じ。)の名義その他の当該財産移転に係る移転元又は移転先を特定するに足りる事項
5号は、財産移転を伴う取引において、
- 当該取引
- 財産の移転元又は移転先の名義(など、これらの者を特定するに足りる事項)
を記録事項として定めています。
「財産移転」とは、財産に係る権利の移転及び財産の占有の移転、と定義されています(施行令15条1項1号)
ただし、括弧書きで、特定事業者が行う取引が財産移転の一部分である場合(つまり、財産移転の一部にのみ関与する場合)は、特定事業者が知り得る限りで、最初の移転元又は最後の移転先の名義等を記録する、とされています。
平成20年パブコメで、例えば、株式取引においては、
- 取引所取引の場合には、金融商品取引清算機関が移転元又は移転先
- 取引所取引以外の取引の場合には、特定事業者が取引を行った相手方である他の事業者等が移転元又は移転先
となる、とされています。
▽平成20年1月30日パブコメ(13頁)別紙1の2(8)|掲載ページはこちら
意見の概要 規則第14条第5号では、取引記録の記録事項として「財産移転・・・を伴う取引又は特定受任行為の代理等にあっては、当該取引又は特定受任行為の代理等及び当該財産移転に係る移転元又は移転先(当該特定事業者が行うのが当該財産移転に係る取引、行為又は手続の一部分である場合は、それを行った際に知り得た限度において最初の移転元又は最後の移転先をいう。以下同じ。)」に係る事項が規定されているが、取引所金融市場等において行われる取引につ いては、移転元又は移転先を記録することは実質的に不可能であると思われる。
意見に対する考え方 規則第14条第5号は、特定事業者が財産移転を伴う取引等を行った際に、当該財産移転に係る移転元又は移転先の名義その他の当該財産移転に係る移転元又は移転先等を特定するに足りる事項を記録することを求めています。
したがって、例えば、株式売買において、 取引所取引の場合には金融商品取引清算機関が移転元又は移転先となり、取引所取引以外の取引の場合には特定事業者が取引を行った相手方である他の事業者等がこれに該当するものと考えられます。
▽平成20年1月30日パブコメ(42頁)別紙2の2(13)ア|掲載ページはこちら
質問の概要 規則第14条第5号に規定する「当該財産移転に係る移転元又は移転先・・・の名義その他の当該財産移転に係る移転元又は移転先を特定するに足りる事項」とは、例えば、顧客が本人の送金指示に基いてA銀行から証券会社に有価証券の買付け代金などを送金する場合、送金を受ける証券会社は、当該顧客から送金されたことを記録すればよいのか。
質問に対する考え方 当該顧客から送金を受けたことを記録すれば足りるものと考えます。
特定金融機関の国内送金の送金人情報を検索するに足る事項(6号)
六 前各号に掲げるもののほか、顧客との間で行う為替取引(本邦から外国へ向けた支払又は外国から本邦へ向けた支払に係るものを除く。)が当該取引を行う特定金融機関と移転元又は移転先に係る特定金融機関(以下この号において「他の特定金融機関」という。)との間の資金決済を伴うものであり、かつ、当該取引に係る情報の授受が当該取引を行う顧客に係る特定金融機関と当該他の特定金融機関との間において電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法をいう。)により行われる場合には、次のイ又はロに掲げる区分に応じ、それぞれ当該イ又はロに定めることを行うに足りる事項
イ 他の特定金融機関への資金の支払を伴う取引である場合 他の特定金融機関から当該他の特定金融機関に保存されている取引記録等に基づき当該取引について次の⑴又は⑵に掲げる確認を求められたときに、それぞれ当該⑴又は⑵に定めること。
⑴ 顧客の確認 求められた日から三営業日以内に当該取引を特定して当該顧客の確認記録を検索すること(確認記録がない場合にあっては、求められた日から三営業日以内に当該取引及び氏名又は名称その他の当該顧客に関する事項を特定すること。)。
⑵ 顧客の支払の相手方の確認 求められた日から三営業日以内に当該取引及び氏名又は名称その他の当該相手方に関する事項を特定すること。
ロ 他の特定金融機関からの資金の受取を伴う取引である場合 他の特定金融機関との間で授受される当該取引に係る情報を検索すること。
特定金融機関の間の国内送金においては、送金先金融機関の依頼に応じて、送金元金融機関が3営業日内に情報をトレースできる態勢をとるべきことを規定しています。
▽平成20年1月30日パブリックコメント(43頁)別紙2の2(13)イ|掲載ページはこちら
質問の概要 規則第14条第6号イについて、「求められた日から3営業日以内に当該取引を特定して当該顧客の本人確認記録を検索すること」 を行うに足りる事項の記録が求められているが、3営業日以内に行うのは検索のみで、 他の特定事業者への通知は各特定事業者の判断によるという理解でよいか。
質問に対する考え方 規則第14条第6号イは、他の特定事業者から顧客について確認を求められている場合を想定した規定であり、求められた日から3営業日以内に検索し、その求めに応じることが必要と考えます。
国際送金の送金人情報(7号)
七 第一号から第五号までに掲げるもののほか、次のイからハまでに掲げる場合においては、当該イからハまでに定める事項
イ 特定金融機関が法第十条第一項の規定により他の特定金融機関又は外国所在為替取引業者(同項に規定する外国所在為替取引業者をいう。以下この号において同じ。)に通知する場合 当該通知をした事項
ロ 特定金融機関が外国所在為替取引業者から法第十条の規定に相当する外国の法令の規定による通知を受けて外国から本邦へ向けた支払の委託又は再委託を受けた場合であって、当該支払を他の特定金融機関又は外国所在為替取引業者に再委託しないとき 当該通知を受けた事項
ハ 特定金融機関が他の特定金融機関から法第十条第三項又は第四項の規定による通知を受けて外国から本邦へ向けた支払の委託又は再委託を受けた場合であって、当該支払を他の特定金融機関又は外国所在為替取引業者に再委託しないとき 当該通知を受けた事項
国際送金の送金人情報を、記録事項として規定しています。
▽平成20年1月30日パブリックコメント(43頁)別紙2の2(13)ウ|掲載ページはこちら
質問の概要 規則第14条第7号では、法第10条の外国為替取引に係る通知義務について、仕向金融機関については通知した事項を、被仕向金融機関については通知を受けた事項を取引記録として記録することとしているが、 SWIFTの原文を保存することで足りるのか。
質問に対する考え方 御指摘のとおり、仕向金融機関については通知した事項を、被仕向金融機関については通知を受けた事項を取引記録として記録することとしており、SWIFTの原文を保存することで十分です。
なお、中継金融機関については、システ ムの技術的制約により通知を受けた事項を再委託先に完全に通知できなかった場合には、通知ができなかった事項については保存の必要があります。
8号の記録事項はいわゆるステーブルコインなどに関係する特定事業者(電子決済手段等取引業者、電子決済等取扱業者)に関するもの、9号の記録事項は暗号資産交換業者に関するものですが、本記事では割愛します。
結び
今回は、犯罪収益移転防止法ということで、取引記録の記録事項について見てみました。
[注記]
本記事を含む一連の勉強記事は、過去の自分に向けて、①自分の独学や経験の記録を見せる、②感覚的な理解を伝えることを優先する、③細かく正確な理解は書物に譲る、ということをコンセプトにした読みものです。ベテランの方が見てなるほどと思うようなことは書かれていないほか、業務上必要であるときなど、正確な内容については別途ご確認ください。また、法改正をはじめとした最新の情報を反映しているとは限りませんので、ご注意ください。
犯罪収益移転防止法に関するその他の記事(≫Read More)
主要法令等
主要法令等
- 犯罪収益移転防止法(「犯罪による収益の移転防止に関する法律」)
- 施行令(「犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令」)
- 施行規則(「犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則」)
- 改正事項に関する資料|JAFICホームページ
- 過去に実施したパブリックコメントの結果|JAFICホームページ
参考資料
- 犯罪収益移転防止法の概要(JAFIC)|JAFICホームページ
業界別資料
- 犯罪収益移転防止法に関するよくある質問・回答|全国銀行協会HP
- 犯罪による収益の移転防止に関する法律及び同政省令に関するQ&A|日本証券業協会HP
参考文献
※注:上記は「全訂版」の旧版
当サイトではアフィリエイトプログラムを利用して商品・サービスを記載しています