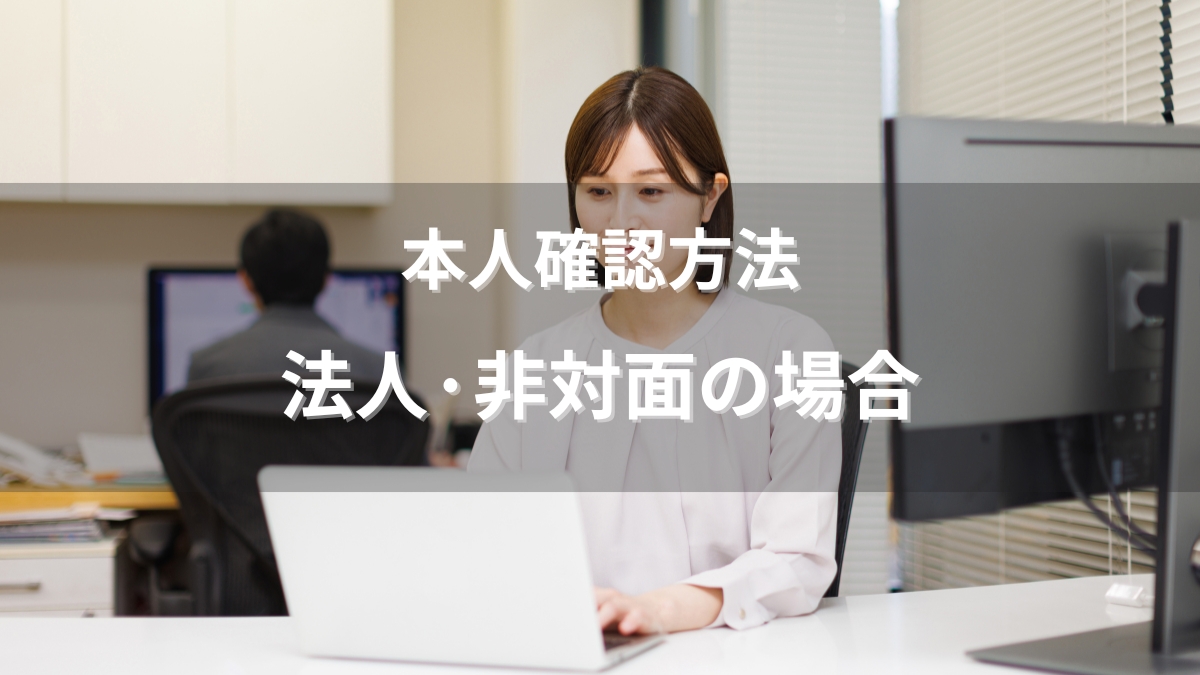今回は、犯罪収益移転防止法ということで、確認記録の作成・保存について見てみたいと思います。
ではさっそく。なお、引用部分の太字、下線、改行などは管理人によるものです。
メモ
このカテゴリーでは、インハウスとしての法務経験からピックアップした、管理人の独学や経験の記録を綴っています。
ネット上の読み物としてざっくばらんに書いており、感覚的な理解を掴むことを目指していますが、書籍などを理解する際の一助になれば幸いです。
確認記録の作成・保存(法6条)
特定事業者は、取引時確認を行った場合には、確認記録を作成し、7年間保存しなければなりません。
これを確認記録の作成・保存義務といい、法6条に定められています。
▽法6条
(確認記録の作成義務等)
第六条 特定事業者は、取引時確認を行った場合には、直ちに、主務省令で定める方法により、当該取引時確認に係る事項、当該取引時確認のためにとった措置その他の主務省令で定める事項に関する記録(以下「確認記録」という。)を作成しなければならない。
2 特定事業者は、確認記録を、特定取引等に係る契約が終了した日その他の主務省令で定める日から、七年間保存しなければならない。
1項は、確認記録の作成について定めており、内容は、
| 項目 | 内容(条文の文言) | 主務省令 |
|---|---|---|
| 作成のタイミング | (確認後)「直ちに」 | |
| 作成方法 | 「主務省令で定める方法により」 | 規則19条 |
| 記録事項 | 「主務省令で定める事項」 例示①:「取引時確認に係る事項」 例示②:「取引時確認のためにとった措置」 | 規則20条 |
のようになっています。
2項は、確認記録の保存について定めており、内容は、
| 項目 | 内容(条文の文言) | 主務省令 |
|---|---|---|
| 起算点 | 「主務省令で定める日」 例示:「特定取引等に係る契約が終了した日」 | 規則21条 |
| 保存の期間 | 「7年間」 |
のようになっています。
上記のように、具体的なところは主務省令つまり犯収法施行規則に定められているので、規則を見ていくことになります。
作成方法(規則19条)
作成方法は、規則19条に定められています。
▽規則19条1項
(確認記録の作成方法)
第十九条 法第六条第一項に規定する主務省令で定める方法は、次の各号に掲げる方法とする。
一~二 (略)
「次の各号に掲げる方法」として1号と2号が定められていますので、順に見てみます。
記録媒体(1項1号)
1号は、確認記録の作成方法として、記録媒体(メディア)について定めています。
▽規則19条1項1号
一 確認記録を文書、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)又はマイクロフィルムを用いて作成する方法
内容を整理すると、
- 文書
- 電磁的記録
- 電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、
- 電子計算機による情報処理の用に供されるもの
- マイクロフィルム
のどれかとなっています。
添付資料の添付(1項2号)
2号は、確認記録の作成方法として、添付資料の添付について定めています。
▽規則19条1項2号
二 次のイからカまでに掲げる場合に応じ、それぞれ当該イからカまでに定めるもの(以下「添付資料」という。)を文書、電磁的記録又はマイクロフィルム(チに掲げる場合にあっては、電磁的記録に限る。)を用いて確認記録に添付する方法
書かれているように、添付資料の媒体(メディア)も、文書、電磁的記録またはマイクロフィルムになっています
添付資料の種類
添付資料の種類については、2号のイ~カに定められています。
ざっくりと確認方法の種類ごとに整理すると、以下のようになっています。
確認方法の種類に応じた添付書類
| 個人or法人 | 確認方法の種類に応じた場面 | 添付資料の種類 |
|---|---|---|
| 共通 | 本人確認書類または補完書類の送付を受けたとき(写しも含む) | 当該本人確認書類または補完書類(またはその写し) |
| 個人 | 本人確認用画像情報の送信を受けたとき | 当該本人確認用画像情報(またはその写し) |
| 個人 | ICチップ情報の送信を受けたとき | 当該ICチップ情報(またはその写し) |
| 共通 | 電子署名法、公的個人認証法、商業登記法の規定により電子署名が行われた特定取引等に関する情報の送信を受けたとき | 当該方法により本人特定事項の確認を行ったことを証明するに足りる電磁的記録 |
| 法人 | インターネット登記情報提供サービスから登記情報の送信を受けたとき | 当該登記情報(またはその写し) |
| 法人 | 国税庁の法人番号公表サイトの公表事項を確認したとき | 当該公表事項(またはその写し) |
該当するものは、すべて添付する必要があります。
管理人的にかみ砕いていうと、ほとんどが「~を受けたとき」となっているように、本人確認のための書類や情報などを受け取ったり取得したときに、それを確認記録に添付しておきなさいということです
添付方法
添付資料の添付方法については、以下のパブコメに解説があります。
紙媒体以外の場合は、物理的に添え付けられている場合と同様に、情報が検索できる状態になっている必要があるとされています。
▽平成20年1月30日パブコメ別紙2の2⑶ア|掲載ページはこちら
質問の概要
○ 本人確認記録に添付することとされている本人確認書類又はその写しについて、どのような措置が「添付」しているものと認められるのか。例えば、本人確認記録を電磁的記録で保存し、本人確認書類等を紙で保存したり画像ファイル等の電磁的記録で保存しておくことは可能か。
質問に対する考え方
「添付」とは、本人確認記録に本人確認書類の写しが物理的に添え付けられている場合のほか、コンピュータシステム等により、物理的に添え付けられている場合と同様に、直ちに本人確認書類の写しに関する情報が検索できる状態になっている場合が考えられます。
確認記録の一部とみなす(2項)
これらの添付方法によって正しく添付された添付資料は、確認記録の一部とみなされます(規則19条2項)。
▽規則19条2項
2 前項第二号に掲げる方法において確認記録に添付した添付資料は、当該確認記録の一部とみなす。
様式
確認記録の様式には、特に制限はないとされています。
▽平成20年1月30日パブコメ(41頁)別紙2の2(10)カ|掲載ページはこちら
質問の概要 本人確認記録について、様式や書式等はあるのか。
質問に対する考え方 本人確認記録については規則第10条に定める事項が記録されていれば足り、様式や書式等は特にありません。
(※)管理人注:規則10条は現在は規則20条
参考様式は、JAFICの「犯罪収益移転防止法の概要」(13-別表8)に掲載されています。
このほか、特定事業者の分野ごとの所管官庁や、業界団体の資料にも参考様式が載っていることがありますので、それらも参考になります。
記録事項(規則20条)
記録事項の種類(1項)
確認記録に何を記録するのか(=記録事項)は、規則20条1項に定められています。
1号~30号まであり、数が多いですが、法6条1項で
当該取引時確認に係る事項、当該取引時確認のためにとった措置その他の主務省令で定める事項に関する記録(以下「確認記録」という。)
とされているとおり、概ね、
- 確認事項等
- 確認のためにとった措置等
- 確認のために措置をとった日付等
- その他
のようにグルーピングをすることができます。
確認記録の記録事項については、以下の関連記事にくわしく書いています。
-
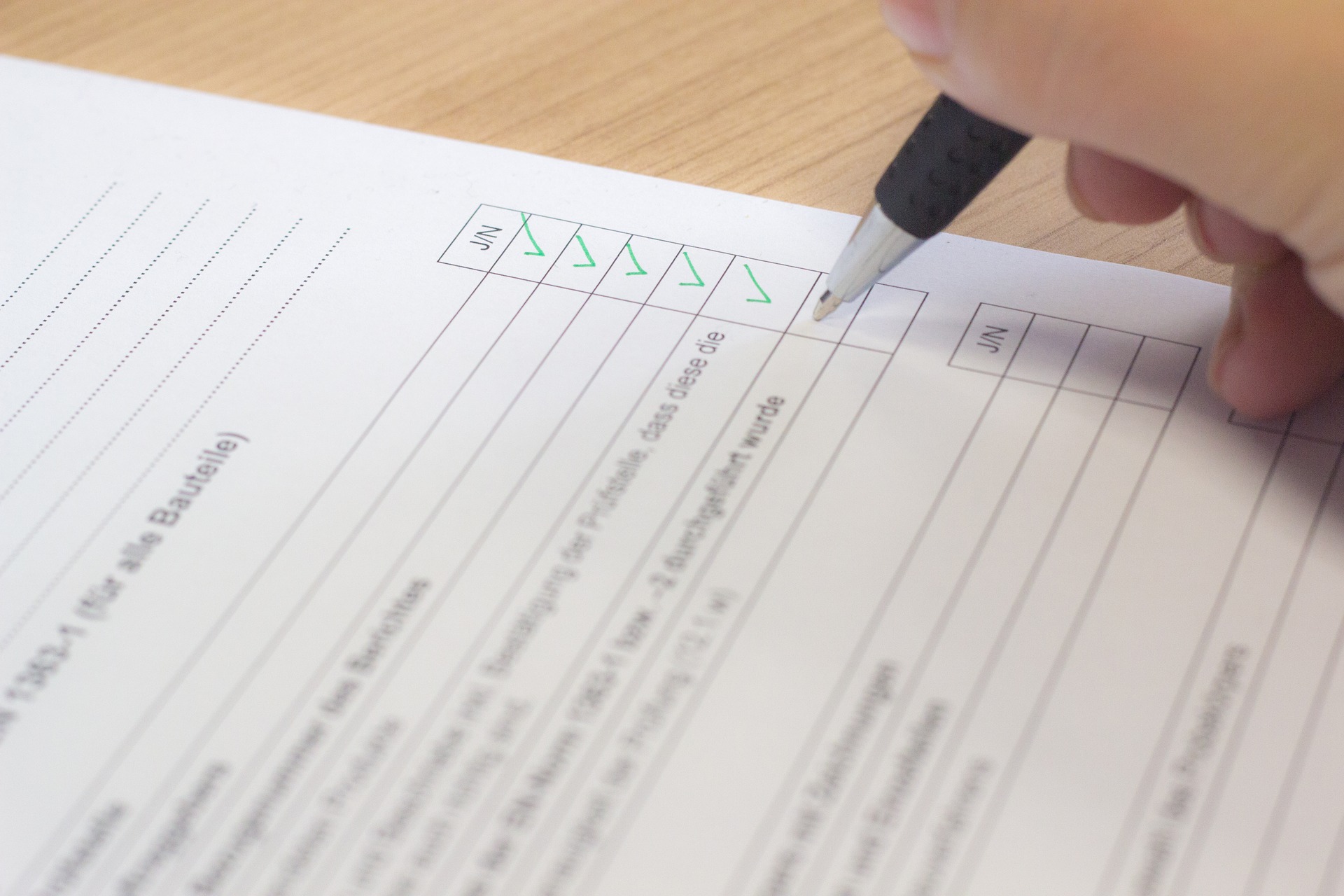
-
犯罪収益移転防止法|確認記録の記録事項
続きを見る
記録事項の省略(2項)
添付資料を添付した場合、添付資料に記載がある事項については、確認記録への記録を省略することができます(規則20条2項)。
▽規則20条2項
2 特定事業者は、添付資料を確認記録に添付するとき又は前項第三号の規定により本人確認書類若しくは補完書類の写しを確認記録に添付するときは、同項各号に掲げるもののうち当該添付資料又は当該本人確認書類若しくは補完書類の写しに記載がある事項については、同項の規定にかかわらず、確認記録に記録しないことができる。
ちなみに、「前項第三号の規定により…確認記録に添付するとき」という部分は、対面での「提示のみ法」による本人確認書類の提示を受けたときに、その写しを確認記録に添付した場合のことです。
この場合、7年間の保存を条件に、本人確認書類の提示を受けた時刻の記載も省略することができます(20条1項3号括弧書き参照)。
記録事項の変更等(3項)
確認記録の記録事項に変更や追加があることを知った場合には、その変更・追加事項を確認記録に付記する必要があります。
その際、既に確認記録に記載されている内容を消去してはならないことになっています(消去の禁止)。
確認記録に付記する代わりに、変更・追加事項についての記録を別途作成してもよいとされています(ただし、確認記録と共に保存する必要あり)。
▽規則20条3項
3 特定事業者は、第一項第二十号から第二十四号まで及び第二十六号から第二十九号までに掲げる事項に変更又は追加があることを知った場合は、当該変更又は追加に係る内容を確認記録に付記するものとし、既に確認記録又は同項第三号の規定により添付した本人確認書類若しくは補完書類の写し若しくは添付資料に記録され、又は記載されている内容(過去に行われた当該変更又は追加に係る内容を除く。)を消去してはならない。この場合において、特定事業者は、確認記録に付記することに代えて、変更又は追加に係る内容の記録を別途作成し、当該記録を確認記録と共に保存することとすることができる。
「第一項第二十号から第二十四号まで及び第二十六号から第二十九号までに掲げる事項」という部分は、先ほどあった1号~30号の記録事項のうち、確認事項等に関連するものです。
保存期間の起算点(規則21条)
確認記録の保存期間は、冒頭で見たとおり7年間です(法6条2項)。
▽法6条2項
2 特定事業者は、確認記録を、特定取引等に係る契約が終了した日その他の主務省令で定める日から、七年間保存しなければならない。
起算点は「主務省令で定める日」で、規則21条に定められています。
▽規則21条1項・2項
(確認記録の保存期間の起算日)
第二十一条 法第六条第二項に規定する主務省令で定める日は、取引終了日及び取引時確認済みの取引に係る取引終了日のうち後に到来する日とする。
2 前項に規定する「取引終了日」とは、次の各号に掲げる確認記録を作成した特定取引等の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日とする。
一 令第七条第一項第一号イからヘまで、チからヌまで、ル(媒介又は代理を行うことを内容とする契約を除く。)、ワ(代理又は媒介を除く。)、カ(媒介を除く。)、ヨ、タ、ツ、ナ、ム、ヰ、オ若しくはコからサまでに掲げる取引、同項第二号、第三号、第四号イ若しくはロ、第六号若しくは第七号に定める取引又は令第九条に規定する取引 当該取引に係る契約が終了した日
二 前号に掲げる取引以外の取引 当該取引が行われた日
つまり、起算点は、取引終了日または取引時確認済みの取引に係る取引終了日のうち、後に到来する日とされています(1項)。
「取引終了日」の内容は、取引の類型により異なっています(2項)。
取引時確認済みの取引に係る取引終了日
「取引時確認済みの取引に係る取引終了日」が何を指すのかは、3項に定められています。
▽規則21項3項(※【 】は管理人注)
3 第一項に規定する「取引時確認済みの取引に係る取引終了日」とは、法第四条第三項の規定により同条第一項の規定を適用しないこととされる取引【=既に確認を行っている顧客等との取引】があった場合において、前項の規定中「確認記録を作成した特定取引等」とあるのを「取引時確認済みの顧客等との特定取引等」と読み替えて同項の規定を適用したときにおける同項に定める日とする。
指示にしたがって読み替えると、こうなります。
▽規則21項2項を読替え
2 前項に規定する「取引終了日」とは、次の各号に掲げる確認記録を作成した特定取引等取引時確認済みの顧客等との特定取引等の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日とする。
一~二 (略)
つまり、既に確認を行っている顧客等との取引については一定の要件の下で取引時確認を省略できることになっていますが(法4条3項)、そのように取引時確認を省略した取引があるときは、その省略にかかる取引の終了日が起算点になるということです(つまり、起算点が後ろにずれて、保存期間が延長される)。
既に確認を行っている顧客等との取引をするときに取引時確認を省略すると、起算点が更新されるようなイメージです
結び
今回は、犯罪収益移転防止法ということで、確認記録の作成・保存について見てみました。
[注記]
本記事を含む一連の勉強記事は、過去の自分に向けて、①自分の独学や経験の記録を見せる、②感覚的な理解を伝えることを優先する、③細かく正確な理解は書物に譲る、ということをコンセプトにした読みものです。ベテランの方が見てなるほどと思うようなことは書かれていないほか、業務上必要であるときなど、正確な内容については別途ご確認ください。また、法改正をはじめとした最新の情報を反映しているとは限りませんので、ご注意ください。
犯罪収益移転防止法に関するその他の記事(≫Read More)
主要法令等
主要法令等
- 犯罪収益移転防止法(「犯罪による収益の移転防止に関する法律」)
- 施行令(「犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令」)
- 施行規則(「犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則」)
- 改正事項に関する資料|JAFICホームページ
- 過去に実施したパブリックコメントの結果|JAFICホームページ
参考資料
- 犯罪収益移転防止法の概要(JAFIC)|JAFICホームページ
業界別資料
- 犯罪収益移転防止法に関するよくある質問・回答|全国銀行協会HP
- 犯罪による収益の移転防止に関する法律及び同政省令に関するQ&A|日本証券業協会HP
参考文献
参考文献
※注:上記は「全訂版」の旧版
当サイトではアフィリエイトプログラムを利用して商品・サービスを記載しています