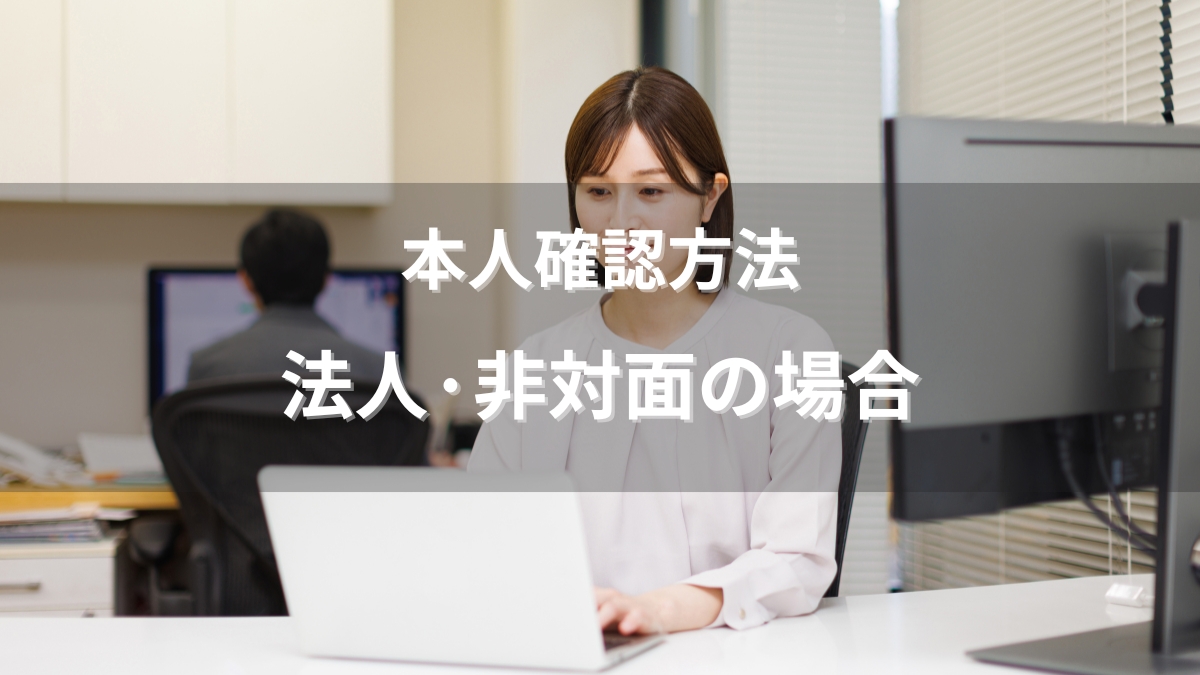今回は、犯罪収益移転防止法ということで、法人の本人確認方法のうち非対面の場合について見てみたいと思います。
ではさっそく。なお、引用部分の太字や下線などは管理人によるものです。
メモ
このカテゴリーでは、インハウスとしての法務経験からピックアップした、管理人の独学や経験の記録を綴っています。
ネット上の読み物としてざっくばらんに書いており、感覚的な理解を掴むことを目指していますが、書籍などを理解する際の一助になれば幸いです。
法人の本人確認方法(非対面の場合)-規則6条1項3号
法人の本人確認方法(非対面の場合)は、最初に全体をざっと見ておくと、以下のようになっています。
法人・非対面(全体像)
| 本人確認方法 | 確認ソース | 申告 | 条文 |
| ①申告+確認法 | 登記情報(登記情報提供サービスから)の確認のみ | 代表者からの申告 | 規則6条1項3号ロ |
| ②申告+確認+送付法 | 登記情報(登記情報提供サービスから)の確認 | 代表者以外の者からの申告 | 同号ロ括弧書き |
| 公表事項(国税庁法人番号公表サイトから)の確認 | 代表者/代表者以外の者からの申告 | 同号ハ括弧書き | |
| ③受理+送付法 | 同号ニ | ||
| ④電子署名法に基づく電子証明書を用いる方法 | 同号ホ | ||
以下、順に見てみます。
01|申告+確認法(3号ロ)
これは、法人の代表者から非対面で申告を受け、かつ、一般財団法人民事法務協会が運営しているインターネット登記情報提供サービスから登記情報の送信を受ける、という方法です。
「申告+確認法」は、対面の場合には一般的に認められていますが(▷こちらの記事を参照)、非対面の場合に「申告+確認法」が使えるのは、
- 「申告」は、法人の代表者として登記されている者からの申告で、
かつ - 「確認」は、インターネット登記情報による確認(⇔法人番号サイトの公表事項ではダメ)
による場合に限られます。
法人の代表者として登記されている者からの申告
条文を確認してみます。規則6条1項3号ロです。
本文に「申告+確認法」が、括弧書きに「申告+確認+送付法」が書かれています。
読みにくいですが、括弧書きの括弧書きで、”代表役員として登記されていない者に限られる”とされていて(赤字の部分)、登記されている代表者は括弧書きに入ってこないようになっているので、つまりは本文で規定されるようになっています。
(⇒申告と登記情報の確認によって本人確認できる)
▽犯収法規則6条1項3号ロ
ロ 当該法人の代表者等から当該顧客等の名称及び本店又は主たる事務所の所在地の申告を受け、かつ、電気通信回線による登記情報の提供に関する法律(平成十一年法律第二百二十六号)第三条第二項に規定する指定法人から登記情報(同法第二条第一項に規定する登記情報をいう。以下同じ。)の送信を受ける方法⏎改行
(当該法人の代表者等(当該顧客等を代表する権限を有する役員として登記されていない法人の代表者等に限る。)と対面しないで当該申告を受けるときは、当該方法に加え、当該顧客等の本店等に宛てて、取引関係文書を書留郵便等により、転送不要郵便物等として送付する方法)
なので、くり返しになりますが、非対面で「申告+確認法」が使えるのは、法人の代表者として登記されている者から申告を受ける場合のみです。
▽平成30年11月30日パブコメNo.107|JAFICホームページ(≫掲載ページ)
質問の概要 代表者等が当該法人を代表する権限を有する役員の場合、当該法人の本店等に宛てた取引関係文書の郵送は不要であるという理解でよいか(ロ関係)。
質問に対する考え方 そのとおりです。
登記情報提供サービスの登記情報による確認
また、確認ソースは、登記情報提供サービスの登記情報により確認する場合(3号ロ)のみであって、国税庁の法人番号サイトの公表事項により確認する場合(3号ハ)には認められていません。
ハの括弧書きには、ロの括弧書きと違って、括弧書きの括弧書き=上記の赤字の部分、がありません
法人番号サイトでは、登記情報と異なり、法人の役員を確認できないからです。
▽上記パブコメNo.109
質問の概要 「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第三十九条第四項の規定により公表されている当該顧客等の名称及び本店又は主たる事務所の所在地を確認し」とは、国税庁により公表されている法人の名称と所在地を確認することと理解しているが、 このハの場合は、ロの登記情報の送信を受ける場合と異なり、転送不要郵便等の送付が本人特定事項の確認方法の要件となっている。しかし、ハにおいてもロと同様に法人の本人特定事項の確認をオンライン完結することが可能と思われるため、転送不要郵便の送付要件を外すことは可能ではないか。
また、取扱いに差異を設けようとする趣旨を説明されたい(ハ関係)。
質問に対する考え方 法人番号公表サイトは、法人の役員を確認できないことから、転送不要郵便物の送付が要件として課されている一方で、登記情報提供サービスは、法人の役員も確認できることから、代表権を保有する役員については転送不要郵便を不要としたものです。
その他補足
なお、法人に関する本人確認が上記の方法で完了するとしても、代表者に関する本人確認は当然ながら別途必要になります。
(「代表者等」についての本人確認。法4条4項)
▽上記パブコメNo.114
質問の概要 法人の代表者等から法人の本人特定事項の申告を受け、一般財団法人民事法務協会から登記情報の送信を受ける方法について、代表者等が法人を代表する権限を有する役員として登記されている場合には、法人に対する本人特定事項の確認は完了(本人確認書類の提示及び取引関係文書の送付)したと考えて相違ないか。また、上記の場合であっても、代表者等に対する本人特定事項の確認は上記とは別に必要という理解でよいか(ロ関係)。
質問に対する考え方 そのとおりです。
また、法人の取引時確認事項のうち、「本人特定事項」以外の「事業の内容」についても、登記情報により確認可能とされています。
(「事業の内容」の確認方法を定める規則10条1項2号のうち、ハに該当)
▽上記パブコメNo.113
質問の概要 一般財団法人民事法務協会から登記情報の送信を受け本人特定事項の確認とする場合、当該情報に記載のある事業内容の確認をもって規則第10条1項2号ハに定める事業内容の確認とみなす理解でよいか(ロ関係)。
質問に対する考え方 そのとおりです。
02|申告+確認+送付法(3号ロ括弧書き・ハ括弧書き)
これは、
法人の代表者等から、非対面で申告を受け、
かつ、
- 一般財団法人民事法務協会が運営しているインターネット登記情報提供サービスから登記情報の送信を受け(3号ロ)
又は - 国税庁法人番号公表サイトで公表されている情報を確認し(3号ハ)
かつ、
本店等に宛てて、取引関係文書を転送不要郵便物等として送付する方法
のことです。
非対面の場合は、基本的に括弧書きに書かれています。
(※ただし、前述のとおり、非対面でも、登記されている代表者からの申告で登記情報により確認するときは、括弧書きの括弧書きで除外されているから、本文に戻る)
以下、登記情報/公表事項の確認と、送付について、どのようなものか簡単に見てみます。
確認について
登記情報の確認(3号ロ括弧書き)
法律系のお仕事をしているとお馴染みですが、インターネット登記情報提供サービスを使って登記情報を確認する方法です。
なお犯収法と直接関係ない余談になりますが、登記情報提供サービスの登記情報は、登記事項証明書と違って証明書としての機能は持たないとされています(▷参考リンク:そのQ&Aはこちら)。あくまでもインターネットで登記情報を閲覧しているだけ、という建付けの制度です。
▽登記情報提供サービスについてはこちら
-
-
登記情報提供サービス
www1.touki.or.jp
条文を見てみます。指定法人から登記情報の送信を受ける、という部分です。
▽犯収法規則6条1項3号ロ括弧書き
ロ 当該法人の代表者等から当該顧客等の名称及び本店又は主たる事務所の所在地の申告を受け、かつ、電気通信回線による登記情報の提供に関する法律(平成十一年法律第二百二十六号)第三条第二項に規定する指定法人から登記情報(同法第二条第一項に規定する登記情報をいう。以下同じ。)の送信を受ける方法⏎改行
(当該法人の代表者等(当該顧客等を代表する権限を有する役員として登記されていない法人の代表者等に限る。)と対面しないで当該申告を受けるときは、当該方法に加え、当該顧客等の本店等に宛てて、取引関係文書を書留郵便等により、転送不要郵便物等として送付する方法)
確認した登記情報は、確認記録への添付も必要です(規則19条1項2号)。
▽犯収法規則19条1項2号ヌ
二 次のイからカまでに掲げる場合に応じ、それぞれ当該イからカまでに定めるもの(以下「添付資料」という。)を文書、電磁的記録又はマイクロフィルム(チに掲げる場合にあっては、電磁的記録に限る。)を用いて確認記録に添付する方法
ヌ 第六条第一項第三号ロに掲げる方法により本人特定事項の確認を行ったとき 当該登記情報又はその写し
公表事項の確認(3号ハ括弧書き)
こちらもお馴染みという感じですが、国税庁の法人番号サイトを利用する方法です。
▽国税庁法人番号公表サイトについてはこちら
-
-
国税庁法人番号公表サイト
www.houjin-bangou.nta.go.jp
条文を確認してみます。公表事項を確認する、という部分です。
▽犯収法規則6条1項3号ハ括弧書き
ハ 当該法人の代表者等から当該顧客等の名称及び本店又は主たる事務所の所在地の申告を受けるとともに、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第三十九条第四項の規定により公表されている当該顧客等の名称及び本店又は主たる事務所の所在地(以下「公表事項」という。)を確認する方法⏎改行
(当該法人の代表者等と対面しないで当該申告を受けるときは、当該方法に加え、当該顧客等の本店等に宛てて、取引関係文書を書留郵便等により、転送不要郵便物等として送付する方法)
確認した公表事項は、確認記録への添付も必要です(規則19条1項2号)。
▽犯収法規則19条1項2号ル
二 次のイからカまでに掲げる場合に応じ、それぞれ当該イからカまでに定めるもの(以下「添付資料」という。)を文書、電磁的記録又はマイクロフィルム(チに掲げる場合にあっては、電磁的記録に限る。)を用いて確認記録に添付する方法
ル 第六条第一項第三号ハに掲げる方法により本人特定事項の確認を行ったとき 当該公表事項又はその写し
送付について
送付とは、条文に書かれているとおり、顧客等の本店等に宛てて、取引関係文書を書留郵便等により、転送不要郵便物等として送付することです。
「取引関係文書」とは、顧客等との取引に係る文書のことで(規則6条1項1号ロ参照)、規則上は預金通帳が例示されています。預金通帳のように、通常、他の者への到達が期待されないものが想定されており、ほかには例えば、支払明細書、契約書などが考えられています。
▽平成20年1月30日パブコメ別紙2-2-⑶-ウ|JAFICホームページ(≫掲載ページ)
質問の概要 非対面取引の場合、書留郵便等で「取引関係文書」を送付することが必要となるが、「取引関係文書」には支払明細書等も含まれるのか。
質問に対する考え方 そのとおりです。
送付先は営業所宛ても可能(規則6条3項)
取引関係文書の送付先は、営業所宛ても可能とされています。
(ただし、当該営業所の記載を本人確認書類or補完書類で確認する必要あり)
条文を確認してみます。
括弧書きで、”ロとハにおいては括弧書きに規定する方法に限る”とされているので、括弧書きのケース、つまり「申告+確認+送付法」のことだと確認できます。
▽犯収法規則6条3項
3 特定事業者は、第一項第三号ロからニまでに掲げる方法(ロ及びハに掲げる場合にあっては、括弧書に規定する方法に限る。)により本人特定事項の確認を行う場合においては、当該顧客等の本店等に代えて、当該顧客等の代表者等から、当該顧客等の営業所であると認められる場所の記載がある当該顧客等の本人確認書類若しくは補完書類の提示を受け、又は当該本人確認書類若しくはその写し若しくは当該補完書類若しくはその写しの送付を受けるとともに、当該場所に宛てて取引関係文書を送付することができる。
送付に代えた交付法(規則6条4項)
「送付」の変形バージョンとして、「送付に代えた交付」というのもあります。
文字どおり、送付の部分の代わりに、訪問して交付するということです。
条文を確認してみます。
ここも、さっきの部分と書き方は同じで、括弧書きで”ロとハにおいては括弧書きに規定する方法に限る”とされているので、つまり「申告+確認+送付法」のケースのことだと確認できます。
▽犯収法規則6条4項
4 特定事業者は、第一項第一号ロ若しくはチからヌまで又は第三号ロからニまでに掲げる方法(ロ及びハに掲げる場合にあっては、括弧書に規定する方法に限る。)により本人特定事項の確認を行う場合においては、取引関係文書を書留郵便等により転送不要郵便物等として送付することに代えて、次の各号に掲げる方法のいずれかによることができる。
一 当該特定事業者の役職員が、当該本人確認書類若しくはその写しに記載され、当該登記情報に記録され、又は行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第三十九条第四項の規定により公表されている当該顧客等の住居又は本店等に赴いて当該顧客等(法人である場合にあっては、その代表者等)に取引関係文書を交付する方法(次号に規定する場合を除く。)
二 当該特定事業者の役職員が、当該顧客等の本人確認書類若しくは補完書類又はその写しに記載されている当該顧客等の住居又は本店等に赴いて当該顧客等(法人である場合にあっては、その代表者等)に取引関係文書を交付する方法(当該本人確認書類若しくは補完書類又はその写しを用いて第二項の規定により当該顧客等の現在の住居又は本店若しくは主たる事務所の所在地を確認した場合に限る。)
三 当該特定事業者の役職員が、当該顧客等の本人確認書類若しくは補完書類又はその写しに記載されている当該顧客等の営業所であると認められる場所に赴いて当該顧客等の代表者等に取引関係文書を交付する方法(当該顧客等の代表者等から、当該本人確認書類若しくは補完書類の提示を受け、又は当該本人確認書類若しくはその写し若しくは当該補完書類若しくはその写しの送付を受ける場合に限る。)
03|受理+送付法(3号二)
これは、法人の本人確認書類(写しも含む)の送付を受けるとともに、取引関係文書を書留郵便等により転送不要郵便物として送付する方法です。
(※送付を受ける、の部分が「受理」)
▽犯収法規則6条1項3号二
ニ 当該法人の代表者等から本人確認書類のうち次条第二号若しくは第四号に定めるもの又はその写しの送付を受けるとともに、当該本人確認書類又はその写しに記載されている当該顧客等の本店等に宛てて、取引関係文書を書留郵便等により、転送不要郵便物等として送付する方法
受理した本人確認書類は、確認記録への添付も必要です(規則19条1項2号)。
▽犯収法規則19条1項2号リ
リ 第六条第一項第三号ニに掲げる方法により本人特定事項の確認を行ったとき当該本人確認書類又はその写し
送付先は営業所宛ても可能(規則6条3項)
ここも、取引関係文書の送付先は営業所宛ても可能とされています。
(ただし、当該営業所の記載を本人確認書類or補完書類で確認する必要あり)
前述の部分と根拠条文は同じで、内容も同じです。
改めて条文を見てみます。受理+送付法=「3号ニ」が入っていることが確認できます。
▽犯収法規則6条3項
3 特定事業者は、第一項第三号ロからニまでに掲げる方法(ロ及びハに掲げる場合にあっては、括弧書に規定する方法に限る。)により本人特定事項の確認を行う場合においては、当該顧客等の本店等に代えて、当該顧客等の代表者等から、当該顧客等の営業所であると認められる場所の記載がある当該顧客等の本人確認書類若しくは補完書類の提示を受け、又は当該本人確認書類若しくはその写し若しくは当該補完書類若しくはその写しの送付を受けるとともに、当該場所に宛てて取引関係文書を送付することができる。
送付に代えた交付法(規則6条4項)
ここの「送付」も、「送付に変えた交付」によることができます。
前述の部分と根拠条文は同じで、内容も同じです。
改めて条文を見てみます。受理+送付法=「3号ニ」が入っていることが確認できます。
▽犯収法規則6条4項
4 特定事業者は、第一項第一号ロ若しくはチからヌまで又は第三号ロからニまでに掲げる方法(ロ及びハに掲げる場合にあっては、括弧書に規定する方法に限る。)により本人特定事項の確認を行う場合においては、取引関係文書を書留郵便等により転送不要郵便物等として送付することに代えて、次の各号に掲げる方法のいずれかによることができる。
一~三 (略)
04|電子署名法に基づく電子証明書を用いる方法(3号ホ)
これは、法人の代表者等から、
- 登記官が作成した電子証明書(商業登記法12条の2第1項及び第3項)
と - 当該電子証明書により確認される電子署名(電子署名法2条1項)が行われた特定取引等に関する情報
の送信を受ける方法、のことです。
▽商業登記に基づく電子認証制度についてはこちら(法務省HP)
-
-
法務省:登記 -商業登記に基づく電子認証制度-
www.moj.go.jp
▽犯収法規則6条1項3号ホ
ホ 当該法人の代表者等から、商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第十二条の二第一項及び第三項の規定に基づき登記官が作成した電子証明書並びに当該電子証明書により確認される電子署名法第二条第一項に規定する電子署名が行われた特定取引等に関する情報の送信を受ける方法
結び
今回は、犯罪収益移転防止法ということで、顧客等が法人である場合の本人確認方法について見てみました。
[注記]
本記事を含む一連の勉強記事は、過去の自分に向けて、①自分の独学や経験の記録を見せる、②感覚的な理解を伝えることを優先する、③細かく正確な理解は書物に譲る、ということをコンセプトにした読みものです。ベテランの方が見てなるほどと思うようなことは書かれていないほか、業務上必要であるときなど、正確な内容については別途ご確認ください。また、法改正をはじめとした最新の情報を反映しているとは限りませんので、ご注意ください。
犯罪収益移転防止法に関するその他の記事(≫Read More)
参考文献
※注:上記は「全訂版」の旧版
当サイトではアフィリエイトプログラムを利用して商品・サービスを記載しています
主要法令等
主要法令等
- 犯罪収益移転防止法(「犯罪による収益の移転防止に関する法律」)
- 施行令(「犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令」)
- 施行規則(「犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則」)
- 改正事項に関する資料|JAFICホームページ
- 過去に実施したパブリックコメントの結果|JAFICホームページ
参考資料
- 犯罪収益移転防止法の概要(JAFIC)|JAFICホームページ
業界別資料
- 犯罪収益移転防止法に関するよくある質問・回答|全国銀行協会HP
- 犯罪による収益の移転防止に関する法律及び同政省令に関するQ&A|日本証券業協会HP