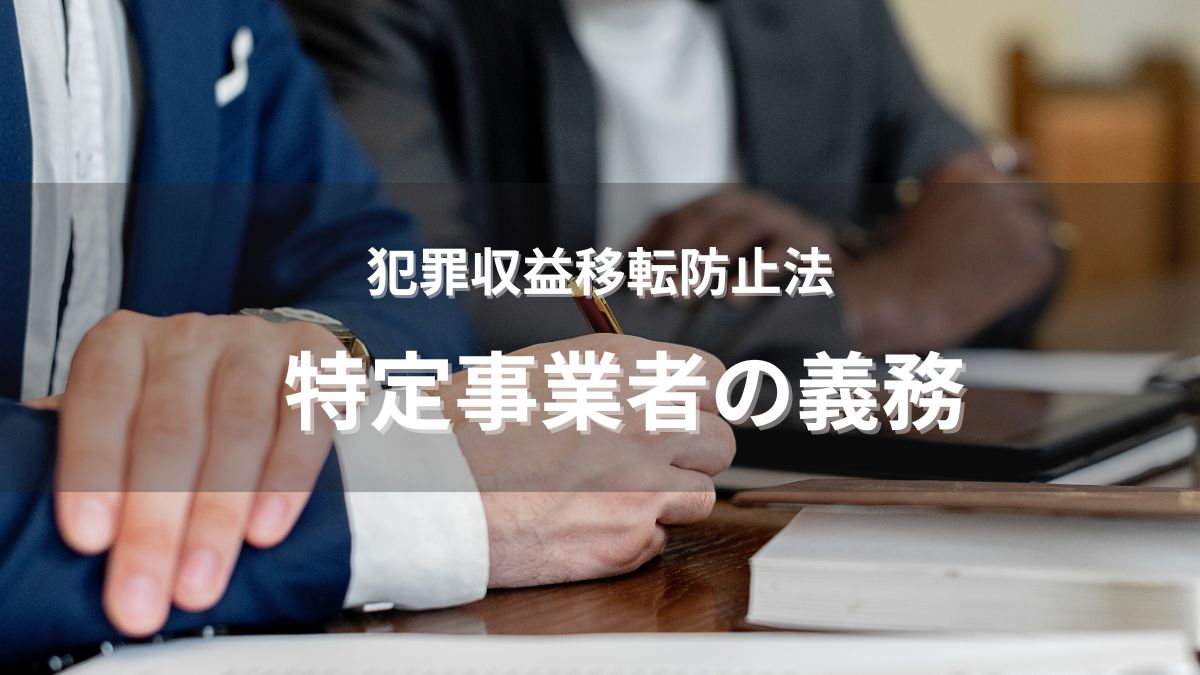今回は、犯罪収益移転防止法ということで、本人特定事項の確認について見てみたいと思います。
ではさっそく。なお、引用部分の太字、下線、改行などは管理人によるものです。
メモ
このカテゴリーでは、インハウスとしての法務経験からピックアップした、管理人の独学や経験の記録を綴っています。
ネット上の読み物としてざっくばらんに書いており、感覚的な理解を掴むことを目指していますが、書籍などを理解する際の一助になれば幸いです。
本人特定事項の確認とは
まず最初に、本人特定事項というのは何なのか?ということを確認しておきたいと思います。
本人特定事項というのは、
| 自然人の場合 | ①氏名 | ②住居 | ③生年月日 |
| 法人の場合 | ①名称 | ②本店又は主たる事務所の所在地 | - |
のことです。
要するに、「どこの誰ですか?」というのを確認すれば本人を特定できるわけです(法人もそう)。自然人の場合は併せて生年月日もよく聞かれるところですので、特に違和感のないところかと思います。
次に、誰の本人特定事項を確認する必要があるのか?という話ですが、もちろん取引の相手方になります。
犯罪収益移転防止法では、取引の相手方のことを
「顧客等」
といいます。
これだけだとそんなに難しくないのですが、代理を介した取引になる場合、
代理人(会社など法人の場合なら、代表権限を有する者など)
についても本人特定事項の確認が必要となっていて、そこが若干ややこしいところです。
つまり、「顧客等」である本人と「代理人」の双方の本人確認が必要になっています。
さらに、代理を介した取引になる場合、顧客等との関係についても確認が必要となっていて、そこも若干ややこしさを増しています。
顧客等との関係というのは、「あなたは取引の本人とどういうご関係の人なの?」ということ、要するに、その取引の権限をきちんと持っていますか?ということであり、
- 顧客等の代理人なの?
- あるいは、法定代理人(ex.親権者など)なの?
- 顧客等が会社であれば、そこの代表取締役社長なの?
- あるいは、取引権限のある本部長や支店長なの?
といったことです。
ここまでの話をまとめると、以下のようになります。
本人特定事項の確認まとめ
| 顧客等 | 確認の対象者 | 確認の内容 |
|---|---|---|
| 自然人の場合 | 顧客等(自然人) | 本人特定事項(「氏名」「住居」「生年月日」) |
| 代理人(※いる場合) | 本人特定事項(「氏名」「住居」「生年月日」) | |
| 顧客等との関係 | ||
| 法人の場合 | 顧客等(法人) | 本人特定事項(「名称」「本店又は主たる事務所の所在地」) |
| 代表権限を有する者など(※必ずいる) | 本人特定事項(「氏名」「住居」「生年月日」) | |
| 顧客等との関係 |
以下、それぞれをもう少し詳しく見てみます。
顧客等についての本人確認
「本人特定事項」の確認
顧客等についての「本人特定事項」の確認自体は、シンプルです。
先ほど見たように、顧客等が自然人なら、
「氏名」「住居」「生年月日」
の確認ですし、
会社などの法人なら、
「名称」「本店又は主たる事務所の所在地」
の確認です。
雑感
事務所をやっていると、ご高齢の依頼者のときに、電話口のあいさつで「〇〇町の〇〇です」と名乗る方がいたりします(若干古風で丁寧な趣)。
これは、苗字や名前だけだと同姓同名の人がいるかもしれないので、併せて町名を名乗っているわけで、そうすれば「ああ、あの人だ」というのがわかるだろう、というわけです(町名は住んでいる場所の情報というよりは、人を特定するための補助情報として使われている)。
もちろん犯収法だのKYCだのといった事がない時代の習慣だと思いますが、昔の人の何気ない知恵のようなものを感じます。
上記の本人特定事項の確認というのも、いってみればこれと同じことです。
なお、どんな書類で確認するのかという本人確認書類の種類については、以下の関連記事にくわしく書いています。
代表的なものでいえば、自然人の場合は運転免許証など、法人の場合は登記事項証明書などになります。
-

-
犯罪収益移転防止法|本人確認書類の種類
続きを見る
「顧客等」とは
ちなみに、「顧客等」の「等」というのが何なのか引っかかるかもしれませんが、ここで「等」といっているのは信託の受益者のことなので(施行令5条)、あまり気にしなくてよいです。
要するに、取引の相手方そのもの(自然人なら自然人、法人なら法人)のことと思っておけばよいです。
条文上の言い方でいうと、「顧客等」=「顧客」+「顧客に準ずる者」なのですが(法2条3項)、顧客に準ずる者というのは信託の受益者だけになっています(施行令5条)。
▽犯収法2条3項
3 この法律において「顧客等」とは、顧客(前項第四十号に掲げる特定事業者にあっては、利用者たる顧客)又はこれに準ずる者として政令で定める者をいう。
▽犯収法施行令5条
(顧客に準ずる者)
第五条 法第二条第三項に規定する顧客に準ずる者として政令で定める者は、信託の受益者(…(略)…。)とする。
「顧客」の正確な解説は、以下のとおりです。ただ、通常はそれほど気にしなくてよいかと思います。
▽「犯罪収益移転防止法の概要」4-【顧客等についての確認】
「顧客」とは、特定事業者が特定業務において行う特定取引等の相手方をいい、これに当たるか否かについては、取引を行うに際して取引上の意思決定を行っているのは誰かということと、取引の利益(計算)が実際には誰に帰属するのかということを総合判断して決定されます。
そのため、例えば、Aの名義において宅地建物取引業者と宅地建物の売買契約を締結しようとする場合であっても、実際にはBがお金を出して宅地建物を購入して使用するつもりであり、AはBの単なる手足として契約の締結をしようとしている場合には、「顧客」はBであり、Aは現に取引の任に当たっている自然人(代表者等)にすぎないと考えられます。
代表者等についての本人確認
代表者等についても「本人特定事項」の確認が必要
冒頭でも見たように、代理を介した取引になる場合、代理人(会社の場合なら、代表権限を有する者など)についても本人特定事項の確認が必要となっています。
具体的には、
- 顧客等が自然人なら、代理人
- 顧客等が法人なら、
- 代表者(※会社の代表者も代理の一種なので)
又は - 取引権限のある取引担当者
- 代表者(※会社の代表者も代理の一種なので)
の本人特定事項の確認です。
顧客等が自然人の場合は、代理を介さなくても取引できますので、代理人は、いる場合もいない場合もあります。
ここでいう代理人には、代理権を与えられた代理人=任意代理人だけではなく、法定代理人(法律上代理権がある者。親権者や成年後見人など)も含まれます。
これに対し、顧客等が法人の場合は、必ず代理を介した取引になります。
なぜかというと、法人は肉体を持たないので、取引は必ず代理で行われる(※社長など会社代表者による代表も、この代理の一種)からです。なので、代表権限を有する者などに関する本人確認が必ず発生します。
条文も確認してみます。
代理人などについても本人特定事項の確認が必要と言っているのは、法4条4項になります。
現に特定取引等の任に当たっている自然人が顧客等と異なるとき…という部分が、自然人の代理人が取引の任に当たっている場合や、顧客等が法人である場合のことを指しています。
会社の代表者が会社のために特定取引等を行うとき…というのは、その例示になります。
▽犯収法4条4項(※「…」は管理人が適宜省略)
4 特定事業者は、顧客等について第一項又は第二項の規定による確認を行う場合において、会社の代表者が当該会社のために当該特定事業者との間で…特定取引等…を行うときその他の当該特定事業者との間で現に特定取引等の任に当たっている自然人が当該顧客等と異なるとき(次項に規定する場合を除く。)は、当該顧客等の当該確認に加え、当該特定取引等の任に当たっている自然人についても、主務省令で定めるところにより、その者の本人特定事項の確認を行わなければならない。
「顧客等との関係」についても確認が必要
また、代理人などの本人特定事項を確認する前提として、顧客等との関係(=つまり取引権限をきちんと持っていること)の確認も必要となっています。
顧客等との関係というのは、ざっくりいうと、
顧客等が自然人の場合の「代理人」だったら
⇒ 代理権(法定代理権を含む)を持っているということ
ですし、
顧客等が法人の場合の「代表者等」だったら
⇒ 代表者であって、代表権を持っているということ
または、
⇒ 代表者以外の取引担当者であれば、取引権限を持っているということ
です。
条文も確認してみます。規則12条5項になります。
顧客等のために特定取引等の任に当たっていると認められる…という部分が、顧客等との関係の確認のことです。
▽犯収法規則12条5項
5 第一項の代表者等は、次の各号に掲げる場合においては、それぞれ当該各号に該当することにより当該顧客等のために特定取引等の任に当たっていると認められる代表者等をいうものとする。
一~二 (略)
なお、厳密にいうと、顧客等との関係の確認というのは、民法上の代理権の有無の確認とは異なるとされています。ただ、管理人的にはかえって理解しにくいように思いますので、本記事では指摘だけにしておきたいと思います。
逐条解説(「逐条解説 犯罪収益移転防止法(犯罪収益移転防止制度研究会)」77頁)や、以下のパブコメにその旨の記載があります。
▽平成24年3月26日パブコメNo.75|JAFICホームページ(掲載ページ)
質問の概要 第11条第4項の規定は、代表者等が代理権を有していることの確認を義務付けるものであるのか。
質問に対する考え方 新規則第11条第4項は、代表者等が顧客等のために特定取引等の任に当たっていることが明らかであることを求めておりますが、これは民法上の代理権を有しているかの確認とは異なるものです。よって、代理権を有していることの確認を義務付けるものではありません。
(※)管理人注:11条4項というのは当時の条数で、現在は上記のとおり12条5項
「代表者等」とは
ここまでさらっと書きましたが、「代表者等」というのは、「顧客等」と違って実はややこしいです。
「代表者等」というと、語感的に社長を思い浮かべますし、間違ってはいないのですが、ここでいう「代表者等」はいわゆる社長などに限られません。
先ほど書いたように、「取引の任に当たっていると認められる人」のことですので、取引権限を与えられた、役員、部長、課長、主任、一般従業員などもこれに該当します。
また、条文上の意味としては、顧客等が自然人の場合の代理人も含んだ概念になっています。
つまり、「顧客等」の「等」(←信託の受益者のみ)とは違って、「代表者等」の「等」の範囲はけっこう広いわけです。
具体的には、くり返しになりますが、
- 顧客等が自然人の場合の、いわゆる代理人も含んだ概念であること
- 顧客等が法人の場合でも、いわゆる社長(代表権を有する者)のみならず、取引権限のある取引担当者も含まれること
に注意すべきで、「代表者等」という語感から感じとれる意味とはずいぶん違っているので、解説や条文を眺めるときには常に念頭に置いておいた方がよいと思います。
条文も確認してみます。
「代表者等」の定義は、以下のように法4条6項の文中に出てきます。
(現に取引の任に当たっている自然人が顧客等と異なるときの、)現に取引の任に当たっている自然人、です。
こういう表現だと、顧客等が自然人である場合の代理人や、会社の取引担当者の場合もたしかに入ることになります。
▽犯収法4条6項
6 顧客等及び代表者等(前二項に規定する現に特定取引等の任に当たっている自然人をいう。以下同じ。)は、…(略)…。
正確な解説は、以下のとおりです。
▽「犯罪収益移転防止法の概要」4-【代表者等についての確認】
特定取引等の任に当たっている自然人が顧客等と異なる場合(例えば、顧客等が法人である場合や、自然人の顧客等の代理人が取引の任に当たっている場合)には、顧客等についての確認に加え、当該取引の任に当たっている自然人(代表者等)について、その本人特定事項の確認を行うこととなります(「代表者等」は、法人を代表する権限を有している者には限られません。)。
また、代表者等の本人特定事項を確認するに当たっては、その前提として、代表者等が委任状を有していること、電話により代表者等が顧客等のために取引の任に当たっていることが確認できることなどの当該代表者等が顧客等のために特定取引等の任に当たっていると認められる事由が必要となります。
※ 犯罪収益移転防止法施行規則の改正により、平成28年10月1日以後は、社員証を有していること、役員として登記されていること(代表権限を有している場合を除く。)は、代表者等が顧客等のために特定取引等の任に当たっていると認められる事由ではなくなりました。
まとめ
最後にもう一度これまでの話をまとめると、以下の表のとおりです。
「 」付きの部分は、条文上の文言になっています。
本人特定事項の確認まとめ
| 顧客等 | 確認の対象者 | 確認の内容 |
|---|---|---|
| 自然人の場合 | 「顧客等」(自然人) | 本人特定事項(「氏名」「住居」「生年月日」) |
| 「代表者等」(※いる場合)≒任意代理人、法定代理人など | 本人特定事項(「氏名」「住居」「生年月日」) | |
| 顧客等との関係≒任意代理権、法定代理権 | ||
| 法人の場合 | 「顧客等」(法人) | 本人特定事項(「名称」「本店又は主たる事務所の所在地」) |
| 「代表者等」(※必ずいる)≒代表者、取引権限のある取引担当者 | 本人特定事項(「氏名」「住居」「生年月日」) | |
| 顧客等との関係≒代表権、取引権限 |
結び
今回は、犯罪収益移転防止法ということで、本人特定事項の確認について見てみました。
[注記]
本記事を含む一連の勉強記事は、過去の自分に向けて、①自分の独学や経験の記録を見せる、②感覚的な理解を伝えることを優先する、③細かく正確な理解は書物に譲る、ということをコンセプトにした読みものです。ベテランの方が見てなるほどと思うようなことは書かれていないほか、業務上必要であるときなど、正確な内容については別途ご確認ください。また、法改正をはじめとした最新の情報を反映しているとは限りませんので、ご注意ください。
犯罪収益移転防止法に関するその他の記事(≫Read More)
主要法令等
主要法令等
- 犯罪収益移転防止法(「犯罪による収益の移転防止に関する法律」)
- 施行令(「犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令」)
- 施行規則(「犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則」)
- 改正事項に関する資料|JAFICホームページ
- 過去に実施したパブリックコメントの結果|JAFICホームページ
参考資料
- 犯罪収益移転防止法の概要(JAFIC)|JAFICホームページ
業界別資料
- 犯罪収益移転防止法に関するよくある質問・回答|全国銀行協会HP
- 犯罪による収益の移転防止に関する法律及び同政省令に関するQ&A|日本証券業協会HP
参考文献
参考文献
※注:上記は「全訂版」の旧版
当サイトではアフィリエイトプログラムを利用して商品・サービスを記載しています