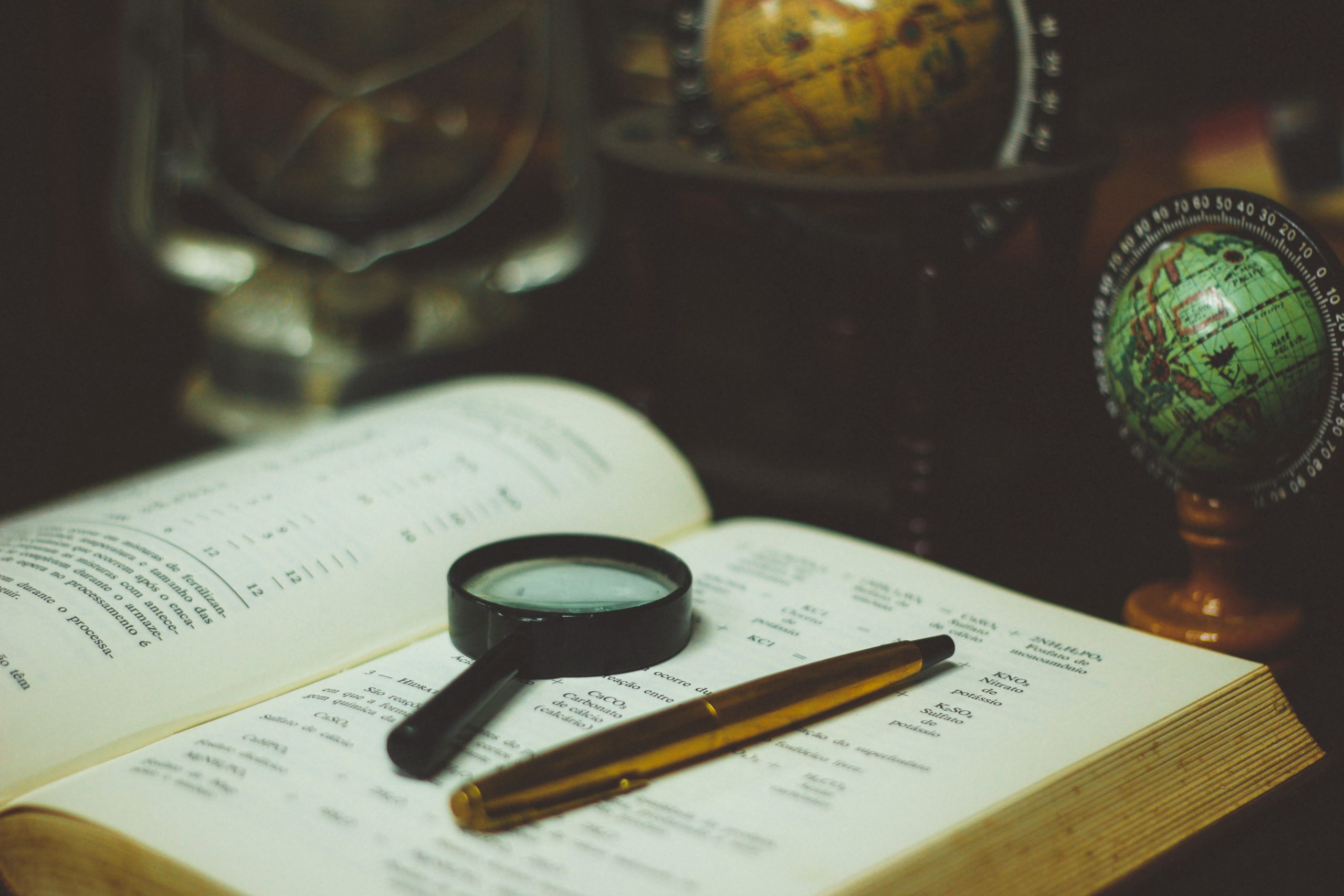感覚でわかるシリーズ。
今回は、会社法上の「株式交換」についてです。
管理人は、学生の時分は何を読んでもイマイチ頭に入ってこず、わかりやすそうな図を見ても「うーん」という感じだったのですが、ある程度年を食ってから自然とわかるようになったので、その感覚を書いてみたいと思います。
株式交換が何なのかは、順繰りにポイントを追っていくようにするとわかりやすいように思います(図か何かで複数のアクションを同時に説明されても、かえって難しい)。
ということで、順番にポイントを見ていきたいと思います。
ポイント①
まず、最初のポイントは、株式交換は、
どこかの会社を完全子会社化するためにやっている
ということです。
完全子会社というのは、100%子会社のことです。
ポイント②
このとき、完全子会社になる会社にも、当然いまの株主がいるので、100%子会社にするためには、その人たちから株式を譲り渡してもらわなければなりません。
ということで、完全親会社となろうとする会社は、完全子会社のいまの株主から株式を全部譲り渡してもらうことになります(会社法769条参照)。
ポイント③
しかし、当然、タダというわけにはいきません。
もし自分が完全子会社になる会社の株式を持っていたとして、いきなり「その会社を完全子会社にしたいから、お前の持っている株式をタダで全部寄こせ!」と言われても、そんなことあり得ないでしょと感じます。
では何を対価として株式を譲ることになるのかというと、普通それは、完全親会社になろうとする会社の株式です(※これ以外の対価のケースもありますが、割愛します)。
自分がもし完全子会社になる予定の会社の株式を持っていたとして、株式交換が決定されたら、株式を譲らざるを得ないのですが、対価としては、完全親会社となる会社の株式が交付されます。
その結果、完全親会社の株主になる、という結末になります。
まとめ
これらをまとめると、以下のようになります(A社が完全親会社になろうとする会社、B社が完全子会社になる予定の会社)。
⇓ 株式交換
こういうふうに、完全子会社化することが目的であることを出発点として、ストーリーで追っていった方が頭に入りやすい気がします(管理人の個人的意見)。
ちょうど、「もとB社株主」と「A株式会社」との間で、それぞれが持っていた「B社株式」と「A社株式(=A社にとっては自社株)」を交換するような形になるので、”株式交換”と呼ぶわけです。
なお、「そんな株式交換はイヤだ」というB社株主のために、反対株主の株式買取請求権というのもあります(会社法785条)。この場合、B社株主は、完全子会社となるB社に対して、公正な価格で株式を買い取るよう請求することができます。
以上、感覚でわかるシリーズでした。
[注記]
感覚でわかるシリーズは専門的・学術的正確さを目指したわけではありませんので、正確な理解については他の文献等を参照されるか、身近な専門家にご相談ください。
「感覚でわかるシリーズ」のその他の記事