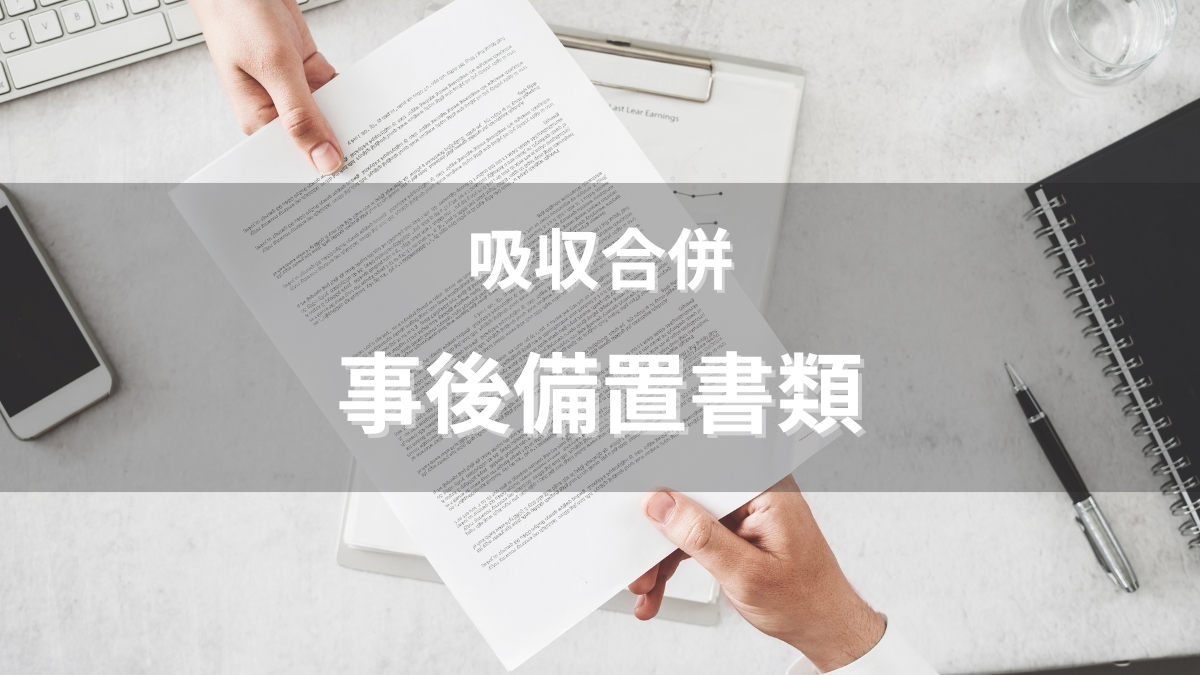今回は、組織再編ということで、吸収合併手続における事後備置書類について見てみたいと思います。
ではさっそく。なお、引用部分の太字、下線、改行などは管理人によるものです。
メモ
このカテゴリーでは、インハウスとしての法務経験からピックアップした、管理人の独学や経験の記録を綴っています。
ネット上の読み物としてざっくばらんに書いており、感覚的な理解を掴むことを目指していますが、書籍などを理解する際の一助になれば幸いです。
事後備置書類とは
吸収合併の存続会社(=吸収する側)は、合併の効力発生後、一定の書類を本店に備え置く義務があります。
この書類を、事後備置書類と呼びます。要するに、事後の情報開示です。
他の手続として「事前備置書類」というのもありますが、何の「事前」「事後」かというと、合併の効力発生日よりも前と後、です
事後備置書類は、主として吸収合併無効の訴え(法828条1項7号)の判断に必要な資料を提供するためという意味合いになります。実際に遂行した吸収合併の経過を開示させるものです。
▽会社法828条1項7号
(会社の組織に関する行為の無効の訴え)
第八百二十八条 次の各号に掲げる行為の無効は、当該各号に定める期間に、訴えをもってのみ主張することができる。
七 会社の吸収合併 吸収合併の効力が生じた日から六箇月以内
以下、順に見てみます。
消滅会社側:なし
吸収合併の場合、消滅会社(=吸収される側)は合併の効力発生日に文字どおり消滅するので、事後備置書類はありません。
▽(参考)会社法2条27号
二十七 吸収合併 会社が他の会社とする合併であって、合併により消滅する会社の権利義務の全部を合併後存続する会社に承継させるものをいう。
▽(参考)会社法750条2項
2 吸収合併消滅会社の吸収合併による解散は、吸収合併の登記の後でなければ、これをもって第三者に対抗することができない。
存続会社側の事後備置書類
存続会社は、吸収合併の効力発生後遅滞なく事後備置書類を作成し本店に備え置く義務があり(法801条1項・3項)、株主と債権者は閲覧等を請求することができます(4項)。
▽会社法801条1項・3項
(吸収合併等に関する書面等の備置き及び閲覧等)
第八百一条 吸収合併存続株式会社は、効力発生日後遅滞なく、吸収合併により吸収合併存続株式会社が承継した吸収合併消滅会社の権利義務その他の吸収合併に関する事項として法務省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を作成しなければならない。
3 次の各号に掲げる存続株式会社等は、効力発生日から六箇月間、当該各号に定めるものをその本店に備え置かなければならない。
一 吸収合併存続株式会社 第一項の書面又は電磁的記録
二・三 (略)
▽同条4項
4 吸収合併存続株式会社の株主及び債権者は、吸収合併存続株式会社に対して、その営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号に掲げる請求をするには、当該吸収合併存続株式会社の定めた費用を支払わなければならない。
一 前項第一号の書面の閲覧の請求
二 前項第一号の書面の謄本又は抄本の交付の請求
三 前項第一号の電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
四 前項第一号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であって吸収合併存続株式会社の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求
備置期間
備置期間は、
- 始期:吸収合併の効力発生日
- 期間:吸収合併の効力発生日後6か月間
となっています(上記条文の3項の下線部参照)。
必要記載事項(規則200条)
事後備置書類の必要記載事項は、規則に定められており、
- 吸収合併の効力発生日(規則200条1号)
- 株主保護手続・債権者保護手続等の経過(2号・3号)
- 消滅会社から承継した重要な権利義務に関する事項(4号)
- 消滅会社の事前備置書類の内容(5号)
- 合併の登記をした日(6号)
- その他吸収合併に関する重要な事項(7号)
となっています。
▽会社法規則200条
(吸収合併存続株式会社の事後開示事項)
第二百条 法第八百一条第一項に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一~七 (略)
以下、順に見てみます。
①吸収合併の効力発生日(1号)
これはそのままですが、吸収合併の効力発生日です。
▽会社法規則200条1号
一 吸収合併が効力を生じた日
やや細かい補足をすると、これは、吸収合併契約に記載された効力発生日(法定記載事項)のことではなく、実際に効力が生じた日のことを指します。
債権者保護手続が終了しないときは、吸収合併契約に定めている日が来ても吸収合併の効力は生じないことになっているので(法750条6項)、実際に吸収合併の効力が生じた日を開示させるということです。
もちろん、特に支障なく進んだ場合は合併契約の記載日どおりに効力が生じますので、通常は、記載日と同じ日を書くことになります
▽会社法750条6項(※【 】は管理人注)
(株式会社が存続する吸収合併の効力の発生等)
第七百五十条 吸収合併存続株式会社は、効力発生日に、吸収合併消滅会社の権利義務を承継する。
6 前各項の規定は、第七百八十九条【=消滅会社側の債権者保護手続】(第一項第三号及び第二項第三号を除き、第七百九十三条第二項において準用する場合を含む。)若しくは第七百九十九条の規定【=存続会社側の債権者保護手続】による手続が終了していない場合又は吸収合併を中止した場合には、適用しない。
②株主保護手続・債権者保護手続等の経過(2号・3号)
これは、合併当事会社それぞれでの、株主保護手続・債権者保護手続等の経過です。
消滅会社側では、
- 合併差止請求手続
- 株主保護手続
- 新株予約権者保護手続
- 債権者保護手続
の経過であり、
存続会社側では、
- 合併差止請求手続
- 株主保護手続
- 債権者保護手続
の経過、となっています(※存続会社側では”新株予約権者保護手続の経過”はない)。
条文も確認してみます。
▽会社法規則200条2号・3号(※【 】は管理人注)
【2号:消滅会社側の株主保護手続・債権者保護手続等の経過】
二 吸収合併消滅会社における次に掲げる事項
イ 法第七百八十四条の二の規定による請求に係る手続【=合併差止請求手続】の経過
ロ 法第七百八十五条【=株主保護手続】及び第七百八十七条の規定【=新株予約権者保護手続】並びに法第七百八十九条(法第七百九十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定【=債権者保護手続】による手続の経過
【3号:存続会社側の株主保護手続・債権者保護手続等の経過】
三 吸収合併存続株式会社における次に掲げる事項
イ 法第七百九十六条の二の規定による請求に係る手続【=合併差止請求手続】の経過
ロ 法第七百九十七条【=株主保護手続】及び第七百九十九条の規定【=債権者保護手続】による手続の経過
③消滅会社から承継した重要な権利義務に関する事項(4号)
これは、吸収合併により、存続会社が消滅会社から承継した重要な権利義務に関する事項です。
▽会社法規則200条4号
四 吸収合併により吸収合併存続株式会社が吸収合併消滅会社から承継した重要な権利義務に関する事項
④消滅会社の事前備置書類の内容(5号)
これは、消滅会社が備え置いた書面または電磁的記録、つまり事前備置書類に記載または記録がされた事項です。
吸収合併の場合、消滅会社は合併の効力発生日に消滅してしまう(=消滅会社側の事前備置書類の内容は開示されなくなる)ので、これを補うために、存続会社側の事後備置書類で開示せよということです。
▽会社法規則200条5号(※【 】は管理人注)
五 法第七百八十二条第一項の規定【=消滅会社側の事前備置】により吸収合併消滅株式会社が備え置いた書面又は電磁的記録に記載又は記録がされた事項(吸収合併契約の内容を除く。)
なお、括弧書きで「吸収合併契約の内容」が除かれているのは、これは存続会社側の事前備置書類に記載されているためです。
⑤合併の登記をした日(6号)
これは、吸収合併に伴う変更の登記(法921条)を行った日、つまり合併の登記日です。
▽会社法規則200条6号(※【 】は管理人注)
【6号:吸収合併に伴い変更の登記をした日】
六 法第九百二十一条の変更の登記をした日
▽会社法921条
(吸収合併の登記)
第九百二十一条 会社が吸収合併をしたときは、その効力が生じた日から二週間以内に、その本店の所在地において、吸収合併により消滅する会社については解散の登記をし、吸収合併後存続する会社については変更の登記をしなければならない。
⑥その他吸収合併に関する重要な事項(7号)
これは、上記①~⑤以外の重要な事項です。
合併に関する監督官庁の認可などが例として挙げられます。
▽会社法規則200条7号
七 前各号に掲げるもののほか、吸収合併に関する重要な事項
結び
吸収合併はいわゆる”吸収型”の組織再編ということで、会社法では吸収分割や株式交換と同じグループで規定されています。
事後備置書類は、インターネットで検索や画像検索をすればいくつか例を見ることもできますので(鵜呑みにはできませんが)、上記のような理屈を押さえつつそれらを参照しながら作ったりチェックしたりするのも一つの方法かと思います。あるいは、会社に以前の事例があればそれらを見ながらやるとか、最初の方や悩ましい場合は外部の法律事務所に相談する、といったことも考えられます。
純粋なグループ内再編(=交渉を伴わないもの)の場合は、ある程度ルーティンワーク的になってきますので、なるだけ定型化していくのが賢いやり方かなと思います。
今回は、組織再編ということで、吸収合併手続における事後備置書類について見てみました。
[注記]
本記事を含む一連の勉強記事は、過去の自分に向けて、①自分の独学や経験の記録を見せる、②感覚的な理解を伝えることを優先する、③細かく正確な理解は書物に譲る、ということをコンセプトにした読みものです。ベテランの方が見てなるほどと思うようなことは書かれていないほか、業務上必要であるときなど、正確な内容については別途ご確認ください。また、法改正をはじめとした最新の情報を反映しているとは限りませんので、ご注意ください。
組織再編に関するその他の記事(≫Read More)
主要法令等
主要法令等
リンクをクリックすると、法令データ提供システム等に遷移します
- 会社法(≫法律情報/英文)
- 会社法施行令
- 会社法規則(「会社法施行規則」)
- 計規(「会社計算規則」)
- 労働契約承継法(「会社分割に伴う労働契約の承継等に関する法律」)
- 労働契約承継法規則(「会社分割に伴う労働契約の承継等に関する法律施行規則」)
- 労働契約承継法指針(「分割会社及び承継会社等が講ずべき当該分割会社が締結している労働契約及び労働協約の承継に関する措置の適切な実施を図るための指針」(平成12年労働省告示第127号))|≫掲載ページ(厚労省HP)
- 労働契約承継法Q&A(「会社分割・事業譲渡・合併における労働者保護のための手続に関するQ&A」〔平成28年12月時点〕)|≫掲載ページ(厚労省HP)
- 金融商品取引法(≫法律情報/英文)
- 民法(≫法律情報/英文)
参考文献
当サイトではアフィリエイトプログラムを利用して商品・サービスを記載しています