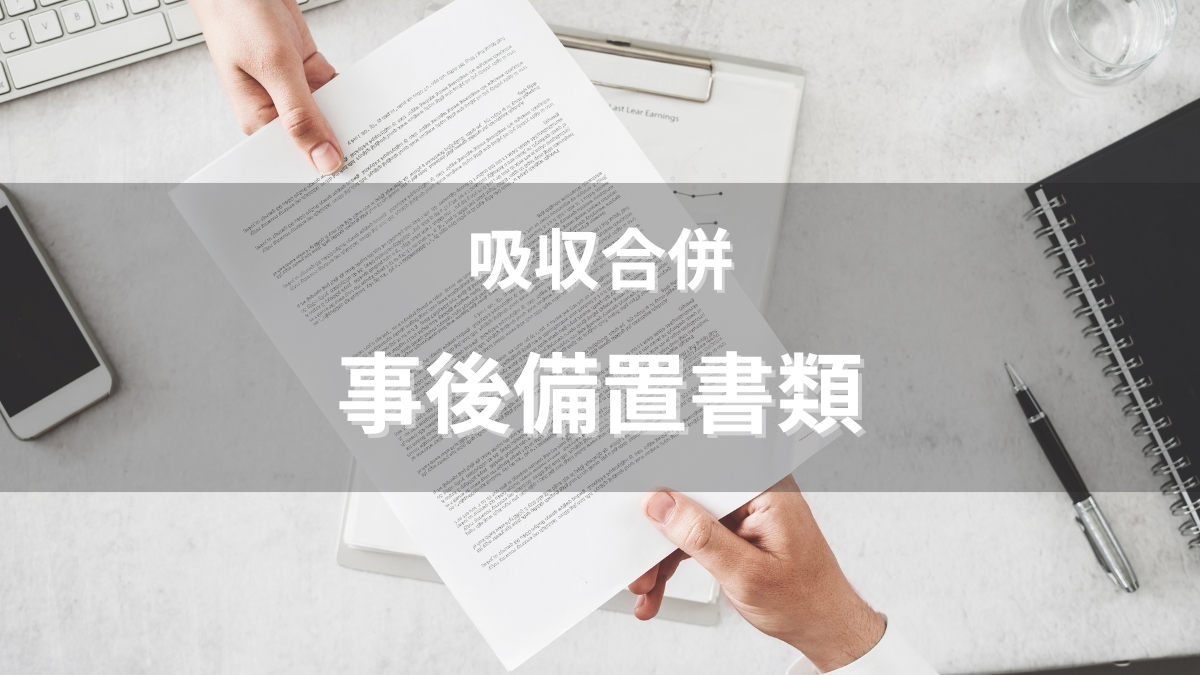今回は、組織再編ということで、吸収合併の手続のうち、株主総会決議と略式・簡易合併(株主総会決議が不要となる場合)について見てみたいと思います。
ではさっそく。なお、引用部分の太字、下線、改行などは管理人によるものです。
メモ
このカテゴリーでは、インハウスとしての法務経験からピックアップした、管理人の独学や経験の記録を綴っています。
ネット上の読み物としてざっくばらんに書いており、感覚的な理解を掴むことを目指していますが、書籍などを理解する際の一助になれば幸いです。
吸収合併契約承認の株主総会決議
吸収合併契約を締結した後、通常、株主総会決議で承認する必要があります。
これは原則としていわゆる特別決議になります(会社法309条2項12号)。特別決議とは、議決権の過半数を有する株主が出席し、そのうち3分の2以上の賛成を得る必要がある決議です。
▽法309条2項12号(※【 】は管理人注)
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる株主総会の決議は、当該株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の過半数(三分の一以上の割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の三分の二(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上に当たる多数をもって行わなければならない。この場合においては、当該決議の要件に加えて、一定の数以上の株主の賛成を要する旨その他の要件を定款で定めることを妨げない。
一~十一 (略)
十二 第五編【=第五編 組織変更、合併、会社分割、株式交換、株式移転及び株式交付】の規定により株主総会の決議を要する場合における当該株主総会
消滅会社側(法783条1項)
まず、消滅会社側(吸収される側の会社)から見てみます。承認時期は効力発生日の前日までです。
▽法783条1項
(吸収合併契約等の承認等)
第七百八十三条 消滅株式会社等は、効力発生日の前日までに、株主総会の決議によって、吸収合併契約等の承認を受けなければならない。
存続会社側(法795条1項)
続いて、存続会社側(吸収する側の会社)を見てみます。承認時期は同じく効力発生日の前日までです。
▽法795条1項
(吸収合併契約等の承認等)
第七百九十五条 存続株式会社等は、効力発生日の前日までに、株主総会の決議によって、吸収合併契約等の承認を受けなければならない。
取締役の説明義務
また、存続会社側では、一定の場合に、株主総会における取締役の説明義務があります(法795条2項・3項)。①合併差損が生じる場合と、②自己株式取得となる場合です。
①の合併差損が生じる場合というのは、
- 消滅会社が債務超過の場合
- 合併により取得する消滅会社の資産から負債を控除した純額(=純資産)よりも、存続会社が実際に支払う対価(合併対価)が高い場合
の2つがあり、取締役は、承認を受けようとする吸収合併が存続会社に差損を生じさせるものである旨を説明する必要があります。
②の自己株式取得となる場合というのはつまり、消滅会社から承継する資産に存続会社の株式が含まれる場合です。
▽法795条2項・3項(※【 】は管理人注)
2 次に掲げる場合には、取締役は、前項の株主総会において、その旨を説明しなければならない。
一 吸収合併存続株式会社又は吸収分割承継株式会社が承継する吸収合併消滅会社又は吸収分割会社の債務の額として法務省令で定める額(次号において「承継債務額」という。)が吸収合併存続株式会社又は吸収分割承継株式会社が承継する吸収合併消滅会社又は吸収分割会社の資産の額として法務省令で定める額(同号において「承継資産額」という。)を超える場合【=合併差損:消滅会社が債務超過】
二 吸収合併存続株式会社又は吸収分割承継株式会社が吸収合併消滅株式会社の株主、吸収合併消滅持分会社の社員又は吸収分割会社に対して交付する金銭等(吸収合併存続株式会社又は吸収分割承継株式会社の株式等を除く。)の帳簿価額が承継資産額から承継債務額を控除して得た額を超える場合【=合併差損:存続会社が取得する純額よりも合併対価の方が高い】
三 (略)
3 承継する吸収合併消滅会社又は吸収分割会社の資産に吸収合併存続株式会社又は吸収分割承継株式会社の株式が含まれる場合【=自己株式取得となる場合】には、取締役は、第一項の株主総会において、当該株式に関する事項を説明しなければならない。
以上のほか、略式合併または簡易合併にあたる場合には、例外的に株主総会決議を省略できることになっていますので、以下、順に見てみます。
略式合併
略式合併とは、合併当事会社の一方が他方の当事会社を支配している場合(特別支配会社である場合)の吸収合併です。
議決権の保有状況からして承認決議がされることが明らかなので、被支配会社側の株主総会決議を省略できることになっています。
特別支配会社とは、他の会社(被支配会社)の総株主の議決権の10分の9(これを上回る割合を被支配会社の定款で定めた場合はその割合)以上を保有している会社のことです。保有には直接保有と間接保有を含みます。
特別支配会社の定義は、事業譲渡の章のところで出てきます。
▽法468条1項
(事業譲渡等の承認を要しない場合)
第四百六十八条 前条の規定は、同条第一項第一号から第四号までに掲げる行為(以下この章において「事業譲渡等」という。)に係る契約の相手方が当該事業譲渡等をする株式会社の特別支配会社(ある株式会社の総株主の議決権の十分の九(これを上回る割合を当該株式会社の定款で定めた場合にあっては、その割合)以上を他の会社及び当該他の会社が発行済株式の全部を有する株式会社その他これに準ずるものとして法務省令で定める法人が有している場合における当該他の会社をいう。以下同じ。)である場合には、適用しない。
消滅会社側の株主総会決議が不要
まず、消滅会社側(吸収される側の会社)から見てみます。
これはつまり、存続会社が消滅会社を支配しているので、消滅会社側での株主総会決議が不要になっているケースです。
▽会社法784条1項(※【 】は管理人注)
(吸収合併契約等の承認を要しない場合)
第七百八十四条 前条第一項【=消滅会社の合併承認の株主総会決議】の規定は、吸収合併存続会社、吸収分割承継会社又は株式交換完全親会社(以下この目において「存続会社等」という。)が消滅株式会社等の特別支配会社である場合には、適用しない。ただし、吸収合併又は株式交換における合併対価等の全部又は一部が譲渡制限株式等である場合であって、消滅株式会社等が公開会社であり、かつ、種類株式発行会社でないときは、この限りでない。
例外的に、消滅会社が公開会社である場合に、合併対価として譲渡制限株式等が交付されるときには、略式合併は認められないことになっています(ただし書参照)。
存続会社側の株主総会決議が不要
続いて、存続会社側(吸収する側の会社)を見てみます。
これはつまり、消滅会社が存続会社を支配しているので、存続会社側での株主総会決議が不要になっているケースです。
▽会社法796条1項(※【 】は管理人注)
(吸収合併契約等の承認を要しない場合等)
第七百九十六条 前条第一項から第三項まで【=存続会社の合併承認の株主総会決議/取締役の説明義務】の規定は、吸収合併消滅会社、吸収分割会社又は株式交換完全子会社(以下この目において「消滅会社等」という。)が存続株式会社等の特別支配会社である場合には、適用しない。ただし、吸収合併消滅株式会社若しくは株式交換完全子会社の株主、吸収合併消滅持分会社の社員又は吸収分割会社に対して交付する金銭等の全部又は一部が存続株式会社等の譲渡制限株式である場合であって、存続株式会社等が公開会社でないときは、この限りでない。
例外的に、存続会社が非公開会社である場合に、合併対価として自社の譲渡制限株式を交付するときには、略式合併は認められないことになっています(ただし書参照)。
一般に、非公開会社における募集株式の発行または移転については、株主総会決議が必要なこと(法199条2項)との平仄を合わせたものです(株主の持株比率維持の利益への配慮)
簡易合併
簡易合併とは、財産の規模の観点から株主に及ぼす影響が軽微なものについて、合併契約承認の株主総会決議を省略できるとしたものです。
要するに合併の規模が小さい場合に手続を緩和したものです。
消滅会社側では不可
吸収合併の場合、消滅会社側は消えてしまうので、簡易合併による株主総会決議の省略というのはありません。
消滅会社の株主にとっては、自分の会社が消えてしまうわけで、影響が軽微とはいえないからです
存続会社側の株主総会決議が不要
存続会社側では、消滅会社の株主への合併対価が存続会社の純資産額の5分の1(これを下回る割合を存続会社の定款で定めた場合にあっては、その割合)を超えない場合には、株主総会決議を省略することができます(法796条2項本文)。
要するに、合併対価として存続会社から出ていく財産が純資産額の20%以下の場合には、合併の規模が小さいので株主総会決議を省略してよいということです。
ただし、例外もあります。①存続会社において合併差損が生じる場合、②存続会社が非公開会社である場合に合併対価として自社の譲渡制限株式を交付するときは、株主総会決議を省略することはできません(ただし書参照)。
▽法796条2項(※【 】は管理人注)
2 前条第一項から第三項まで【=存続会社の合併承認の株主総会決議/取締役の説明義務】の規定は、第一号に掲げる額の第二号に掲げる額に対する割合が五分の一(これを下回る割合を存続株式会社等の定款で定めた場合にあっては、その割合)を超えない場合には、適用しない。ただし、同条第二項各号に掲げる場合【=合併差損】又は前項ただし書【=存続会社が非公開会社で合併対価として譲渡制限株式を交付】に規定する場合は、この限りでない。
一 次に掲げる額の合計額
イ 吸収合併消滅株式会社若しくは株式交換完全子会社の株主、吸収合併消滅持分会社の社員又は吸収分割会社(以下この号において「消滅会社等の株主等」という。)に対して交付する存続株式会社等の株式の数に一株当たり純資産額を乗じて得た額
ロ 消滅会社等の株主等に対して交付する存続株式会社等の社債、新株予約権又は新株予約権付社債の帳簿価額の合計額
ハ 消滅会社等の株主等に対して交付する存続株式会社等の株式等以外の財産の帳簿価額の合計額
二 存続株式会社等の純資産額として法務省令で定める方法【=施行規則196条】により算定される額
また、議決権の6分の1を超える株主が、株主保護手続における通知または公告の日から2週間以内に吸収合併に反対する旨を存続会社に通知した場合も、株主総会決議が必要となっています(3項)。
▽同条3項(※【 】は管理人注)
3 前項本文に規定する場合において、法務省令で定める数【=施行規則197条】の株式(前条第一項の株主総会において議決権を行使することができるものに限る。)を有する株主が第七百九十七条第三項の規定による通知又は同条第四項の公告の日から二週間以内に吸収合併等に反対する旨を存続株式会社等に対し通知したときは、当該存続株式会社等は、効力発生日の前日までに、株主総会の決議によって、吸収合併契約等の承認を受けなければならない。
「純資産額」の意義
ちなみに、「純資産額」の内容は、施行規則に規定されており、
- 「純資産額」=(①+②+③+④+⑤+⑥)-⑦
- 資本金の額
- 資本準備金の額
- 利益準備金の額
- 剰余金(法446条)の額
- 評価・換算差額等の額
- 新株予約権の帳簿価額
- 自己株式と自己新株予約権の帳簿価額の合計額
となっています(規則196条)。なお、上記は簡略化のため、基準時の違いを省いて項目だけを書いています。
こう見ると何のことかわかりにくそうですが、ざっくりいえば、「純資産額」の言葉どおり、概ねB/Sの以下「純資産」の部分の額になります。なぜかというと、①~⑥は純資産の項目で、⑦は資本の減少つまり純資産のマイナス項目だからです。
【存続会社の貸借対照表(B/S)】
| 資産 | 負債 |
| 純資産 |
略式・簡易組織再編(吸収型)のまとめ
本記事は吸収合併に焦点を当てていますが、もう少し広めに、吸収型の組織再編(吸収合併、吸収分割、株式交換)において略式・簡易の手続がどこで認められているかをまとめてみると、以下のようになります。
吸収型における略式・簡易組織再編の有無
| 吸収合併 | 吸収分割 | 株式交換 | ||||
| 消滅側 | 存続側 | 分割側 | 設立側 | 子会社側 | 親会社側 | |
| 略式組織再編 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 簡易組織再編 | × | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 |
略式は、”議決権の支配関係からして当然に可決されるから決議なんて要らないよ”というもので、こういった特別支配関係は吸収合併・吸収分割・株式交換の全てで考えられますので、全部「〇」になっています。
簡易は、”出ていく財産の規模が小さくて影響が軽微だから決議なんて要らないよ”というもので、
- 存続側、設立側、親会社側(つまり受ける側)は、本記事で見たように交付する対価の規模が小さい場合(=純資産額の20%以下)
- 分割側(つまり出す側)は、承継させる資産の規模が小さい場合(=総資産額の20%以下)
に認められています。
吸収合併での消滅側(会社が消えてしまう)、株式交換での子会社側(株主は自分の持っている子会社株式を全部移転させられてしまう)の場合には、簡易組織再編はありません(表の「×」部分参照)。
ちなみに、略式組織再編があるのは吸収型の組織再編のみで、新設型の組織再編(新設合併、新設分割、株式移転)にはありません。
結び
簡易合併の要件を満たすかどうかの正確なところは、通常、経理マターになると思いますので、普通は向こうも大体知っていますが、一応連携することになります(まあ、吸収合併の場合はグループ内再編であれば普通無対価でやると思いますので、要件充足に迷いはないと思いますが)。
今回は、組織再編ということで、吸収合併の手続のうち、株主総会決議と略式・簡易合併について見てみました。
[注記]
本記事を含む一連の勉強記事は、過去の自分に向けて、①自分の独学や経験の記録を見せる、②感覚的な理解を伝えることを優先する、③細かく正確な理解は書物に譲る、ということをコンセプトにした読みものです。ベテランの方が見てなるほどと思うようなことは書かれていないほか、業務上必要であるときなど、正確な内容については別途ご確認ください。また、法改正をはじめとした最新の情報を反映しているとは限りませんので、ご注意ください。
組織再編に関するその他の記事(≫Read More)
主要法令等
主要法令等
リンクをクリックすると、法令データ提供システム等に遷移します
- 会社法(≫法律情報/英文)
- 会社法施行令
- 会社法規則(「会社法施行規則」)
- 計規(「会社計算規則」)
- 労働契約承継法(「会社分割に伴う労働契約の承継等に関する法律」)
- 労働契約承継法規則(「会社分割に伴う労働契約の承継等に関する法律施行規則」)
- 労働契約承継法指針(「分割会社及び承継会社等が講ずべき当該分割会社が締結している労働契約及び労働協約の承継に関する措置の適切な実施を図るための指針」(平成12年労働省告示第127号))|≫掲載ページ(厚労省HP)
- 労働契約承継法Q&A(「会社分割・事業譲渡・合併における労働者保護のための手続に関するQ&A」〔平成28年12月時点〕)|≫掲載ページ(厚労省HP)
- 金融商品取引法(≫法律情報/英文)
- 民法(≫法律情報/英文)
参考文献
当サイトではアフィリエイトプログラムを利用して商品・サービスを記載しています