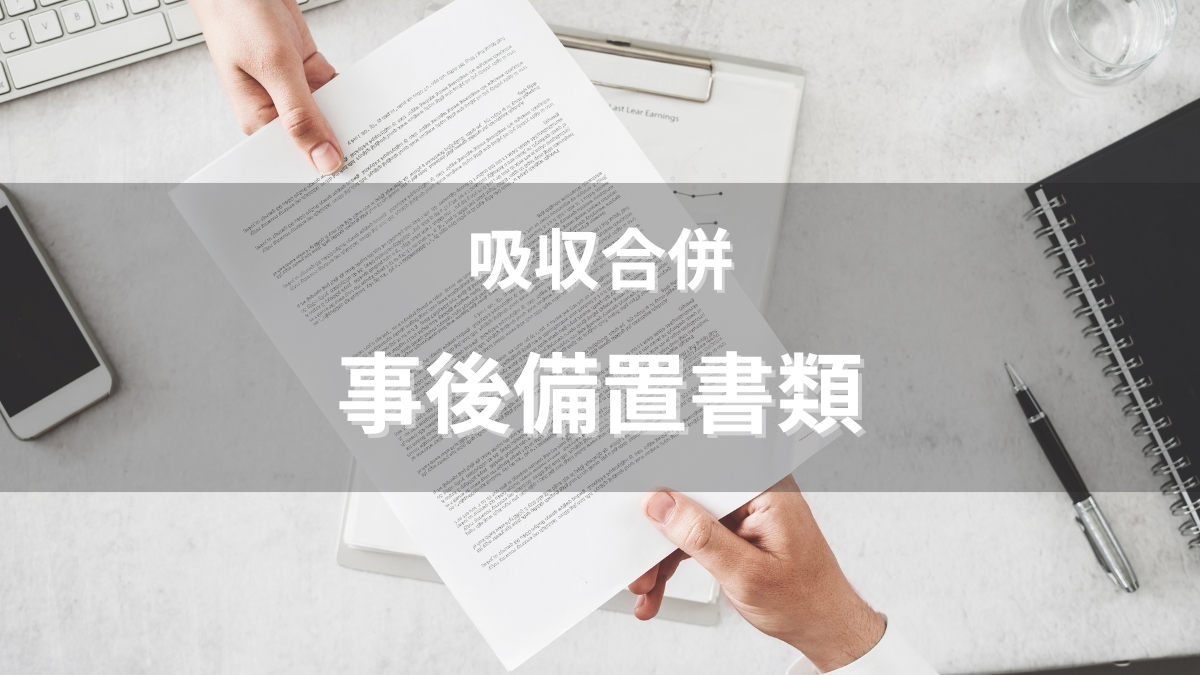今回は、組織再編ということで、吸収合併における合併契約について見てみたいと思います。
ではさっそく。なお、引用部分の太字、下線、改行などは管理人によるものです。
メモ
このカテゴリーでは、インハウスとしての法務経験からピックアップした、管理人の独学や経験の記録を綴っています。
ネット上の読み物としてざっくばらんに書いており、感覚的な理解を掴むことを目指していますが、書籍などを理解する際の一助になれば幸いです。
合併契約の締結
吸収合併をする場合、合併当事会社(消滅会社と存続会社)は、吸収合併締約を締結しなければなりません。
▽会社法748条
(合併契約の締結)
第七百四十八条 会社は、他の会社と合併をすることができる。この場合においては、合併をする会社は、合併契約を締結しなければならない。
合併契約の法定記載事項
吸収合併契約には、法定記載事項が定められています。
▽会社法749条1項
(株式会社が存続する吸収合併契約)
第七百四十九条 会社が吸収合併をする場合において、吸収合併後存続する会社(以下この編において「吸収合併存続会社」という。)が株式会社であるときは、吸収合併契約において、次に掲げる事項を定めなければならない。
一~六 (略)
先に全体像を見ておくと、以下のとおりです。
以下、それぞれの事項を順に見てみます。
合併当事会社(1号)
これは、合併当事会社(=消滅会社と存続会社)の商号と住所です。
▽会社法749条1項1号(※【 】は管理人注)
【1号:合併当事会社】
一 株式会社である吸収合併存続会社(以下この編において「吸収合併存続株式会社」という。)及び吸収合併により消滅する会社(以下この編において「吸収合併消滅会社」という。)の商号及び住所
合併条件-株主への対価に関する事項(2号・3号)
これは、存続会社が消滅会社の株主に合併対価を交付する場合は、
- 合併対価の種類と数・額(または算定方法)
- 割当比率
が法定記載事項になっているということです。
合併対価の種類というのは、存続会社の株式、社債、新株予約権、新株予約権付社債、その他の財産(ex. 金銭や親会社株式)といった、合併対価の内容のことです。
合併対価の数・額というのは、合併対価の種類に応じ、具体的には、
- 合併対価が株式の場合
→株式の数(または算定方法) - 合併対価が社債の場合
→社債の種類と総額(または算定方法) - 合併対価が新株予約権の場合
→新株予約権の内容と数(または算定方法) - 合併対価が新株予約権付社債の場合
→社債部分につき上記2、新株予約権部分につき上記3 - 合併対価がその他の財産(ex. 金銭、親会社株式など)の場合
→財産の内容と数or額(または算定方法)
となっています。
割当比率は、合併の場合は合併比率といい、消滅会社の株式1株当たりどの程度の対価を割り当てるかということです。例えば、対価が株式の場合であれば、消滅会社の株式と存続会社の株式との交換比率であり、消滅会社の株式1株につき交付する存続会社の株式の割当比率を指します。
条文も確認してみます。
なお、条文で「交付するときは」と書かれているように、無対価の吸収合併も可能です。
▽会社法749条1項2号・3号(※【 】は管理人注)
【2号・3号:株主への対価に関する事項】
二 吸収合併存続株式会社が吸収合併に際して株式会社である吸収合併消滅会社(以下この編において「吸収合併消滅株式会社」という。)の株主又は持分会社である吸収合併消滅会社(以下この編において「吸収合併消滅持分会社」という。)の社員に対してその株式又は持分に代わる金銭等【=つまり合併対価】を交付するときは、当該金銭等についての次に掲げる事項
イ 当該金銭等が吸収合併存続株式会社の株式であるときは、当該株式の数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び種類ごとの数)又はその数の算定方法並びに当該吸収合併存続株式会社の資本金及び準備金の額に関する事項
ロ 当該金銭等が吸収合併存続株式会社の社債(新株予約権付社債についてのものを除く。)であるときは、当該社債の種類及び種類ごとの各社債の金額の合計額又はその算定方法
ハ 当該金銭等が吸収合併存続株式会社の新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを除く。)であるときは、当該新株予約権の内容及び数又はその算定方法
ニ 当該金銭等が吸収合併存続株式会社の新株予約権付社債であるときは、当該新株予約権付社債についてのロに規定する事項及び当該新株予約権付社債に付された新株予約権についてのハに規定する事項
ホ 当該金銭等が吸収合併存続株式会社の株式等以外の財産であるときは、当該財産の内容及び数若しくは額又はこれらの算定方法
三 前号に規定する場合には、吸収合併消滅株式会社の株主(吸収合併消滅株式会社及び吸収合併存続株式会社を除く。)又は吸収合併消滅持分会社の社員(吸収合併存続株式会社を除く。)に対する同号の金銭等の割当てに関する事項【=割当比率】
「合併対価の柔軟化」とは
合併対価の解説では「合併対価の柔軟化」というキーワードをよく見かけますが、これは要するに、昔からあったのは存続会社の株式を合併対価とする吸収合併だけれども、会社法制定後はそれ以外の財産を合併対価とすることも認められるようになったということです(財産と評価できるものであれば足り、特に制限がなくなった)。
上記の条文や他のキーワードとあわせて整理すると、ざっと以下のとおりです。
| 存続会社の株式 | 昔からある合併対価。上記2号イ参照 |
| 存続会社の社債 | 上記2号ロ参照 |
| 存続会社の新株予約権 | 上記2号ハ参照 |
| 存続会社の新株予約権付社債 | 上記2号ニ参照 |
| 金銭 | 上記2号ホ参照。金銭のみを対価とする合併は特に「交付金合併」と呼ばれる |
| 存続会社の親会社の株式 | 上記2号ホ参照。特に「三角合併」と呼ばれる |
なお、消滅会社が種類株式発行会社である場合には、
- ある種類株式の種類株主に対しては対価の割当てをしないとき
→その旨とその株式の種類 - 対価の割当てについて株式の種類ごとに異なる取扱いを行うとき
→その旨とその異なる取扱いの内容
が法定記載事項になっています(2項。消滅会社が種類株式発行会社である場合の特則)。
▽会社法749条2項(※【 】は管理人注)
2 前項に規定する場合において、吸収合併消滅株式会社が種類株式発行会社であるときは、吸収合併存続株式会社及び吸収合併消滅株式会社は、吸収合併消滅株式会社の発行する種類の株式の内容に応じ、同項第三号に掲げる事項【=割当てに関する事項】として次に掲げる事項を定めることができる。
一 ある種類の株式の株主に対して金銭等の割当てをしないこととするときは、その旨及び当該株式の種類
二 前号に掲げる事項のほか、金銭等の割当てについて株式の種類ごとに異なる取扱いを行うこととするときは、その旨及び当該異なる取扱いの内容
割当ての平等
また、割当比率については、消滅会社の株主の有する株式の数(種類株式発行会社にあっては各種類の株式の数)に応じて対価を交付することを内容としなければならないとされています(3項)。
▽会社法749条3項(※【 】は管理人注)
3 第一項に規定する場合には、同項第三号に掲げる事項【=割当てに関する事項】についての定めは、吸収合併消滅株式会社の株主(吸収合併消滅株式会社及び吸収合併存続株式会社並びに前項第一号の種類の株式の株主を除く。)の有する株式の数(前項第二号に掲げる事項についての定めがある場合にあっては、各種類の株式の数)に応じて金銭等を交付することを内容とするものでなければならない。
つまり、いわゆる株主平等原則(法109条1項)に従って合併対価を交付しなければならないということです。
合併条件-新株予約権者への対価に関する事項(4号・5号)
これは、消滅会社が新株予約権を発行している場合の話です。この場合、
- 対価の種類と数・額(または算定方法)
- 割当比率
が法定記載事項になっているということです。
これは、消滅会社の新株予約権は吸収合併の効力発生日に消滅するため(法750条4項)、その新株予約権者に対して対価(新株予約権または金銭)を交付する必要があるということです。存続会社が消滅会社の新株予約権を実質的に承継するというイメージです。
具体的には、
- 対価が新株予約権の場合
→新株予約権の内容と数(または算定方法) - 対価が新株予約権付社債に付された新株予約権の場合
→存続会社が社債に係る債務を承継する旨、並びに、社債の種類と総額(または算定方法) - 対価が金銭の場合
→金額(または算定方法)
となっています。上記2の前半部分はつまり、社債部分を存続会社が承継するということです。
条文も確認してみます。
▽会社法749条1項4号・5号(※【 】は管理人注)
【4号・5号:新株予約権者への対価に関する事項】
四 吸収合併消滅株式会社が新株予約権を発行しているときは、吸収合併存続株式会社が吸収合併に際して当該新株予約権の新株予約権者に対して交付する当該新株予約権に代わる当該吸収合併存続株式会社の新株予約権又は金銭についての次に掲げる事項
イ 当該吸収合併消滅株式会社の新株予約権の新株予約権者に対して吸収合併存続株式会社の新株予約権を交付するときは、当該新株予約権の内容及び数又はその算定方法
ロ イに規定する場合において、イの吸収合併消滅株式会社の新株予約権が新株予約権付社債に付された新株予約権であるときは、吸収合併存続株式会社が当該新株予約権付社債についての社債に係る債務を承継する旨並びにその承継に係る社債の種類及び種類ごとの各社債の金額の合計額又はその算定方法
ハ 当該吸収合併消滅株式会社の新株予約権の新株予約権者に対して金銭を交付するときは、当該金銭の額又はその算定方法
五 前号に規定する場合には、吸収合併消滅株式会社の新株予約権の新株予約権者に対する同号の吸収合併存続株式会社の新株予約権又は金銭の割当てに関する事項【=割当比率】
▽会社法750条4項
4 吸収合併消滅株式会社の新株予約権は、効力発生日に、消滅する。
存続会社の資本金・準備金の額に関する事項(2号イ後段)
これは、合併対価が存続会社の株式である場合(先ほど見た2号イ)は、存続会社の資本金及び準備金の額に関する事項が法定記載事項になっているということです。
▽会社法749条1項2号(※【 】は管理人注)※再掲
【2号:資本金・準備金の額(2号イ後段)】
イ 当該金銭等【=合併対価】が吸収合併存続株式会社の株式であるときは、当該株式の数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び種類ごとの数)又はその数の算定方法並びに当該吸収合併存続株式会社の資本金及び準備金の額に関する事項
なお、必ずしも増加する確定額を記載する必要はなく、適用される会社計算規則の規定に従う旨の記載でもよいと解されています(吸収合併の場合、法445条5項→計規35条・36条)。
合併の効力発生日(6号)
最後は、合併の効力発生日です。
▽会社法749条1項6号(※【 】は管理人注)
【6号:合併の効力発生日】
六 吸収合併がその効力を生ずる日(以下この節において「効力発生日」という。)
合併契約の任意的記載事項
以上のほかにも、合併契約において、法定記載事項以外の事項(任意的記載事項)を記載することもできます。
例えば、無対価での吸収合併の場合、”対価を交付しない旨”は法定記載事項ではないので(先ほど見たように、条文は「交付するときは」と書かれている)、合併契約書に記載する義務はありませんが、明確化の観点から記載することが多いかと思います。
無対価での吸収合併は、完全親会社が完全子会社を吸収合併する場合や、完全子会社同士が吸収合併する場合などが典型的なケースになります。純粋なグループ内再編の場合はよくあることと思います。
合併契約とサイドレター
さらに、任意的記載事項を、合併契約書と結びついた別の合意書として作成するケースもあります(いわゆるサイドレター)。
例えば表明保証などが考えられますが、ただ、吸収合併の場合は、相手会社である消滅会社が文字どおり消えてしまう(存続会社と合体する)という性質上、例えば補償請求の定めをしても意味がないので、事後のリスク管理の部分は役に立たない(事前のリスク管理の部分は役に立つ)という面があります。
ちなみに、これに対して、吸収分割の場合は、実質的には事業譲渡に似てきますので、いわゆる一般的なM&A契約書で見かけるような分厚い内容のサイドレターを作成するケースがあります。サイドレターとはいっても、見た目上のメインの契約書はサイドレターの方のような感じになります。
この場合も、基本的な構成は株式譲渡契約書(SPA)等と共通しますので、結局そちらで見るような内容と組み合わせて検討していくことになります。
▽関連カテゴリ(SPA等)
-

-
M&A - 法律ファンライフ
houritsushoku.com
結び
今回は、組織再編ということで、吸収合併における合併契約について見てみました。
[注記]
本記事を含む一連の勉強記事は、過去の自分に向けて、①自分の独学や経験の記録を見せる、②感覚的な理解を伝えることを優先する、③細かく正確な理解は書物に譲る、ということをコンセプトにした読みものです。ベテランの方が見てなるほどと思うようなことは書かれていないほか、業務上必要であるときなど、正確な内容については別途ご確認ください。また、法改正をはじめとした最新の情報を反映しているとは限りませんので、ご注意ください。
組織再編に関するその他の記事(≫Read More)
主要法令等・参考文献
主要法令等
リンクをクリックすると、法令データ提供システム等に遷移します
- 会社法(≫法律情報/英文)
- 会社法施行令
- 会社法規則(「会社法施行規則」)
- 計規(「会社計算規則」)
- 労働契約承継法(「会社分割に伴う労働契約の承継等に関する法律」)
- 労働契約承継法規則(「会社分割に伴う労働契約の承継等に関する法律施行規則」)
- 労働契約承継法指針(「分割会社及び承継会社等が講ずべき当該分割会社が締結している労働契約及び労働協約の承継に関する措置の適切な実施を図るための指針」(平成12年労働省告示第127号))|≫掲載ページ(厚労省HP)
- 労働契約承継法Q&A(「会社分割・事業譲渡・合併における労働者保護のための手続に関するQ&A」〔平成28年12月時点〕)|≫掲載ページ(厚労省HP)
- 金融商品取引法(≫法律情報/英文)
- 民法(≫法律情報/英文)
当サイトではアフィリエイトプログラムを利用して商品・サービスを記載しています
参考文献