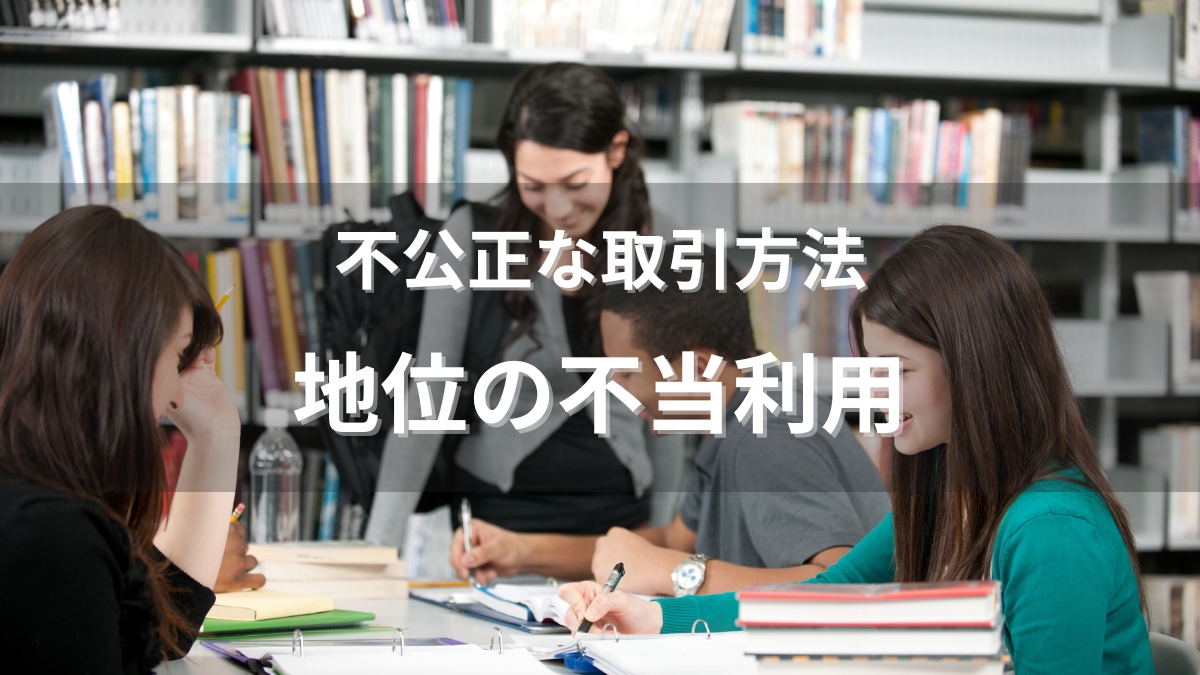今回は、独占禁止法ということで、企業結合審査について見てみたいと思います。
企業結合規制の類型については、前の記事に書いています。
-

-
独占禁止法を勉強しよう|企業結合規制
続きを見る
ではさっそく。なお、引用部分の太字、下線、改行などは管理人によるものです。
メモ
このカテゴリーでは、インハウスとしての法務経験からピックアップした、管理人の独学や経験の記録を綴っています。
ネット上の読み物としてざっくばらんに書いており、感覚的な理解を掴むことを目指していますが、書籍などを理解する際の一助になれば幸いです。
企業結合審査とは
企業結合審査とは、M&A(合併・買収)による企業結合で、一定の市場における競争が実質的に制限されることになるかどうかを公正取引委員会が審査することです。
企業結合審査に関する主な法令等は、以下のようになっています。
| 法律 | 公取規則 | 解釈・運用 |
|---|---|---|
| 独占禁止法 | ➢届出等規則 (「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第九条から第十六条までの規定による認可の申請、報告及び届出等に関する規則」) ➢意見聴取規則 (「公正取引委員会の意見聴取に関する規則」) ➢審査規則 (「公正取引委員会の審査に関する規則」) | ➢企業結合手続対応方針 (「企業結合審査の手続に関する対応方針」) |
企業結合審査に関しては、企業結合手続対応方針(「企業結合審査の手続に関する対応方針」)において、手続の流れや詳細が示されています。
以下、企業結合審査の流れ→届出基準→審査対象基準の順に見てみます。
企業結合審査の流れ
企業結合審査の大まかな流れは、
- 届出
↓ - 第1次審査
↓ - 第2次審査
↓ - (抵触する場合)問題解消措置や排除措置命令など
となっています。
▽企業結合手続対応方針 1
1 趣旨
公正取引委員会は、株式取得等(株式の取得、合併、共同新設分割、吸収分割、共同株式移転及び事業等の譲受けをいう。以下同じ。)の企業結合計画(以下「企業結合計画」という。)については、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)に基づく事前届出制を採っており、独占禁止法に定められた手続に従い、企業結合計画が一定の取引分野における競争を実質的に制限することとなるか否かについての審査(以下「企業結合審査」という。)を行っているところ、近年、企業結合審査の手続については、一層の迅速性及び透明性の向上が求められてきている。
(以下略)
01|届出(事前届出制)
届出というのは、上記で見たように、企業結合計画の事前届出制のことです。要するに、 一定規模以上の会社が株式取得などにより企業結合を行う際には、公正取引委員会に届出をする義務があります。
届出義務がある場合については、定型的な要件が独占禁止法に定められており(届出基準)、これに該当する場合は事前届出が必要になります。
▽公正取引委員会のXアカウント
【 #ひとこと講座 ⑫】
— 公正取引委員会 (@jftc) May 9, 2018
独占禁止法は競争を制限するような合併などの企業結合も規制対象としています。一定規模以上の会社が株式取得,合併,分割,共同株式移転,事業等の譲受けを行う際には公正取引委員会への事前届出が必要です。 #企業結合https://t.co/PgL2wwVnZv pic.twitter.com/acltHevTsS
届出前相談
なお、届出の前の相談という制度もあります(届出前相談)。公取委の考え方について、その時点での情報に基づき可能な範囲での説明を知ることができます。
▽企業結合手続対応方針 2
2 届出前相談
企業結合計画に関し、独占禁止法第10条第2項(同条第5項の規定によりみなして適用する場合を含む。)、第15条第2項、第15条の2第2項及び第3項、第15条の3第2項並びに第16条第2項の規定に基づく当委員会に対する届出を予定する会社(以下「届出予定会社」という。)は、当該届出を行う前に、当委員会に対し、当該企業結合計画に関する相談(以下「届出前相談」という。)を行うことができる。届出前相談において、届出予定会社は、届出書の記載方法等に関して相談することができる(届出前相談窓口は、別紙届出書提出先)(注1)。
(以下略)
02|審査(企業結合審査)
審査は、届出を受理したら行われる第1次審査と、その後の本格的な第2次審査に分かれます。
つまり、届出をしたらその全てが二次審査の対象になるというわけではありません
▽企業結合審査対応指針 3-⑴
⑴ 届出書の受理
企業結合計画に関し、当委員会に届出を行う会社(以下「届出会社」という。)が企業結合計画の届出書を当委員会に提出し、当委員会がこれを受理すると、当委員会は、第1次審査を開始する。
企業結合計画の届出書の様式及び届出に必要な書類については、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第9条から第16条までの規定による認可の申請、報告及び届出等に関する規則(昭和28年公正取引委員会規則第1号。以下「届出規則」という。)第2条の6、第5条、第5条の2、第5条の3及び第6条において規定されている。当委員会は、これらの規定に基づき提出された届出書を受理したときは、届出規則第7条第1項及び第2項に基づき、届出会社に対し届出受理書を交付する。
(注2)「第1次審査」とは、当委員会が、届出書を受理した後に行う企業結合審査であって、より詳細な審査が必要であるとして、届出会社に対し、独占禁止法第10条第9項(独占禁止法第15条第3項、第15条の2第4項、第15条の3第3項及び第16条第3項において読み替えて準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する必要な報告、情報又は資料の提出(以下「報告等」という。)の要請以降に行うものを除く企業結合審査をいう。また、報告等の要請以降に行う企業結合審査を「第2次審査」という。
審査の対象となるかどうかの判断基準(審査対象基準)は、「一定の取引分野」において「競争を実質的に制限することとなる」かどうかという見地から、企業結合規制の類型ごとに企業結合ガイドラインに示されています。
▽公正取引委員会のXアカウント
【#どっきんメモ -独禁法 #企業結合-】#独占禁止法 では,競争を制限することとなる企業結合を規制しているよ。
— 公正取引委員会 (@jftc) June 15, 2021
一定規模以上の会社が株式取得などで企業結合を行う際は,公取委に事前に届け出る必要があって,公取委は問題ないか審査するんだ。
過去の審査結果・届出基準→https://t.co/D31W4E5iYs pic.twitter.com/cjpkCNshsc
03|行政措置
審査の結果、違反する(=競争を実質的に制限する)と判定された場合は、問題解消措置や排除措置命令などが検討されることになります。
排除措置命令
企業結合規制についての排除措置命令の根拠条文は、法17条の2になります。
実体要件は、企業結合規制の類型に違反すること、手続要件は、私的独占/不当な取引制限/不公正な取引方法の禁止と同じように、第8章第2節に規定する手続に従うこととなっています。
▽法17条の2
第十七条の二 第十条第一項、第十一条第一項、第十五条第一項、第十五条の二第一項、第十五条の三第一項、第十六条第一項又は前条の規定に違反する行為があるときは、公正取引委員会は、第八章第二節に規定する手続に従い、事業者に対し、株式の全部又は一部の処分、事業の一部の譲渡その他これらの規定に違反する行為を排除するために必要な措置を命ずることができる。
② 第九条第一項若しくは第二項、第十三条、第十四条又は前条の規定に違反する行為があるときは、公正取引委員会は、第八章第二節に規定する手続に従い、当該違反行為者に対し、株式の全部又は一部の処分、会社の役員の辞任その他これらの規定に違反する行為を排除するために必要な措置を命ずることができる。
問題解消措置
問題解消措置(=競争の実質的制限を解消する措置)については、以下のとおり企業結合ガイドラインに記載があります。
▽企業結合ガイドライン 第7-1
第7 競争の実質的制限を解消する措置
1 基本的な考え方
企業結合が一定の取引分野における競争を実質的に制限することとなる場合においても、当事会社が一定の適切な措置を講じることにより、その問題を解消することができる場合がある(以下、このような措置を「問題解消措置」という。)。
問題解消措置としてどのような措置が適切かは、個々の企業結合に応じて、個別具体的に検討されるべきものであるが、問題解消措置は、事業譲渡等構造的な措置が原則であり、当事会社グループが価格等をある程度自由に左右することができないように、企業結合によって失われる競争を回復することができるものであることが基本となる。ただし、技術革新等により市場構造の変動が激しい市場においては、一定の行動に関する措置を採ることが妥当な場合も考えられる。
また、問題解消措置は、原則として、当該企業結合が実行される前に講じられるべきものである。
やむを得ず、当該企業結合の実行後に問題解消措置を講じることとなる場合には、問題解消措置を講じる期限が適切かつ明確に定められていることが必要である。また、例えば、問題解消措置として事業部門の全部又は一部の譲渡を行う場合には、当該企業結合の実行前に譲受先等が決定していることが望ましく、そうでないときには、譲受先等について公正取引委員会の事前の了解を得ることが必要となる場合がある。
(以下略)
企業結合審査のフローチャート
企業結合手続対応方針の最後の部分に、審査の流れをフローチャートで示したものがあり、まとめとしてわかりやすいのでおすすめです。
届出基準
届出基準は、以下で見るように、独占禁止法の条文に規定されています。
01|株式保有の制限
国内売上高合計額(企業結合集団内の会社等の国内売上高の合計額)が200億円を超える会社が、株式発行会社及びその子会社の国内売上高の合計額が50億円を超える会社の株式に係る議決権を20%又は50%を超えて取得する場合、事前に公正取引委員会に届け出る必要があります(法10条2項等)。
届出が受理されてから30日を経過するまで、その会社は株式を取得することができません(法10条8項)。
▽法10条2項・8項
② 会社であつて、その国内売上高(国内において供給された商品及び役務の価額の最終事業年度における合計額として公正取引委員会規則で定めるものをいう。以下同じ。)と当該会社が属する企業結合集団(会社及び当該会社の子会社並びに当該会社の親会社であつて他の会社の子会社でないもの及び当該親会社の子会社(当該会社及び当該会社の子会社を除く。)から成る集団をいう。以下同じ。)に属する当該会社以外の会社等(会社、組合(外国における組合に相当するものを含む。以下この条において同じ。)その他これらに類似する事業体をいう。以下この条において同じ。)の国内売上高を公正取引委員会規則で定める方法により合計した額(以下「国内売上高合計額」という。)が二百億円を下回らない範囲内において政令で定める金額を超えるもの(以下この条において「株式取得会社」という。)は、他の会社であつて、その国内売上高と当該他の会社の子会社の国内売上高を公正取引委員会規則で定める方法により合計した額が五十億円を下回らない範囲内において政令で定める金額を超えるもの(以下この条において「株式発行会社」という。)の株式の取得をしようとする場合(金銭又は有価証券の信託に係る株式について、自己が、委託者若しくは受益者となり議決権を行使することができる場合又は議決権の行使について受託者に指図を行うことができる場合において、受託者に株式発行会社の株式の取得をさせようとする場合を含む。)において、当該株式取得会社が当該取得の後において所有することとなる当該株式発行会社の株式に係る議決権の数と、当該株式取得会社の属する企業結合集団に属する当該株式取得会社以外の会社等(第四項において「当該株式取得会社以外の会社等」という。)が所有する当該株式発行会社の株式に係る議決権の数とを合計した議決権の数の当該株式発行会社の総株主の議決権の数に占める割合が、百分の二十を下回らない範囲内において政令で定める数値(複数の数値を定めた場合にあつては、政令で定めるところにより、それぞれの数値)を超えることとなるときは、公正取引委員会規則で定めるところにより、あらかじめ当該株式の取得に関する計画を公正取引委員会に届け出なければならない。ただし、あらかじめ届出を行うことが困難である場合として公正取引委員会規則で定める場合は、この限りでない。
⑧ 第二項の規定による届出を行つた会社は、届出受理の日から三十日を経過するまでは、当該届出に係る株式の取得をしてはならない。ただし、公正取引委員会は、その必要があると認める場合には、当該期間を短縮することができる。
▽公正取引委員会のXアカウント
【#どっきんメモ -独禁法 企業結合-】
— 公正取引委員会 (@jftc) January 31, 2024
独占禁止法では、競争を制限することとなる企業結合を規制しているよ。
一定規模以上の会社が株式取得や合併等の企業結合を行う際は、公取委に事前に届け出る必要があって、公取委は問題ないか審査するんだ!
過去の審査結果・届出基準→ https://t.co/D31W4DOfWs pic.twitter.com/HbMdzTrc31
02|役員兼任の制限
役員兼任の制限については、届出義務はありません。
03|合併の制限
国内売上高合計額が200億円を超える会社と国内売上高合計額が50億円を超える会社が合併する場合、事前に公正取引委員会に届け出る必要があります(法15条2項)。
届出が受理されてから30日を経過するまで、その会社は合併をすることができません(法15条3項)。
▽法15条2項・3項
② 会社は、合併をしようとする場合において、当該合併をしようとする会社(以下この条において「合併会社」という。)のうち、いずれか一の会社に係る国内売上高合計額が二百億円を下回らない範囲内において政令で定める金額を超え、かつ、他のいずれか一の会社に係る国内売上高合計額が五十億円を下回らない範囲内において政令で定める金額を超えるときは、公正取引委員会規則で定めるところにより、あらかじめ当該合併に関する計画を公正取引委員会に届け出なければならない。ただし、すべての合併会社が同一の企業結合集団に属する場合は、この限りでない。
③ 第十条第八項から第十四項までの規定は、前項の規定による届出に係る合併の制限及び公正取引委員会がする第十七条の二第一項の規定による命令について準用する。…(略)…。
▽公正取引委員会のXアカウント
【#どっきんメモ -独禁法 #企業結合-】#独占禁止法 では,競争を制限することとなる企業結合を規制しているよ。
— 公正取引委員会 (@jftc) July 1, 2021
一定規模以上の会社が株式取得や合併等の企業結合を行う際は,公取委に事前に届け出る必要があって,公取委は問題ないか審査するんだ。
過去の審査結果・届出基準→https://t.co/D31W4E5iYs pic.twitter.com/UbXJ4GE1uv
04|会社分割の制限
次のような会社分割を行う場合、事前に公正取引委員会に届け出る必要があります(法15条の2)。
共同新設分割の場合(2項)
- 分割の対象が事業の全部であって、当事会社中に国内売上高合計額が200億円を超える会社と国内売上高合計額が50億円を超える会社がある場合
- 分割の対象が事業の重要部分であって、当事会社中に対象部分の国内売上高が100億円を超える会社と対象部分の国内売上高が30億円を超える会社がある場合
- 分割の対象が事業の全部又は事業の重要部分であって、当事会社中に国内売上高合計額が200億円を超える会社と対象部分の国内売上高が30億円を超える会社がある場合又は当事会社中に対象部分の国内売上高が100億円を超える会社と国内売上高合計額が50億円を超える会社がある場合
吸収分割の場合(3項)
- 分割によって事業を承継しようとする会社の国内売上高合計額が50億円を超える場合で、国内売上高合計額が200億円を超える会社から事業の全部を承継するとき又は対象部分の国内売上高が100億円を超える会社から事業の重要部分を承継するとき
- 分割によって事業を承継しようとする会社の国内売上高合計額が200億円を超える場合で、国内売上高合計額が50億円を超える会社から事業の全部を承継するとき又は対象部分の国内売上高が30億円を超える会社から事業の重要部分を承継するとき
条文は、法15条の2第2項・第3項になります。
届出が受理されてから30日を経過するまで、その会社は会社分割をすることができません(第4項)。
▽法15条の2第2項~第4項
② 会社は、共同新設分割をしようとする場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、公正取引委員会規則で定めるところにより、あらかじめ当該共同新設分割に関する計画を公正取引委員会に届け出なければならない。ただし、すべての共同新設分割をしようとする会社が同一の企業結合集団に属する場合は、この限りでない。
一~四 (略)
③ 会社は、吸収分割をしようとする場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、公正取引委員会規則で定めるところにより、あらかじめ当該吸収分割に関する計画を公正取引委員会に届け出なければならない。ただし、すべての吸収分割をしようとする会社が同一の企業結合集団に属する場合は、この限りでない。
一~四 (略)
④ 第十条第八項から第十四項までの規定は、前二項の規定による届出に係る共同新設分割及び吸収分割の制限並びに公正取引委員会がする第十七条の二第一項の規定による命令について準用する。…(略)…。
05|共同株式移転の制限
国内売上高合計額が200億円を超える会社と国内売上高合計額が50億円を超える会社が共同株式移転をする場合、事前に公正取引委員会に届け出る必要があります(法15条の3第2項)。
届出が受理されてから30日を経過するまで、その会社は共同株式移転をすることができません(第3項)。
▽法15条の3第2項・第3項
② 会社は、共同株式移転をしようとする場合において、当該共同株式移転をしようとする会社のうち、いずれか一の会社に係る国内売上高合計額が二百億円を下回らない範囲内において政令で定める金額を超え、かつ、他のいずれか一の会社に係る国内売上高合計額が五十億円を下回らない範囲内において政令で定める金額を超えるときは、公正取引委員会規則で定めるところにより、あらかじめ当該共同株式移転に関する計画を公正取引委員会に届け出なければならない。ただし、すべての共同株式移転をしようとする会社が同一の企業結合集団に属する場合は、この限りでない。
③ 第十条第八項から第十四項までの規定は、前項の規定による届出に係る共同株式移転の制限及び公正取引委員会がする第十七条の二第一項の規定による命令について準用する。…(略)…。
06|事業譲受け等の制限
国内売上高合計額が200億円を超える会社が、国内売上高(単体)が30億円を超える会社から事業の全部を譲り受ける場合、又は譲受け対象部分の国内売上高が30億円を超える会社の事業等の重要部分を譲り受ける場合、事前に公正取引委員会に届け出る必要があります(法16条2項)。
届出が受理されてから30日を経過するまで、その会社は事業等を譲り受けることができません(3項)。
▽法16条2項・3項
② 会社であつて、その会社に係る国内売上高合計額が二百億円を下回らない範囲内において政令で定める金額を超えるものは、次の各号のいずれかに該当する場合には、公正取引委員会規則で定めるところにより、あらかじめ事業又は事業上の固定資産(以下この条において「事業等」という。)の譲受けに関する計画を公正取引委員会に届け出なければならない。ただし、事業等の譲受けをしようとする会社及び当該事業等の譲渡をしようとする会社が同一の企業結合集団に属する場合は、この限りでない。
一 国内売上高が三十億円を下回らない範囲内において政令で定める金額を超える他の会社の事業の全部の譲受けをしようとする場合
二 他の会社の事業の重要部分又は事業上の固定資産の全部若しくは重要部分の譲受けをしようとする場合であつて、当該譲受けの対象部分に係る国内売上高が三十億円を下回らない範囲内において政令で定める金額を超えるとき。
③ 第十条第八項から第十四項までの規定は、前項の規定による届出に係る事業等の譲受けの制限及び公正取引委員会がする第十七条の二第一項の規定による命令について準用する。…(略)…。
審査対象基準
審査の対象となるかどうかの具体的な判断基準は、独占禁止法に規定はなく、企業結合ガイドラインに示されています。
01|株式保有の制限
ガイドラインの判断基準を大まかに分けると、以下のとおりです。
審査の対象となる場合
▽企業結合ガイドライン 第1-1-⑴-ア
⑴ 会社の株式保有
ア 会社が他の会社の株式を保有することにより、株式を所有する会社(以下「株式所有会社」という。)と株式を所有される会社(以下「株式発行会社」という。)との間に結合関係が形成・維持・強化され、企業結合審査の対象となるのは、次のような場合である。
(ア) 株式発行会社の総株主の議決権に占める株式所有会社の属する企業結合集団(法第10条第2項に規定する企業結合集団をいう。以下同じ)に属する会社等が保有する株式に係る議決権を合計した議決権の割合が50%を超える場合。ただし、株式発行会社の総株主の議決権のすべてをその設立と同時に取得する場合は、通常、企業結合審査の対象とはならない(後記⑷ア参照)。
(イ) 株式発行会社の総株主の議決権に占める株式所有会社の属する企業結合集団に属する会社等が保有する株式に係る議決権を合計した議決権の割合が20%を超え、かつ、当該割合の順位が単独で第1位となる場合
審査の対象となりうる場合
▽企業結合ガイドライン 第1-1-⑴-イ
イ 前記ア以外の場合については、通常、企業結合審査の対象とはならない場合が多いと考えられるが、次に掲げる事項を考慮して結合関係が形成・維持・強化されるか否かを判断する。ただし、議決権保有比率(株式発行会社の総株主の議決権に占める株式所有会社の保有する株式に係る議決権の割合をいう。以下同じ。)が10%以下又は議決権保有比率の順位が第4位以下のときは、結合関係が形成・維持・強化されず、企業結合審査の対象とならない。
(ア) 議決権保有比率の程度
(イ) 議決権保有比率の順位、株主間の議決権保有比率の格差、株主の分散の状況その他株主相互間の関係
(ウ) 株式発行会社が株式所有会社の議決権を有しているかなどの当事会社相互間の関係
(エ) 一方当事会社の役員又は従業員が、他方当事会社の役員となっているか否かの関係
(オ) 当事会社間の取引関係(融資関係を含む。)
(カ) 当事会社間の業務提携、技術援助その他の契約、協定等の関係
(キ) 当事会社と既に結合関係が形成されている会社を含めた上記(ア)~(カ)の事項
審査の対象とならない場合
▽企業結合ガイドライン 第1-1-⑷
⑷ 企業結合審査の対象とならない株式保有
次のアの場合は、原則として、結合関係が形成・強化されるものではないので、通常、企業結合審査の対象とはならない。また、次のイの場合についても、原則として、結合関係が形成・強化されるものではないので、通常、企業結合審査の対象とはならない場合が多いと考えられるが、当事会社の属する企業結合集団に属する会社等以外の他の株主と当該企業結合集団に属する会社等との間に結合関係が形成・強化される場合には、その結合関係が企業結合審査の対象となる。
ア 株式発行会社の総株主の議決権のすべてをその設立と同時に取得する場合(前記(1)ア(ア)参照)
イ 株式所有会社と株式発行会社が同一の企業結合集団に属する場合
02|役員兼任の制限
ガイドラインの判断基準を大まかに分けると、以下のとおりです。
審査の対象となる場合
▽企業結合ガイドライン 第1-2-⑵-ア
⑵ 役員兼任による結合関係
ア 会社の役員又は従業員が他の一の会社の役員を兼任することにより、兼任当事会社間で結合関係が形成・維持・強化され、企業結合審査の対象となるのは、次の場合である。
(ア) 兼任当事会社のうちの1社の役員総数に占める他の当事会社の役員又は従業員の割合が過半である場合
(イ) 兼任する役員が双方に代表権を有する場合
審査の対象となりうる場合
▽企業結合ガイドライン 第1-2-⑵-イ
イ 前記ア以外の場合は、次に掲げる事項を考慮して、結合関係が形成・維持・強化されるか否かを判断する。
(ア) 常勤又は代表権のある取締役による兼任か否か
(イ) 兼任当事会社のうちの1社の役員総数に占める他の当事会社の役員又は従業員の割合
(ウ) 兼任当事会社間の議決権保有状況
(エ) 兼任当事会社間の取引関係(融資関係を含む。)、業務提携等の関係
審査の対象とならない場合
▽企業結合ガイドライン 第1-2-⑷
⑷ 企業結合審査の対象とならない役員兼任
ア 次の(ア)、(イ)のような場合は、原則として、結合関係が形成・維持・強化されるものではないので、通常、企業結合審査の対象とはならない。
(ア) 代表権のない者のみによる兼任であって、兼任当事会社のいずれにおいても役員総数に占める他の当事会社の役員又は従業員の割合が10%以下である場合
(イ) 議決権保有比率が10%以下の会社間における常勤取締役でない者のみによる兼任であって、兼任当事会社のいずれにおいても役員総数に占める他の当事会社の役員又は従業員の割合が25%以下である場合
イ 兼任当事会社が同一の企業結合集団に属する場合は、原則として、結合関係が形成・強化されるものではないので、通常、企業結合審査の対象とはならない場合が多いと考えられるが、当事会社の属する企業結合集団に属する会社等以外の他の株主と結合関係が形成・強化される場合には、その結合関係が企業結合審査の対象となる。
03|合併の制限
ガイドラインの判断基準を大まかに分けると、以下のとおりです。
合併自体が最も強固な結合方法であるため(他の会社を丸ごと飲み込む)、基本的には審査対象になるという書きぶりになっています。
基本的な考え方
▽企業結合ガイドライン 第1-3-⑴
⑴ 合併
合併の場合は、複数の会社が一つの法人として一体となるので、当事会社間で最も強固な結合関係が形成されることとなる。したがって、株式保有や役員兼任を通じて一定の結合関係がありながら、競争への影響をみる上では、結合関係がそれほど強くないことから問題ないとされた場合でも、合併により結合関係が強まり、問題とされる場合もあり得る。
審査の対象とならない場合
▽企業結合ガイドライン 第1-3-⑶
⑶ 企業結合審査の対象とならない合併
次のアの場合は、原則として、結合関係が形成・強化されるものではないので、通常、企業結合審査の対象とはならない。また、次のイの場合についても、原則として、結合関係が形成・強化されるものではないので、通常、企業結合審査の対象とはならない場合が多いと考えられるが、当事会社の属する企業結合集団に属する会社等以外の他の株主と結合関係が形成・強化される場合には、その結合関係が企業結合審査の対象となる。
ア 専ら株式会社を合名会社、合資会社、合同会社若しくは相互会社に組織変更し、合名会社を株式会社、合資会社若しくは合同会社に組織変更し、合資会社を株式会社、合名会社若しくは合同会社に組織変更し、合同会社を株式会社、合名会社若しくは合資会社に組織変更し、又は相互会社を株式会社に組織変更する目的で行う合併
イ すべての合併をしようとする会社が同一の企業結合集団に属する場合
04|会社分割の制限
ガイドラインの判断基準を大まかに分けると、以下のとおりです。
企業結合規制の対象となっている会社分割(共同新設分割と吸収分割)は、実質的には部分的な合併であるため、合併類似の考え方で判断されるという書きぶりになっています。
基本的な考え方
▽企業結合ガイドライン 第1-4-⑴
⑴ 共同新設分割・吸収分割
共同新設分割又は吸収分割の場合には、事業を承継させようとする会社の分割対象部分(事業の全部又は重要部分)が、事業を承継しようとする会社に包括的に承継されるので、競争に与える影響は合併に類似するものである。
また、共同新設分割又は吸収分割の場合において、事業を承継しようとする会社と当該会社の株式を割り当てられる会社との間に結合関係が形成・維持・強化され、企業結合審査の対象となるか否かは、前記1の考え方に従って判断されることになる。
審査の対象とならない場合
▽企業結合ガイドライン 第1-4-⑷
⑷ 企業結合審査の対象とならない分割
すべての共同新設分割又は吸収分割をしようとする会社が同一の企業結合集団に属する場合は、原則として、結合関係が形成・強化されるものではないので、通常、企業結合審査の対象とはならない場合が多いと考えられるが、当事会社の属する企業結合集団に属する会社等以外の他の株主と結合関係が形成・強化される場合には、その結合関係が企業結合審査の対象となる。
05|共同株式移転の制限
ガイドラインの判断基準を大まかに分けると、以下のとおりです。
共同株式移転は、持株会社が誕生しこれを通じた結合関係が形成されるものですが、合併類似の考え方で判断されるという書きぶりになっています。
基本的な考え方
▽企業結合ガイドライン 第1-5-⑴
⑴ 共同株式移転
共同株式移転は、新たに設立される会社が複数の会社の株式の全部を取得するので、合併と同様に、当事会社間で強固な結合関係が形成されることとなる。
したがって、株式保有や役員兼任を通じて一定の結合関係がありながら、競争への影響をみる上では、結合関係がそれほど強くないことから問題ないとされた場合でも、共同株式移転により結合関係が強まり、問題とされる場合もあり得る。
審査の対象とならない場合
▽企業結合ガイドライン 第1-5-⑶
⑶ 企業結合審査の対象とならない共同株式移転
すべての共同株式移転をしようとする会社が同一の企業結合集団に属する場合は、原則として、結合関係が形成・強化されるものではないので、通常、企業結合審査の対象とはならない場合が多いと考えられるが、当事会社の属する企業結合集団に属する会社等以外の他の株主と結合関係が形成・強化される場合には、その結合関係が企業結合審査の対象となる。
06|事業譲受け等の制限
ガイドラインの判断基準を大まかに分けると、以下のとおりです。
基本的な考え方
▽企業結合ガイドライン 第1-6-⑴
⑴ 事業等の譲受け
事業の全部譲受けは、譲渡会社の事業活動が譲受会社と一体化するという意味では、競争に与える影響は合併に類似するものであるが、譲受け後は譲渡会社と譲受会社との間につながりはないので、譲渡対象部分が譲受会社に新たに加わる点に着目すれば足りる。事業の重要部分の譲受け及び事業上の固定資産の譲受けについても、同様である。
審査の対象とならない場合
▽企業結合ガイドライン 第1-6-⑷
⑷ 企業結合審査の対象とならない事業等の譲受け
次のアの場合は、原則として、結合関係が形成・強化されるものではないので、通常、企業結合審査の対象とはならない。また、次のイの場合についても、原則として、結合関係が形成・強化されるものではないので、通常、企業結合審査の対象とはならない場合が多いと考えられるが、当事会社の属する企業結合集団に属する会社等以外の他の株主と結合関係が形成・強化される場合には、その結合関係が企業結合審査の対象となる。
ア 100%出資による分社化のために行われる事業又は事業上の固定資産の譲受け(以下「事業等の譲受け」という。)
イ 事業等の譲受けをしようとする会社と事業等の譲渡をしようとする会社が同一の企業結合集団に属する場合
結び
今回は、独占禁止法ということで、企業結合審査について見てみました。
なお、令和7年6月には「企業結合審査ガイドブック」というテキストも出来ていますので、これも参考になります。
▽公正取引委員会のXアカウント
【「この一冊で企業結合審査が大体分かる」ガイドブックができました!】
— 公正取引委員会 (@jftc) June 12, 2025
企業結合審査の概要はもちろんのこと、手続の流れなどを図を用いて分かりやすく、網羅的に解説しています。企業、弁護士、専門家の皆さまだけではなく、一般の方々も是非御覧ください!https://t.co/v62j09NjqF#ガイドブック pic.twitter.com/LIv99g0fnC
次の記事は、違反に対する措置(エンフォースメント)についてです。
-

-
独占禁止法を勉強しよう|違反に対する措置(エンフォースメント)-行政措置
続きを見る
[注記]
本記事を含む一連の勉強記事は、過去の自分に向けて、①自分の独学や経験の記録を見せる、②感覚的な理解を伝えることを優先する、③細かく正確な理解は書物に譲る、ということをコンセプトにした読みものです。ベテランの方が見てなるほどと思うようなことは書かれていないほか、業務上必要であるときなど、正確な内容については別途ご確認ください。また、法改正をはじめとした最新の情報を反映しているとは限りませんので、ご注意ください。
独占禁止法に関するその他の記事(≫Read More)
主要法令等・参考文献
主要法令等
リンクをクリックすると、法令データ提供システムまたは公正取引委員会HPに遷移します
- 独占禁止法(≫法律情報/英文)
- 排除型私的独占ガイドライン(「排除型私的独占に係る独占禁止法上の指針」)|公取委HP
- 一般指定(「不公正な取引方法」(昭和57年6月18日公正取引委員会告示第15号))|公取委HP
- 新聞特殊指定(「新聞業における特定の不公正な取引方法」(平成11年7月21日公正取引委員会告示第9号))|公取委HP
- 物流特殊指定(「特定荷主が物品の運送又は保管を委託する場合の特定の不公正な取引方法」(平成16年3月8日公正取引委員会告示第1号))|公取委HP
- 大規模小売業告示(「大規模小売業者による納入業者との取引における特定の不公正な取引方法」(平成17年5月13日公正取引委員会告示第11号))|公取委HP
- 不当廉売ガイドライン(「不当廉売に関する独占禁止法上の考え方」)|公取委HP
- 流通・取引慣行ガイドライン(「流通・取引慣行に関する独占禁止法の指針」)|公取委HP
- 優越的地位濫用ガイドライン(「優越的地位の濫用に関する独占禁止法上の考え方」)|公取委HP
- 役務委託優越的地位濫用ガイドライン(「役務の委託取引における優越的地位の濫用に関する独占禁止法上の指針」)|公取委HP
- 意見聴取規則(「公正取引委員会の意見聴取に関する規則」)
- 審査規則(「公正取引委員会の審査に関する規則」)
- 審査手続指針(「独占禁止法審査手続に関する指針」)|公取委HP
- 独禁法Q&A(「よくある質問コーナー(独占禁止法)」)|公取委HP
【企業結合規制関連】
- 届出等規則(「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第九条から第十六条までの規定による認可の申請、報告及び届出等に関する規則」)
- 企業結合ガイドライン(「企業結合審査に関する独占禁止法の運用指針」)|公取委HP
- 企業結合手続対応方針(「企業結合審査の手続に関する対応方針」)|公取委HP
【違反に対する措置(エンフォースメント)関連】
参考文献
リンクをクリックすると、Amazonのページまたは公正取引委員会HPに遷移します
- 独占禁止法〔第5版〕(菅久修一 編著、品川武、伊永大輔、鈴木健太 著)
- 注釈 独占禁止法(根岸哲 編)
- 優越的地位濫用ガイドブック(「優越的地位の濫用 ~知っておきたい取引ルール~」(公正取引委員会))|公取委HP(≫掲載ページ)
- 優越的地位の濫用規制に関する講習|公取委HP
当サイトではアフィリエイトプログラムを利用して商品・サービスを記載しています