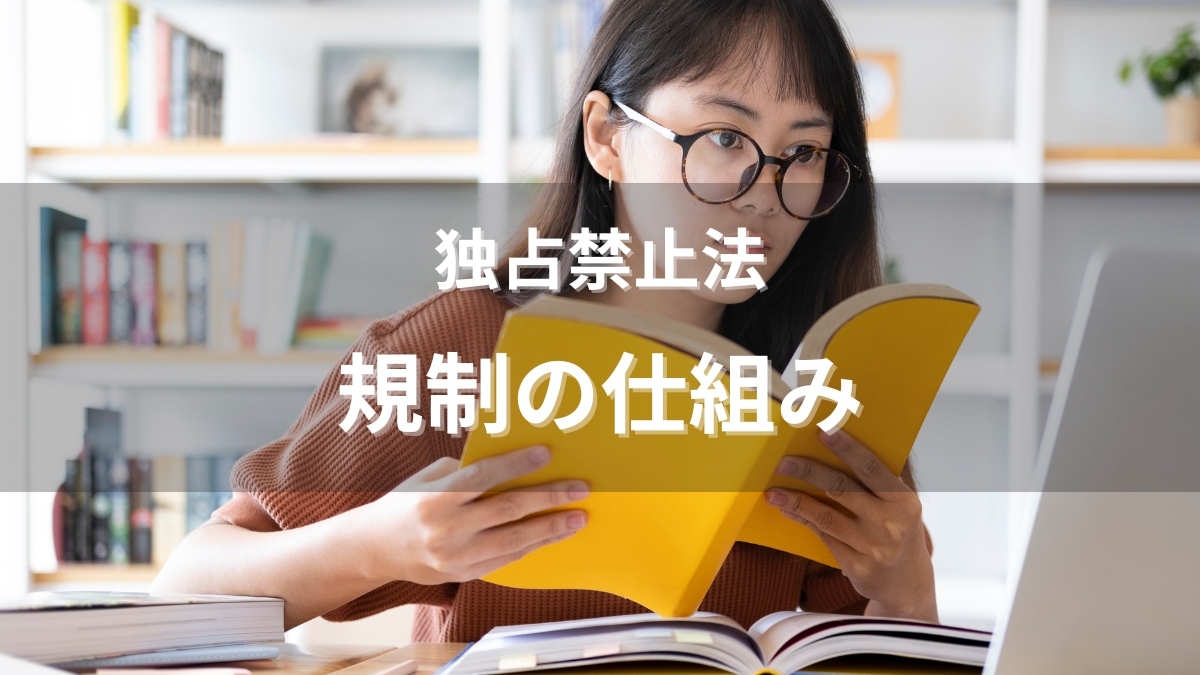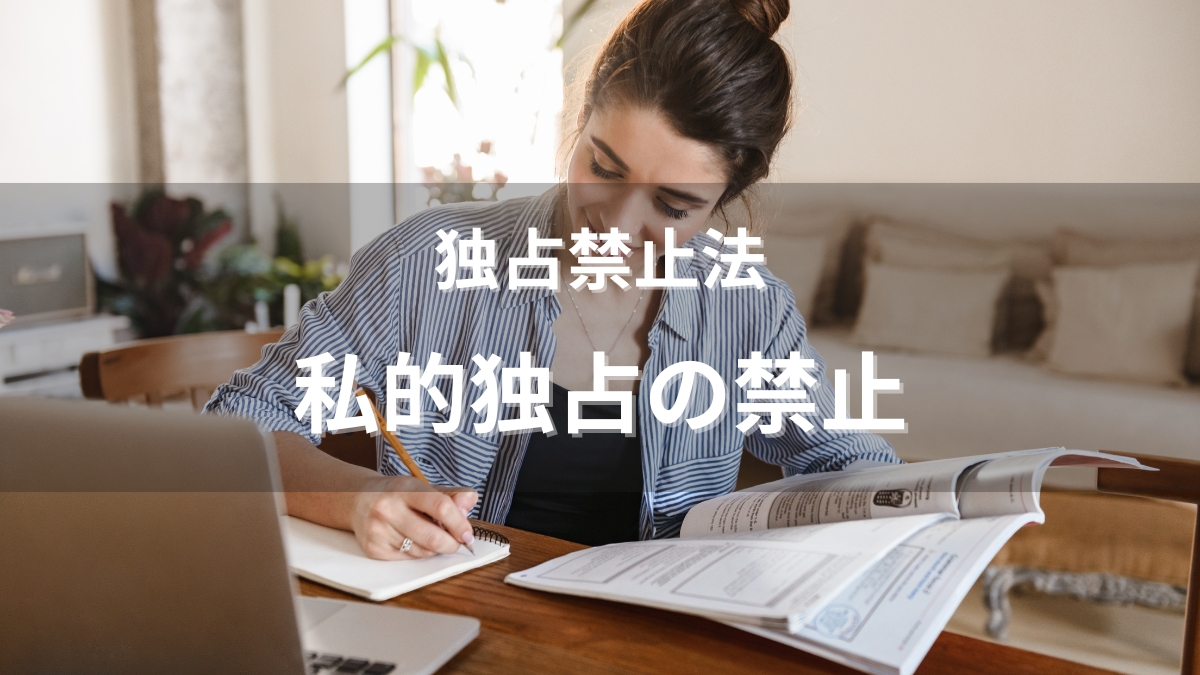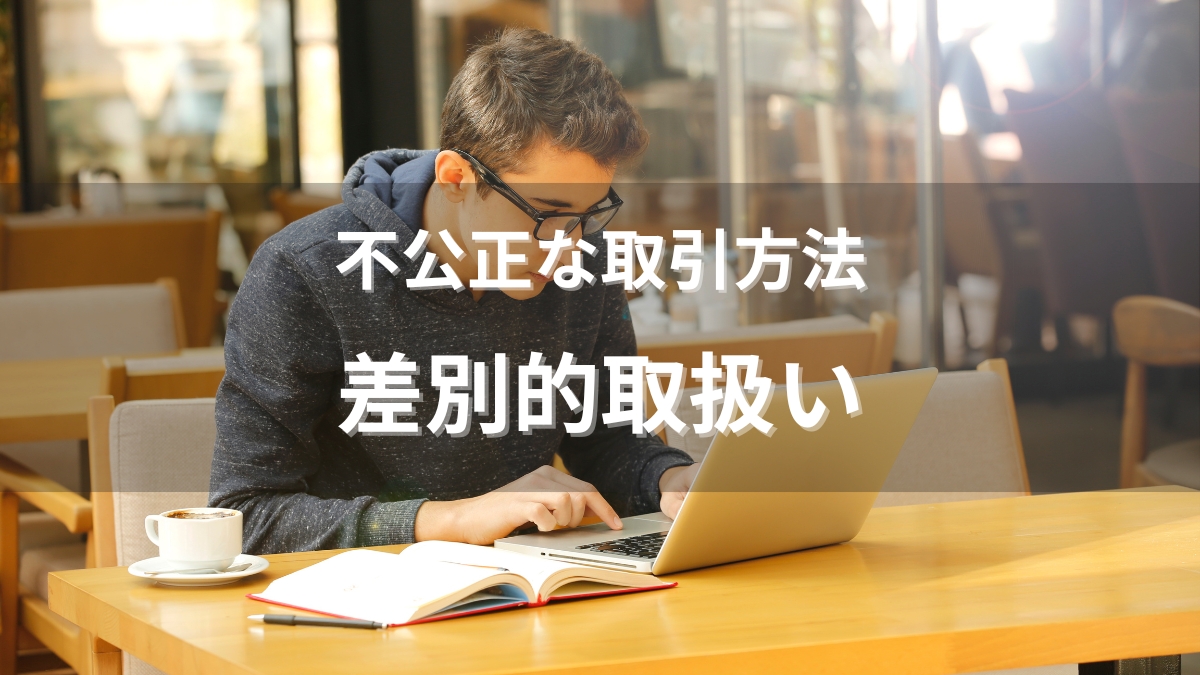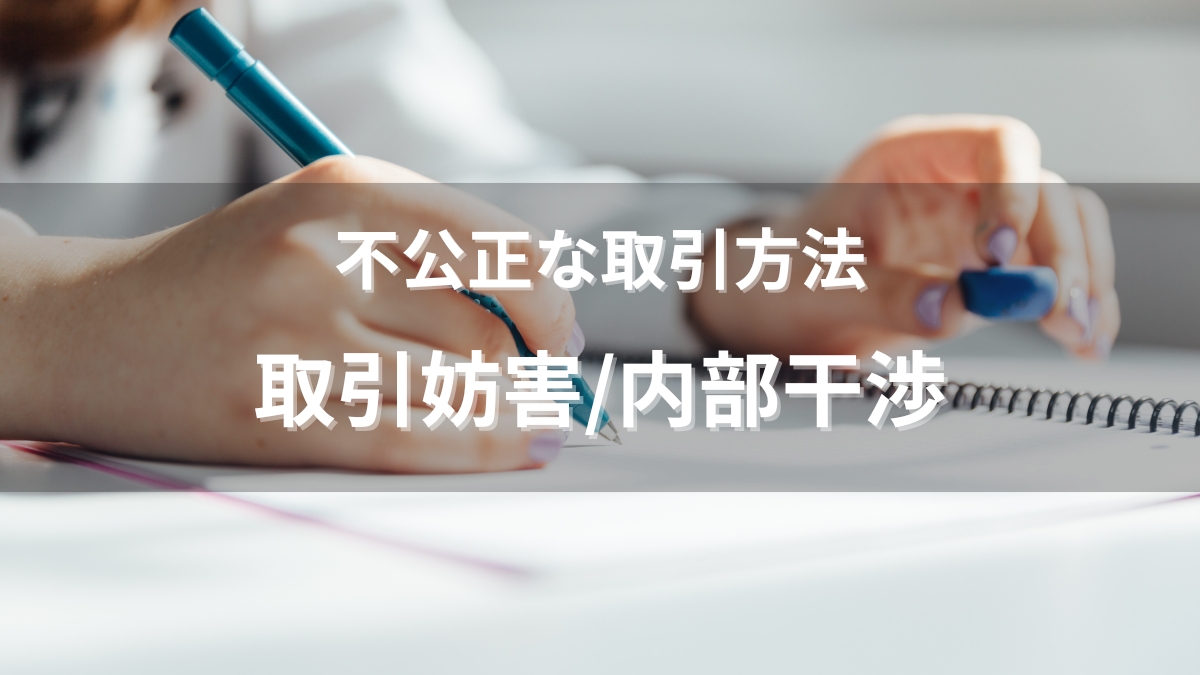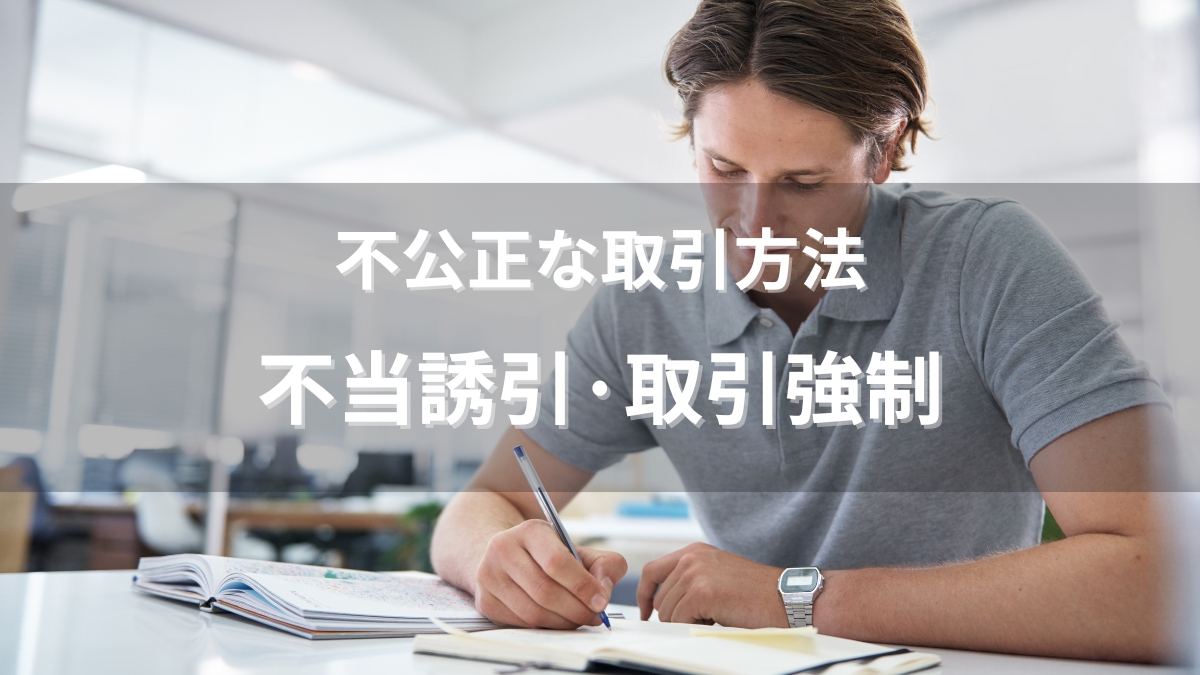今回は、独占禁止法を勉強しようということで、規制の仕組み(全体像)について見てみたいと思います。
ではさっそく。なお、引用部分の太字、下線、改行などは管理人によるものです。
メモ
このカテゴリーでは、インハウスとしての法務経験からピックアップした、管理人の独学や経験の記録を綴っています。
ネット上の読み物としてざっくばらんに書いており、感覚的な理解を掴むことを目指していますが、書籍などを理解する際の一助になれば幸いです。
独占禁止法を勉強する意味(私見)
最初から余談気味ですが、独占禁止法を勉強することになるときというのは、大体、以下2つのシチュエーションなのではないかなと思います(管理人の経験からの個人的見解)。
- 真正面から問題になるような企業(あるいはそういう業界)の場合は、真正面から必要
- そうでない場合でも、独占禁止法に連なる下請法と景品表示法は、企業一般に問題になるケースが多く(というかほとんど)、また、優越的地位の濫用についてはちょくちょく気になるケースに遭遇することがある
②の場合というのはつまり、こういうイメージです。
独占禁止法 ←優越的地位の濫用は一般条項的である故に微妙に遭遇する
┗ 下請法 ←これは一般的に問題になる(資本金によってはならないこともある)
┗ 景表法 ←これも一般的に問題になる
なので、独占禁止法を隅から隅まで見る必要があるというシチュエーションでなくても、下請法や景品表示法を見るときにその土台となっている素地としてとか、優越的地位の濫用などは見ておいた方がいいような気がします。
本記事では、法律の目的→規制の仕組み(行為規制と構造規制)→違反に対する措置という順で、独占禁止法の全体像をざっと見てみます。
法律の目的
まず法律の目的から見ていくと、目的を定める法1条は以下のように長い文章になっていますが、ひと言でいうと、「公正かつ自由な競争を促進」して「一般消費者の利益を確保」することになります。
▽独占禁止法1条
第一条 この法律は、私的独占、不当な取引制限及び不公正な取引方法を禁止し、事業支配力の過度の集中を防止して、結合、協定等の方法による生産、販売、価格、技術等の不当な制限その他一切の事業活動の不当な拘束を排除することにより、公正且つ自由な競争を促進し、事業者の創意を発揮させ、事業活動を盛んにし、雇傭及び国民実所得の水準を高め、以て、一般消費者の利益を確保するとともに、国民経済の民主的で健全な発達を促進することを目的とする。
目的規定の定め方というのは、一般的には、
「A」することにより「B」し、もって「C」することを目的とする。
※「A」は手段(規制の内容)
※「B」は直接の目的
※「C」は究極的な目的
というふうになっていますが、これになぞらえて読むと、
【手段】
〇私的独占、不当な取引制限及び不公正な取引方法を禁止し、事業支配力の過度の集中を防止して、結合、協定等の方法による生産、販売、価格、技術等の不当な制限その他一切の事業活動の不当な拘束を排除することにより、
【直接の目的】
〇公正且つ自由な競争を促進し、事業者の創意を発揮させ、事業活動を盛んにし、雇傭及び国民実所得の水準を高め、
【究極的な目的】
〇以て、一般消費者の利益を確保するとともに、国民経済の民主的で健全な発達を促進することを目的とする
となっています。
感覚的にいうと、自由な競争を促進するが、同時に(自由でありさえすればよいわけではなく)公正な競争でなければならない、というニュアンスかなと思います(管理人の理解の仕方)。
▽公正取引委員会のXアカウント
【#2024ひとこと講座 5 独禁法は何のためにある?】
— 公正取引委員会 (@jftc) April 11, 2024
独禁法は「公正かつ自由な競争の促進」を目的としています。
公正かつ自由な競争が行われることで、企業は、より安く、より良い商品を開発して成長します。
これにより、消費者も様々なメリットを受けられます。https://t.co/SoosxeXpra pic.twitter.com/4rdPnMWWqU
規制の仕組み
規制の内容は、大きく「行為規制」と「構造規制」の2つに分かれます。
行為規制
「行為規制」は、自由な競争を制限する行為と、公正な競争を阻害する行為を規制するもので、以下のような3本柱になっています。
行為規制(以下①~③の禁止)
- 私的独占
市場支配力のある事業者が、他の事業者を不当に支配して市場において競争が行われないようにすること - 不当な取引制限(カルテル等)
競争事業者間で、相互に事業活動を拘束し競争制限する協定・合意をすること - 不公正な取引方法
公正な競争を阻害するおそれがある取引方法
厳密に1対1で対応しているわけではないですが、法律の目的との対応関係でいうと、
- 自由な競争を促進
=自由な競争を制限またはおそれのある行為を規制
→①私的独占/②不当な取引制限の禁止 - 同時に、公正な競争でなければならない
=公正な競争を阻害する行為を規制
→③不公正な取引方法の禁止
という感じになるかと思います。
③の不公正な取引方法には、法定類型(2条9項2号~5号)と、公正な競争を阻害するおそれがある取引として公正取引委員会が指定するもの(指定類型。2条9項6号)とがあります。そして、指定類型には、全ての業種に適用される「一般指定」と、特定業種に適用される「特殊指定」があります。
一般指定は、大まかにいうと、①自由な競争を制限するおそれがあるような行為、②競争手段そのものが公正とはいえない行為、③大企業が優越的な地位を利用して取引相手に無理な要求を押しつける行為の3つのグループに分けることができます。
以上を表でまとめると、行為規制の全体イメージは以下のような感じになります。
行為規制の全体イメージ
| 法律の目的との関係 | 行為規制の3本柱(1⃣~3⃣) | 備考 | ||
| 自由な競争を制限する行為 | 1⃣ 私的独占の禁止 | |||
| 2⃣ 不当な取引制限の禁止 | ||||
| 公正な競争を阻害する行為(フェアプレーでないもの) | 3⃣ 不公正な取引方法の禁止 | 法定類型+一般指定 | ①自由な競争を制限するおそれがあるような行為 ➢取引拒絶 ➢差別価格 ➢不当廉売 ➢再販売価格拘束 |
|
| ②競争手段そのものが公正とはいえない行為 ➢欺瞞的顧客誘引 ➢不当利益顧客誘引(過大な景品) ➢抱き合わせ販売 |
景品表示法はこの関連 | |||
| ③大企業が優越的な地位を利用して取引相手に無理な要求を押しつける行為 ➢優越的地位の濫用 |
下請法はこの関連 | |||
| 特殊指定 | a. 新聞業(新聞特殊指定) b. 特定荷主が行う不公正な取引方法(物流特殊指定) c. 大規模小売業者が行う不公正な取引方法(大規模小売業告示) |
|||
また、行為規制に関する主なガイドライン(=行政解釈・運用)には、たとえば以下のようなものがあります。
- 排除型私的独占ガイドライン(「排除型私的独占に係る独占禁止法上の指針」)
- 不当廉売ガイドライン(「不当廉売に関する独占禁止法上の考え方」)
- 流通・取引慣行ガイドライン(「流通・取引慣行に関する独占禁止法の指針」)
- 優越的地位濫用ガイドライン(「優越的地位の濫用に関する独占禁止法上の考え方」)
行為規制の3本柱については、以下の関連記事にくわしく書いています。
構造規制
「構造規制」というと何かイメージしにくいですが、いわゆる企業結合規制のことで、競争を制限することとなるような企業の組織変更を規制するものです。
独占禁止法が規制する企業結合の類型は、7類型(①株式保有、②役員の兼任、③合併、④会社分割、⑤共同株式移転、⑥事業の譲受け、⑦事業の賃借等)になっています。
構造規制に関する主なガイドラインには、たとえば以下のようなものがあります。
- 企業結合ガイドライン(「企業結合審査に関する独占禁止法の運用指針」)
- 企業結合手続対応方針(「企業結合審査の手続に関する対応方針」)
構造規制については、以下の関連記事にくわしく書いています。
違反に対する措置
違反に対する措置としては、行政・刑事・民事の3種類全てが存在します。
行政措置については、審査手続→(不服がある場合)審判請求→行政措置、という流れをたどります。独占禁止法に違反する競争制限的な行為や状態を将来に向けて排除するための「排除措置命令」と、課徴金を国庫に納付するよう命じる「課徴金納付命令」とがあります。
刑事罰については、公正取引委員会には訴追権はなく、公正取引委員会が告発することにより検察が刑事訴追します。
民事責任については、独禁法違反の被害者は、民法709条に基づき損害賠償請求できるのは当然として、公正取引委員会の排除措置命令が確定した場合に、無過失の損害賠償請求ができるようになっています(法25条、26条)。また、不公正な取引方法については、差止請求ができるようになっています(法24条)。
違反に対する措置の全体像は、表にすると以下のような感じになります。
違反に対する措置の全体像
| 措置・制裁 | 私的独占 | 不当な取引制限 (カルテル) | 不公正な取引方法 | |
|---|---|---|---|---|
| 行政措置 | 排除措置命令 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 課徴金納付命令 | 〇 | 〇 | 〇 (告示類型は除く) | |
| 刑事罰 | 違反者個人/違反企業/違反企業代表者 | 〇 | 〇 | |
| 民事責任 | 損害賠償請求 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 差止請求 | 〇 |
違反に対する措置については、以下の関連記事にくわしく書いています。
ガイドライン・パンフレット一覧
ここまでにいくつか抜粋しましたが、独占禁止法に関するガイドラインの一覧は、以下の公正取引委員会HPで見ることができます。
パンフレット一覧のページもあります。
学習の進め方
最後に余談ですが、全体をざっと学習していくときは、たとえば以下のようなイメージで進めていくのがいいのではないかと思います(管理人の個人的イメージ)。
**********
まず、独禁法の全体の仕組みとして、規制の仕組みと、基本概念をみる。そうすると、行為規制、構造規制、エンフォースメント(違反に対する措置)、という感じに分かれている。
行為規制には、①私的独占、②不当な取引制限、③不公正な取引方法の規制の3つがあり、これが行為規制の3本柱になっている。行為類型ごとに個別の「行為要件」(縦断的な要件)と、行為類型に共通する「効果要件」(横断的な要件)がある。
構造規制というのは、企業結合規制のことで、規制の内容と審査の仕組みをみる。
エンフォースメント(実現のための措置の意)としては、行政措置・刑事罰・民事責任の3種すべてがある。
**********
結び
今回は、独占禁止法を勉強しようということで、規制の仕組み(全体像)について見てみました。
ちなみに、独占禁止法には以下のような有名ブログがありますので、参考までご紹介しておきます。
-

-
独占禁止法を勉強しよう|基本概念
続きを見る
[注記]
本記事を含む一連の勉強記事は、過去の自分に向けて、①自分の独学や経験の記録を見せる、②感覚的な理解を伝えることを優先する、③細かく正確な理解は書物に譲る、ということをコンセプトにした読みものです。ベテランの方が見てなるほどと思うようなことは書かれていないほか、業務上必要であるときなど、正確な内容については別途ご確認ください。また、法改正をはじめとした最新の情報を反映しているとは限りませんので、ご注意ください。
独占禁止法に関するその他の記事(≫Read More)
主要法令等・参考文献
主要法令等
リンクをクリックすると、法令データ提供システムまたは公正取引委員会HPに遷移します
- 独占禁止法(≫法律情報/英文)
- 排除型私的独占ガイドライン(「排除型私的独占に係る独占禁止法上の指針」)|公取委HP
- 一般指定(「不公正な取引方法」(昭和57年6月18日公正取引委員会告示第15号))|公取委HP
- 新聞特殊指定(「新聞業における特定の不公正な取引方法」(平成11年7月21日公正取引委員会告示第9号))|公取委HP
- 物流特殊指定(「特定荷主が物品の運送又は保管を委託する場合の特定の不公正な取引方法」(平成16年3月8日公正取引委員会告示第1号))|公取委HP
- 大規模小売業告示(「大規模小売業者による納入業者との取引における特定の不公正な取引方法」(平成17年5月13日公正取引委員会告示第11号))|公取委HP
- 不当廉売ガイドライン(「不当廉売に関する独占禁止法上の考え方」)|公取委HP
- 流通・取引慣行ガイドライン(「流通・取引慣行に関する独占禁止法の指針」)|公取委HP
- 優越的地位濫用ガイドライン(「優越的地位の濫用に関する独占禁止法上の考え方」)|公取委HP
- 役務委託優越的地位濫用ガイドライン(「役務の委託取引における優越的地位の濫用に関する独占禁止法上の指針」)|公取委HP
- 意見聴取規則(「公正取引委員会の意見聴取に関する規則」)
- 審査規則(「公正取引委員会の審査に関する規則」)
- 審査手続指針(「独占禁止法審査手続に関する指針」)|公取委HP
- 独禁法Q&A(「よくある質問コーナー(独占禁止法)」)|公取委HP
【企業結合規制関連】
- 届出等規則(「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第九条から第十六条までの規定による認可の申請、報告及び届出等に関する規則」)
- 企業結合ガイドライン(「企業結合審査に関する独占禁止法の運用指針」)|公取委HP
- 企業結合手続対応方針(「企業結合審査の手続に関する対応方針」)|公取委HP
【違反に対する措置(エンフォースメント)関連】
参考文献
リンクをクリックすると、Amazonのページまたは公正取引委員会HPに遷移します
- 独占禁止法〔第5版〕(菅久修一 編著、品川武、伊永大輔、鈴木健太 著)
- 注釈 独占禁止法(根岸哲 編)
- 優越的地位濫用ガイドブック(「優越的地位の濫用 ~知っておきたい取引ルール~」(公正取引委員会))|公取委HP(≫掲載ページ)
- 優越的地位の濫用規制に関する講習|公取委HP
当サイトではアフィリエイトプログラムを利用して商品・サービスを記載しています