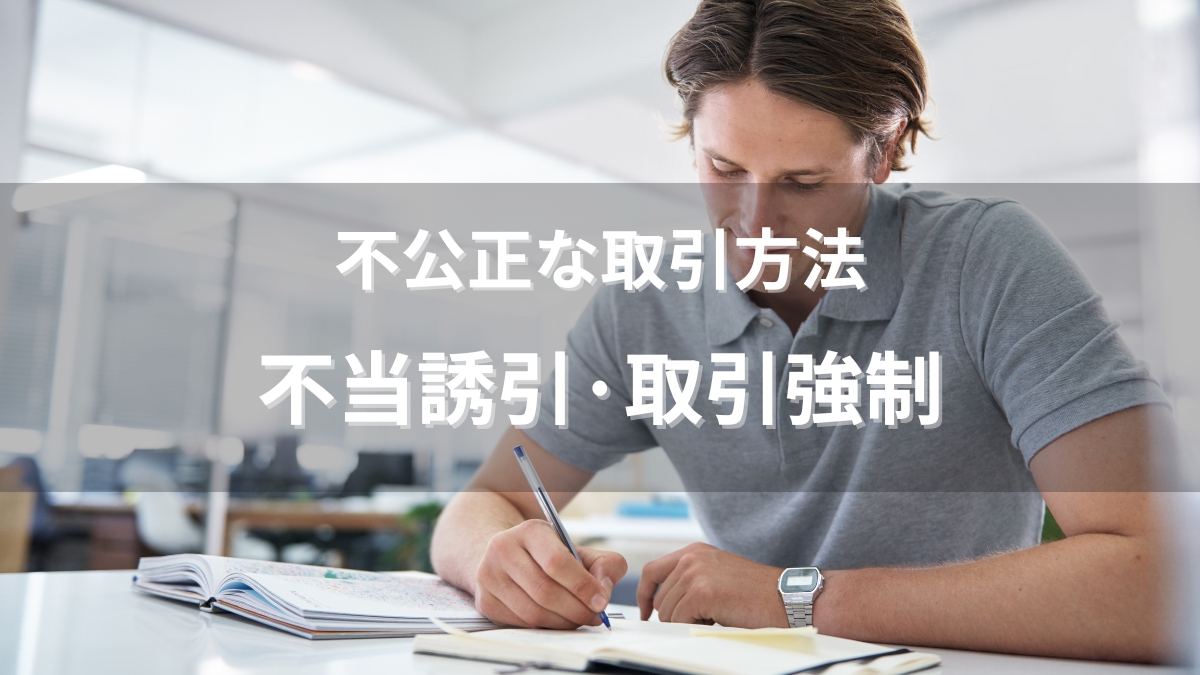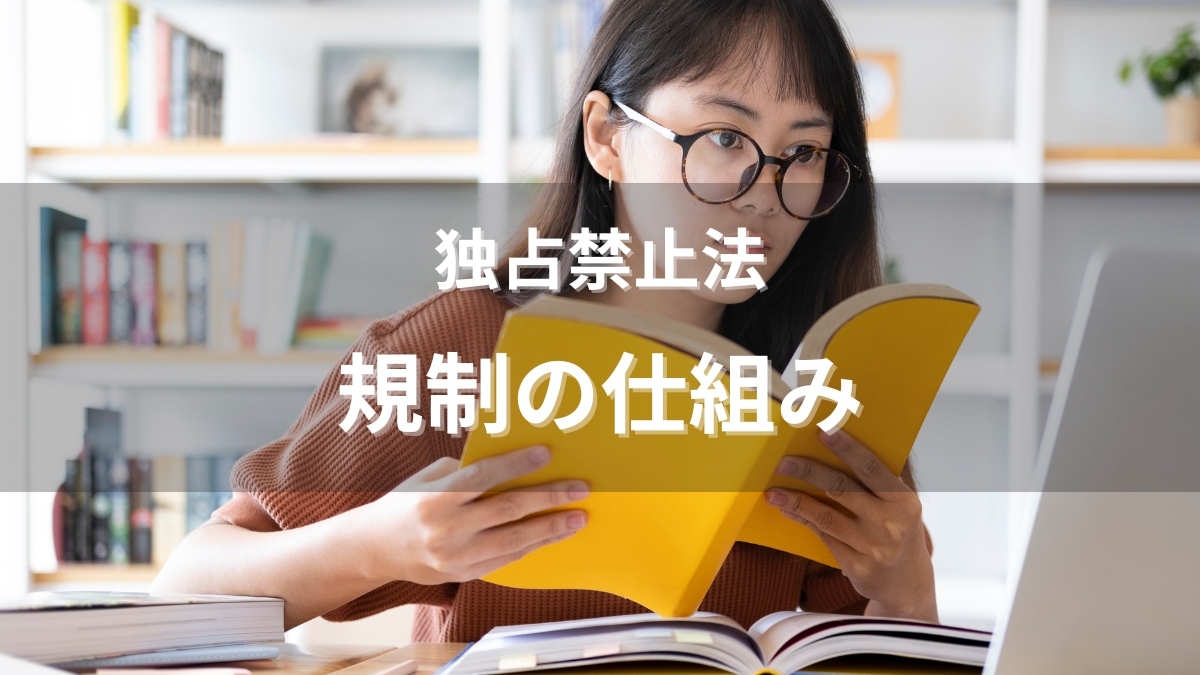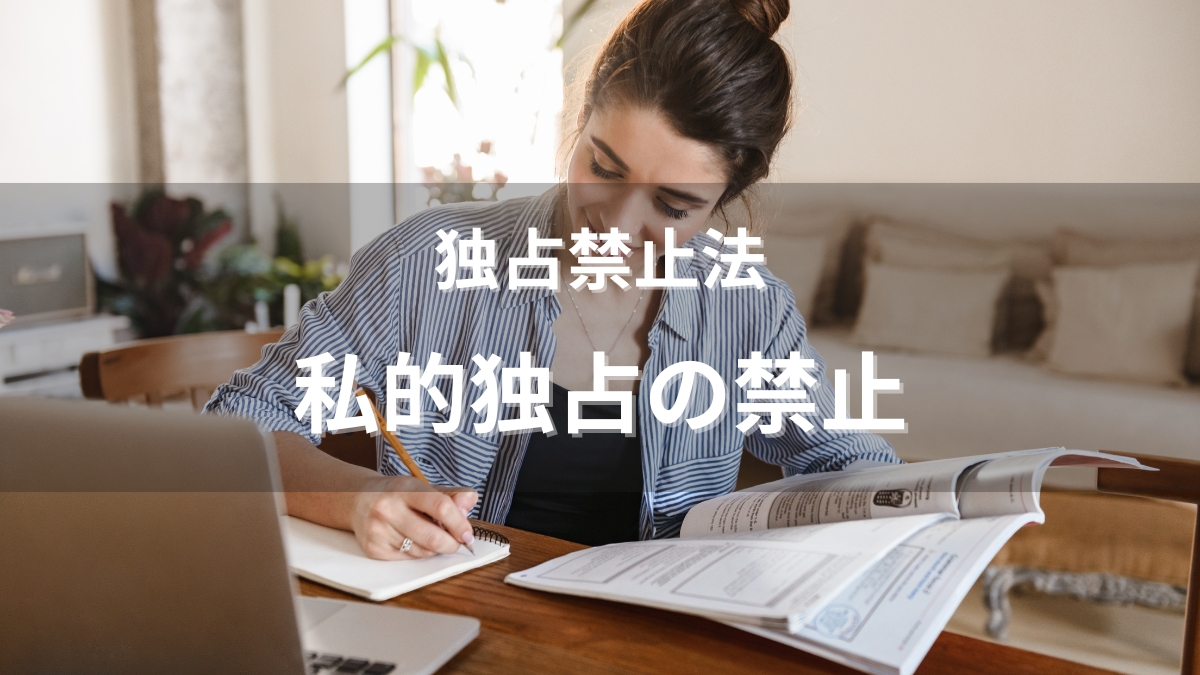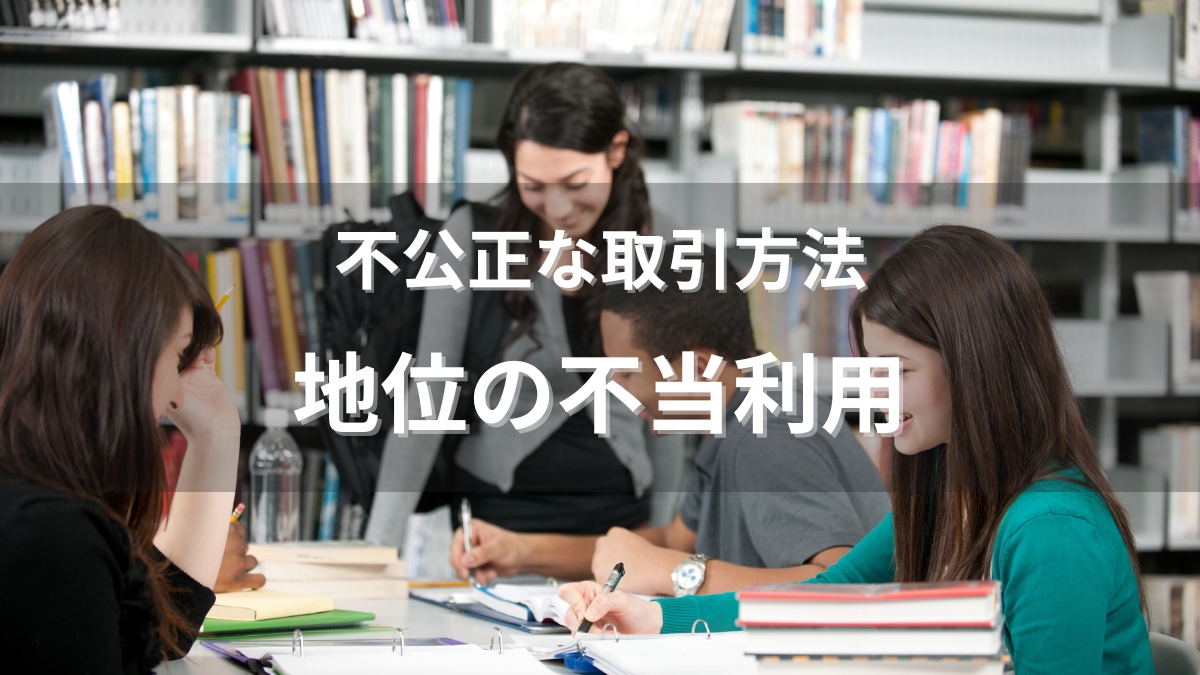今回は、独占禁止法を勉強しようということで、不公正な取引方法のうち不当な顧客誘引・取引強制について見てみたいと思います。
ではさっそく。なお、引用部分の太字、下線、改行などは管理人によるものです。
メモ
このカテゴリーでは、インハウスとしての法務経験からピックアップした、管理人の独学や経験の記録を綴っています。
ネット上の読み物としてざっくばらんに書いており、感覚的な理解を掴むことを目指していますが、書籍などを理解する際の一助になれば幸いです。
不当な顧客誘引・取引強制のグループ
不当な顧客誘引・取引強制は、告示類型のみとなっています。
不当に競争者の顧客を自己と取引するように「誘引」することが、不当な顧客誘引であり、欺瞞的顧客誘引と不当利益顧客誘引があります(一般指定8項・9項)。
不当に競争者の顧客を自己と取引するように「強制」することが、取引強制です(一般指定10項)。いわゆる抱き合わせ販売等です。
全体像は以下のとおりです。
「不当な顧客誘引・取引強制」のグループ(6号ハ参照)
| 行為類型 | 細分類 | 法定類型 (法2条9項) | 告示類型 (一般指定) | 公正競争阻害性 |
|---|---|---|---|---|
| 欺瞞的顧客誘引 | (6号ハ→) | 8項 | 不当に | |
| 不当利益顧客誘引 | (6号ハ→) | 9項 | 正常な商慣習に照らして不当に | |
| 抱き合わせ販売 | 抱き合わせ販売 | (6号ハ→) | 10項前段 | 不当に |
| 抱き合わせ販売以外の強制 | (6号ハ→) | 10項後段 | 不当に |
▽法2条9項6号ハ
六 前各号に掲げるもののほか、次のいずれかに該当する行為であつて、公正な競争を阻害するおそれがあるもののうち、公正取引委員会が指定するもの
ハ 不当に競争者の顧客を自己と取引するように誘引し、又は強制すること。
不当な顧客誘引①欺瞞的顧客誘引
欺瞞的顧客誘引は、告示類型になります。
▽一般指定8項
(ぎまん的顧客誘引)
8 自己の供給する商品又は役務の内容又は取引条件その他これらの取引に関する事項について、実際のもの又は競争者に係るものよりも著しく優良又は有利であると顧客に誤認させることにより、競争者の顧客を自己と取引するように不当に誘引すること。
ここで、
- 「優良」は「自己の供給する商品又は役務の内容」を良く見せること、
- 「有利」は「取引条件」(価格など)を良く見せること、
です。
行為要件
以下、行為要件をざっと見てみます。
「自己の供給する商品又は役務の内容又は取引条件その他これらの取引に関する事項について」
これは、誤認の対象を示しています。
「商品又は役務の内容」か、または、「取引条件」です。
「実際のもの又は競争者に係るものよりも著しく優良又は有利である」
これは、誤認の比較対象を示しています。
実際のものと比べるか、または、競合他社のものと比べるか、です。
「著しく」というのは、社会的に見て許容される誇張の限度を超えるという意味です。
「顧客に」
この「顧客」は消費者に限られていないので、景品表示法と異なり、事業者も含まれます。
ただ、「誤認させる」というのは情報格差を利用した行為なので、事業者の場合には自ずと一般消費者より情報や知識や経験に長けているだろうということで、「不当に誘引」されたかどうかについては一定程度判断が厳格になると解されます。
この点に関しては、フランチャイズの場合に、事業者ではあるものの実態としては知識・経験・情報等の点において一般消費者とあまり変わらないフランチャイジーがいるため、社会的に問題となりがちです(コンビニオーナーなど)。
フランチャイズについてはガイドライン(「フランチャイズ・システムに関する独占禁止法上の考え方について」)があるので、以下、欺瞞的顧客誘引の関連部分を引用してみます。
▽フランチャイズ・システムガイドライン 2-⑶
2 本部の加盟者募集について
⑶ 本部が、加盟者の募集に当たり、上記(2)に掲げるような重要な事項について、十分な開示を行わず、又は虚偽若しくは誇大な開示を行い、これらにより、実際のフランチャイズ・システムの内容よりも著しく優良又は有利であると誤認させ、競争者の顧客を自己と取引するように不当に誘引する場合には、不公正な取引方法の一般指定の第八項(ぎまん的顧客誘引)に該当する。
一般指定の第八項(ぎまん的顧客誘引)に該当するかどうかは、例えば、次のような事項を総合勘案して、加盟者募集に係る本部の取引方法が、実際のものよりも著しく優良又は有利であると誤認させ、競争者の顧客を不当に誘引するものであるかどうかによって判断される。
[1] 予想売上げ又は予想収益の額を提示する場合、その額の算定根拠又は算定方法が合理性を欠くものでないか。また、実際には達成できない額又は達成困難である額を予想額として示していないか。
[2] ロイヤルティの算定方法に関し、必要な説明を行わないことにより、ロイヤルティが実際よりも低い金額であるかのように開示していないか。例えば、売上総利益には廃棄した商品や陳列中紛失等した商品の原価(以下「廃棄ロス原価」という。)が含まれると定義した上で、当該売上総利益に一定率を乗じた額をロイヤルティとする場合、売上総利益の定義について十分な開示を行っているか、又は定義と異なる説明をしていないか。
[3] 自らのフランチャイズ・システムの内容と他本部のシステムの内容を、客観的でない基準により比較することにより、自らのシステムが競争者に比べて優良又は有利であるかのように開示をしていないか。例えば、実質的に本部が加盟者から徴収する金額は同水準であるにもかかわらず、比較対象本部のロイヤルティの算定方法との差異について説明をせず、比較対象本部よりも自己のロイヤルティの率が低いことを強調していないか。
[4] フランチャイズ契約を中途解約する場合、実際には高額な違約金を本部に徴収されることについて十分な開示を行っているか、又はそのような違約金は徴収されないかのように開示していないか(注2)。
(注2) フランチャイズ契約において、中途解約の条件が不明確である場合、加盟に当たって加盟希望者の適正な判断が妨げられるだけでなく、加盟後においても、加盟者はどの程度違約金を負担すれば中途解約できるのか不明であるために解約が事実上困難となることから、本部は中途解約の条件をフランチャイズ契約上明確化するとともに、加盟者募集時に十分説明することが望ましい。
「誤認させる」
これは、「誤認させる」という文言のみで、誤認させる手段・方法は特に限定されていません。
表示が典型ですが、景品表示法と異なり、表示以外の手段も規制対象となり得ます(⇔景品表示法はあくまでも不当表示の規制なので、手段は表示に限られる)。
たとえば、マルチ商法で用いられることのある集団催眠じみた心理的な手段など、誤認させる方法が表示以外のものである場合も、欺瞞的顧客誘引の規制対象となります(過去の適用例)。なお、マルチ商法は、現在は特定商取引法(特定商取引に関する法律)で主に規制されています。
「競争者の顧客を自己と取引するように不当に誘引する」
この「誘引」とは、誘引するだけで足り、実際に取引に至ったかどうかは関係ありません。
効果要件(公正競争阻害性)
この効果要件というのは、「不当に」という文言の部分のことです。
行為要件を満たすだけでは公正競争阻害性があるとはいえず、別途「不当」と認められることが必要となります。
補足:景品表示法の表示規制
欺瞞的顧客誘引の領域には、景品表示法の表示規制(不当表示の規制)があります。
独占禁止法の欺瞞的顧客誘引との適用範囲の違いは、①一般消費者に対する誘引に限られること、②表示による誘引に限られることです。
つまり、景品表示法の表示規制は、「消費者」を対象にした「不当表示」の規制なので、それ以外については独占禁止法によるということです。
景品表示法の表示規制については、以下の関連記事などに書いています。
不当な顧客誘引②不当利益顧客誘引
不当利益顧客誘引は、告示類型になります。
▽一般指定9項
(不当な利益による顧客誘引)
9 正常な商慣習に照らして不当な利益をもつて、競争者の顧客を自己と取引するように誘引すること。
行為要件
「不当な利益」
この「利益」は、経済上の利益を広く指します。
取引の相手方にとって通常利益と思われると客観的に認められるもの、です。
「競争者の顧客を自己を取引するように誘引する」
欺瞞的顧客誘引と同様に、「顧客」には一般消費者も事業者も含まれます。
「誘引」というのは、上記の経済上の利益が、自己との取引を誘引するということです。
効果要件(公正競争阻害性)
この効果要件というのは、「正常な商慣習に照らして不当な」という文言の部分のことです。
行為要件に該当するだけでは公正競争阻害性があるとはいえず、別途「正常な商慣習に照らして不当」といえることが必要となります。
補足:景品表示法上の景品規制
欺瞞的顧客誘引の領域には、独占禁止法とは別に、景品表示法上の景品規制(過大な景品の規制)があります。
景品表示法は、一般消費者に対する誘引に限られるので、事業者に対する過大な景品は、独占禁止法における不当利益顧客誘引の問題になります。
景品表示法上の景品規制については、以下の関連記事などに書いています。
取引強制抱き合わせ販売等
抱き合わせ販売等は、告示類型になります。
▽一般指定10項
(抱き合わせ販売等)
10 相手方に対し、不当に、商品又は役務の供給に併せて他の商品又は役務を自己又は自己の指定する事業者から購入させ、その他自己又は自己の指定する事業者と取引するように強制すること。
前段は、抱き合わせ販売、後段は、抱き合わせ販売以外の強制です。
行為要件
抱き合わせ販売(10項前段)
「商品又は役務の供給に併せて他の商品又は役務を」「自己又は自己の指定する事業者から購入させ」るように強制すること、つまり、他の商品又は役務を自己又は自己の指定する事業者から一緒に購入することを条件とすることです。
主たる商品(「商品又は役務」)と一緒に、従たる商品(「他の商品又は役務」)を抱き合わせて販売することです。ポイントの1つ目として、別個の商品であることが必要です。
ポイントの2つ目として、「購入させる」という強制的要素が必要です。
これらについては、流通・取引慣行ガイドライン(「流通・取引慣行に関する独占禁止法上の指針」)に抱き合わせ販売の関連部分があるので、以下参考に引用します。
▽流通・取引慣行ガイドライン 第2-7-⑶
7 抱き合わせ販売
⑶ ある商品の供給に併せて購入させる商品が「他の商品」といえるか否かについては、組み合わされた商品がそれぞれ独自性を有し、独立して取引の対象とされているか否かという観点から判断される。具体的には、判断に当たって、それぞれの商品について、需要者が異なるか、内容・機能が異なるか(組み合わされた商品の内容・機能が抱き合わせ前のそれぞれの商品と比べて実質的に変わっているかを含む。)、需要者が単品で購入することができるか(組み合わされた商品が通常一つの単位として販売又は使用されているかを含む。)等の点が総合的に考慮される。
当該商品の供給に併せて他の商品を「購入させること」に当たるか否かは、ある商品の供給を受けるに際し客観的にみて少なからぬ顧客が他の商品の購入を余儀なくされるか否かによって判断される。
また、ある商品を購入した後に必要となる補完的商品に係る市場(いわゆるアフターマーケット)において特定の商品を購入させる行為も、抱き合わせ販売に含まれる。
抱き合わせ販売以外の強制(10項後段)
これは、「その他自己又は自己の指定する事業者と取引するように強制」することです。
効果要件(公正競争阻害性)
この効果要件というのは、「不当に」という文言の部分です。
行為要件に該当するだけでは公正競争阻害性があるとはいえず、別途「不当に」といえることが必要となります。
上記で引用した流通・取引慣行ガイドラインに関連部分があるので、以下参考に引用します。
▽流通・取引慣行ガイドライン 第2-7-⑴⑵
7 抱き合わせ販売
⑴ 考え方
複数の商品を組み合わせることにより、新たな価値を加えて取引の相手方に商品を提供することは、技術革新・販売促進の手法の一つであり、こうした行為それ自体が直ちに独占禁止法上問題となるものではない。
しかし、事業者が、ある商品(主たる商品)の供給に併せて他の商品(従たる商品)を購入させることは、当該事業者の主たる商品の市場における地位等によっては、従たる商品の市場における既存の競争者の事業活動を阻害したり、参入障壁を高めたりするような状況等をもたらす可能性がある。
⑵ 独占禁止法上問題となる場合
ある商品(主たる商品)の市場における有力な事業者が、取引の相手方に対し、当該商品の供給に併せて他の商品(従たる商品)を購入させることによって、従たる商品の市場において市場閉鎖効果が生じる場合には(注10)、不公正な取引方法に該当し、違法となる(一般指定10項(抱き合わせ販売等))。
なお、「市場閉鎖効果が生じる場合」に当たるかどうかについては、前記第1部の3⑴及び⑵アにおいて述べた考え方に基づき判断される。例えば、抱き合わせ販売を行う事業者の主たる商品の市場シェアが大きいほど、当該行為が長期間にわたるほど、対象とされる相手方の数が多いほど、そうでない場合と比較して、市場閉鎖効果が生じる可能性が高くなる。また、従たる商品の市場における商品差別化が進んでいない場合には、そうでない場合と比較して、当該事業者の従たる商品が購入されることにより競争者の従たる商品が購入されなくなるおそれが高く、市場閉鎖効果が生じる可能性が高くなる。
…(略)…
(注10) 抱き合わせ販売は、顧客の選択の自由を妨げるおそれがあり、価格、品質、サービスを中心とする能率競争の観点から、競争手段として不当である場合にも、不公正な取引方法に該当し、違法となる。事業者による抱き合わせ販売が競争手段として不当であるか否かは、主たる商品の市場力や従たる商品の特性、抱き合わせの態様のほか、当該行為の対象とされる相手方の数、当該行為の反復、継続性、行為の伝播性等の行為の広がりを総合的に考慮する。
結び
今回は、独占禁止法を勉強しようということで、不公正な取引方法のうち不当な顧客誘引・取引強制について見てみました。
-
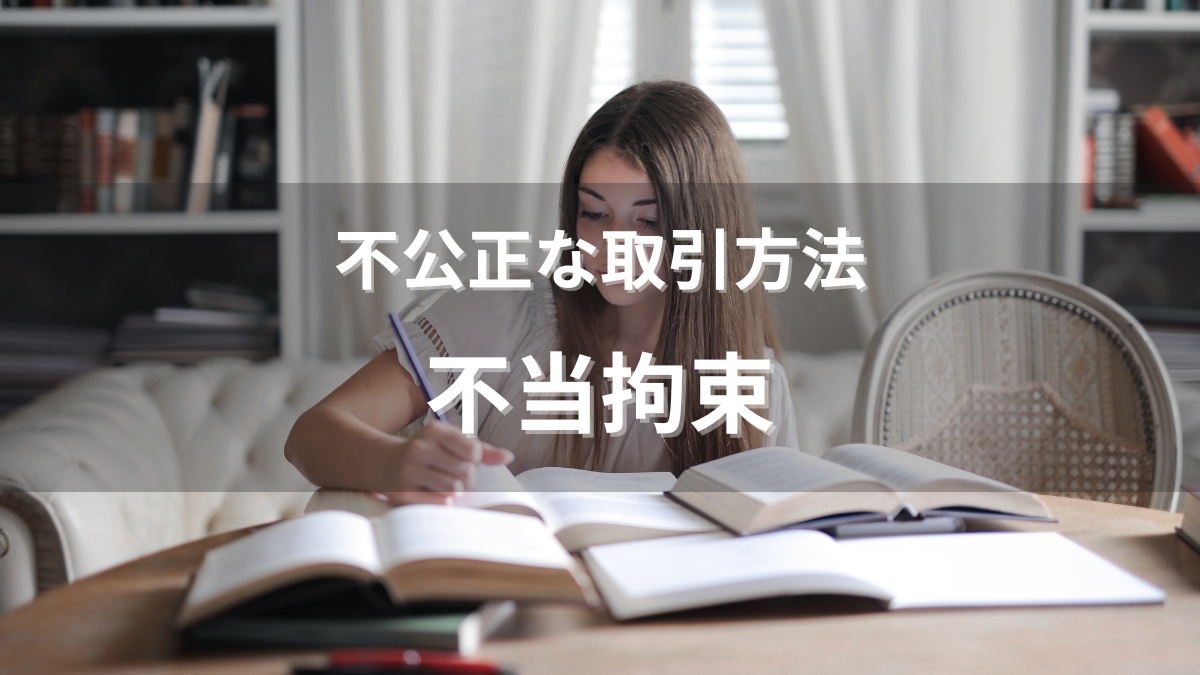
-
独占禁止法を勉強しよう|不公正な取引方法-不当拘束
続きを見る
[注記]
本記事を含む一連の勉強記事は、過去の自分に向けて、①自分の独学や経験の記録を見せる、②感覚的な理解を伝えることを優先する、③細かく正確な理解は書物に譲る、ということをコンセプトにした読みものです。ベテランの方が見てなるほどと思うようなことは書かれていないほか、業務上必要であるときなど、正確な内容については別途ご確認ください。また、法改正をはじめとした最新の情報を反映しているとは限りませんので、ご注意ください。
独占禁止法に関するその他の記事(≫Read More)
主要法令等・参考文献
主要法令等
リンクをクリックすると、法令データ提供システムまたは公正取引委員会HPに遷移します
- 独占禁止法(≫法律情報/英文)
- 排除型私的独占ガイドライン(「排除型私的独占に係る独占禁止法上の指針」)|公取委HP
- 一般指定(「不公正な取引方法」(昭和57年6月18日公正取引委員会告示第15号))|公取委HP
- 新聞特殊指定(「新聞業における特定の不公正な取引方法」(平成11年7月21日公正取引委員会告示第9号))|公取委HP
- 物流特殊指定(「特定荷主が物品の運送又は保管を委託する場合の特定の不公正な取引方法」(平成16年3月8日公正取引委員会告示第1号))|公取委HP
- 大規模小売業告示(「大規模小売業者による納入業者との取引における特定の不公正な取引方法」(平成17年5月13日公正取引委員会告示第11号))|公取委HP
- 不当廉売ガイドライン(「不当廉売に関する独占禁止法上の考え方」)|公取委HP
- 流通・取引慣行ガイドライン(「流通・取引慣行に関する独占禁止法の指針」)|公取委HP
- 優越的地位濫用ガイドライン(「優越的地位の濫用に関する独占禁止法上の考え方」)|公取委HP
- 役務委託優越的地位濫用ガイドライン(「役務の委託取引における優越的地位の濫用に関する独占禁止法上の指針」)|公取委HP
- 意見聴取規則(「公正取引委員会の意見聴取に関する規則」)
- 審査規則(「公正取引委員会の審査に関する規則」)
- 審査手続指針(「独占禁止法審査手続に関する指針」)|公取委HP
- 独禁法Q&A(「よくある質問コーナー(独占禁止法)」)|公取委HP
【企業結合規制関連】
- 届出等規則(「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第九条から第十六条までの規定による認可の申請、報告及び届出等に関する規則」)
- 企業結合ガイドライン(「企業結合審査に関する独占禁止法の運用指針」)|公取委HP
- 企業結合手続対応方針(「企業結合審査の手続に関する対応方針」)|公取委HP
【違反に対する措置(エンフォースメント)関連】
参考文献
リンクをクリックすると、Amazonのページまたは公正取引委員会HPに遷移します
- 独占禁止法〔第5版〕(菅久修一 編著、品川武、伊永大輔、鈴木健太 著)
- 注釈 独占禁止法(根岸哲 編)
- 優越的地位濫用ガイドブック(「優越的地位の濫用 ~知っておきたい取引ルール~」(公正取引委員会))|公取委HP(≫掲載ページ)
- 優越的地位の濫用規制に関する講習|公取委HP
当サイトではアフィリエイトプログラムを利用して商品・サービスを記載しています