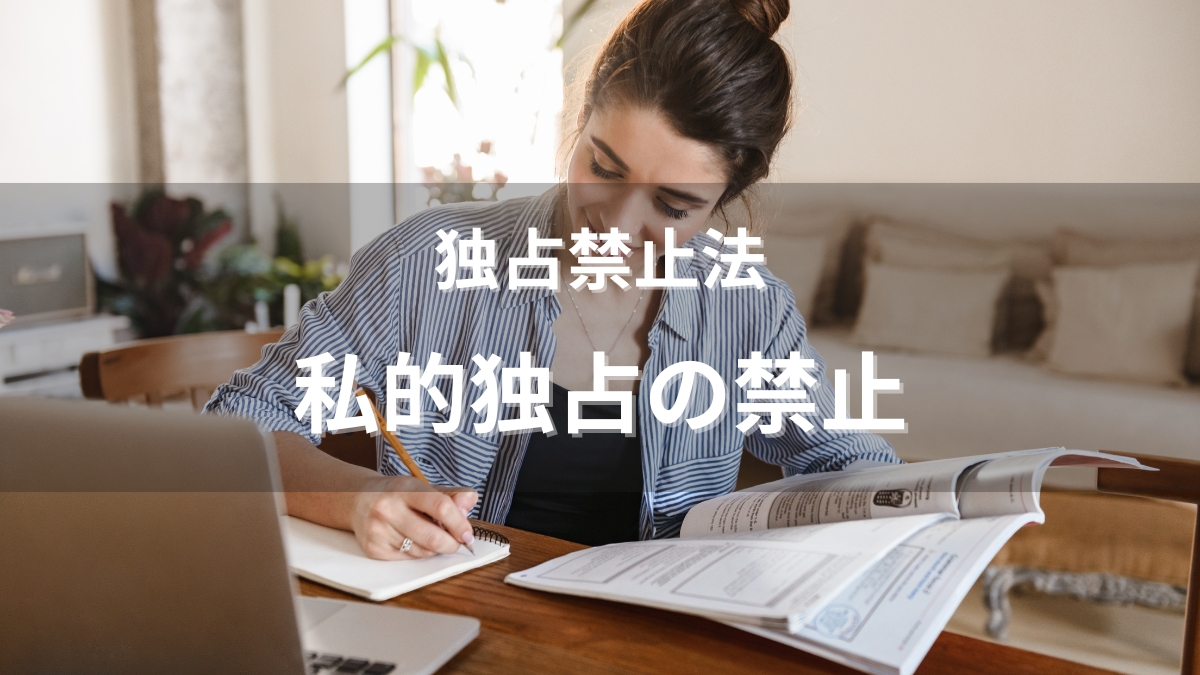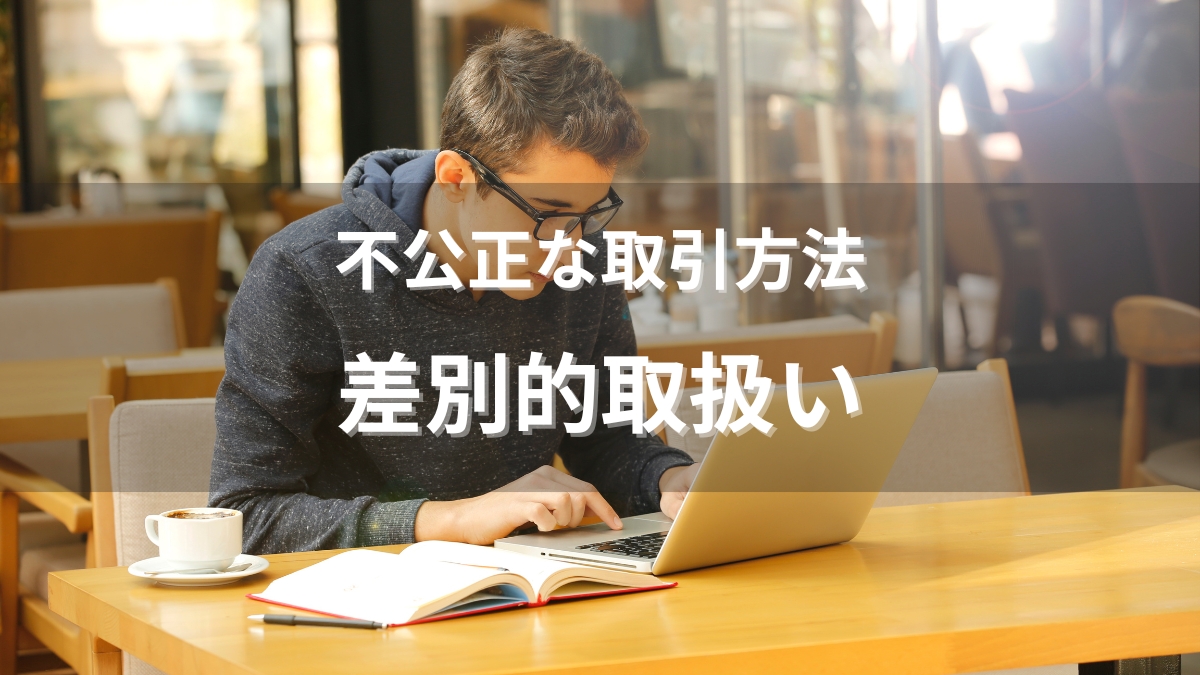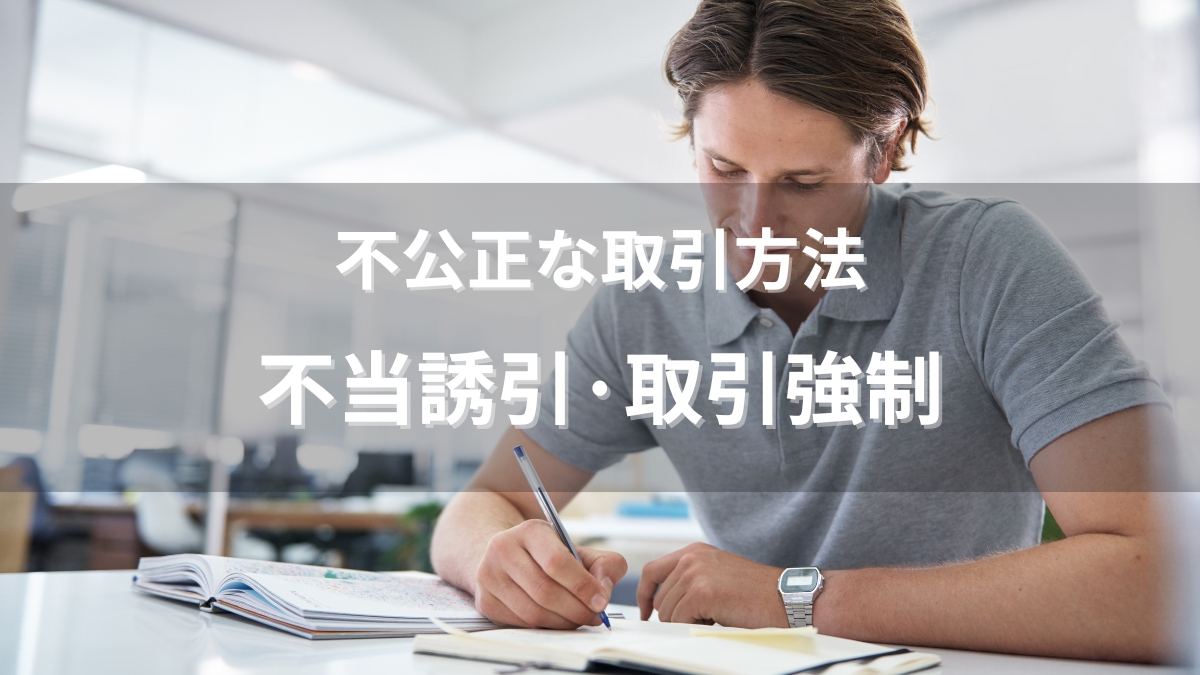今回は、独占禁止法を勉強しようということで、私的独占の禁止について見てみたいと思います。
ではさっそく。なお、引用部分の太字、下線、改行などは管理人によるものです。
メモ
このカテゴリーでは、インハウスとしての法務経験からピックアップした、管理人の独学や経験の記録を綴っています。
ネット上の読み物としてざっくばらんに書いており、感覚的な理解を掴むことを目指していますが、書籍などを理解する際の一助になれば幸いです。
私的独占の禁止
基本的な条文は、私的独占の禁止を定める法3条と、その定義を定める法2条5項になります。
▽法3条
第三条 事業者は、私的独占又は不当な取引制限をしてはならない。
▽法2条5項
⑤ この法律において「私的独占」とは、事業者が、単独に、又は他の事業者と結合し、若しくは通謀し、その他いかなる方法をもつてするかを問わず、他の事業者の事業活動を排除し、又は支配することにより、公共の利益に反して、一定の取引分野における競争を実質的に制限することをいう。
私的独占の「私的」というのはどういう意味かというと、公的独占を除く意味です。つまり、「公的」に、制度上認められた独占(インフラ系の事業とか)以外の独占、という意味になります。
理屈では、独占的事業者は売り手も買い手も考えられますが、現実問題としては買い手は不特定多数存在するのが通常であるため、実際に問題になるのはほとんどの場合売り手の独占です。
なお、語感的には、私的独占というと”独占的な状態”(1社あるいは限られた企業が市場を独占しているような状態)をイメージしますが、独占しているというだけで違法になるわけではありません。市場を独占していることを問題とするのではなく、法2条5項の行為要件と効果要件を満たすような、他の事業者の事業活動を排除・支配する行為が問題とされます。
▽公正取引委員会のXアカウント
「私的独占」は、事業者が単独又は共同で、他の事業者の事業活動を排除したり、支配したりすることにより、市場における競争を実質的に制限することを指します。
— 公正取引委員会 (@jftc) April 18, 2024
”市場が独占されている”状態が問題ではないのがポイントです!https://t.co/HdB5KcTYx8#独占禁止法 pic.twitter.com/Vx2q9AMMzc
行為要件
行為としては、「排除」と「支配」が規定されています。
これはどういうことかというと、
- 競争が生じないようにするためには、独占的事業者(1社あるいは少数の大企業で市場を占有しているような事業者)なら、新規参入者の参入を阻んだり既存業者を市場から退出させる(=排除)か、新規参入者や既存業者を自社のコントロール下においたりすること(=支配)を考えるだろう、
- そういった行為が競争制限性をもつとき(「競争を実質的に制限」)に、これを私的独占として規制する、
という趣旨になります。
以下、行為要件をざっと見てみます。
「単独に、又は他の事業者と結合し、若しくは通謀し、その他いかなる方法をもつてするかを問わず」
「単独に、又は他の事業者と結合し、若しくは通謀し、その他いかなる方法をもつてするかを問わず」とは、排除・支配という行為が、単独の事業者によるものであっても、複数の事業者によるものであっても、私的独占に該当しうるという意味です。
「排除」(排除型私的独占)
「排除」とは、他の事業者が独自の事業活動を続けることを困難にすること又は参入を困難にすることです(排除型私的独占)。
つまり、競争者の数を減少させる、または増加させないことで、市場の支配を強めるということです。
具体的にどんな類型があるかについては、いわゆる排除型私的独占ガイドラインに記載されており、
- 商品を供給しなければ発生しない費用を下回る対価設定
- 排他的取引
- 抱き合わせ
- 供給拒絶
- 差別的取扱い
があるとされています。
以下は、ガイドラインから抜粋を記載しています。
①商品を供給しなければ発生しない費用を下回る対価設定
▽排除型私的独占ガイドライン 第2-2-⑴
⑴ 排除行為に該当し得る行為
自由競争経済は、需給の調整を市場メカニズムに委ね、事業者が市場の需給関係に適応しつつ価格決定を行う自由を有することを前提とするものであり、企業努力による価格引下げ競争は、本来、競争政策が維持・促進しようとする能率競争(良質・廉価な商品を提供して顧客を獲得する競争をいう。)の中核をなすものである。このことを踏まえれば、公正かつ自由な競争を促進する独占禁止法の目的に照らし、価格引下げ競争に対する介入は最小限にとどめられるべきである。
しかし、一般に、商品を供給しなければ発生しない費用さえ回収できないような対価を設定すれば、その商品の供給が増大するにつれ損失が拡大することとなるため、このような行為は、特段の事情がない限り、経済合理性のないものである(注8)。したがって、ある商品について、このような対価を設定することによって競争者の顧客を獲得することは、企業努力又は正常な競争過程を反映せず、自らと同等又はそれ以上に効率的な事業者の事業活動を困難にさせ、競争に悪影響を及ぼす場合がある。このように、ある商品について、その商品を供給しなければ発生しない費用を下回る対価を設定する行為は、排除行為に該当し得る(注9)。
(以下略)
②排他的取引
▽排除型私的独占ガイドライン 第2-3-⑴
⑴ 排除行為に該当し得る行為
事業者が、相手方に対し、自己の競争者から商品の供給を受けないことを取引の条件としたとしても、競争者が当該相手方に代わり得る取引先を容易に見いだすことができる場合には、競争者は、価格、品質等による競争に基づき市場での事業活動を継続して行うことができる。したがって、当該行為は、それ自体で直ちに排除行為となるものではない。
しかし、ある事業者が、相手方に対し、自己の競争者との取引を禁止し、又は制限することを取引の条件とすることにより、競争者が当該相手方に代わり得る取引先を容易に見いだすことができない場合には、その事業活動を困難にさせ、競争に悪影響を及ぼす場合がある。このように、相手方に対し、自己の競争者との取引を禁止し、又は制限することを取引の条件とする行為(以下「排他的取引」という。)は、排除行為に該当し得る(注12)。
(以下略)
③抱き合わせ
▽排除型私的独占ガイドライン 第2-4-⑴
⑴ 排除行為に該当し得る行為
複数の商品を組み合わせることにより、新たな価値を加えて相手方に商品を提供することは、技術革新・販売促進の手法の一つである。したがって、当該行為は、それ自体で直ちに排除行為となるものではない。
しかし、ある事業者が、相手方に対し、ある商品(主たる商品)の供給に併せて他の商品(従たる商品)を購入させることは、従たる商品の市場において他に代わり得る取引先を容易に見いだすことができない競争者の事業活動を困難にさせ、従たる商品の市場における競争に悪影響を及ぼす場合がある。このように、相手方に対し、ある商品の供給(又は購入)に併せて他の商品を購入(又は供給)させる行為(以下「抱き合わせ」という。)は、排除行為に該当し得る(注15)。
(以下略)
④供給拒絶、⑤差別的取扱い
▽排除型私的独占ガイドライン 第2-5-⑴
⑴ 排除行為に該当し得る行為
事業者が、誰に商品を供給するか、どのような条件で商品を供給するかは、基本的には事業者の自由である。したがって、事業者が独立した事業主体として、商品の供給先を選択し、供給先事業者(新たに供給を受けようとする事業者を含む。以下同じ。)との間で供給に係る取引の内容、実績等を考慮して供給の条件を定めることは、原則として排除行為となるものではない。
しかし、ある事業者が、供給先事業者が市場(川下市場)で事業活動を行うために必要な商品を供給する市場(川上市場)において、合理的な範囲を超えて、供給の拒絶、供給に係る商品の数量若しくは内容の制限又は供給の条件若しくは実施についての差別的な取扱い(以下「供給拒絶等」という。)をすることは、川上市場においてその事業者に代わり得る他の供給者を容易に見いだすことができない供給先事業者(以下「拒絶等を受けた供給先事業者」という。)の川下市場における事業活動を困難にさせ、川下市場における競争に悪影響を及ぼす場合がある。このように、供給先事業者が市場(川下市場)で事業活動を行うために必要な商品について、合理的な範囲を超えて供給拒絶等をする行為(以下「供給拒絶・差別的取扱い」という。)は、排除行為に該当し得る(注17)(注18)。
「支配」(支配型私的独占)
「支配」とは、企業の事業活動についての自主的な決定を行うことができない状態をもたらす行為のことです(支配型私的独占)。
他の事業者を直接・間接に拘束しあるいは強制することによって、その事業活動を自己の意思に従わせることをいいます。
効果要件
以下、効果要件もざっと見てみます。
「一定の取引分野における」
行為要件を満たす行為が競争を実質的に制限するかどうかを判断するための前提として必要な要件になります。
要するに、市場の占有率を判断するには、市場の範囲を決める必要があるということです。
「競争を実質的に制限」
ここでいう競争の実質的制限は、市場支配力の形成・維持・強化のことです。
「公共の利益に反して」
これは、保護法益である自由競争経済秩序の維持と、排除行為により得られる利益との比較衡量により判断されます。
行為要件と効果要件が認められれば「公共の利益に反する」ことは事実上推定され、違反行為を争う側で得られる利益を明らかにする必要があります。得られる利益としては、事業活動における合理性、経済合理性、競争促進性などが主張されます。
そして、上記2つの利益(太字部分)を比較して検討がされることになります。
結び
今回は、独占禁止法を勉強しようということで、私的独占の禁止について見てみました。
-

-
独占禁止法を勉強しよう|不当な取引制限の禁止
続きを見る
[注記]
本記事を含む一連の勉強記事は、過去の自分に向けて、①自分の独学や経験の記録を見せる、②感覚的な理解を伝えることを優先する、③細かく正確な理解は書物に譲る、ということをコンセプトにした読みものです。ベテランの方が見てなるほどと思うようなことは書かれていないほか、業務上必要であるときなど、正確な内容については別途ご確認ください。また、法改正をはじめとした最新の情報を反映しているとは限りませんので、ご注意ください。
独占禁止法に関するその他の記事(≫Read More)
主要法令等・参考文献
主要法令等
リンクをクリックすると、法令データ提供システムまたは公正取引委員会HPに遷移します
- 独占禁止法(≫法律情報/英文)
- 排除型私的独占ガイドライン(「排除型私的独占に係る独占禁止法上の指針」)|公取委HP
- 一般指定(「不公正な取引方法」(昭和57年6月18日公正取引委員会告示第15号))|公取委HP
- 新聞特殊指定(「新聞業における特定の不公正な取引方法」(平成11年7月21日公正取引委員会告示第9号))|公取委HP
- 物流特殊指定(「特定荷主が物品の運送又は保管を委託する場合の特定の不公正な取引方法」(平成16年3月8日公正取引委員会告示第1号))|公取委HP
- 大規模小売業告示(「大規模小売業者による納入業者との取引における特定の不公正な取引方法」(平成17年5月13日公正取引委員会告示第11号))|公取委HP
- 不当廉売ガイドライン(「不当廉売に関する独占禁止法上の考え方」)|公取委HP
- 流通・取引慣行ガイドライン(「流通・取引慣行に関する独占禁止法の指針」)|公取委HP
- 優越的地位濫用ガイドライン(「優越的地位の濫用に関する独占禁止法上の考え方」)|公取委HP
- 役務委託優越的地位濫用ガイドライン(「役務の委託取引における優越的地位の濫用に関する独占禁止法上の指針」)|公取委HP
- 意見聴取規則(「公正取引委員会の意見聴取に関する規則」)
- 審査規則(「公正取引委員会の審査に関する規則」)
- 審査手続指針(「独占禁止法審査手続に関する指針」)|公取委HP
- 独禁法Q&A(「よくある質問コーナー(独占禁止法)」)|公取委HP
【企業結合規制関連】
- 届出等規則(「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第九条から第十六条までの規定による認可の申請、報告及び届出等に関する規則」)
- 企業結合ガイドライン(「企業結合審査に関する独占禁止法の運用指針」)|公取委HP
- 企業結合手続対応方針(「企業結合審査の手続に関する対応方針」)|公取委HP
【違反に対する措置(エンフォースメント)関連】
参考文献
リンクをクリックすると、Amazonのページまたは公正取引委員会HPに遷移します
- 独占禁止法〔第5版〕(菅久修一 編著、品川武、伊永大輔、鈴木健太 著)
- 注釈 独占禁止法(根岸哲 編)
- 優越的地位濫用ガイドブック(「優越的地位の濫用 ~知っておきたい取引ルール~」(公正取引委員会))|公取委HP(≫掲載ページ)
- 優越的地位の濫用規制に関する講習|公取委HP
当サイトではアフィリエイトプログラムを利用して商品・サービスを記載しています