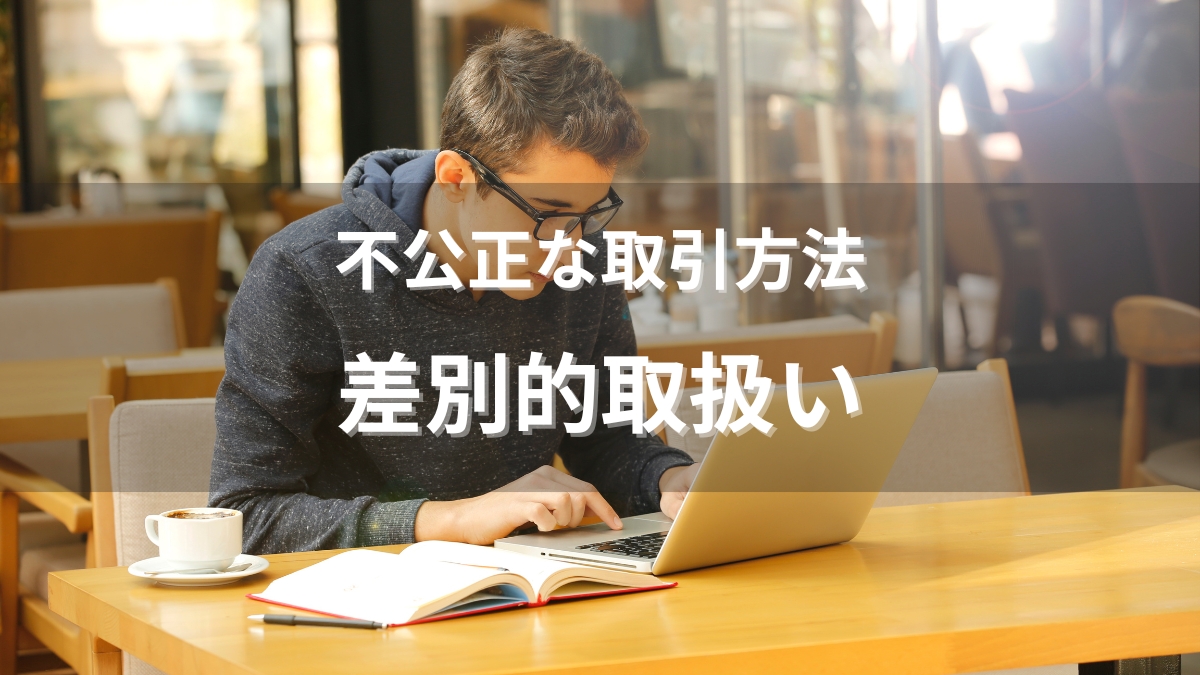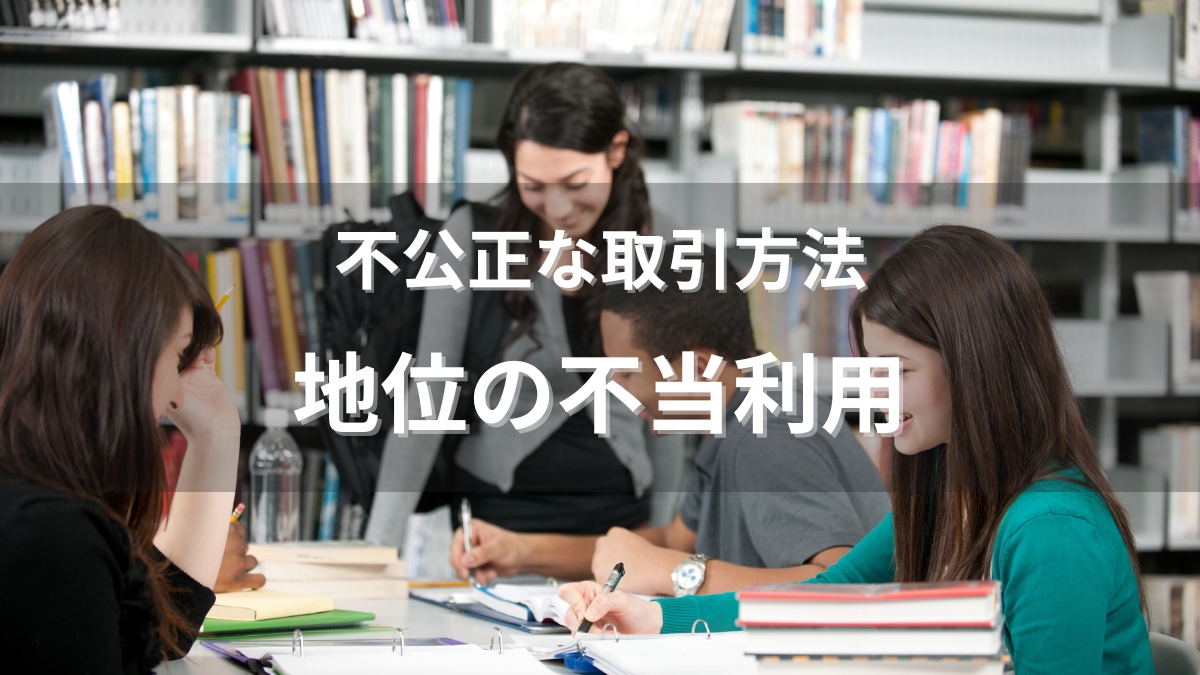今回は、独占禁止法を勉強しようということで、企業結合規制について見てみたいと思います。
ではさっそく。なお、引用部分の太字、下線、改行などは管理人によるものです。
メモ
このカテゴリーでは、インハウスとしての法務経験からピックアップした、管理人の独学や経験の記録を綴っています。
ネット上の読み物としてざっくばらんに書いており、感覚的な理解を掴むことを目指していますが、書籍などを理解する際の一助になれば幸いです。
企業結合規制
企業結合規制は、競争を制限することとなるような企業の組織変更を規制するものです。
会社の株式取得、合併、分割、共同株式移転、事業の譲受けなどによって競争が実質的に制限されることとなる場合に、こうした企業結合が禁止されます。
なお、独禁法全体の位置づけから見ると、企業結合は、私的独占に対する規制の補完的・予防的規定といわれます。
ともに競争の実質的制限を規制しようとするものですが、私的独占に対する規制は、大企業による市場支配力の形成・維持・強化を問題とする「行為規制」であるのに対し、企業結合規制は、結合による当該市場の構造変化を問題にするという意味で「構造規制」であるといえます。
独禁法が規制する企業結合の類型には、6つの類型(①株式保有、②役員の兼任、③合併、④会社分割、⑤共同株式移転、⑥事業の譲受け等)があります。
▽公正取引委員会のXアカウント
【#2020ひとこと講座 16】#独占禁止法 は競争を制限するような合併などの企業結合も規制対象としています。
— 公正取引委員会 (@jftc) May 14, 2020
一定規模以上の会社が株式取得,合併,分割,共同株式移転,事業等の譲受けを行う際には公正取引委員会への事前届出が必要です。 https://t.co/P0KVlvjLMM#企業結合 pic.twitter.com/uylZcUcsQY
主な法令等
企業結合規制に関する主な法令等は、以下のようになっています。
| 法律 | 公取規則 | 解釈・運用 |
|---|---|---|
| 独占禁止法 | ➢届出等規則 (「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第九条から第十六条までの規定による認可の申請、報告及び届出等に関する規則」) ➢意見聴取規則 (「公正取引委員会の意見聴取に関する規則」) ➢審査規則 (「公正取引委員会の審査に関する規則」) | ➢企業結合ガイドライン (「企業結合審査に関する独占禁止法の運用指針」) |
企業結合規制に関しては、企業結合ガイドライン(「企業結合審査に関する独占禁止法の運用指針」)で、どのような企業結合が問題となるかの考え方が示されています。
以下、企業結合規制の類型を見てみます。
企業結合規制の類型
独禁法が規制する企業結合の類型には、
- 株式保有
- 役員の兼任
- 合併
- 会社分割
- 共同株式移転
- 事業の譲受け等
という6つの類型があります。
①株式保有の制限
これは、会社が他の会社の株式を取得すること、または他の会社の株式を所有することです。
▽法10条1項
第十条 会社は、他の会社の株式を取得し、又は所有することにより、一定の取引分野における競争を実質的に制限することとなる場合には、当該株式を取得し、又は所有してはならず、及び不公正な取引方法により他の会社の株式を取得し、又は所有してはならない。
なぜ「所有」まで規制されているのか?というと、株式取得時には企業結合規制として問題にならない場合でも、その後の状況の変化によっては株式を「所有」していることが規制対象になり得るということです。
▽公正取引委員会のXアカウント
【#どっきんメモ -独禁法 企業結合-】
— 公正取引委員会 (@jftc) January 31, 2024
独占禁止法では、競争を制限することとなる企業結合を規制しているよ。
一定規模以上の会社が株式取得や合併等の企業結合を行う際は、公取委に事前に届け出る必要があって、公取委は問題ないか審査するんだ!
過去の審査結果・届出基準→ https://t.co/D31W4DOfWs pic.twitter.com/HbMdzTrc31
②役員兼任の制限
これは、会社の役員又は従業員が他の会社の役員の地位を兼ねることです。
▽法13条1項
第十三条 会社の役員又は従業員(継続して会社の業務に従事する者であつて、役員以外の者をいう。以下この条において同じ。)は、他の会社の役員の地位を兼ねることにより一定の取引分野における競争を実質的に制限することとなる場合には、当該役員の地位を兼ねてはならない。
③合併の制限
これは、会社法でいう「合併」の制限のことです。
▽法15条1項
第十五条 会社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、合併をしてはならない。
一 当該合併によつて一定の取引分野における競争を実質的に制限することとなる場合
二 当該合併が不公正な取引方法によるものである場合
会社法でいう「合併」には吸収合併と新設合併がありますが、その両方とも企業結合規制の対象となっています。合併は「飲み込む」というイメージになります。
▽公正取引委員会のXアカウント
【#2024ひとこと講座 12独禁法】
— 公正取引委員会 (@jftc) April 25, 2024
<企業結合-合併のルール->
例えば、全てのライバル会社を買収したら競争がなくなってしまいますね。独禁法は、競争を制限するような合併等の企業結合も規制対象としています。
一定規模以上の会社が企業結合する際は事前届出が必要です。 https://t.co/nMsR8cCLKE pic.twitter.com/4PnsEXrTnM
④会社分割の制限
これは、会社法でいう「会社分割」の制限のことです。
▽法15条の2第1項
第十五条の二 会社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、共同新設分割(会社が他の会社と共同してする新設分割をいう。以下同じ。)をし、又は吸収分割をしてはならない。
一 当該共同新設分割又は当該吸収分割によつて一定の取引分野における競争を実質的に制限することとなる場合
二 当該共同新設分割又は当該吸収分割が不公正な取引方法によるものである場合
会社法でいう「会社分割」には、①吸収分割と②新設分割(②´共同新設分割も含む)があります。共同新設分割というのは、新設分割を2社以上で行う場合を指します。
会社分割は「事業の一部を切り出す」というイメージになります。
ただし、独禁法で企業結合規制の対象となっているのは、①吸収分割と、②´共同新設分割です。
上記の図で見るとわかるように、共同新設分割と吸収分割は実質的には部分的な合併であるため、企業結合規制がかかっているといえます。
⑤共同株式移転の制限
共同株式移転というのは、株式移転を2社以上で行う場合のことです。
株式移転というのは、新設会社との間で行う株式交換と思っておけばよいと思います。
▽法15条の3第1項
第十五条の三 会社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、共同株式移転(会社が他の会社と共同してする株式移転をいう。以下同じ。)をしてはならない。
一 当該共同株式移転によつて一定の取引分野における競争を実質的に制限することとなる場合
二 当該共同株式移転が不公正な取引方法によるものである場合
上記の図で見るとわかるように、共同株式移転は、持ち株会社が誕生しこれを通じて結合関係が形成されるため、企業結合規制がかかっているといえます。
⑥事業の譲受け等の制限
これは、譲渡会社の事業や固定資産を譲受会社に承継させることです(1~2号)。
事業の賃借/事業の経営の受任/事業上の損益全部を共通にする契約の締結についても(3~5号)、事業の譲受けに準じて扱われています。
▽法16条1項
第十六条 会社は、次に掲げる行為をすることにより、一定の取引分野における競争を実質的に制限することとなる場合には、当該行為をしてはならず、及び不公正な取引方法により次に掲げる行為をしてはならない。
一 他の会社の事業の全部又は重要部分の譲受け
二 他の会社の事業上の固定資産の全部又は重要部分の譲受け
三 他の会社の事業の全部又は重要部分の賃借
四 他の会社の事業の全部又は重要部分についての経営の受任
五 他の会社と事業上の損益全部を共通にする契約の締結
続いて、以下では共通する効果要件(「一定の取引分野」「競争を実質的に制限することとなる」)について見てみます。
「一定の取引分野」
一定の取引分野というのは、ざっくりいうと、シェアを判断するにはマーケットの範囲を決めないといけない(市場の範囲を画定しないといけない)という話です。
そういった”市場の範囲の画定”については、①商品の範囲を画定する、②取引の地域の範囲(地理的範囲)を画定するという方法で行われます。
需要者にとっての代替性というのは、実質的な値上がりがあったときに他の商品や地域への乗り換えが起こる可能性の大小、ということを意味します。
そして、その可能性が小さいということはつまり、独占的事業者が値上げにより利潤を拡大できる=その企業結合によって競争上何らかの影響が及びうる範囲である、ということになります
▽企業結合ガイドライン 第2-1
1 一定の取引分野の画定の基本的考え方
一定の取引分野は、企業結合により競争が制限されることとなるか否かを判断するための範囲を示すものであり、一定の取引の対象となる商品・役務(以下、両者を併せて「商品」という。また、特に商品について記述する場合には「財」、役務について記述する場合には「サービス」という。)の範囲、取引の地域の範囲(以下「地理的範囲」という。)等に関して、基本的には、需要者にとっての代替性という観点から判断される。
また、必要に応じて供給者にとっての代替性という観点も考慮される。
需要者にとっての代替性をみるに当たっては、ある地域において、ある事業者が、ある商品を独占して供給しているという仮定の下で、当該独占事業者が、利潤最大化を図る目的で、小幅ではあるが実質的であり、かつ一時的ではない価格引上げ(注2)(注3)をした場合に、当該商品及び地域について、需要者が当該商品の購入を他の商品又は地域に振り替える程度を考慮する。他の商品又は地域への振替の程度が小さいために、当該独占事業者が価格引上げにより利潤を拡大できるような場合には、その範囲をもって、当該企業結合によって競争上何らかの影響が及び得る範囲ということとなる。
供給者にとっての代替性については、当該商品及び地域について、小幅ではあるが実質的であり、かつ一時的ではない価格引上げがあった場合に、他の供給者が、多大な追加的費用やリスクを負うことなく、短期間(1年以内を目途)のうちに、別の商品又は地域から当該商品に製造・販売を転換する可能性の程度を考慮する。そのような転換の可能性の程度が小さいために、当該独占事業者が価格引上げにより利潤を拡大できるような場合には、その範囲をもって、当該企業結合によって競争上何らかの影響が及び得る範囲ということとなる。
また、第三者にサービスの「場」を提供し、そこに異なる複数の需要者層が存在する多面市場を形成するプラットフォームの場合、基本的に、それぞれの需要者層ごとに一定の取引分野を画定し、後記第4の2⑴キのとおり多面市場の特性を踏まえて企業結合が競争に与える影響について判断する。
(以下略)
「競争を実質的に制限することとなる」
条文の引用部分で見たとおり、どの規制類型にも「競争を実質的に制限することとなる」という要件がありましたが、この要件は、「競争を実質的に制限する」の部分と、「こととなる」の部分とに分かれます。
「競争を実質的に制限する」
「競争を実質的に制限する」の考え方は以下のとおりです。
▽企業結合ガイドライン 第3-1-⑴
⑴ 「競争を実質的に制限する」の考え方
判例(東宝株式会社ほか1名に対する件(昭和28年12月7日東京高等裁判所判決))では、「競争を実質的に制限する」について、次のような考え方が示されている。
ア 株式会社新東宝(以下「新東宝」という。)は、自社の制作する映画の配給について自ら行うこともできたが、東宝株式会社(以下「東宝」という。)との協定により、当該配給をすべて東宝に委託することとし、自らは、映画の制作のみを行っていた。新東宝は、当該協定失効後も引き続き当該協定の内容を実行していたが、昭和24年11月に、右協定の失効を理由として、新東宝の制作した映画は自らこれを配給することを言明したことから、東宝との間に紛争が生じた。この紛争の中で、右の協定が法違反であるとして、公正取引委員会による審判が開始され、公正取引委員会は、昭和26年6月5日の審決において、東宝と新東宝の協定は、法第3条(不当な取引制限)及び第4条第1項第3号(注4)の規定に違反すると認定した。
(注4)法第4条第1項(現行法では、この規定は存在しない。)
事業者は、共同して左の各号の一に該当する行為をしてはならない。
第3号 技術、製品、販路又は顧客を制限すること
イ 被審人東宝の審決取消しの訴えに対して、東京高等裁判所は、競争の実質的制限に関し、「競争を実質的に制限するとは、競争自体が減少して、特定の事業者又は事業者集団がその意思で、ある程度自由に、価格、品質、数量、その他各般の条件を左右することによって、市場を支配することができる状態をもたらすことをいう」と判示した。
「こととなる」
「こととなる」の考え方は以下のとおりです。
▽企業結合ガイドライン 第3-1-⑵
⑵ 「こととなる」の考え方
法第4章の各規定では、法第3条又は法第8条の規定と異なり、一定の取引分野における競争を実質的に制限する「こととなる」場合の企業結合を禁止している。この「こととなる」とは、企業結合により、競争の実質的制限が必然ではないが容易に現出し得る状況がもたらされることで足りるとする蓋然性を意味するものである。したがって、法第4章では、企業結合により市場構造が非競争的に変化して、当事会社グループが単独で又は他の会社と協調的行動をとることによって、ある程度自由に価格、品質、数量、その他各般の条件を左右することができる状態が容易に現出し得るとみられる場合には、一定の取引分野における競争を実質的に制限することとなり、禁止される。
企業結合形態別の判断方法
「一定の取引分野」で「競争を実質的に制限することとなる」については、水平型企業結合/垂直型企業結合/混合型企業結合の3つに分類され、それぞれごとに、判断枠組みや判断要素が整理されています(企業結合ガイドライン)。
なお、水平とか垂直というのが独禁法ではよく出てきますが、「水平」というのは競争事業者間のこと、「垂直」というのは取引事業者間のことと思っておけばよいと思います。「混合」は、両方が混ざっているということです。
▽企業結合ガイドライン 第3-2
企業結合には様々な形態があるが、
① 水平型企業結合(同一の一定の取引分野において競争関係にある会社間の企業結合をいう。以下同じ。)
② 垂直型企業結合(例えば、メーカーとその商品の販売業者との間の合併など取引段階を異にする会社間の企業結合をいう。以下同じ。)
③ 混合型企業結合(例えば、異業種に属する会社間の合併、一定の取引分野の地理的範囲を異にする会社間の株式保有など水平型企業結合又は垂直型企業結合のいずれにも該当しない企業結合をいう。以下同じ。)
に分類することができる。
水平型企業結合は、一定の取引分野における競争単位の数を減少させるので、競争に与える影響が最も直接的であり、一定の取引分野における競争を実質的に制限することとなる可能性は、垂直型企業結合や混合型企業結合に比べ高い。これに対し、垂直型企業結合及び混合型企業結合は、一定の取引分野における競争単位の数を減少させないので、水平型企業結合に比べて競争に与える影響は大きくなく、一定の場合を除き、通常、一定の取引分野における競争を実質的に制限することとなるとは考えられない。
企業結合審査の対象となる企業結合が、水平型企業結合、垂直型企業結合、混合型企業結合のいずれに該当するかによって、当該企業結合が一定の取引分野における競争を実質的に制限することとなるか否かを判断する際の検討の枠組みや判断要素が異なる。
水平型企業結合
水平型企業結合の場合の基本的考え方については、以下のとおりです。
▽企業結合ガイドライン 第4-1
1 基本的考え方等
前記のとおり、水平型企業結合は、一定の取引分野における競争単位の数を減少させるので、競争に与える影響が最も直接的であり、一定の取引分野における競争を実質的に制限することとなる企業結合は、水平型企業結合に多い。
水平型企業結合が一定の取引分野における競争を実質的に制限することとなるのは、当事会社グループの単独行動による場合と、当事会社グループとその一又は複数の競争者(以下「競争者」という。)が協調的行動をとることによる場合とがあり、個々の事案においては、2つの観点から問題となるか否かが検討される。したがって、例えば、ある企業結合について、単独行動による競争の実質的制限の観点からは問題とならなくても、協調的行動による競争の実質的制限の観点からは問題となる場合がある。
(以下略)
垂直型企業結合
垂直型企業結合の場合の基本的考え方については、以下のとおりです。
▽企業結合ガイドライン 第5-1-⑴
⑴ 基本的考え方
前記第3の2のとおり、垂直型企業結合は、一定の取引分野における競争単位の数を減少させないので、水平型企業結合に比べて競争に与える影響は大きくなく、市場の閉鎖性・排他性、協調的行動等による競争の実質的制限の問題を生じない限り、通常、一定の取引分野における競争を実質的に制限することとなるとは考えられない。垂直型企業結合についても、単独行動による競争の実質的制限と協調的行動による競争の実質的制限の2つの観点から検討される。
(以下略)
混合型企業結合
混合型企業結合の場合の基本的考え方については、以下のとおりです。
▽企業結合ガイドライン 第6-1-⑴
⑴ 基本的考え方
前記第3の2のとおり、混合型企業結合は、一定の取引分野における競争単位の数を減少させないので、水平型企業結合に比べて競争に与える影響は大きくなく、市場の閉鎖性・排他性、潜在的競争の消滅、協調的行動等による競争の実質的制限の問題を生じない限り、通常、一定の取引分野における競争を実質的に制限することとなるとは考えられない。混合型企業結合についても、単独行動による競争の実質的制限と協調的行動による競争の実質的制限の2つの観点から検討される。
企業結合審査のフローチャート
企業結合ガイドラインの最後の部分に、判断方法の流れをフローチャートで示したものがあり、まとめとしてわかりやすいのでおすすめです。
結び
今回は、独占禁止法を勉強しようということで、企業結合規制について見てみました。
-

-
独占禁止法|企業結合審査とは(審査の流れ・届出基準・審査対象基準など)
続きを見る
[注記]
本記事を含む一連の勉強記事は、過去の自分に向けて、①自分の独学や経験の記録を見せる、②感覚的な理解を伝えることを優先する、③細かく正確な理解は書物に譲る、ということをコンセプトにした読みものです。ベテランの方が見てなるほどと思うようなことは書かれていないほか、業務上必要であるときなど、正確な内容については別途ご確認ください。また、法改正をはじめとした最新の情報を反映しているとは限りませんので、ご注意ください。
独占禁止法に関するその他の記事(≫Read More)
主要法令等・参考文献
主要法令等
リンクをクリックすると、法令データ提供システムまたは公正取引委員会HPに遷移します
- 独占禁止法(≫法律情報/英文)
- 排除型私的独占ガイドライン(「排除型私的独占に係る独占禁止法上の指針」)|公取委HP
- 一般指定(「不公正な取引方法」(昭和57年6月18日公正取引委員会告示第15号))|公取委HP
- 新聞特殊指定(「新聞業における特定の不公正な取引方法」(平成11年7月21日公正取引委員会告示第9号))|公取委HP
- 物流特殊指定(「特定荷主が物品の運送又は保管を委託する場合の特定の不公正な取引方法」(平成16年3月8日公正取引委員会告示第1号))|公取委HP
- 大規模小売業告示(「大規模小売業者による納入業者との取引における特定の不公正な取引方法」(平成17年5月13日公正取引委員会告示第11号))|公取委HP
- 不当廉売ガイドライン(「不当廉売に関する独占禁止法上の考え方」)|公取委HP
- 流通・取引慣行ガイドライン(「流通・取引慣行に関する独占禁止法の指針」)|公取委HP
- 優越的地位濫用ガイドライン(「優越的地位の濫用に関する独占禁止法上の考え方」)|公取委HP
- 役務委託優越的地位濫用ガイドライン(「役務の委託取引における優越的地位の濫用に関する独占禁止法上の指針」)|公取委HP
- 意見聴取規則(「公正取引委員会の意見聴取に関する規則」)
- 審査規則(「公正取引委員会の審査に関する規則」)
- 審査手続指針(「独占禁止法審査手続に関する指針」)|公取委HP
- 独禁法Q&A(「よくある質問コーナー(独占禁止法)」)|公取委HP
【企業結合規制関連】
- 届出等規則(「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第九条から第十六条までの規定による認可の申請、報告及び届出等に関する規則」)
- 企業結合ガイドライン(「企業結合審査に関する独占禁止法の運用指針」)|公取委HP
- 企業結合手続対応方針(「企業結合審査の手続に関する対応方針」)|公取委HP
【違反に対する措置(エンフォースメント)関連】
参考文献
リンクをクリックすると、Amazonのページまたは公正取引委員会HPに遷移します
- 独占禁止法〔第5版〕(菅久修一 編著、品川武、伊永大輔、鈴木健太 著)
- 注釈 独占禁止法(根岸哲 編)
- 優越的地位濫用ガイドブック(「優越的地位の濫用 ~知っておきたい取引ルール~」(公正取引委員会))|公取委HP(≫掲載ページ)
- 優越的地位の濫用規制に関する講習|公取委HP
当サイトではアフィリエイトプログラムを利用して商品・サービスを記載しています