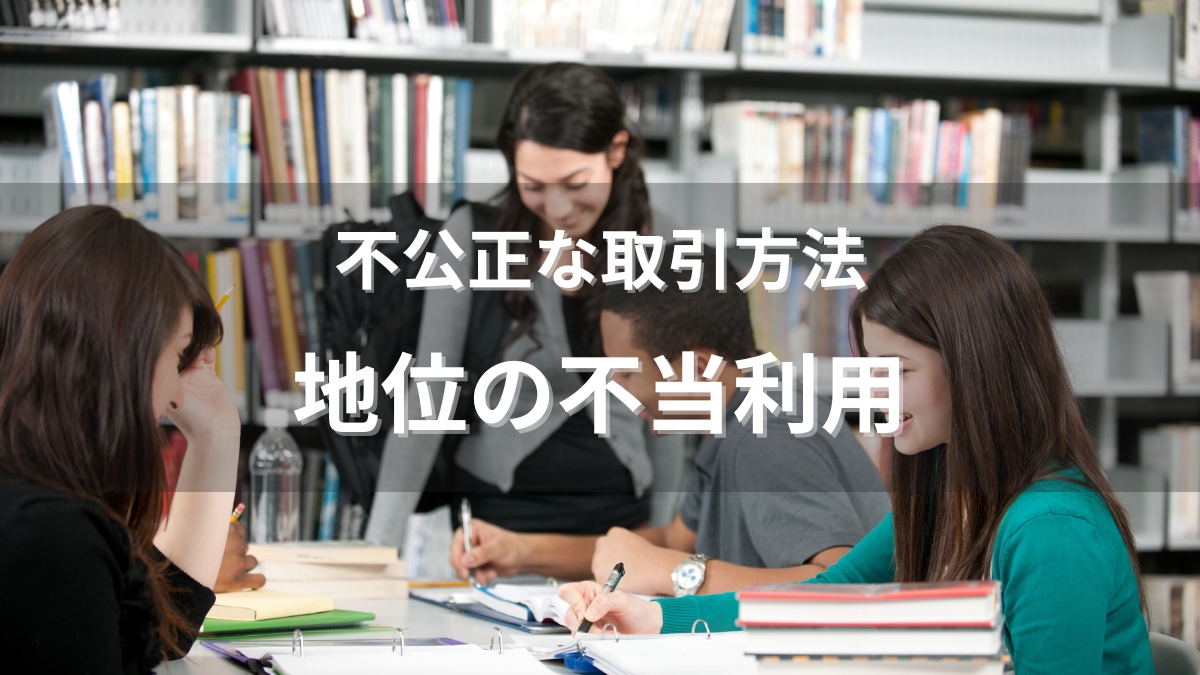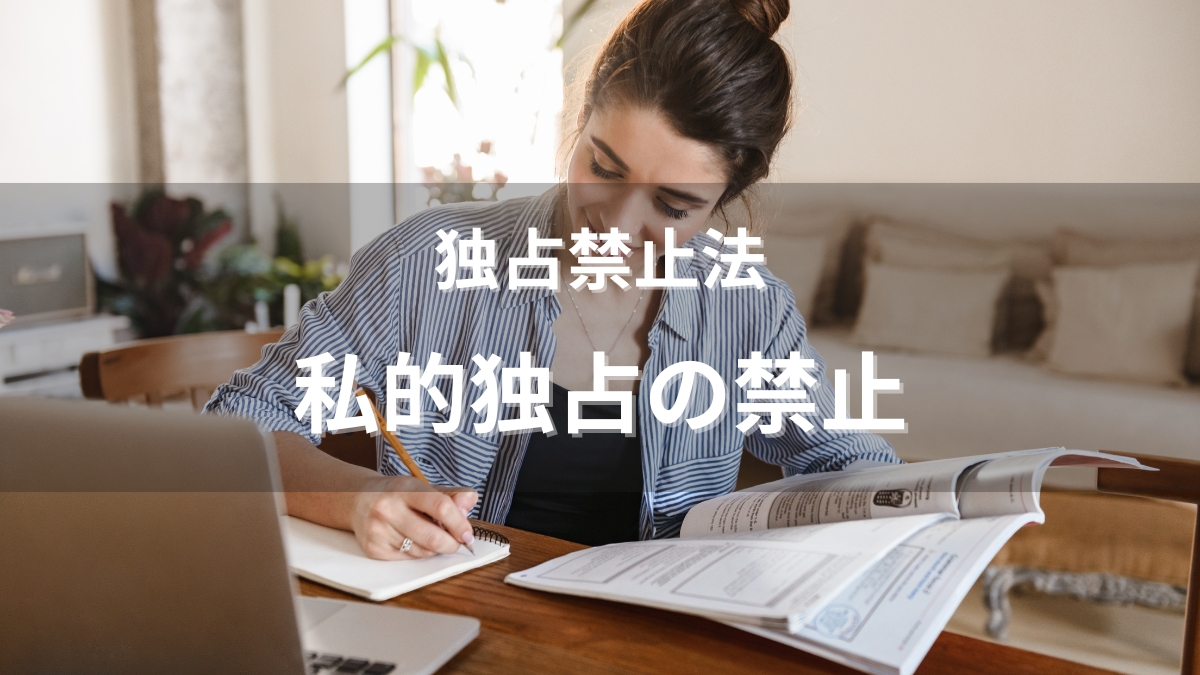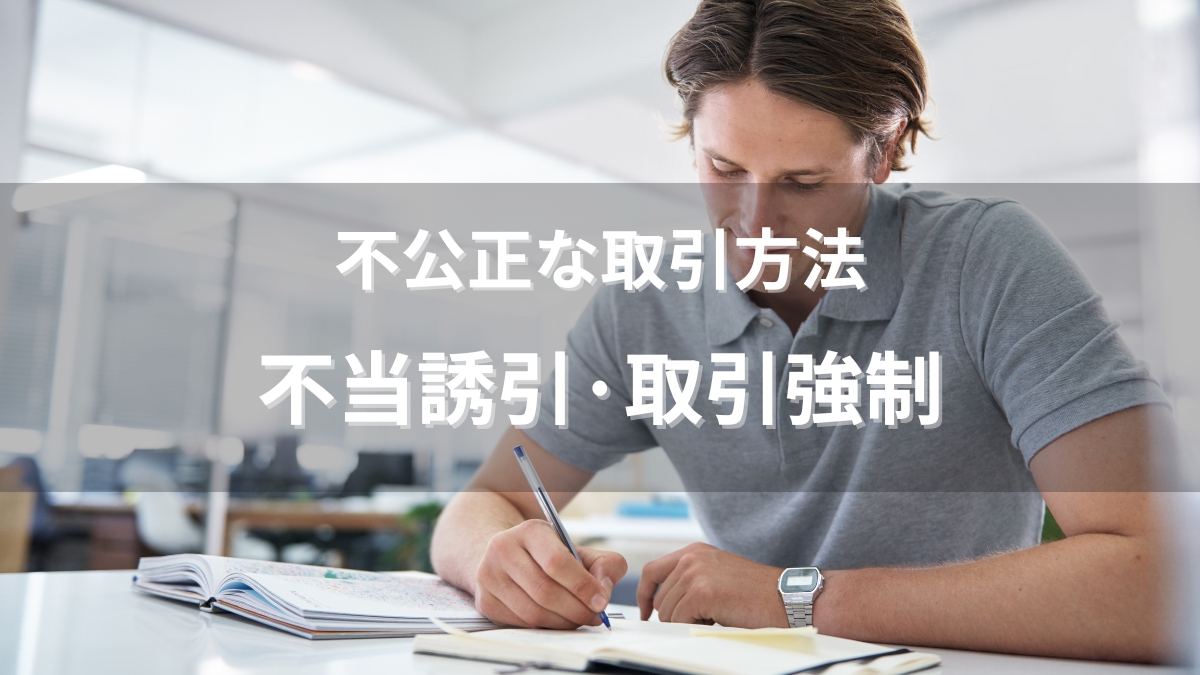今回は、独占禁止法を勉強しようということで、不公正な取引方法のうち地位の不当利用(=優越的地位の濫用)について見てみたいと思います。
ではさっそく。なお、引用部分の太字、下線、改行などは管理人によるものです。
メモ
このカテゴリーでは、インハウスとしての法務経験からピックアップした、管理人の独学や経験の記録を綴っています。
ネット上の読み物としてざっくばらんに書いており、感覚的な理解を掴むことを目指していますが、書籍などを理解する際の一助になれば幸いです。
地位の不当利用のグループ
地位の不当利用(=優越的地位の濫用)には、法定類型と告示類型の両方があります。
法定類型には、①取引に関係ない商品・役務の購入(購入要請)、②金銭役務・経済上の利益提供(利益提供要請)、③取引条件の不利益変更の3つがあります(法2条9項5号)。
告示類型は、④取引の相手方に対する不当干渉です(一般指定13項)。
ということで、全体像は以下のようになります。
「地位の不当利用」のグループ(6号ホ参照)
| 行為類型 | 細分類 | 法定類型 (法2条9項) | 告示類型 (一般指定) | 公正競争阻害性 |
|---|---|---|---|---|
| 優越的地位の濫用 | ①取引に関係ない商品・役務の購入(購入要請) | 5号イ | 正常な商慣習に照らして不当に | |
| ②金銭役務・経済上の利益提供(利益提供要請) | 5号ロ | 正常な商慣習に照らして不当に | ||
| ③取引条件の不利益変更 | 5号ハ | 正常な商慣習に照らして不当に | ||
| ④取引の相手方に対する不当干渉(不当干渉) | (6号ホ→) | 13項 | 正常な商慣習に照らして不当に |
▽法2条9項6号ホ
六 前各号に掲げるもののほか、次のいずれかに該当する行為であつて、公正な競争を阻害するおそれがあるもののうち、公正取引委員会が指定するもの
ホ 自己の取引上の地位を不当に利用して相手方と取引すること。
主な法令等
優越的地位の濫用に関する主な法令等には、以下のようなものがあります。
| 法律/告示 | 解釈・運用 | 解説 |
|---|---|---|
| 独占禁止法 + 一般指定13項 | ➢優越的地位濫用ガイドライン (「優越的地位の濫用に関する独占禁止法上の考え方」) ➢役務委託優越的地位濫用ガイドライン(「役務の委託取引における優越的地位の濫用に関する独占禁止法上の指針」) <特定の業種に関するもの> ➢「『大規模小売業者による納入業者との取引における特定の不公正な取引方法』の運用基準」 ➢「フランチャイズ・システムに関する独占禁止法上の考え方について」 ➢「役務の委託取引における優越的地位の濫用に関する独占禁止法上の指針」 | ➢優越的地位濫用ガイドブック (「優越的地位の濫用~知っておきたい取引ルール~」 |
優越的地位の濫用に関しては、優越的地位濫用ガイドライン(「優越的地位の濫用に関する独占禁止法上の考え方」)に解釈が細かく記載されています。
ガイドラインの目次は以下のようになっており、目次を見るだけでも大体の構造がわかるかと思います。
| はじめに | ||
| 第1 優越的地位の濫用規制についての基本的考え方 | ||
| 第2 「自己の取引上の地位が相手方に優越していることを利用して」の考え方 | ⑴ 乙の甲に対する取引依存度 | |
| ⑵ 甲の市場における地位 | ||
| ⑶ 乙にとっての取引先変更の可能性 | ||
| ⑷ その他甲と取引することの必要性を示す具体的事実 | ||
| 第3 「正常な商慣習に照らして不当に」の考え方 | ||
| 第4 優越的地位の濫用となる行為類型 | 1 独占禁止法第2条第9項第5号イ(購入・利用強制) | |
| 2 独占禁止法第2条第9項第5号ロ | ⑴ 協賛金等の負担の要請 | |
| ⑵ 従業員等の派遣の要請 | ||
| ⑶ その他経済上の利益の提供の要請 | ||
| 3 独占禁止法第2条第9項第5号ハ | ⑴ 受領拒否 | |
| ⑵ 返品 | ||
| ⑶ 支払遅延 | ||
| ⑷ 減額 | ||
| ⑸ その他取引の相手方に不利益となる取引条件の設定等 |
以下、行為要件→効果要件の順に内容を見てみます。
行為要件
優越的地位の利用(法2条9項5号柱書)
五 自己の取引上の地位が相手方に優越していることを利用して、正常な商慣習に照らして不当に、次のいずれかに該当する行為をすること。
イ~ハ (略)
「優越的地位の利用」の基本的な考え方としては、絶対的優越ではなく、相対的優越で足りるとされています。
▽優越的地位濫用ガイドライン 第2-1
1 取引の一方の当事者(甲)が他方の当事者(乙)に対し、取引上の地位が優越しているというためには、市場支配的な地位又はそれに準ずる絶対的に優越した地位である必要はなく、取引の相手方との関係で相対的に優越した地位であれば足りると解される。甲が取引先である乙に対して優越した地位にあるとは、乙にとって甲との取引の継続が困難になることが事業経営上大きな支障を来すため、甲が乙にとって著しく不利益な要請等を行っても、乙がこれを受け入れざるを得ないような場合である。
判断要素としては、
- 乙の甲に対する取引依存度
- 甲の市場における地位
- 乙にとっての取引先変更の可能性
- その他甲と取引することの必要性を示す具体的事実
が挙げられており、これらを総合的に考慮して、優越的地位の利用が判断されます。
各要素の内容を簡単に見てみると、以下のようになっています。
▽優越的地位濫用ガイドライン 第2-2-⑴~⑷
⑴ 乙の甲に対する取引依存度
乙の甲に対する取引依存度とは、一般に、乙が甲に商品又は役務を供給する取引の場合には、乙の甲に対する売上高を乙全体の売上高で除して算出される。
⑵ 甲の市場における地位
甲の市場における地位としては、甲の市場におけるシェアの大きさ、その順位等が考慮される。
⑶ 乙にとっての取引先変更の可能性
乙にとっての取引先変更の可能性としては、他の事業者との取引開始や取引拡大の可能性、甲との取引に関連して行った投資等が考慮される。
⑷ その他甲と取引することの必要性を示す具体的事実
その他甲と取引することの必要性を示す具体的事実としては、甲との取引の額、甲の今後の成長可能性、取引の対象となる商品又は役務を取り扱うことの重要性、甲と取引することによる乙の信用の確保、甲と乙の事業規模の相違等が考慮される。
購入要請(5号イ)
イ 継続して取引する相手方(新たに継続して取引しようとする相手方を含む。ロにおいて同じ。)に対して、当該取引に係る商品又は役務以外の商品又は役務を購入させること。
これは、取引に関係ない商品・役務を購入させることです。
「当該取引に係る商品又は役務以外の商品又は役務」には、自己の指定する事業者が供給する商品又は役務も含まれます。
「購入させる」には、事実上、購入を余儀なくさせていると認められる場合も含まれます。つまり、実質的判断になります。
判断基準の内容は、以下のようになっています。
▽優越的地位濫用ガイドライン 第4-1-⑴⑵
⑴ 取引上の地位が相手方に優越している事業者が、取引の相手方に対し、当該取引に係る商品又は役務以外の商品又は役務の購入を要請する場合であって、当該取引の相手方が、それが事業遂行上必要としない商品若しくは役務であり、又はその購入を希望していないときであったとしても、今後の取引に与える影響を懸念して当該要請を受け入れざるを得ない場合には、正常な商慣習に照らして不当に不利益を与えることとなり、優越的地位の濫用として問題となる。
⑵ 他方、取引の相手方に対し、特定の仕様を指示して商品の製造又は役務の提供を発注する際に、当該商品若しくは役務の内容を均質にするため又はその改善を図るため必要があるなど合理的な必要性から、当該取引の相手方に対して当該商品の製造に必要な原材料や当該役務の提供に必要な設備を購入させる場合には、正常な商慣習に照らして不当に不利益を与えることとならず、優越的地位の濫用の問題とはならない。
利益提供要請(5号ロ)
ロ 継続して取引する相手方に対して、自己のために金銭、役務その他の経済上の利益を提供させること。
これは、金銭・役務などの経済上の利益を提供させることです。
「経済上の利益」の提供とは、協賛金・協力金等の名目のいかんを問わず行われる、金銭の提供、作業への労務の提供などをいいます。
何を提供させようとするかによって、
- 協賛金等の負担の要請(=”お金を出せ”)
- 従業員等の派遣の要請(=”人(労力)を出せ”)
- その他経済上の利益の提供の要請
の3つに分けて解説されています。
判断基準の内容は、以下のようになっています。
▽優越的地位濫用ガイドライン 第4-2-⑴~⑶
⑴ 協賛金等の負担の要請
ア 取引上の地位が相手方に優越している事業者が、取引の相手方に対し、協賛金等の名目による金銭の負担を要請する場合であって、当該協賛金等の負担額及びその算出根拠、使途等について、当該取引の相手方との間で明確になっておらず、当該取引の相手方にあらかじめ計算できない不利益を与えることとなる場合や、当該取引の相手方が得る直接の利益(注9)等を勘案して合理的であると認められる範囲を超えた負担となり、当該取引の相手方に不利益を与えることとなる場合(注10)には、正常な商慣習に照らして不当に不利益を与えることとなり、優越的地位の濫用として問題となる。
イ 事業者が、催事、広告等を行うに当たり、取引の相手方に対し、その費用の一部として協賛金等の負担を要請することがある。このような要請は、流通業者によって行われることが多いが、流通業者が商品の納入業者に協賛金等の負担を要請する場合には、当該費用を負担することが納入商品の販売促進につながるなど当該納入業者にとっても直接の利益となることがある。協賛金等が、それを負担することによって得ることとなる直接の利益の範囲内であるものとして、取引の相手方の自由な意思により提供される場合には、正常な商慣習に照らして不当に不利益を与えることとならず、優越的地位の濫用の問題とはならない。
⑵ 従業員等の派遣の要請
ア 取引上の地位が相手方に優越している事業者が、取引の相手方に対し、従業員等(注11)の派遣を要請する場合であって、どのような場合に、どのような条件で従業員等を派遣するかについて、当該取引の相手方との間で明確になっておらず、当該取引の相手方にあらかじめ計算できない不利益を与えることとなる場合や、従業員等の派遣を通じて当該取引の相手方が得る直接の利益(注12)等を勘案して合理的であると認められる範囲を超えた負担となり、当該取引の相手方に不利益を与えることとなる場合(注13)には、正常な商慣習に照らして不当に不利益を与えることとなり、優越的地位の濫用として問題となる。取引の相手方に対し、従業員等の派遣に代えて、これに相当する人件費を負担させる場合も、これと同様である。
イ メーカーや卸売業者が百貨店、スーパー等の小売業者からの要請を受け、自己が製造した商品又は自己が納入した商品の販売等のためにその従業員等を派遣する場合がある。こうした従業員等の派遣は、メーカーや卸売業者にとって消費者ニーズの動向を直接把握できる、小売業者にとって専門的な商品知識の不足が補われる等の利点を有している場合がある。従業員等の派遣が、それによって得ることとなる直接の利益の範囲内であるものとして、取引の相手方の自由な意思により行われる場合には、正常な商慣習に照らして不当に不利益を与えることとならず、優越的地位の濫用の問題とはならない。また、従業員等の派遣の条件についてあらかじめ当該取引の相手方と合意(注14)し、かつ、派遣のために通常必要な費用を自己が負担する場合も、これと同様である。
⑶ その他経済上の利益の提供の要請
ア 協賛金等の負担の要請や従業員等の派遣の要請以外であっても、取引上の地位が相手方に優越している事業者が、正当な理由がないのに、取引の相手方に対し、発注内容に含まれていない、金型(木型その他金型に類するものを含む。以下同じ。)等の設計図面、特許権等の知的財産権、従業員等の派遣以外の役務提供その他経済上の利益の無償提供を要請する場合であって、当該取引の相手方が今後の取引に与える影響を懸念してそれを受け入れざるを得ない場合には、正常な商慣習に照らして不当に不利益を与えることとなり、優越的地位の濫用として問題となる(注 15)。
イ 一方、前記アに列記した経済上の利益が無償で提供される場合であっても、当該経済上の利益が、ある商品の販売に付随して当然に提供されるものであって、当該商品の価格にそもそも反映されているようなときは、正常な商慣習に照らして不当に不利益を与えることとならず、優越的地位の濫用の問題とはならない。
取引条件の不利益変更(5号ハ)
ハ 取引の相手方からの取引に係る商品の受領を拒み、取引の相手方から取引に係る商品を受領した後当該商品を当該取引の相手方に引き取らせ、取引の相手方に対して取引の対価の支払を遅らせ、若しくはその額を減じ、その他取引の相手方に不利益となるように取引の条件を設定し、若しくは変更し、又は取引を実施すること。
これは、取引条件を相手方にとって不利益に変更することです。
ガイドラインでは、
- 受領拒否
- 返品
- 支払遅延
- 減額
- その他取引の相手方に不利益となる取引条件の設定等
の5つに分けて解説されています。
判断基準の内容は、以下のようになっています。
▽優越的地位濫用ガイドライン 第4-3-⑴~⑸
⑴ 受領拒否
ア 取引上の地位が相手方に優越している事業者が、取引の相手方から商品を購入する契約をした後において、正当な理由がないのに、当該商品の全部又は一部の受領を拒む場合(注16)であって、当該取引の相手方が、今後の取引に与える影響等を懸念してそれを受け入れざるを得ない場合には、正常な商慣習に照らして不当に不利益を与えることとなり、優越的地位の濫用として問題となる(注17)。
イ 他方、①当該取引の相手方から購入した商品に瑕疵がある場合、注文した商品と異なる商品が納入された場合、納期に間に合わなかったために販売目的が達成できなかった場合等、当該取引の相手方側の責めに帰すべき事由がある場合、②商品の購入に当たって当該取引の相手方との合意により受領しない場合の条件を定め、その条件に従って受領しない場合(注18)、③あらかじめ当該取引の相手方の同意を得て(注19)、かつ、商品の受領を拒むことによって当該取引の相手方に通常生ずべき損失(注20)を負担する場合には、正常な商慣習に照らして不当に不利益を与えることとならず、優越的地位の濫用の問題とはならない。
⑵ 返品
ア 取引上の地位が相手方に優越している事業者が、取引の相手方に対し、当該取引 の相手方から受領した商品を返品する場合であって、どのような場合に、どのような条件で返品するかについて、当該取引の相手方との間で明確になっておらず、当該取引の相手方にあらかじめ計算できない不利益を与えることとなる場合、その他正当な理由がないのに、当該取引の相手方から受領した商品を返品する場合であって、当該取引の相手方が、今後の取引に与える影響等を懸念してそれを受け入れざるを得ない場合には、正常な商慣習に照らして不当に不利益を与えることとなり、優越的地位の濫用として問題となる。
イ 他方、①当該取引の相手方から購入した商品に瑕疵がある場合、注文した商品と異なる商品が納入された場合、納期に間に合わなかったために販売目的が達成できなかった場合等、当該取引の相手方側の責めに帰すべき事由により、当該商品を受領した日から相当の期間内に、当該事由を勘案して相当と認められる数量の範囲内(注21)で返品する場合、②商品の購入に当たって当該取引の相手方との合意により返品の条件を定め、その条件に従って返品する場合(注22)、③あらかじめ当該取引の相手方の同意を得て、かつ、商品の返品によって当該取引の相手方に通常生ずべき損失を自己が負担する場合、④当該取引の相手方から商品の返品を受けたい旨の申出があり、かつ、当該取引の相手方が当該商品を処分することが当該取引の相手方の直接の利益(注23)となる場合には、正常な商慣習に照らして不当に不利益を与えることとならず、優越的地位の濫用の問題とはならない。
⑶ 支払遅延
ア 取引上の地位が相手方に優越している事業者が、正当な理由がないのに、契約で定めた支払期日に対価を支払わない場合であって、当該取引の相手方が、今後の取引に与える影響等を懸念してそれを受け入れざるを得ない場合には、正常な商慣習に照らして不当に不利益を与えることとなり、優越的地位の濫用として問題となる。 また、契約で定めた支払期日より遅れて対価を支払う場合だけでなく、取引上の地位が優越している事業者が、一方的に対価の支払期日を遅く設定する場合や、支払期日の到来を恣意的に遅らせる場合にも、当該取引の相手方に正常な商慣習に照らして不当に不利益を与えることとなりやすく、優越的地位の濫用として問題となりやすい。
イ 他方、あらかじめ当該取引の相手方の同意を得て、かつ、対価の支払の遅延によって当該取引の相手方に通常生ずべき損失を自己が負担する場合には、正常な商慣習に照らして不当に不利益を与えることとならず、優越的地位の濫用の問題とはならない。
⑷ 減額
ア 取引上の地位が相手方に優越している事業者が、商品又は役務を購入した後にお いて、正当な理由がないのに、契約で定めた対価を減額する場合であって、当該取引の相手方が、今後の取引に与える影響等を懸念してそれを受け入れざるを得ない場合には、正常な商慣習に照らして不当に不利益を与えることとなり、優越的地位の濫用として問題となる。 契約で定めた対価を変更することなく、商品又は役務の仕様を変更するなど対価を実質的に減額する場合も、これと同様である。
イ 他方、①当該取引の相手方から購入した商品又は提供された役務に瑕疵がある場合、注文内容と異なる商品が納入され又は役務が提供された場合、納期に間に合わなかったために販売目的が達成できなかった場合等、当該取引の相手方側の責めに帰すべき事由により、当該商品が納入され又は当該役務が提供された日から相当の期間内に、当該事由を勘案して相当と認められる金額の範囲内(注24)で対価を減額する場合、②対価を減額するための要請が対価に係る交渉の一環として行われ、その額が需給関係を反映したものであると認められる場合には、正常な商慣習に照らして不当に不利益を与えることとならず、優越的地位の濫用の問題とはならない。
⑸ その他取引の相手方に不利益となる取引条件の設定等
前記第4の1、第4の2及び第4の3⑴から⑷までの行為類型に該当しない場合であっても、取引上の地位が優越している事業者が、取引の相手方に正常な商慣習に照らして不当に不利益となるように取引の条件を設定し、若しくは変更し、又は取引を実施する場合には、優越的地位の濫用として問題となる。
上記⑸の「その他取引の相手方に不利益となる取引条件の設定等」としては、
- 取引の対価の一方的決定
- やり直しの要請
- その他当該取引の相手方に正常な商慣習に照らして不当に不利益を与えること
などが挙げられています(優越的地位濫用ガイドライン)。
▽公正取引委員会のXアカウント
【 #優越的地位の濫用 とは】
— 公正取引委員会 (@jftc) February 22, 2019
優越的地位の濫用規制( #独占禁止法 )は,
取引上優越した地位にある事業者が,取引の相手方に対し,
協賛金負担や従業員派遣などをさせることにより,正常な商習慣に照らして不当に不利益を与えることを禁止しています。
パンフレット(PDF)→https://t.co/ZJ3RLSjIj6 pic.twitter.com/sDIB0wM3GA
不当干渉(一般指定13項)
告示類型である不当干渉(一般指定13項)は、取引行為ではない点で法定類型とは異質ですが、優越的地位を利用して相手会社の役員選任について不当に干渉することを禁じるものです。
▽法2条9項6号ホ
六 前各号に掲げるもののほか、次のいずれかに該当する行為であつて、公正な競争を阻害するおそれがあるもののうち、公正取引委員会が指定するもの
ホ 自己の取引上の地位を不当に利用して相手方と取引すること。
↓ 告示による指定
▽告示類型(一般指定13項)
(取引の相手方の役員選任への不当干渉)
13 自己の取引上の地位が相手方に優越していることを利用して、正常な商慣習に照らして不当に、取引の相手方である会社に対し、当該会社の役員(法第二条第三項の役員をいう。以下同じ。)の選任についてあらかじめ自己の指示に従わせ、又は自己の承認を受けさせること。
効果要件(公正競争阻害性)
取引上の地位が優越していること自体は取引の実態として普通にあり得ることであり、それ自体を違法とするものではありません。
そこで、「正常な商慣習に照らして不当に」との文言が使われています。
ただ、優越的地位の「濫」用と呼ばれるとおり、優越的地位の濫用という行為類型においては、行為要件自体が優越的地位を利用して不合理な行為を受け入れさせているものといえるので(=行為要件自体が不当性を含んでいる)、行為要件に該当すれば、通常は公正競争阻害性についても推認されるといえます。
言い換えると、濫用(=地位の相対的優越を利用して不合理を受け入れさせる)の判断と、公正競争阻害性の判断は、重なる部分が多いということです。
下請法の規制
優越的地位の濫用については、これらの行為をより迅速かつ効果的に規制しようとする別の法律として下請法(「下請代金支払遅延等防止法」)があります。
下請法は、独占禁止法の補完法とか補助立法といわれていますが、どういうところが”より迅速かつ効果的な規制”なのかというと、
- 資本金に一定以上の差がある親事業者をいわば定型的に「優越的地位」にあるとみて、
- かつ、濫用が行われがちな取引類型を括り出して適用対象にし、
- 書面の交付義務など、親事業者のより細やかな義務や禁止行為を規定した、
というイメージです(管理人の理解の仕方)。
独占禁止法の補完法である点については、下請法の講習会テキスト(「下請取引適正化推進講習会テキスト」(公正取引委員会・中小企業庁))に以下のようなわかりやすい解説があります。
▽講習会テキスト 1-⑴|公取委HP(≫掲載ページ)
1 下請代金支払遅延等防止法の内容
⑴ 本法制定の趣旨
下請取引における下請代金の支払遅延等の行為は、独占禁止法の不公正な取引方法のうち優越的地位の濫用行為に該当し、同法第19条の規定に違反するおそれがある行為であるが、同法により規制する場合は、当該行為が「取引上優越した地位を利用したものかどうか」、「不当に不利益なものかどうか」を個別に認定する必要がある。この認定には、相当の期間を要し問題解決の時機を逸するおそれがある上、親事業者と下請事業者との継続的取引関係をむしろ悪化させる要因となる場合もあり、結果として下請事業者の利益にならないことも考えられる。
また、下請取引の性格上、下請事業者が親事業者の違反行為を公正取引委員会又は中小企業庁に申告することは、余り期待できない。
したがって、下請事業者の利益を確保するためには、独占禁止法の違反事件処理手続とは別の簡易な手続が必要であるとの考えから、下請代金支払遅延等防止法(以下「本法」という。)が、昭和31年に独占禁止法の補完法として制定された。
すなわち、本法は、適用対象を明確にし、違反行為の類型を具体的に法定するとともに、独占禁止法に比較して簡易な手続を規定し、迅速かつ効果的に下請事業者の保護を図ろうとするものである。
▽公正取引委員会のXアカウント
【#2024ひとこと講座 26 下請法とは?】
— 公正取引委員会 (@jftc) May 21, 2024
下請取引における優越的地位の濫用行為を迅速・効果的に規制するため、独禁法の補完法として制定されたのが「下請代金支払遅延等防止法(略称:下請法)」です。
適用対象が明確で、違反行為の類型も具体的に法定されているのが特徴。https://t.co/flhdezpEhu pic.twitter.com/rzevDeyVBA
下請法の規制の内容については、以下の関連記事などにくわしく書いています。
結び
今回は、独占禁止法を勉強しようということで、不公正な取引方法のうち地位の不当利用(=優越的地位の濫用)について見てみました。
優越的地位の濫用については、以下のような相談・情報提供窓口があります。
-
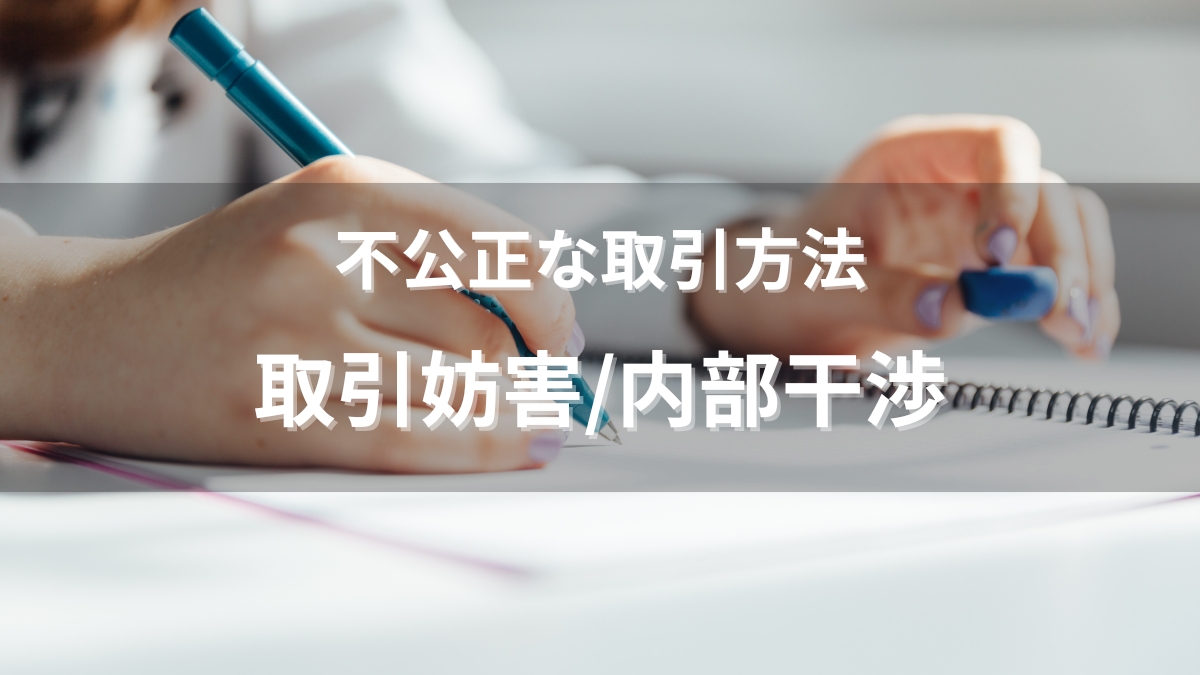
-
独占禁止法を勉強しよう|不公正な取引方法-取引妨害・内部干渉
続きを見る
[注記]
本記事を含む一連の勉強記事は、過去の自分に向けて、①自分の独学や経験の記録を見せる、②感覚的な理解を伝えることを優先する、③細かく正確な理解は書物に譲る、ということをコンセプトにした読みものです。ベテランの方が見てなるほどと思うようなことは書かれていないほか、業務上必要であるときなど、正確な内容については別途ご確認ください。また、法改正をはじめとした最新の情報を反映しているとは限りませんので、ご注意ください。
独占禁止法に関するその他の記事(≫Read More)
主要法令等・参考文献
主要法令等
リンクをクリックすると、法令データ提供システムまたは公正取引委員会HPに遷移します
- 独占禁止法(≫法律情報/英文)
- 排除型私的独占ガイドライン(「排除型私的独占に係る独占禁止法上の指針」)|公取委HP
- 一般指定(「不公正な取引方法」(昭和57年6月18日公正取引委員会告示第15号))|公取委HP
- 新聞特殊指定(「新聞業における特定の不公正な取引方法」(平成11年7月21日公正取引委員会告示第9号))|公取委HP
- 物流特殊指定(「特定荷主が物品の運送又は保管を委託する場合の特定の不公正な取引方法」(平成16年3月8日公正取引委員会告示第1号))|公取委HP
- 大規模小売業告示(「大規模小売業者による納入業者との取引における特定の不公正な取引方法」(平成17年5月13日公正取引委員会告示第11号))|公取委HP
- 不当廉売ガイドライン(「不当廉売に関する独占禁止法上の考え方」)|公取委HP
- 流通・取引慣行ガイドライン(「流通・取引慣行に関する独占禁止法の指針」)|公取委HP
- 優越的地位濫用ガイドライン(「優越的地位の濫用に関する独占禁止法上の考え方」)|公取委HP
- 役務委託優越的地位濫用ガイドライン(「役務の委託取引における優越的地位の濫用に関する独占禁止法上の指針」)|公取委HP
- 意見聴取規則(「公正取引委員会の意見聴取に関する規則」)
- 審査規則(「公正取引委員会の審査に関する規則」)
- 審査手続指針(「独占禁止法審査手続に関する指針」)|公取委HP
- 独禁法Q&A(「よくある質問コーナー(独占禁止法)」)|公取委HP
【企業結合規制関連】
- 届出等規則(「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第九条から第十六条までの規定による認可の申請、報告及び届出等に関する規則」)
- 企業結合ガイドライン(「企業結合審査に関する独占禁止法の運用指針」)|公取委HP
- 企業結合手続対応方針(「企業結合審査の手続に関する対応方針」)|公取委HP
【違反に対する措置(エンフォースメント)関連】
参考文献
リンクをクリックすると、Amazonのページまたは公正取引委員会HPに遷移します
- 独占禁止法〔第5版〕(菅久修一 編著、品川武、伊永大輔、鈴木健太 著)
- 注釈 独占禁止法(根岸哲 編)
- 優越的地位濫用ガイドブック(「優越的地位の濫用 ~知っておきたい取引ルール~」(公正取引委員会))|公取委HP(≫掲載ページ)
- 優越的地位の濫用規制に関する講習|公取委HP
当サイトではアフィリエイトプログラムを利用して商品・サービスを記載しています