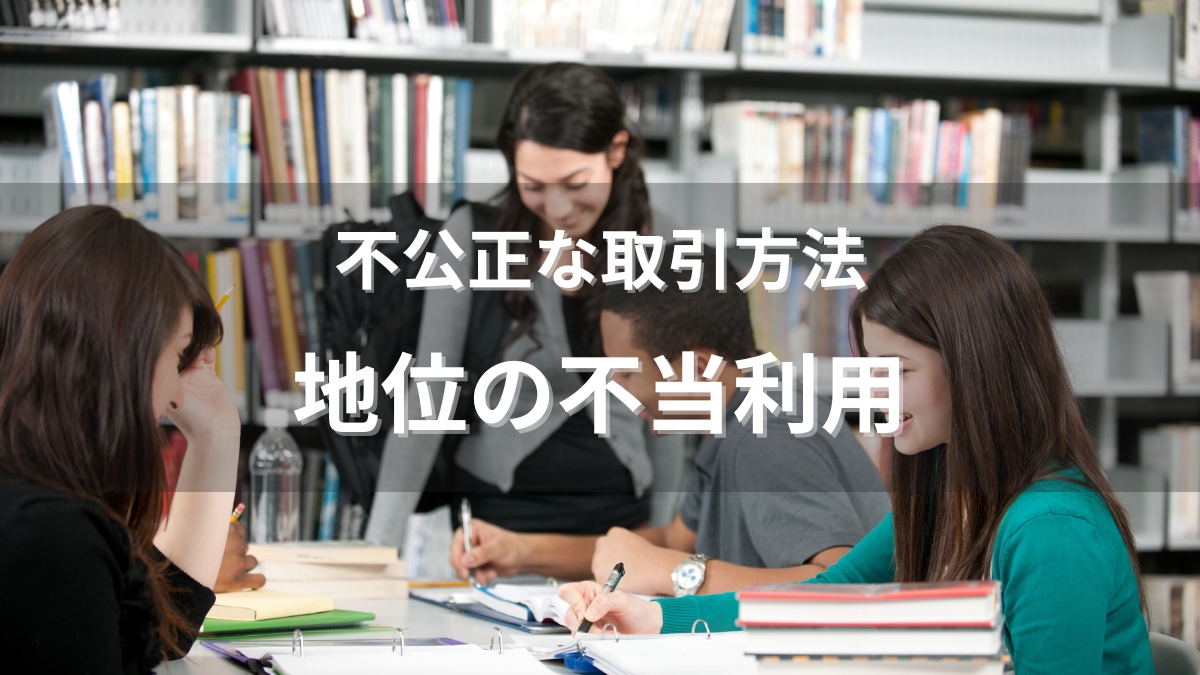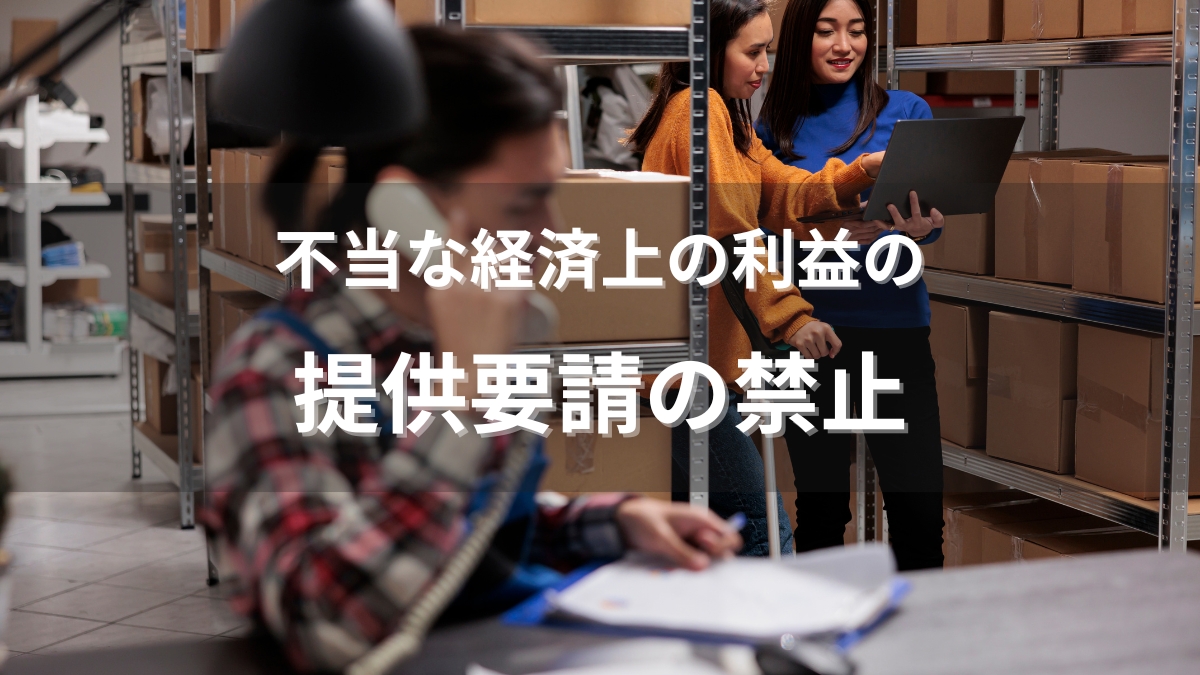今回は、下請法を勉強しようということで、まず規制の仕組み(全体像)を見てみたいと思います。
ではさっそく。なお、引用部分の太字、下線、改行などは管理人によるものです。
メモ
このカテゴリーでは、インハウスとしての法務経験からピックアップした、管理人の独学や経験の記録を綴っています。
ネット上の読み物としてざっくばらんに書いており、感覚的な理解を掴むことを目指していますが、書籍などを理解する際の一助になれば幸いです。
規制の仕組み(全体像)
下請法の規制の仕組み自体は、非常にシンプルです。
下請法の適用要件を満たす場合は、親事業者に4項目の義務と11項目の禁止が課せられる、というふうになっています。
下請法の概要|公正取引委員会HP
下請法の適用要件
下請法は、適用対象となる下請取引の範囲を、取引の主体と取引の内容という2つの側面から定めています。
まず、取引の主体については、親事業者が下請事業者に対し優越的地位にあると見られる”立場の格差”を、資本金の大小の差によって定型的に判断できるようにしています。
つまり、資本金の規模の差によって力関係の差を定型的に定めています。これが「資本金区分」です。以下の4パターンがあります。
次に、取引の内容については、濫用が行われがちな取引類型を括り出して、以下の4つを適用対象としています。
▽公正取引委員会のXアカウント
【#下請取引適正化推進月間】 #下請法 の基本①
— 公正取引委員会 (@jftc) November 7, 2023
下請法が適用されるには、
(1)取引の内容
(2)資本金区分
の2つの条件を満たす取引である必要があります。https://t.co/flhdezpEhu#下請 pic.twitter.com/o2DBsIOOqf
適用の効果
以上により親事業者が下請法の適用対象となる場合、親事業者には、以下のような4項目の義務と11項目の禁止が課せられます。
親事業者の4つの義務は、「~しなければならない」という作為義務であり、親事業者の11の禁止行為は、「~してはならない」という不作為義務です。
▽公正取引委員会のXアカウント
親事業者には、4つの義務と11項目の禁止事項が定められています。
— 公正取引委員会 (@jftc) May 27, 2024
義務や禁止事項に反した場合、下請事業者の了解を得ていても、親事業者に違法性の意識がなくても、下請法違反になります。(2/2)
義務→https://t.co/MC9eJuSb06
禁止行為→https://t.co/fVA6Ec4nPU pic.twitter.com/IkoDJUmH02
主な法令など
下請法に関する主な法令などを表にしてみると、以下のとおりです。
| 法令 | 解釈・運用 | 解説書 |
|---|---|---|
| ➢下請法 (「下請代金支払遅延等防止法」) ➢下請法施行令 (「下請代金支払遅延等防止法施行令」) | ➢下請法運用基準 (「下請代金支払遅延等防止法に関する運用基準」) ➢下請法Q&A (「よくある質問コーナー(下請法)」) | ➢ポイント解説下請法(親事業者向け) (「下請代金支払遅延等防止法ガイドブック」) ➢講習会テキスト (「下請取引適正化推進講習会テキスト」) |
内容を調べたいときは、「下請法運用基準」と「講習会テキスト」が重要になります。
下請法の解釈は「下請法運用基準」で示されていますので、この運用基準がルールの一部として重要です。また、運用基準の内容を含めつつ全体を解説している教材が「講習会テキスト」であり、実務上の基本書のような感じになっています。講習会テキストには細かいQ&Aも掲載されています。
どれもネット上で見ることができます。
下請法の位置づけ
では下請法はそもそも何をしたいのか?ということで、法律の中での位置づけについても見てみます。
下請法は、親事業者の下請事業者に対する優越的地位の濫用行為を取り締まるために制定された法律で、正式名称は「下請代金支払遅延等防止法」(昭和31年法律第120号)といいます。
法律の目的は、以下のとおり「親事業者の下請事業者に対する取引を公正ならしめ」「下請事業者の利益を保護」することです。
▽下請法1条
(目的)
第一条 この法律は、下請代金の支払遅延等を防止することによつて、親事業者の下請事業者に対する取引を公正ならしめるとともに、下請事業者の利益を保護し、もつて国民経済の健全な発達に寄与することを目的とする。
独占禁止法の補完法
「優越的地位の濫用」は独占禁止法の行為規制のひとつですが、下請法は、独占禁止法の補完法とか補助立法といわれていて、この「優越的地位の濫用」行為をより迅速かつ効果的に規制しようとするものです。
位置づけを見た目にわかるようにすると、以下のような感じになります。
独占禁止法との関係
- 行為規制
- 私的独占
- 不当な取引制限
- 不公正な取引方法
- ①差別的取扱い
- ②不当対価
- ③不当な顧客誘引・取引強制
- ④不当拘束
- ⑤優越的地位の濫用 ←この部分の補完法
- ⑥取引妨害・内部干渉
- 構造規制(企業結合規制)
「優越的地位の濫用」というのは、優越的地位を利用して以下のような行為をすることです。独占禁止法の2条9項5号イ・ロ・ハと6号ホに定められています。
では、これに対して下請法のどこが「より迅速かつ効果的な規制」なのか?というと、
- 独占禁止法では、「優越的地位」を個別に判定する必要があるのに対し、
- 下請法では、
- 資本金に一定以上の差がある親事業者をいわば定型的に「優越的地位」にあるとみて、かつ、
- 濫用が行われがちな取引類型を括り出して適用対象にし、
- 書面の交付義務など、親事業者のより細やかな義務や禁止行為を規定した
という感じになります。
正確にいうと、以下のような内容になります。
▽講習会テキスト 1-⑴
1 下請代金支払遅延等防止法の内容
⑴ 本法制定の趣旨
下請取引における下請代金の支払遅延等の行為は、独占禁止法の不公正な取引方法のうち優越的地位の濫用行為に該当し、同法第19条の規定に違反するおそれがある行為であるが、同法により規制する場合は、当該行為が「取引上優越した地位を利用したものかどうか」、「不当に不利益なものかどうか」を個別に認定する必要がある。この認定には、相当の期間を要し問題解決の時機を逸するおそれがある上、親事業者と下請事業者との継続的取引関係をむしろ悪化させる要因となる場合もあり、結果として下請事業者の利益にならないことも考えられる。
また、下請取引の性格上、下請事業者が親事業者の違反行為を公正取引委員会又は中小企業庁に申告することは、余り期待できない。
したがって、下請事業者の利益を確保するためには、独占禁止法の違反事件処理手続とは別の簡易な手続が必要であるとの考えから、下請代金支払遅延等防止法(以下「本法」という。)が、昭和31年に独占禁止法の補完法として制定された。
すなわち、本法は、適用対象を明確にし、違反行為の類型を具体的に法定するとともに、独占禁止法に比較して簡易な手続を規定し、迅速かつ効果的に下請事業者の保護を図ろうとするものである。
▽公正取引委員会のXアカウント
【#2024ひとこと講座 26 下請法とは?】
— 公正取引委員会 (@jftc) May 21, 2024
下請取引における優越的地位の濫用行為を迅速・効果的に規制するため、独禁法の補完法として制定されたのが「下請代金支払遅延等防止法(略称:下請法)」です。
適用対象が明確で、違反行為の類型も具体的に法定されているのが特徴。https://t.co/flhdezpEhu pic.twitter.com/rzevDeyVBA
独占禁止法と下請法の適用関係
下請法は独占禁止法の補完法なので、下請法が適用されない場合でも、独占禁止法に基づく優越的地位の濫用規制が適用される可能性はあります。その点、注意が必要です。
ちなみに、では、独占禁止法と下請法の両方の要件を満たす場合にどうなるのか?というと、管理人が見た範囲では、意外とはっきりしません。昔の「優越的地位濫用ガイドライン」に、”双方が適用可能な場合には、通常、下請法を適用する”旨の記載があったようですが、今は見当たりません。
また、解説書には、“事実上下請法が優先的に適用される”と書いたものなどもありますが、通常とか事実上の意味が、必ずしもはっきりはしていないように思います。
なお、下請法に基づく勧告に従った場合には独占禁止法が適用されないこと(排除措置命令や課徴金納付命令が課されない)については、明文があります(下請法8条)。
▽下請法8条
(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律との関係)
第八条 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)第二十条及び第二十条の六の規定は、公正取引委員会が前条第一項から第三項までの規定による勧告をした場合において、親事業者がその勧告に従つたときに限り、親事業者のその勧告に係る行為については、適用しない。
特別法的な位置づけであるのは間違いないですが、”特別法は一般法に優先する”という意味での特別法・一般法の関係というのとは若干違うということなのかもしれません。
(下請法が適用される場合は独占禁止法の適用が排除される、というわけではない。例えば、下請法に基づく勧告に従わなかったときは独占禁止法上の措置が発動されることがある。講習会テキスト1の⑹のイ参照)
なので、”補完法”とか”補助立法”とかいう表現が使われていることが多いのではなかろうか、と思います(管理人の私見)。
学習するときの流れ
最後に、(仕事上必要になって)下請法を勉強しないといけなくなったときの、学習の流れについて考えてみます。
本記事で見たように下請法の仕組み自体は比較的シンプルなので、学習の流れも、それに沿っていく感じでいいと思います。
まず、要件(適用要件)と効果に分ける。
そして、下請法の適用要件については、①資本金区分と②取引の内容によって判断される。
適用対象となった場合の効果としては、親事業者に4つの義務と11の禁止行為が課せられる。
最後に、違反行為に対する措置等(エンフォースメント)がある。
これらの流れを踏まえると、学習の流れはたとえば以下のようになるかと思います。
学習の流れ
- 規制の仕組み
- まず全体像を掴む
- 下請法の適用要件
- 「資本金区分」の要件と「取引の内容」の要件を掴む
- 適用の効果
- 親事業者の4つの義務と、11の禁止行為を頭に入れる
- 11の禁止行為は、(ⅰ)4条1項のグループ(直ちに違法となるグループ)と、(ⅱ)4条2項のグループ(下請事業者の利益を不当に害するときに違法となるグループ)に分かれる
- 違反行為に対する措置等
- 違反に対する措置(エンフォースメント)を把握する
結び
今回は、下請法を勉強しようということで、規制の仕組み(全体像)について見てみました。
下請法に関する各種の情報については、以下の公正取引委員会のページからアクセスできます。
下請法|公正取引委員会HP
次の記事は、資本金区分(取引の主体に関する要件)についてです。
-

-
下請法|資本金区分(取引の主体に関する要件)
続きを見る
[注記]
本記事を含む一連の勉強記事は、過去の自分に向けて、①自分の独学や経験の記録を見せる、②感覚的な理解を伝えることを優先する、③細かく正確な理解は書物に譲る、ということをコンセプトにした読みものです。ベテランの方が見てなるほどと思うようなことは書かれていないほか、業務上必要であるときなど、正確な内容については別途ご確認ください。また、法改正をはじめとした最新の情報を反映しているとは限りませんので、ご注意ください。
下請法に関するその他の記事(≫Read More)
参考文献
※注:「優越的地位濫用規制と下請法の解説と分析」には第4版があります
当サイトではアフィリエイトプログラムを利用して商品・サービスを記載しています
主要法令等
主要法令等
参考資料