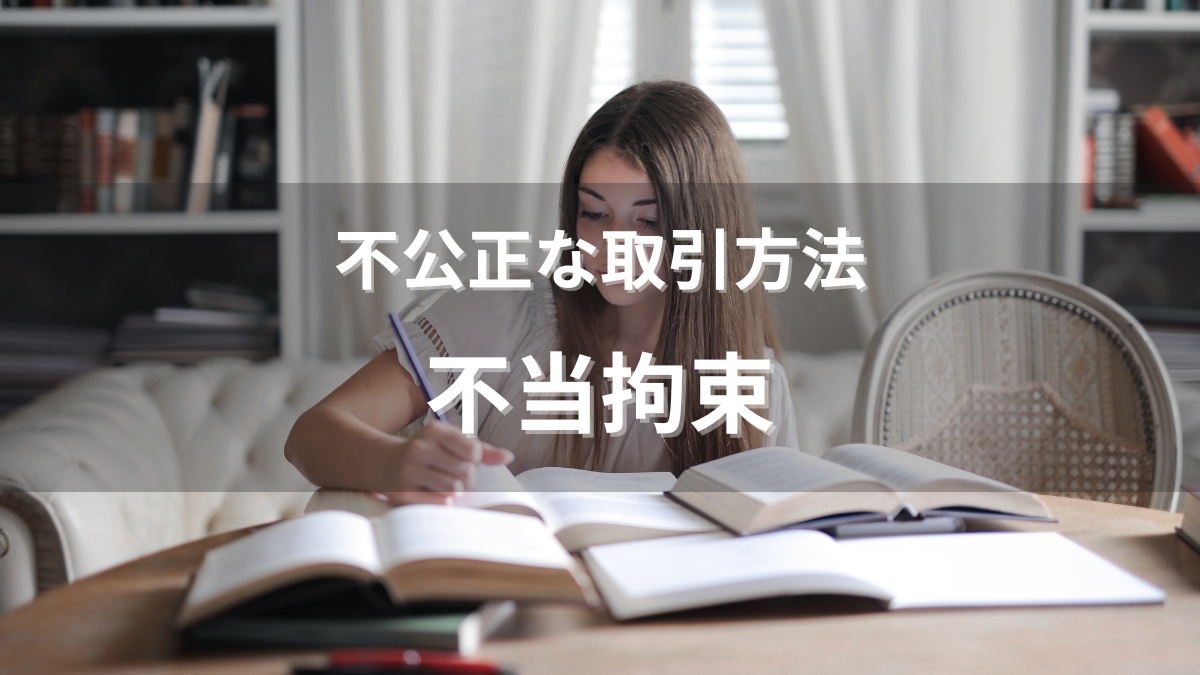今回は、独占禁止法を勉強しようということで、独禁法のいくつかの基本概念について見てみたいと思います。
ではさっそく。なお、引用部分の太字、下線、改行などは管理人によるものです。
メモ
このカテゴリーでは、インハウスとしての法務経験からピックアップした、管理人の独学や経験の記録を綴っています。
ネット上の読み物としてざっくばらんに書いており、感覚的な理解を掴むことを目指していますが、書籍などを理解する際の一助になれば幸いです。
「競争」
独禁法の基本概念として、「競争」と「一定の取引分野」の2つは最初の方で見るのが通例のように思いますので、まずこの2つから見ていきたいと思います。
ただ、かなり抽象度が高くて無味乾燥ですので、さらっと流しています
「競争」については、法2条4項で定義されています。
▽法2条4項
④ この法律において「競争」とは、二以上の事業者がその通常の事業活動の範囲内において、かつ、当該事業活動の施設又は態様に重要な変更を加えることなく次に掲げる行為をし、又はすることができる状態をいう。
一 同一の需要者に同種又は類似の商品又は役務を供給すること
二 同一の供給者から同種又は類似の商品又は役務の供給を受けること
長い定義ですが、とりあえず総論的には"2以上の事業者が競い合う関係"のことであると思っておいてよいと思います。
法解釈であると同時に経済学と外縁を接する領域なので、しっかりした理解のためには経済学的な理解も必要になるようです。
「一定の取引分野」
「一定の取引分野」については、独禁法に多数登場するものの、定義規定は置かれていません。
ですので解釈になるわけですが、とりあえず総論的には”競争の場”のこと、つまり「市場」「マーケット」のことであると思っておいてよいと思います。
あとは、個別の条文において解釈が異なりますので、そのことを念頭に置きつつ、個別の規制内容について見るときに具体的に掘り下げる感じになります。
「行為要件」と「効果要件」
次に、上記の2つの基本概念を含み、独禁法に横断的に存在する効果要件について見てみます。
前の記事で独禁法の規制の仕組みについて書いていますが、独禁法の適用される場面(適用要件)について大まかな構造を見ると、独禁法の行為規制には、行為規制ごとに存在する行為要件のほか、類型的に共通する効果要件があります(全てではないですが)。
つまり、各行為規制で、こういう行為をしてはダメですよという行為要件に該当するとしても、それだけで独禁法が適用されるわけではなく、行為の結果として競争にとって一定の悪影響が発生する(おそれがある)ことも要件になっています。それを効果要件と呼びます。
行為規制の要件
行為規制の3本柱である①私的独占/②不当な取引制限/③不公正な取引方法の類型に沿って要件をまとめてみると、以下のようになります。太字の部分が効果要件です。
| 行為規制 | 行為要件 | 効果要件 | 効果要件の文言 |
|---|---|---|---|
| ①私的独占/②不当な取引制限 | 行為規制ごとに存在 | 競争の実質的制限 | 「公共の利益に反して、一定の取引分野における競争を実質的に制限する」 |
| ③不公正な取引方法(法2条9項) | 行為規制ごとに存在 | 公正競争阻害性 | 「正当な理由なく」(1号・3号・4号) 「不当に」(2号・6号) 「正常な商慣習に照らして不当に」(5号) |
構造規制の要件
また、構造規制(企業結合規制)の方にも、「競争の実質的制限」の効果要件があります。
上記の表となるだけパラレルなように要件をまとめてみると、以下のようになります(管理人の個人的理解)。
| 構造規制 | 届出基準 | 効果要件 | 効果要件の文言 |
|---|---|---|---|
| 企業結合規制 | 企業結合の類型ごとに存在 ①株式保有 ②役員の兼任 ③合併 ④会社分割 ⑤共同株式移転 ⑥事業の譲受け ⑦事業の賃借等 | 競争の実質的制限 | 「一定の取引分野における競争を実質的に制限することとなる」 |
「競争の実質的制限」と「公正競争阻害性」
上記の表で見たように、「競争の実質的制限」と「公正競争阻害性」というのが、類型的に共通する効果要件になります。
表を見るだけでも何となくのイメージは湧くかなと思います(厳密な分け方ではないですが)。
競争の実質的制限
若干文章でも補足すると、まず「競争の実質的制限」というのは、一定の取引分野における競争を実質的に制限することです。解釈上は、特定の事業者または事業者集団が、市場支配力を形成・維持・強化している状態を意味するとされます。
競争を実質的に制限することとなるかどうかを判断するためには、市場(マーケット)の範囲画定が必要であるため、「一定の取引分野」という概念が入っています。これを市場の画定と言ったりもします。
これは何のことか一言でいうと、市場の占有率、いわゆるシェアは、市場の範囲を決めなければ決まってこないということです
公正競争阻害性
次に、「公正競争阻害性」というのは、競争を実質的に制限するには至らないが、ある程度において公正な自由競争を妨げるものと認められる場合のことです。
公正競争阻害性を判断するためには、市場(マーケット)の範囲を決めることは必然的には必要でないため、法文上は「一定の取引分野」という概念は入っていません(ただし、結局、解釈上の考慮要素としては入ってきます)。
それぞれの効果要件を見ても現れているように、「競争」や「一定の取引分野」という概念が要素になっていますので、これらが独禁法の基本概念になっているというのが見てとれると思います。
結び
今回は、独占禁止法を勉強しようということで、独禁法の基本概念について見てみました。
-
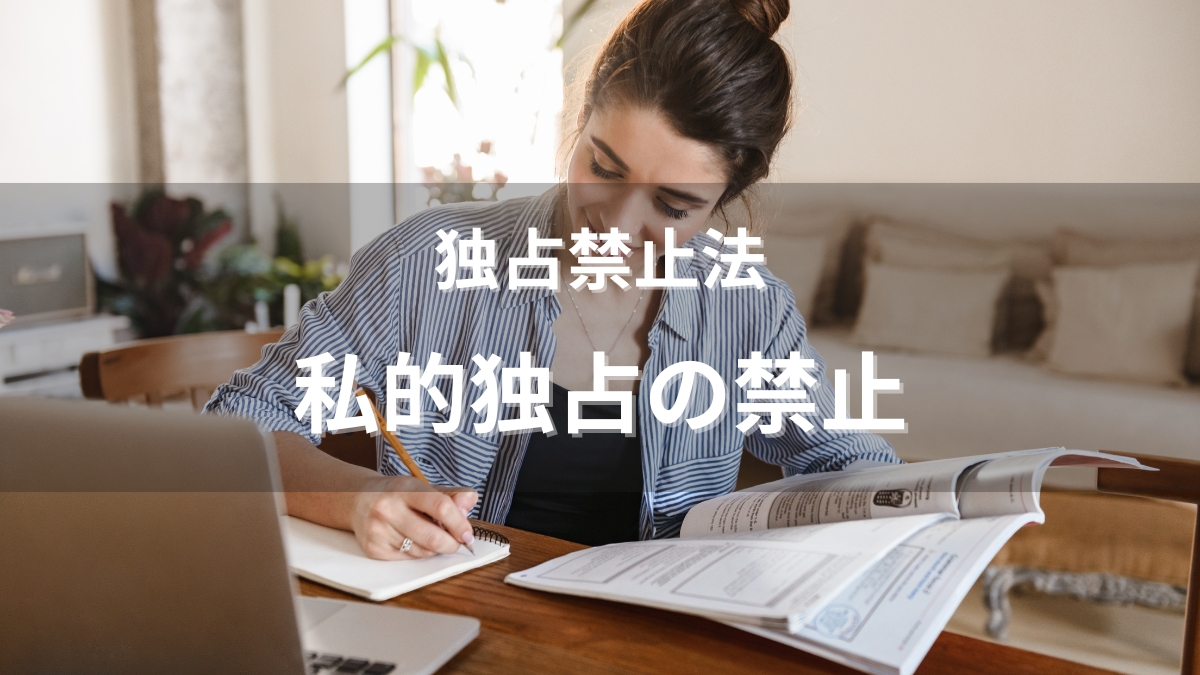
-
独占禁止法を勉強しよう|私的独占の禁止
続きを見る
[注記]
本記事を含む一連の勉強記事は、過去の自分に向けて、①自分の独学や経験の記録を見せる、②感覚的な理解を伝えることを優先する、③細かく正確な理解は書物に譲る、ということをコンセプトにした読みものです。ベテランの方が見てなるほどと思うようなことは書かれていないほか、業務上必要であるときなど、正確な内容については別途ご確認ください。また、法改正をはじめとした最新の情報を反映しているとは限りませんので、ご注意ください。
独占禁止法に関するその他の記事(≫Read More)
主要法令等・参考文献
主要法令等
リンクをクリックすると、法令データ提供システムまたは公正取引委員会HPに遷移します
- 独占禁止法(≫法律情報/英文)
- 排除型私的独占ガイドライン(「排除型私的独占に係る独占禁止法上の指針」)|公取委HP
- 一般指定(「不公正な取引方法」(昭和57年6月18日公正取引委員会告示第15号))|公取委HP
- 新聞特殊指定(「新聞業における特定の不公正な取引方法」(平成11年7月21日公正取引委員会告示第9号))|公取委HP
- 物流特殊指定(「特定荷主が物品の運送又は保管を委託する場合の特定の不公正な取引方法」(平成16年3月8日公正取引委員会告示第1号))|公取委HP
- 大規模小売業告示(「大規模小売業者による納入業者との取引における特定の不公正な取引方法」(平成17年5月13日公正取引委員会告示第11号))|公取委HP
- 不当廉売ガイドライン(「不当廉売に関する独占禁止法上の考え方」)|公取委HP
- 流通・取引慣行ガイドライン(「流通・取引慣行に関する独占禁止法の指針」)|公取委HP
- 優越的地位濫用ガイドライン(「優越的地位の濫用に関する独占禁止法上の考え方」)|公取委HP
- 役務委託優越的地位濫用ガイドライン(「役務の委託取引における優越的地位の濫用に関する独占禁止法上の指針」)|公取委HP
- 意見聴取規則(「公正取引委員会の意見聴取に関する規則」)
- 審査規則(「公正取引委員会の審査に関する規則」)
- 審査手続指針(「独占禁止法審査手続に関する指針」)|公取委HP
- 独禁法Q&A(「よくある質問コーナー(独占禁止法)」)|公取委HP
【企業結合規制関連】
- 届出等規則(「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第九条から第十六条までの規定による認可の申請、報告及び届出等に関する規則」)
- 企業結合ガイドライン(「企業結合審査に関する独占禁止法の運用指針」)|公取委HP
- 企業結合手続対応方針(「企業結合審査の手続に関する対応方針」)|公取委HP
【違反に対する措置(エンフォースメント)関連】
参考文献
リンクをクリックすると、Amazonのページまたは公正取引委員会HPに遷移します
- 独占禁止法〔第5版〕(菅久修一 編著、品川武、伊永大輔、鈴木健太 著)
- 注釈 独占禁止法(根岸哲 編)
- 優越的地位濫用ガイドブック(「優越的地位の濫用 ~知っておきたい取引ルール~」(公正取引委員会))|公取委HP(≫掲載ページ)
- 優越的地位の濫用規制に関する講習|公取委HP
当サイトではアフィリエイトプログラムを利用して商品・サービスを記載しています