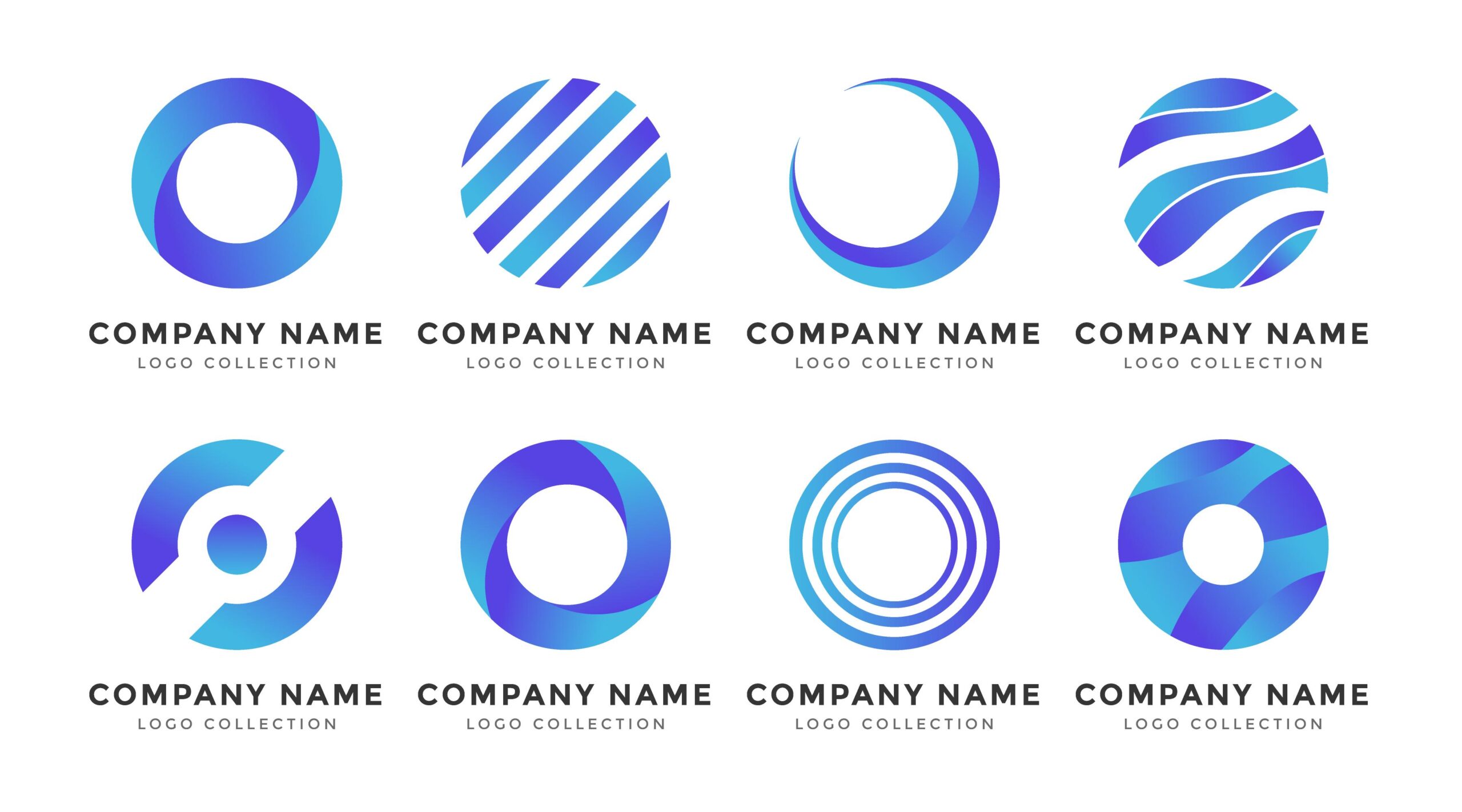今回は、商標法ということで、商標の「使用」概念について見てみたいと思います。
ではさっそく。なお、引用部分の太字、下線、改行などは管理人によるものです。
メモ
このカテゴリーでは、インハウスとしての法務経験からピックアップした、管理人の独学や経験の記録を綴っています。
ネット上の読み物としてざっくばらんに書いており、感覚的な理解を掴むことを目指していますが、書籍などを理解する際の一助になれば幸いです。
商標の「使用」とは
商標権とは、指定商品・指定役務について登録商標を独占的に使用する権利のことです(▷参考記事はこちら)。
実は、この「使用」の具体的内容は商標法で細かく定められています。
▽商標法2条3項・4項
3 この法律で標章について「使用」とは、次に掲げる行為をいう。
一~十 (略)
4 前項において、商品その他の物に標章を付することには、次の各号に掲げる各標章については、それぞれ当該各号に掲げることが含まれるものとする。
一~二 (略)
この中には、商品のパッケージに登録商標を付すような、日常感覚でわかる「使用」もある一方、使用という言葉からはちょっと想像しづらいような「使用」も含まれています。
しかし、この「使用」が何かをイメージできないと、結局、商標権をとったらどういう場面の使用を独占できるのか(あるいはできないのか)がわからないことになります。そこで、本記事ではこの「使用」とは何かについて見てみます。
商品についての使用と役務についての使用に大きく分けることができますが、全体をざっと見てみると、以下のとおりです。
商標の「使用」概念
| 商品or役務 | 「使用」概念 |
|---|---|
| 商品 | 商品や商品の包装に標章を付ける行為 |
| 商品や商品の包装に標章を付けたものを流通(販売等)させる行為 | |
| 役務(サービス) | 役務の提供にあたり顧客が利用するものに標章を付ける行為 |
| 標章を付けた物を利用して役務を提供する行為 | |
| 役務を提供する道具に標章を付けて展示する行為 | |
| 役務の提供にあたり顧客のものに標章を付ける行為 | |
| 標章を表示してインターネット等を通じた役務を提供する行為 | |
| 商品・役務に共通 | 広告や取引書類等に標章を付して展示・流布したり、インターネット等で提供する行為 |
| 商品・役務の流通(販売等)のために音の標章を発する行為 |
たくさんありますが、大きく括ると、
① マークを付ける行為
② マークを付けたものを流通させる行為
③ 広告使用
の3つが、主な「使用」のイメージになります。以下、順に見てみます。
商品についての使用
01|マークを付ける行為(1号)
一 商品又は商品の包装に標章を付する行為
これは、商品や商品の包装にマークを付ける行為です。
まずこれが基本といえます。
02|譲渡、引渡、展示、輸出、輸入、インターネット等での提供(2号)
二 商品又は商品の包装に標章を付したものを譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、輸入し、又は電気通信回線を通じて提供する行為
これは、商品や商品の包装にマークを付けたものを流通(販売等)させる行為です。
内容としては、
「譲渡」・・・有償・無償を問わず、所有権を移転すること
「引き渡し」・・・現実的な支配つまり占有の移転
「展示」・・・一般に示すこと
となっています。
会社規模や業界にもよると思いますが、「輸出」「輸入」といった使用態様も意外と検討する必要が出てくる場合があり、これらは例えば商標権に基づいて輸出入を差止めする(あるいはされてしまう)といったことも可能ですので、けっこうスケールの大きい話になり得ます(する側もされる側も影響は甚大)
「電気通信回線を通じて提供」とは、ダウンロード可能な電子情報財(ダウンロード可能なものは商標法上の商品に含まれます。参考記事はこちら)をインターネット等を通じて提供することです。
規定されている行為がたくさんあるのでイメージしづらいですが、ひと言でいうと、”拡布”(商品を取引に置く一切の行為)です。
不正競争防止法における「混同惹起行為」(不競法2条1項1号)に関して、平成5年改正前は「拡布」という概念があり、これとほぼパラレルといえます(経済産業省 知的財産政策室編「逐条解説 不正競争防止法」(令和元年7月1日施行版)72頁参照)
役務についての使用
01|マークを付ける行為(3号)
三 役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物(譲渡し、又は貸し渡す物を含む。以下同じ。)に標章を付する行為
これは、役務の提供にあたり顧客が利用するものにマークを付ける行為です。
例えば、引越業者が段ボールにマークを付すことが、これにあたります。
02|役務の提供(4号)
四 役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物に標章を付したものを用いて役務を提供する行為
これは、マークを付けた物を利用して役務を提供する行為です。
例えば、引越業者が、マークを付けた段ボールを用いて引越サービスを行うことが、これにあたります。
03|展示(5号)
五 役務の提供の用に供する物(役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物を含む。以下同じ。)に標章を付したものを役務の提供のために展示する行為
これは、役務を提供する道具にマークを付けて展示する行為です。
04|顧客のものにマークを付ける行為(6号)
六 役務の提供に当たりその提供を受ける者の当該役務の提供に係る物に標章を付する行為
これは、役務の提供にあたり顧客のものにマークを付ける行為です。
05|インターネット等での提供(7号)
七 電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつて認識することができない方法をいう。次号及び第二十六条第三項第三号において同じ。)により行う映像面を介した役務の提供に当たりその映像面に標章を表示して役務を提供する行為
これは、マークを表示して、インターネット等を通じた役務を提供する行為です。
商品と役務に共通の使用
01|広告的使用(8号)
八 商品若しくは役務に関する広告、価格表若しくは取引書類に標章を付して展示し、若しくは頒布し、又はこれらを内容とする情報に標章を付して電磁的方法により提供する行為
これは、広告や取引書類等にマークを付して展示・流布したり、インターネット等で提供する行為です。
02|音商標の使用(9号)
九 音の標章にあつては、前各号に掲げるもののほか、商品の譲渡若しくは引渡し又は役務の提供のために音の標章を発する行為
音商標については、商品・役務の流通(販売等)のために音を発する行為が「使用」になります。
また、音商標の「付する」には、デバイスに音を記録することも含まれます。
▽法2条4項2号
4 前項において、商品その他の物に標章を付することには、次の各号に掲げる各標章については、それぞれ当該各号に掲げることが含まれるものとする。
二 音の標章 商品、役務の提供の用に供する物又は商品若しくは役務に関する広告に記録媒体が取り付けられている場合(商品、役務の提供の用に供する物又は商品若しくは役務に関する広告自体が記録媒体である場合を含む。)において、当該記録媒体に標章を記録すること。
03|立体商標の使用(2条4項1号)
立体商標の場合を念頭に、「付する」には、商品自体の形状をそのまま商標とすることが含まれます。
商品自体の形状を立体商標とする場合、「付する」という行為が観念できない(その物自体がすでに商標)ためです。
▽法2条4項1号
4 前項において、商品その他の物に標章を付することには、次の各号に掲げる各標章については、それぞれ当該各号に掲げることが含まれるものとする。
一 文字、図形、記号若しくは立体的形状若しくはこれらの結合又はこれらと色彩との結合の標章 商品若しくは商品の包装、役務の提供の用に供する物又は商品若しくは役務に関する広告を標章の形状とすること。
04|政令で定める商標の使用(10号)
十 前各号に掲げるもののほか、政令で定める行為
将来的に政令によって新しい商標が追加された場合には、その使用の定義については本号で定められます(政令に委任される)。
結び
今回は、商標法ということで、商標の「使用」概念について見てみました。
身近な例としては、以前に、絵文字の「ぴえん」が商標登録されたら絵文字が使えなくなるのか?というのがネットニュースになっていたことがありました。
しかし、日常生活の中で普通に絵文字として使うことは上記のような商標の「使用」にはあたりませんので、(仮に万が一登録されたとしても)このような使用が禁止されることはないのだな、といったこともわかります。
-

-
「ぴえん」絵文字の商標出願ってどうなるの?
続きを見る
[注記]
本記事を含む一連の勉強記事は、過去の自分に向けて、①自分の独学や経験の記録を見せる、②感覚的な理解を伝えることを優先する、③細かく正確な理解は書物に譲る、ということをコンセプトにした読みものです。ベテランの方が見てなるほどと思うようなことは書かれていないほか、業務上必要であるときなど、正確な内容については別途ご確認ください。また、法改正をはじめとした最新の情報を反映しているとは限りませんので、ご注意ください。
商標法に関するその他の記事(≫Read More)
主要法令等
主要法令等
参考資料
- 知的財産権制度入門テキスト(特許庁)|特許庁HP
- 工業所有権法(産業財産権法)逐条解説(特許庁)|特許庁HP
参考文献
参考文献
当サイトではアフィリエイトプログラムを利用して商品・サービスを記載しています