今回は、下請法ということで、親事業者の義務のうち支払期日を定める義務と遅延利息の支払義務について見てみたいと思います。
下請法の適用対象になったとき、親事業者には以下のような4つの義務が課せられます。
【親事業者の4つの義務】
① 発注書面の交付義務 (第3条)
② 取引記録書類の作成・保存義務 (第5条)
③ 支払期日を定める義務 (第2条の2) ←本記事
④ 遅延利息の支払義務 (第4条の2) ←本記事
その中で、本記事は黄色ハイライトを引いた箇所の話です。
ではさっそく。なお、引用部分の太字、下線、改行などは管理人によるものです。
メモ
このカテゴリーでは、インハウスとしての法務経験からピックアップした、管理人の独学や経験の記録を綴っています。
ネット上の読み物としてざっくばらんに書いており、感覚的な理解を掴むことを目指していますが、書籍などを理解する際の一助になれば幸いです。
支払期日を定める義務(法2条の2)
親事業者は、下請代金について、商品の受領日(サービスの場合は役務提供日)から起算して60日以内のできるだけ短い期間内に支払期日を定めなければなりません。
下請取引は親事業者の立場が強いことが多く、親事業者が下請代金の支払期日を不当に遅く設定するおそれがあることから、下請事業者の利益を保護するためこの規定が設けられています。
▽下請法2条の2第1項
(下請代金の支払期日)
第二条の二 下請代金の支払期日は、親事業者が下請事業者の給付の内容について検査をするかどうかを問わず、親事業者が下請事業者の給付を受領した日(役務提供委託の場合は、下請事業者がその委託を受けた役務の提供をした日。次項において同じ。)から起算して、六十日の期間内において、かつ、できる限り短い期間内において、定められなければならない。
ちなみに、受領日から起算して、と書かれているので、「60日以内」は受領日も算入することになります(初日算入)。
期間の計算では初日不算入が原則ですが(民法140条参照)、「から起算して」はこの原則によらず初日を算入するときの法令用語になります(▷参考記事はこちら)
支払期日の法定
とはいえ、現実には支払期日を定める義務に違反しているケースもあり得ますので、2項において、以下のように支払期日の定まり方が決められています。
▽下請法2条の2第2項
2 下請代金の支払期日が定められなかったときは親事業者が下請事業者の給付を受領した日が、前項の規定に違反して下請代金の支払期日が定められたときは親事業者が下請事業者の給付を受領した日から起算して六十日を経過した日の前日が下請代金の支払期日と定められたものとみなす。
つまりまとめると、支払期日の定まり方には以下の3パターンがあることになります。
もちろん、②③は支払期日が定まるとはいっても、支払期日を定める義務には違反していることになります(以下参照)。
▽講習会テキスト〔R5.11版〕1-⑸-イ「支払期日と支払遅延の関係」
(ウ) 支払期日が受領日から60日を超えて定められている場合は、受領日から60日目までに下請代金を支払わないとき(この場合、本法に定める範囲を超えて支払期日が設定されており、それ自体が支払期日を定める義務に違反する。)。
▽公正取引委員会のXアカウント
【#2024ひとこと講座 33 下請法】
— 公正取引委員会 (@jftc) June 5, 2024
<親事業者の義務 -支払期日を定める義務->
親事業者は、下請代金の支払期日を事前に決めておく必要があります。
物品等の受領後60日以内で、できる限り短い期間になるように支払期日を定めなければいけません。 https://t.co/PmtTTt4ajE#下請法 #支払期日 pic.twitter.com/Z8VBATIouZ
具体的な記載の仕方
下請代金の支払期日は3条書面の必要記載事項にもなっているので(下請法3条)、”あれ?支払期日って3条書面のところでも記載事項として出てこなかったっけ?それと支払期日を定める義務とは何が違うの?”という気もするかもしれません。
これは、単に支払期日を定めるだけでなく、書面化して交付する必要もある、ということです。
つまり、時系列で並べると、
- 支払期日を定める :支払期日を定める義務(下請法2条の2)
↓ - 書面化して交付する :発注書面の交付義務(下請法3条)
という対応関係になっています。
具体的な記載の仕方については、講習会テキストでは以下のように解説されています。
▽講習会テキスト〔R5.11版〕1-⑷-イ【Q47】
3条書面に記載する支払期日について、以下のような記載は問題ないか。
① 「〇月〇日まで」
② 「納品後〇日以内」
③ 「〇月〇日」
④ 「毎月末日納品締切、翌月〇日支払」「支払期日」は具体的な日が特定できるよう定める必要がある。
①、②は、支払の期限を示しており、具体的な日が特定できないため認められない。
③は、具体的な日が特定可能であり、認められる。
④は、月単位の締切制度を採用した場合の記載であるが、この場合も具体的な日が特定可能であり、認められる。
なお、定められた支払期日より前に下請代金を支払うことは差し支えない。
このように、支払期日は特定して定める必要があり、「納品後○日以内」といった支払期日の設定は不可とされています。
下請法運用基準等との関係
下請法の解釈・運用を定めているのは下請法運用基準(「下請代金支払遅延等防止法に関する運用基準」)になりますが、支払期日を定める義務については、運用基準に記載はありません。
ただ、「受領」の定義については、運用基準のうち、受領拒否の禁止(法4条1項1号)の部分でくわしく書かれています。
また、講習会テキストでは、支払期日の起算日である「受領日」にまつわるいくつかの論点が、支払遅延の禁止(同2号)の部分で書かれていたりします。
なので、支払期日を定めるにあたってはこれらも参照する必要がありますが、当ブログでは、支払期日規制にまつわる論点として、以下の関連記事にまとめています。
-
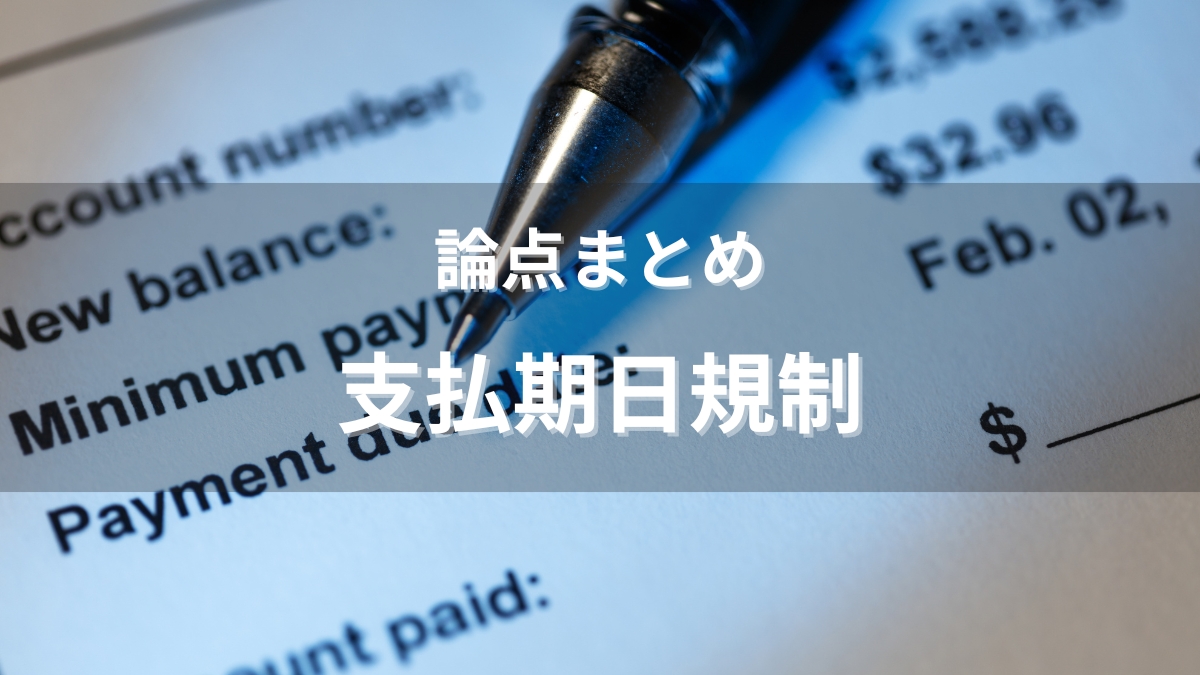
-
下請法|支払期日規制にまつわる論点まとめ(起算日と例外・締切制度など)
続きを見る
遅延利息の支払義務(法4条の2)
遅延利息の支払義務は、下請取引について支払遅延がなされた場合の特別の遅延利息を法定したものです。
下請事業者は立場が弱いことが多いので、親事業者と下請事業者との間で自主的に遅延利息を約定することは困難とみて、この規定が設けられています。
▽下請法4条の2
(遅延利息)
第四条の二 親事業者は、下請代金の支払期日までに下請代金を支払わなかつたときは、下請事業者に対し、下請事業者の給付を受領した日(役務提供委託の場合は、下請事業者がその委託を受けた役務の提供をした日)から起算して六十日を経過した日から支払をする日までの期間について、その日数に応じ、当該未払金額に公正取引委員会規則で定める率を乗じて得た金額を遅延利息として支払わなければならない。
特別の遅延利息
特別の遅延利息というのは、受領日から起算して60日を経過した日から実際に支払をする日までの期間、年14.6%の割合による遅延利息を(日割りで)支払う義務になります。
「60日を経過した日」というのは要するに、受領日を1日目として数えて61日目のことになります。
考え方としては、
- 「受領日から起算して」と書かれているとおり、受領日は算入される
- そして、受領日から起算して60日目を支払期限として扱っている
(※「法定支払期日」といったりもする=法2条の2(支払期日を定める義務)の第2項で「受領日から起算して60日を経過した日の前日」と表現されているもの) - そうすると、61日目から遅延に陥っている
ということになります。
受領日を1日目として数えて60日目いっぱいまではセーフ、61日目からはアウト、ということです(60日目の24時00分00秒=61日目の0時00分00秒が境界線)。
遅延利息の利率
年14.6%という遅延利息の利率は、公正取引委員会規則(「下請代金支払遅延等防止法第四条の二の規定による遅延利息の率を定める規則」)に定められています。
▽下請代金支払遅延等防止法第四条の二の規定による遅延利息の率を定める規則
下請代金支払遅延等防止法(昭和三十一年法律第百二十号)第四条の二の規定に基づき、この規則を定める。
下請代金支払遅延等防止法第四条の二の規定による下請代金の支払遅延に対する遅延利息の率は、年十四・六パーセントとする。
この利率は、民法の法定利率や約定利率に優先して適用されます。
例えば、当事者間でこの利率と異なる約定利率(10%など)を定めていても、その約定利率は排除されます。
▽公正取引委員会のXアカウント
【#2024ひとこと講座 34 下請法】
— 公正取引委員会 (@jftc) June 9, 2024
<親事業者の義務 -遅延利息の支払義務->
親事業者は、支払期日までに下請代金を支払わなければなりません。さらに、物品の受領日から60日経過した場合は利息を支払う義務があり、これを「遅延利息」と呼びます。
遅延利息は年率14.6%です。 https://t.co/Ngl7DyaSB9 pic.twitter.com/McdBgFyDhF
結び
今回は、下請法ということで、親事業者の義務のうち支払期日を定める義務と遅延利息の支払義務について見てみました。
次の記事は、親事業者の禁止行為のうち受領拒否の禁止についてです。
-
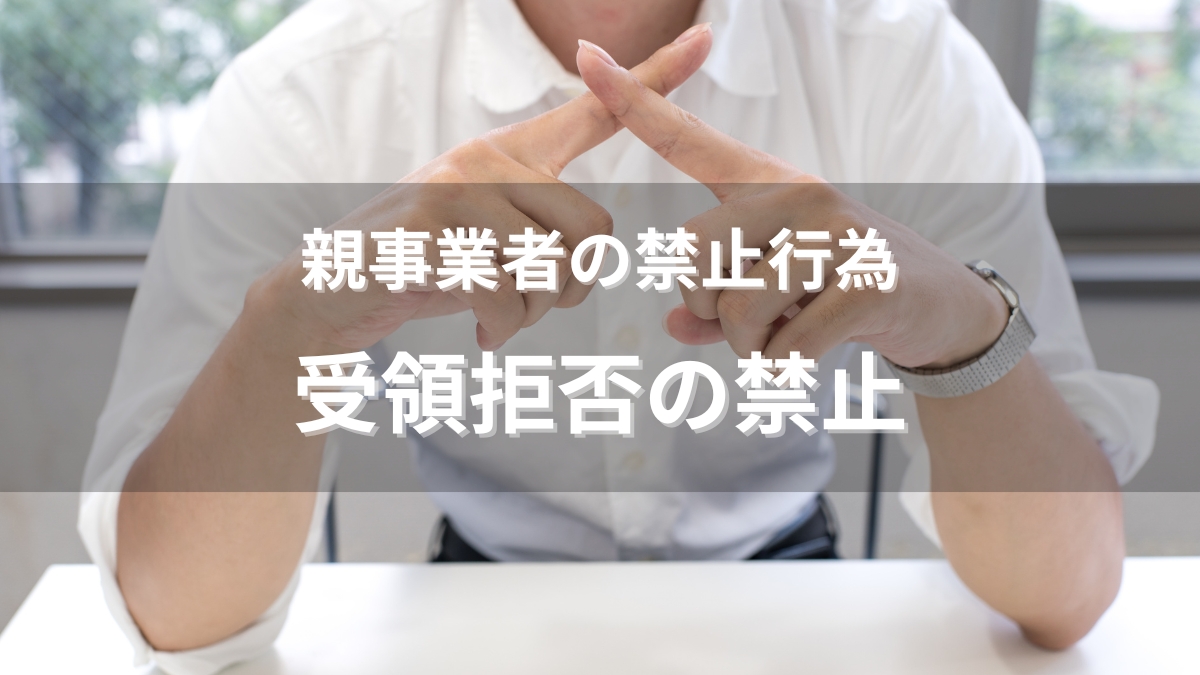
-
下請法|親事業者の禁止行為-受領拒否の禁止
続きを見る
[注記]
本記事を含む一連の勉強記事は、過去の自分に向けて、①自分の独学や経験の記録を見せる、②感覚的な理解を伝えることを優先する、③細かく正確な理解は書物に譲る、ということをコンセプトにした読みものです。ベテランの方が見てなるほどと思うようなことは書かれていないほか、業務上必要であるときなど、正確な内容については別途ご確認ください。また、法改正をはじめとした最新の情報を反映しているとは限りませんので、ご注意ください。
下請法に関するその他の記事(≫Read More)
参考文献
※注:「優越的地位濫用規制と下請法の解説と分析」には第4版があります
当サイトではアフィリエイトプログラムを利用して商品・サービスを記載しています
主要法令等
主要法令等
参考資料







