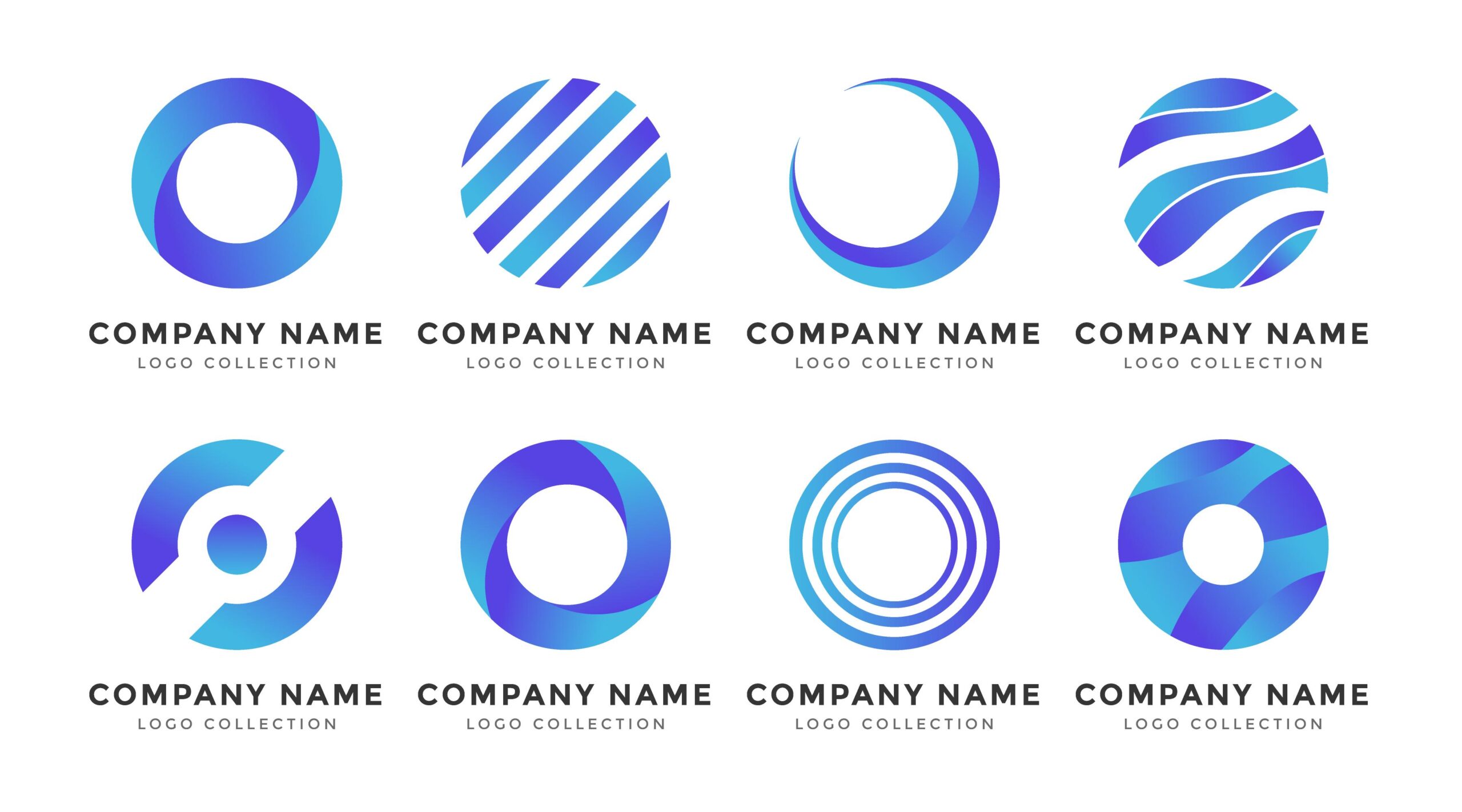今回は、商標法ということで、商標の種類について見てみたいと思います。
ではさっそく。なお、引用部分の太字、下線、改行などは管理人によるものです。
メモ
このカテゴリーでは、インハウスとしての法務経験からピックアップした、管理人の独学や経験の記録を綴っています。
ネット上の読み物としてざっくばらんに書いており、感覚的な理解を掴むことを目指していますが、書籍などを理解する際の一助になれば幸いです。
商標の種類(構成要素による分類)
商標とは、事業者が、自分の取り扱う商品やサービスを他人のものと区別するために使用するマーク(標章)のことですが、商標は、このマーク(標章)の構成要素に着目して分類することができます。
文字、図形、記号、立体的形状や、これらを組み合わせたもの、などのタイプがあります。
条文でいうと、商標の定義を定めている法2条1項のうち、以下の黄色ハイライト部分になります。
▽商標法2条1項
(定義等)
第二条 この法律で「商標」とは、人の知覚によつて認識することができるもののうち、文字、図形、記号、立体的形状若しくは色彩又はこれらの結合、音その他政令で定めるもの(以下「標章」という。)であつて、次に掲げるものをいう。
一・二 (略)
表にしてみると、以下のようになります。
商標の種類
| マーク(標章)の構成要素 | 商標の種類 |
|---|---|
| 文字のみ | 文字商標 |
| 図形のみ | 図形商標 |
| 記号のみ | 記号商標 |
| 立体的形状のみ | 立体商標 |
| 色彩のみ | 色彩商標 |
| 文字/図形/記号/立体的形状/色彩のうち2つ以上の結合 | 結合商標 |
| 音 | 音商標 |
| その他政令で定めるもの | ー |
具体例は、特許庁HPに掲載されている「知的財産権制度入門テキスト」の「第4節 商標制度の概要」の中で画像付きで解説されていますので、そちらを見るとわかりやすいかと思います(百聞は一見に如かず)。
以下、順に見てみます。
文字商標
これは、文字のみからなる商標のことをいい、文字は、カタカナ、ひらがな、漢字、ローマ字、数字等によって表されます。
では、文字書体(フォント)によって何か違いが出るのか?という疑問が湧きますが、違いはあります。商標の類似性を判断するときに、同一又は類似の範囲の判断に差異が出ることがあり得ます。
文字書体は、”一番クセのない書体”という感じの書体で特許庁が指定したものがあるので(管理人の理解)、こだわりがない場合はこれによってもよいことになっています。これを標準文字といいます。
商標法5条3項に定めがあり、標準文字のみによって商標登録を受けようとするときは、その旨を出願の願書に記載しなければならないとされています。
▽商標法5条3項
3 商標登録を受けようとする商標について、特許庁長官の指定する文字(以下「標準文字」という。)のみによつて商標登録を受けようとするときは、その旨を願書に記載しなければならない。
標準文字制度
標準文字制度とは、「登録を求める対象としての商標が文字のみにより構成される場合において、出願人が特別の態様について権利要求をしないときは、出願人の意思表示に基づき、商標登録を受けようとする商標を願書に記載するだけで、特許庁長官があらかじめ定めた一定の文字書体(標準文字)によるものをその商標の表示態様として公表し及び登録する制度」です。
解説やQ&Aが、以下の特許庁HPに掲載されています。
▽参考リンク
商標法第5条第3項に規定する標準文字について|特許庁HP
ただし、特許庁が定めたものだからといって、標準文字にすれば商標権の保護範囲が広くなるとか、そういうわけではありません。商標の類似性を判断する際には、標準文字の書体をベースにして通常の類否判断がされるだけです。
そのため、文字書体について特にこだわりのない出願人にとって、選ぶ手間が省けて便利な制度というものであり、それ以上でも以下でもありません。
▽標準文字の指定に関するQ&A 2-2|特許庁HP
実際に使用をする文字書体が決まっている場合も、標準文字で出願したほうがよいですか。
標準文字の商標の文字書体は、特許庁長官が定めた文字書体です。
使用する文字書体が決まっている場合は、標準文字でなく、その文字書体で商標登録出願することをお勧めします。
なお、標準文字で商標登録がなされた場合、その商標権の及ぶ範囲は、登録された商標(標準文字)と同一又は類似の範囲であり、通常の商標登録と比較してその範囲の広狭に差異はありません。
図形商標
これは、図形のみからなる商標で、写実的なものから図案化したものや、幾何学的模様などです。
一般的な感覚でわかりやすくいうと、いわゆるロゴです。なので、ロゴ商標のことだと思っておいてよいと思います(もちろん、図形に文字等を組み合わせた結合商標もロゴ商標)。
たとえば、某運送業者や、某スポーツ用品メーカーなどが、動物を図案化した商標を使っているのが思い浮かぶかと思います
記号商標
これは、記号のみからなる商標で、暖簾(のれん)記号、文字を図案化し組み合わせた記号、記号的な紋章のことをいいます。
”暖簾記号”とは、聞き慣れない言葉ですが、文字と図形が一体的に記号として把握されるようなもののことです。
例えば、某しょうゆメーカーの商標(文字を六角形で囲っているような一体的な記号)などが思い浮かぶかと思います
”文字を図案化し組み合わせた記号”とは、例えば、図案化した文字を組み合わせてエンブレムのようにしたようなものがあります。
例えば、図案化されたアルファベットを複数組み合わせたものとして、某高級鞄ブランドの商標などが思い浮かぶかと思います
立体商標
これは、立体的形状からなる商標です。
例えば、キャラクター、動物等の人形のような、立体的形状からなるものです。
例えば、某フライドチキンメーカーのおじさんや、某お菓子メーカーの舌を出した女の子などが思い浮かぶかと思います
また、商品や容器の立体的形状もあります。
例えば、某乳酸菌飲料メーカーの容器などが思い浮かぶかと思います
色彩商標
これは、単色又は複数の色彩の組合せのみからなる商標(図形等に色彩が付されたものではない商標)であって、輪郭なく使用できるもののことです。
例えば、商品の包装紙や、広告用の看板など、色彩を付する対象物によって形状を問わず使用される色彩です。
実際の色彩商標としては、某文房具メーカーの消しゴムのパッケージの色の組み合わせなどが思い浮かぶかと思います
”輪郭なく使用できるもの”というのは、平成26年法改正前は色彩のみの商標は認められておらず、例えば図形などと組み合わせる必要があった(=輪郭あり)のに対して、そういう制限がなくなったということです。
単色の場合
また、意外な気もしますが、色の組み合わせだけではなく、単色の場合も排除されていません。
単色の事例としては、最近のルブタン商標事件の知財高裁判決が有名です。”女性用ハイヒール靴の靴底部分に付した赤色”という色彩(単色)の商標登録出願でしたが、結論としては、自他識別力を欠くとして登録が認められませんでした。
知財高裁での争点は、使用による識別力獲得(法3条2項。いわゆるセカンダリーミーニング)の有無でしたが、以下で述べられているような独占適応性までは認められないとされました。
▽知財高判令和5年1月31日(令和4(行ケ)10089号)|裁判所HP(裁判例検索)
2 単一の色彩のみからなる商標の商標法3条2項の該当性について
「 …商標法3条2項の趣旨は、同条1項3号に該当する商標であっても、特定の者が長年その業務に係る商品又は役務について使用した結果、その商標がその商品又は役務と密接に結びついて出所表示機能を持つに至り、公益上の見地から不適当とされていた特定人による当該商標の独占的使用を例外的に認めるということにある。
こうした商標法3条2項の趣旨に照らせば、自由選択の必要性等に基づく公益性の要請が特に強いと認められる、単一の色彩のみからなる商標が同条同項の「使用をされた結果需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができるもの」に当たるというためには、当該商標が使用をされた結果、特定人による当該商標の独占使用を認めることが公益性の例外として認められる程度の高度の自他商品識別力等を獲得していること(独占適応性)を要するものと解するべきである。…」
結合商標
これは、異なる意味合いを持つ文字と文字を組み合わせた商標や、文字、図形、記号、立体的形状の二つ以上を組み合わせた商標のことです。
”異なる意味合いを持つ文字と文字を組み合わせた商標”というのがわかりにくいですが、2つ以上の語の組み合わせからなる商標のことです。つまり、結局文字しかないわけですが、これも結合商標と呼ばれます。
”文字、図形、記号、立体的形状の二つ以上を組み合わせた商標”の方は、特にわかりにくいところはなく、読んでそのままです。
結合商標には、以上の2つの場合があるというのがポイントです。
音商標
これは、音楽、音声、自然音等からなる商標であり、聴覚で認識される商標です。
例えば、テレビCMに使われるサウンドロゴや、パソコンの起動音などがあります。
出願の際には、五線譜などを用いて音(メロディー)を特定します。
▽商標法施行規則4条の5
(音商標の願書への記載)
第四条の五 音からなる商標(以下「音商標」という。)の商標法第五条第一項第二号の規定による願書への記載は、文字若しくは五線譜又はこれらの組み合わせを用いて商標登録を受けようとする音を特定するために必要な事項を記載することによりしなければならない。ただし、必要がある場合には、五線譜に加えて一線譜を用いて記載することができる。
上記の条文では「文字…を用いて」とも書いており、文字で音を特定するってどういうこと?と思いますが、例えば「本商標は、『バンバン』と2回手をたたく音が聞こえた後に、『ニャオ』という猫の鳴き声が聞こえる構成となっており、全体で3秒間の長さである。」といった例が挙げられています(特許庁「商標審査基準」(改定第15版)24頁)。
その他政令で定める商標
以上のほか、「その他政令で定めるもの」とされていて、将来的には、例えば、におい、味、触覚などが政令で新しい構成要素として追加されることなどが考えられます。
現在のところ、まだ政令で追加されたものはありません。
J-PlatPatの「図形等分類表」
これらの商標の具体例は、前述のように、特許庁HPに掲載されている「知的財産権制度入門テキスト」などでざっと見ることができますが、もっと見てみたい場合は、J-PlatPatで手軽に見ることができます。
また、J-PlatPatには「図形等分類表」というページがあり、文字のみで構成される商標以外について、分類ごとに検索できるようになっています。
図形等分類表|J-PlatPat
分類の見出しを見るだけでもイメージづくりになるかもしれません。
▽「図形等分類」|J-PlatPat(ヘルプボタンより)
「商標の図形要素の分類として国際的に広く採用されているウィーン図形分類を基に、日本独自に更に細分化した分類です。特許庁が審査のための検索キーとして付与します。図形要素だけでなく、音(音商標)や動き(動き商標)についての分類もあります。
文字しかない商標の場合、図形等分類は付与されません。」
結び
今回は、商標法ということで、商標の種類について見てみました。
ネット記事のなかでは以下のものがわかりやすくまとまっており、画像も豊富ですのでおすすめです。
[注記]
本記事を含む一連の勉強記事は、過去の自分に向けて、①自分の独学や経験の記録を見せる、②感覚的な理解を伝えることを優先する、③細かく正確な理解は書物に譲る、ということをコンセプトにした読みものです。ベテランの方が見てなるほどと思うようなことは書かれていないほか、業務上必要であるときなど、正確な内容については別途ご確認ください。また、法改正をはじめとした最新の情報を反映しているとは限りませんので、ご注意ください。
商標法に関するその他の記事(≫Read More)
主要法令等
主要法令等
参考資料
- 知的財産権制度入門テキスト(特許庁)|特許庁HP
- 工業所有権法(産業財産権法)逐条解説(特許庁)|特許庁HP
参考文献
参考文献
当サイトではアフィリエイトプログラムを利用して商品・サービスを記載しています