今回は、景品表示法ということで、表示規制のうち有利誤認表示について見てみたいと思います。
ではさっそく。なお、引用部分の太字、下線、改行などは管理人によるものです。
メモ
このカテゴリーでは、インハウスとしての法務経験からピックアップした、管理人の独学や経験の記録を綴っています。
ネット上の読み物としてざっくばらんに書いており、感覚的な理解を掴むことを目指していますが、書籍などを理解する際の一助になれば幸いです。
有利誤認表示とは
有利誤認表示とは、不当表示のひとつで、要するに、価格その他の取引条件について有利性を偽る表示のことです。
消費者庁HPに、有利誤認についての簡潔な解説が載っています。
有利誤認|消費者庁HP
有利誤認表示の禁止(景表法5条2号)
有利誤認表示の禁止は、景表法5条2号に定められています。
▽景表法5条2号
(不当な表示の禁止)
第五条 事業者は、自己の供給する商品又は役務の取引について、次の各号のいずれかに該当する表示をしてはならない。
二 商品又は役務の価格その他の取引条件について、実際のもの又は当該事業者と同種若しくは類似の商品若しくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも取引の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認される表示であつて、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認められるもの
そのままだと読みにくいので、簡略化しつつ区切ると、
○ 商品又は役務の「価格」「その他の取引条件」について
○ 「実際のもの」又は「当該事業者と同種若しくは類似の商品若しくは役務を供給している他の事業者に係るもの」よりも
○ 著しく有利であると
○ 一般消費者に誤認される表示であって、
○ 不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあるもの
のようになっています。以下、ざっと意味合いを見てみます。
「価格」「その他の取引条件」について
「価格」「その他の取引条件」について、とされているように、有利誤認表示は、
- 「価格」に関する有利誤認と
- 「その他の取引条件」に関する有利誤認
の、大きく2つに分けることができます。
「実際のもの」「他の事業者に係るもの」よりも
これは、何と比べて有利なのか?という点です。この点については、「実際のもの」と「他の事業者に係るもの」があります。
「著しく有利」と誤認される
「著しく有利」の部分については、価格表示ガイドラインのなかで、以下のように考え方が説明されています。
つまり、広告表示は魅力的に、ある程度大げさに書いているであろうこと(”パッフィング”(お化粧)などと表現されることもあります)は消費者もわかっているものですが、「著しく」とは、そのような一般的な誇張の限度を超えていることを指しています。
▽価格表示ガイドライン 第2-1-⑵
⑵ 「有利であると一般消費者に誤認される」とは、当該表示によって販売価格が実際と異なって安いという印象を一般消費者に与えることをいう。また、「著しく有利」であると誤認される表示か否かは、当該表示が、一般的に許容される誇張の程度を超えて、商品又は役務の選択に影響を与えるような内容か否かにより判断される。
⑶ なお、景品表示法上問題となるか否かは、表示媒体における表示内容全体をみて、一般消費者が当該表示について著しく有利であると誤認するか否かにより判断されるものであり、その際、事業者の故意又は過失の有無は問題とされない。
(※)価格表示ガイドラインなので、「有利」の内容は、価格を想定した書き方になっています
ちなみに、優良誤認表示の禁止の考え方についても、不実証広告ガイドラインに、同じような考え方が記載されています
「一般消費者」に誤認される
これは、一般消費者に対する不当表示を問題とする趣旨です(景表法自体が、消費者を保護するための規制なので)。この点は、景表法の不当表示全般に共通しています。
なので、事業者に対する不当表示は、景表法にいう有利誤認表示にはあたらないことになります。
これについては、一般法である独占禁止法に立ち戻って、不公正な取引方法のひとつである「不当利益顧客誘引」(独禁法2条9項6号ハ→一般指定9項)の問題となります。
-
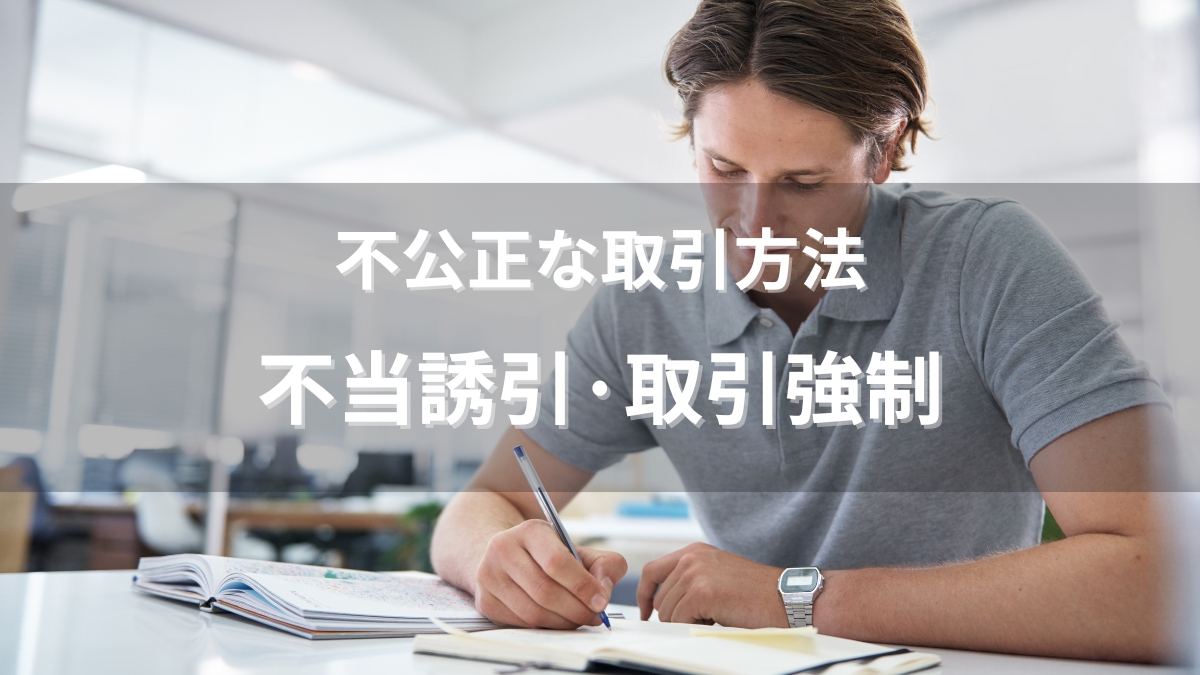
-
独占禁止法を勉強しよう|不公正な取引方法-不当な顧客誘引・取引強制
続きを見る
「不当に顧客を誘引」「一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害」するおそれ
これらについては、優良誤認表示と同じ要件となっています。
意味も同じであり、一般消費者に誤認される表示であれば普通はいずれも満たしますので、確認的な要件である(上記の各要件に加えて、上乗せで何かを要求しているわけではない)と解されています。
有利誤認表示の種類
先ほど見たように、有利誤認表示は、「価格」に関する有利誤認と、「その他の取引条件」に関する有利誤認の、大きく2つに分けることができます。
理屈でいうと、有利誤認は取引条件の有利性を偽ることであり、価格はそのうちのひとつですが、現実には価格の有利性のところに論点が集中するので、このようになっています。
01|価格に関する有利誤認(価格表示ガイドライン)
価格に関する有利誤認については、価格表示ガイドライン(「不当な価格表示についての景品表示法上の考え方」)が定められています。
価格表示ガイドライン|消費者庁HP(≫掲載ページ)
消費者的には価格が最も重要な判断基準なので、価格にまつわる有利誤認表示をくわしく掘り下げたのが、このガイドラインです(けっこう長く、全部で18頁ある)。
不当表示(有利誤認表示)となる場合の一般論としては、以下のように3つに整理されています。
▽価格表示ガイドライン 第2-2
2 景品表示法上問題となる価格表示
上記1を踏まえると、次のような価格表示を行う場合には、景品表示法に違反する不当表示(以下、単に「不当表示」という。)に該当するおそれがある。
⑴ 実際の販売価格よりも安い価格を表示する場合
⑵ 販売価格が、過去の販売価格や競争事業者の販売価格等と比較して安いとの印象を与える表示を行っているが、例えば、次のような理由のために実際は安くない場合
ア 比較に用いた販売価格が実際と異なっているとき。
イ 商品又は役務の内容や適用条件が異なるものの販売価格を比較に用いているとき。
⑶ その他、販売価格が安いとの印象を与える表示を行っているが、実際は安くない場合
概ね、項目としては、
- (1)→販売価格単体表示
- (2)→二重価格表示
- (3)→販売価格の安さを強調する表示
というふうに対応しています。
以下、順に見てみます。
①販売価格単体表示
これは、販売価格を単体で表示する場合です。
わかりやすくいえば
あんパン 100円
というような価格表示のことです。
これが不当表示になるケースがあるのか?という感じですが、実際にはその表示価格で購入できないような場合には、不当表示となるおそれがあります。
具体的には、
- 実際の販売価格より安い価格を販売価格として表示する
→あんパンの実際の販売価格は120円 - 通常他の関連する商品や役務と併せて一体的に販売されている商品について、これらの関連する商品や役務の対価を別途請求する場合に、その旨を明示しないで、商品の販売価格のみを表示する
→(例が悪いですが)あんパンと抹茶オレのセット販売しかしておらず、抹茶オレのお金は別途かかる - 表示された販売価格が適用される顧客が限定されているにもかかわらず、その条件を明示しないで、商品の販売価格のみを表示する
→あんパンを100円で購入できるのは会員限定
といった場合です。
そこで、販売価格単体表示も含め価格表示全般にいえることとして、
- 販売価格
- 当該価格が適用される商品の範囲(関連する商品/役務が一体的に提供されているか否か等)
- 当該価格が適用される顧客の条件
について正確に表示する必要があるとされています。
▽価格表示ガイドライン 第3-1
特定の商品の販売に際して販売価格が表示される場合には、一般消費者は、表示された販売価格で当該商品を購入できると認識するものと考えられる。
このため、販売価格に関する表示を行う場合には、⑴販売価格、⑵当該価格が適用される商品の範囲(関連する商品、役務が一体的に提供されているか否か等)、⑶当該価格が適用される顧客の条件について正確に表示する必要があり、これらの事項について実際と異なる表示を行ったり、あいまいな表示を行う場合には、一般消費者に販売価格が安いとの誤認を与え、不当表示に該当するおそれがある。
なお、以上の考え方は、販売価格を単体で表示する場合だけではなく、第4以下で記述する二重価格表示等における販売価格の表示についても同様に当てはまるものである。
②二重価格表示
これは、販売価格を比較対照価格とともに表示する場合です。
要するに、”何かの価格と比較して、価格がそれよりも安い”とする表示のことです。
この場合、
- 実際の販売価格よりも高い何らかの価格(=比較対照価格)と
- 実際の販売価格
とが併記されるわけですが、価格表示ガイドラインでは、何と比較するかによって、二重価格表示を以下のような類型に分類しています。
二重価格表示についての基本的な考え方としては、
その内容が適正な場合には、一般消費者の適正な商品選択と事業者間の価格競争の促進に資する面がある
とされており(価格表示ガイドライン 第4-1)、二重価格表示それ自体について否定的な評価がされているわけではありません。
しかし、内容が適正でない場合には安いとの誤認を与えるおそれがあるため、二重価格表示全般に共通する考え方として、
- 同一ではない商品の価格を比較対照価格に用いて表示を行う場合
- 比較対照価格に用いる価格について実際と異なる表示やあいまいな表示を行う場合
には、不当表示に該当するおそれがあるとされています。
そのうえで、それぞれの類型ごとに、有利誤認表示に該当するかどうかの具体的な判断基準が示されています。
二重価格表示の類型については、以下の関連記事にくわしく書いています。
-

-
景品表示法|有利誤認表示-二重価格表示の類型
続きを見る
③販売価格の安さを強調するその他の表示
販売価格の安さを強調する表示とは、安さの理由や程度を強調する表示が用いられる場合のことで、
- 安さの理由を説明する「倒産品処分」「工場渡し価格」等の用語を用いた表示
- 安さの程度を説明する「大幅値下げ」「他店より安い」等の用語を用いた表示
があるとされています。
これらは、実際と異なって安さを強調するものである場合は、不当表示となるおそれがあります。具体的には、
- 実際には特に安くなっている商品がない場合
- 実際には適用対象となる商品の範囲が限定されている場合
- 実際には限定条件がある場合
などが考えられます。
例えば、倒産処分品と表示しているのに実際には普通の仕入品で価格は従来どおりであったり(aの例)、冬服全品大幅値下げと表示しているのに特に安くなっているのは一部の商品に限られているケース(bの例)、などがあり得ます。
そのため、販売価格の安さを強調する表示については、
- 適用対象となる商品の範囲及び条件を明示する
- 安さの理由や安さの程度について具体的に明示する
ことにより、一般消費者が誤認しないようにする必要があるとされています。
▽価格表示ガイドライン 第6-1
販売価格が安いという印象を与えるすべての表示が景品表示法上問題となるものではないが、これらの表示については、販売価格が通常時等の価格と比較してほとんど差がなかったり、適用対象となる商品が一部に限定されているにもかかわらず、表示された商品の全体について大幅に値引きされているような表示を行うなど、実際と異なって安さを強調するものである場合には、一般消費者に販売価格が安いとの誤認を与え、不当表示に該当するおそれがある。
また、競争事業者の店舗の販売価格よりも自店の販売価格を安くする等の広告表示において、適用対象となる商品について、一般消費者が容易に判断できないような限定条件を設けたり、価格を安くする旨の表示と比較して著しく小さな文字で限定条件を表示するなど、限定条件を明示せず、価格の有利性を殊更強調する表示を行うことは、一般消費者に自己の販売価格が競争事業者のものよりも著しく有利であるとの誤認を与え、不当表示に該当するおそれがある。
このため、安さの理由や安さの程度を説明する用語等を用いて、販売価格の安さを強調する表示を行う場合には、適用対象となる商品の範囲及び条件を明示するとともに、安さの理由や安さの程度について具体的に明示することにより、一般消費者が誤認しないようにする必要がある。
まとめ
以下、まとめ代わりに、価格表示ガイドラインの目次を記載してみます。ざっと眺めるだけでも、価格に関する有利誤認の全体像がわかります。
価格表示ガイドラインの目次
| 大目次 | 目次 | 細目次 |
|---|---|---|
| はじめに | ||
| 第1 本考え方の構成及び適用範囲 | 1 本考え方の構成 | |
| 2 本考え方の適用範囲 | ||
| 3 個別事案の判断 | ||
| 第2 不当な価格表示に関する景品表示法上の考え方 | 1 景品表示法の内容 | |
| 2 景品表示法上問題となる価格表示 | ||
| 第3 販売価格に関する表示について | 1 基本的考え方 | |
| 2 不当表示に該当するおそれのある表示 | ||
| 第4 二重価格表示について | 1 二重価格表示についての基本的考え方 | |
| 2 過去の販売価格等を比較対照価格とする二重価格表示について | ⑴ 基本的考え方 | |
| ⑵ 不当表示に該当するおそれのある表示 | ||
| 3 希望小売価格を比較対照価格とする二重価格表示について | ⑴ 基本的考え方 | |
| ⑵ 不当表示に該当するおそれのある表示 | ||
| 4 競争事業者の販売価格を比較対照価格とする二重価格表示について | ⑴ 基本的考え方 | |
| ⑵ 不当表示に該当するおそれのある表示 | ||
| 5 他の顧客向けの販売価格を比較対照価格とする二重価格表示について | ⑴ 基本的考え方 | |
| ⑵ 不当表示に該当するおそれのある表示 | ||
| 第5 割引率又は割引額の表示について | 1 基本的考え方 | |
| 2 不当表示に該当するおそれのある表示 | ||
| 第6 販売価格の安さを強調するその他の表示について | 1 基本的考え方 | |
| 2 不当表示に該当するおそれのある表示 |
02|その他の取引条件に関する有利誤認
価格以外の取引条件に係る有利誤認としては、
- 数量に関する有利誤認
- 支払条件に関する有利誤認
- 景品類に関する有利誤認
- その他の取引条件に関する有利誤認
などがあるとされています。なお、これらは価格に関するものではないので、価格表示ガイドラインに記載はありません。
①(数量)は、実際の数量よりも多いと誤認される表示をするケースであり、役務の提供量(時間、期間など)も同様です。文字や絵だけではなく、過大包装もこの問題になります。
②(支払条件)は、利息の受取額が表示された内容よりも低い額であったりするケースです(表示された利息額が支払われるのは一定の条件を満たすケースに限られる)。
③(景品類)は、表示されている景品類よりも実際に提供される景品類が過少だったり低い品質であったりするケースであり、景品類と謳っていながら価格に景品類の費用が上乗せされているといったケースも含まれます。
④(その他の取引条件)はこれら以外の諸々であり、家電などの品質保証が表示された内容のものでなかったり、送料無料を謳っていながら価格に送料が上乗せされているといったケースなど、様々なものがあります。
結び
今回は、景品表示法ということで、表示規制のうち有利誤認表示について見てみました。
[注記]
本記事を含む一連の勉強記事は、過去の自分に向けて、①自分の独学や経験の記録を見せる、②感覚的な理解を伝えることを優先する、③細かく正確な理解は書物に譲る、ということをコンセプトにした読みものです。ベテランの方が見てなるほどと思うようなことは書かれていないほか、業務上必要であるときなど、正確な内容については別途ご確認ください。また、法改正をはじめとした最新の情報を反映しているとは限りませんので、ご注意ください。
景品表示法に関するその他の記事(≫Read More)
主要法令等
主要法令等
- 定義告示(「不当景品類及び不当表示防止法第2条の規定により景品類及び表示を指定する件」)
- 定義告示運用基準(「景品類等の指定の告示の運用基準について」)
- 不実証広告ガイドライン(「不当景品類及び不当表示防止法第7条第2項の運用指針-不実証広告規制に関する指針-」)
- 価格表示ガイドライン(「不当な価格表示についての景品表示法上の考え方」)
- 将来価格執行方針(「将来の販売価格を比較対照価格とする二重価格表示に対する執行方針」)
- 比較広告ガイドライン(「比較広告に関する景品表示法上の考え方」)
- 2008年No.1報告書(平成20年6月13日付け「No.1表示に関する実態調査報告書」(公正取引委員会事務総局))
- 2024年No.1報告書(令和6年9月26日付け「No.1表示に関する実態調査報告書」(消費者庁表示対策課))
- 打消し表示留意点(「打消し表示に関する表示方法及び表示内容に関する留意点(実態調査報告書のまとめ)」)
参考資料
- よくわかる景品表示法と公正競争規約〔令和6年12月改訂〕(消費者庁)|消費者庁HP(≫掲載ページ)
- 事例でわかる景品表示法〔令和6年12月改訂〕(消費者庁)|消費者庁HP(≫掲載ページ)
- 違反事例集(「景品表示法における違反事例集」)|消費者庁HP(≫掲載ページ)
参考文献
当サイトではアフィリエイトプログラムを利用して商品・サービスを記載しています







