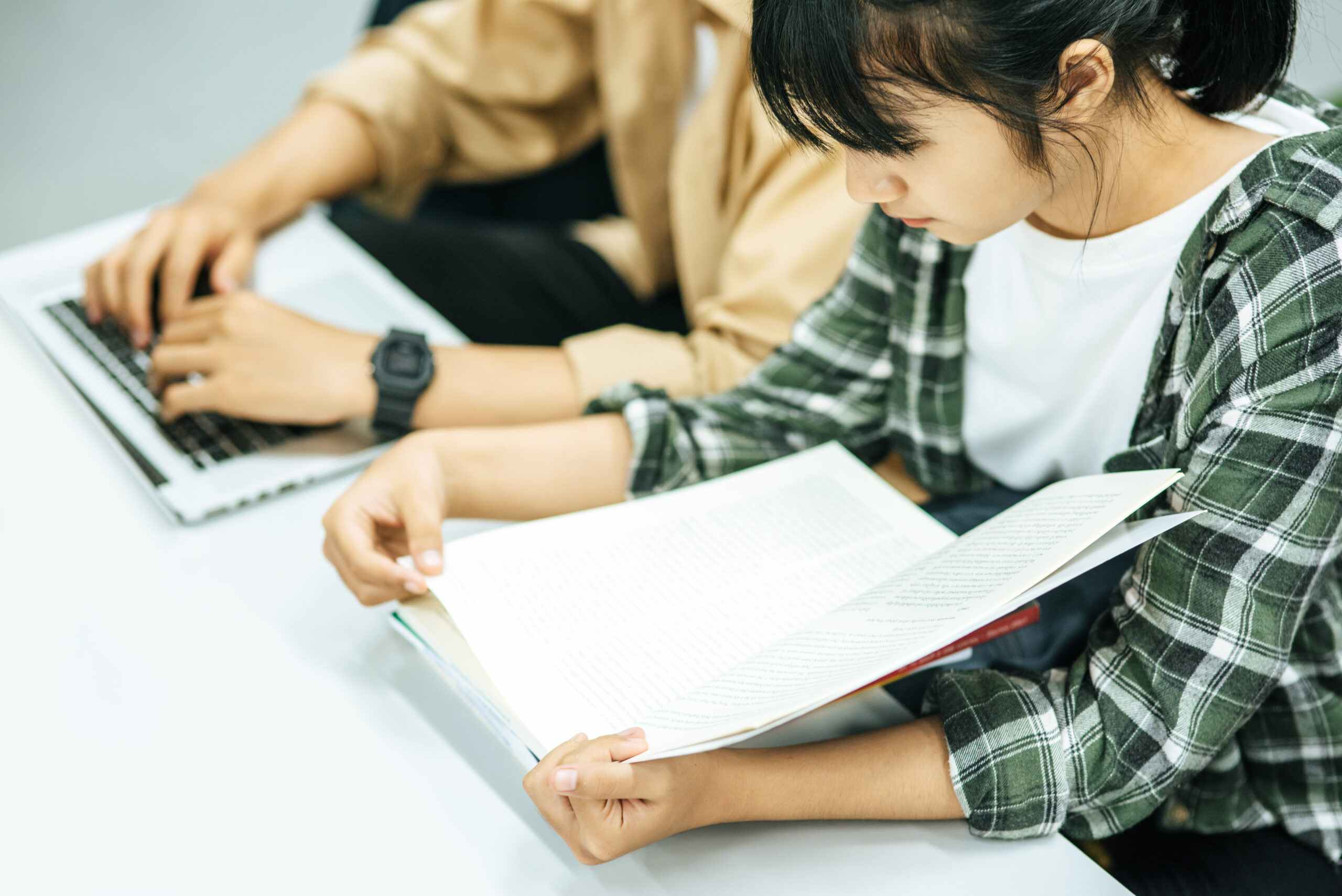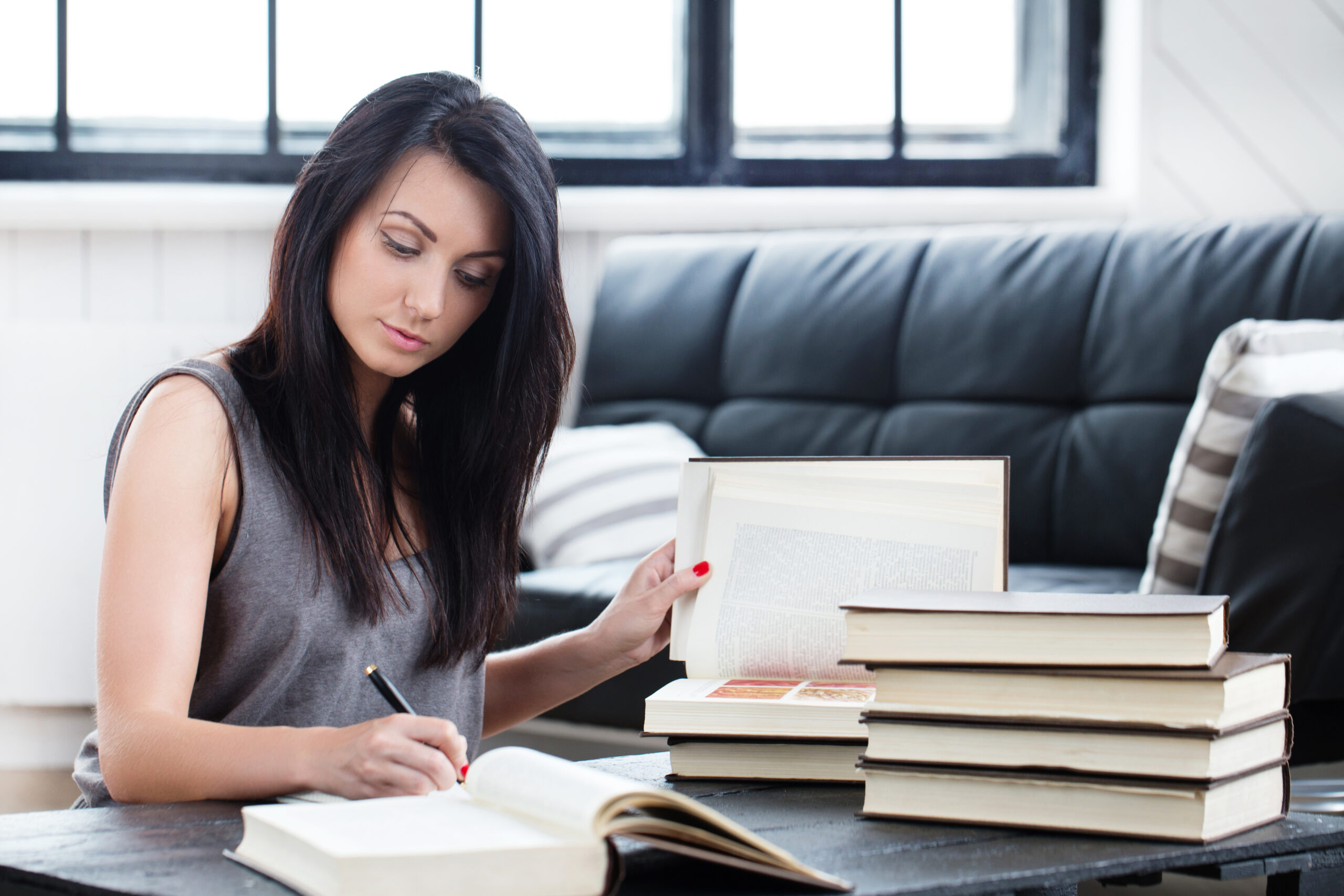今回は、法令解釈ということで、学理的解釈の分類について見てみたいと思います。
契約書などで直接役に立つということはない気がしますが、いろんなところで目にする「〇〇解釈」はまとめるとどうなっているのかが見えて、全体がクリアになります。
ではさっそく。なお、引用部分の太字、下線、改行などは管理人によるものです。
メモ
このカテゴリーでは、インハウスとしての法務経験からピックアップした、管理人の独学や経験の記録を綴っています。
ネット上の読み物としてざっくばらんに書いており、感覚的な理解を掴むことを目指していますが、書籍などを理解する際の一助になれば幸いです。
学理的解釈
学理的解釈とは、学理(学問上の研究や考察)によって法令を解釈することです。
普段よく”法令の解釈”といっているのは、通常、この学理的解釈を指しています。ざっくりいえば、理屈で解釈しようとすることです。
学理的解釈は大きく文理解釈と論理解釈に分けられ、通常、以下のように分類されます。
学理的解釈の分類
- 文理解釈
- 論理解釈
- 拡張解釈
- 縮小解釈
- 変更解釈
- 反対解釈
- 類推解釈
- もちろん解釈
以下、順に見てみます。
文理解釈
文理解釈というのは、法令の文言(文字や文章の意味)に重きを置いて規定を解釈しようとすることです。
法令は様々な検討のうえで内容が決められて、表現上も熟慮して書かれているものなので、まずは書いていることを素直に読もうとするのが基本です。
そういった意味で、文理解釈が基本といわれます(伸び縮みさせたり、書いていないことを読み取ろうとするというのは、そうするときもあるんだけれども、最初にとるべきスタンスではない)。
日常的に用いられているような用語は、法令においてもそのような通常の意味で読むのが原則とされます。
注意点
ただ、だからといって、実際のところは、日常的な感覚でだいたいが読めるというわけでもないです。
法律専門用語や法令用語は、日常的に使われない用語もたくさんありますし、(日常的に使われる用語であっても)日常的な意味とは違った独特の意味や用法がありますが、これらはそのように専門的に決まった意味合いで読むことになります。
論理解釈
論理解釈というのは、法令の文言以外の道理に重きを置いて規定を解釈しようとすることで、
- 拡張解釈
- 縮小解釈
- 変更解釈
- 反対解釈
- 類推解釈
- もちろん解釈
の6つが挙げられますが、大きく、前半3つのグループと後半3つのグループに分けることができます。
前半の3つは、意味を伸ばしたり縮めたりするものの、あくまでも書いている文言に準拠した解釈、後半の3つは文言に書いていないことを読み取る解釈になります。
文言に準拠しつつ拡張したり縮小したりする解釈
拡張解釈とは、文言の通常の意味よりも広く解釈することで、逆に、縮小解釈とは、文言の通常の意味よりも狭く解釈することです。
ただ、元々ある文言の意味の限界は超えていないというか、その文言の中に読み取れる範囲での拡張・縮小、というイメージです。
変更解釈は、文字通り、元々ある文言の意味を変更して解釈することですが、直感的に「そんなのアリなの?」と感じるように、立法のミスのような極端な場合にだけ出てくるものですので、あまり気にしなくてよいと思います(むしろ基本的にはやってはいけない解釈方法)。
文言に書いていないことを読み取る解釈
反対解釈は、文言に書かれている場合と反対の場合について、書いてあることと反対の結論であると解釈するものです。
例えば、
明日晴れたらドライブに行こう
というのは、よく読むと、明日雨が降った場合(晴れなかった場合)にどうするのかは、実は書いていません。
でも普通は、明日雨が降ったらドライブには行かないんだろうな、と考えます。それは、晴れのドライブが気持ちいいからとか、雨が降ったらなんだかんだで濡れるからやめとこうという趣旨で言っているんだろうな、といったことを無意識のうちに考えているからです。
このように発言の実質的意味(趣旨)から、直接には書かれていない事柄、つまり明日雨が降った場合に関して、ドライブには行かないという反対の結論を読み取っているわけです。これが反対解釈です。
そうではなく、買ったばかりの新車でとにかくドライブしたいだけというのが実質的意味である場合には、必ずしも反対解釈は妥当でない(結局、雨が降ってもドライブに行く)ことになります
類推解釈は、文言には書かれていないけれども似通ったものについて、書いてあることと同質的だと認められる場合には同じ結論を導き出すということです。
先ほどの例でいうと、ドライブに行く以外は何も書いていないわけですが、晴れのドライブが気持ちいいからという実質的意味を踏まえれば、
明日晴れたらピクニックに行くのもアリだね
というように、ピクニックもドライブも晴れの日に気持ちいいアウトドアイベントだから同質的であると考えれば、こういう類推解釈もできます。
もちろん解釈は、類推解釈の一種で、当然にそのような類推解釈が可能であるケース(類推できることはもちろんであるという意味)の解釈のことです。
拡張解釈と類推解釈の違い
この6つの概念の区別で一番疑問に思うのは、拡張解釈も類推解釈も元々書いてある内容から広げるものみたいだけど、どう違うの?という点かと思います。
これは、前半3つのグループと後半3つのグループの違い、つまり、元々の文言の範囲内といえるなら拡張解釈、範囲を超えるなら類推解釈、という区別をすることになります。
つまり、拡張解釈は元々の文言の範囲内に含めて考えることができるものであるのに対し、類推解釈は、元々の文言の範囲内には読み込めない=ゆえに別の事柄だが、法の目的や規定の趣旨を踏まえて同質性を認めることが可能な場合には適用を推し及ぼす、というものです。
ただ、これは結局、概念的・抽象的にはこのようにいえるというだけで、具体的な事例でこれは拡張解釈・これは類推解釈というように一義的には決まらない面があります。
この区別でよく引き合いに出される例は、刑法での
拡張解釈は許されるが類推解釈は許されない
というものです(罪刑法定主義の派生原則である「類推解釈の禁止」から)。
具体的には、過失往来危険罪の「汽車」にガソリンカー(ガソリンエンジンを動力として走行する鉄道車両)を含めるという拡張解釈をした判例(大判昭和15年8月22日刑集19巻540頁)が例として挙げられますが、当然、被告人側は類推解釈であり許されないとして争っています。
しかし、汽車等の交通往来の安全という規定の趣旨や、汽車とガソリンカーは単に動力の種類が違う点に主たる差異があるにすぎない(動力源の違いは重要でない)ということから、拡張解釈できると考えるわけです。こういうふうに、結局、実質的根拠が重要になります。
ガソリンカーは「汽車」という文言の範囲内か範囲外か?といっても、文言とにらめっこしているだけで結論が出てくるというわけではないです
解釈ということのイメージ(管理人の私見)
素朴な疑問として、「文理解釈」って解釈なのか?(そのまま読むだけで済むなら、それは解釈っていわなくてもいいんじゃないの?)という疑問があるように思います。
”解釈”というと手を加えるものみたいなイメージがあるので、元々ある何かを伸ばしたり縮めたり操作するもの=つまり論理解釈のようなものが”解釈”なんじゃないの?という感覚があるのではという気もします(法律をかじり始めた頃の管理人)。
これは、解釈という表現に関して、「規範を抜き出す作業」みたいなイメージを持つと多少解消されるのではと思います。
つまり、卵の殻を割って中身を出すような作業というか、条文という殻から規範という中身を出すような作業が「解釈」というような話です。
殻を割ると言ったのは、文言を読み砕いて意味を取り出すような感じのことだからです。
その結果、出てきた中身(規範)がたまたま卵の殻(条文)そのままだった、というのが文理解釈の場合だと思えばよいように思います。
多かれ少なかれ、条文というのはルールを記号で書いているような面があるので、その記号からルール(実体、中身)を抜き出しているのが「解釈」だと思えば、
- そのまま抜き出して不都合のないものはそのまま(=文理「解釈」)で、
- しかし、そのまま抜き出すだけではうまくいかない(広すぎる、狭すぎる、あるいは直接には書かれていないことが問題になっているetc)ものは、加工を加えつつ抜き出すことを検討する(=論理「解釈」)
というふうにイメージすることができます。
例えば、先ほど見た
明日晴れたらドライブに行こう
は、規範を抜き出すような読み方をすれば、
要件:明日晴れる
効果:ドライブに行く
というように規範をとることができるわけですが、これが文理解釈のイメージといえるかと思います。
そのまんま読んでいるだけといえばだけですが、これも、発言、字面、文章から、意味を取り出しているわけです(=解釈)。
それだけでなくさらに、
要件:明日晴れない
効果:ドライブに行かない
という規範をも抜き出そうとしているのが、反対解釈といえるかと思います。(※もちろん、こういう要件効果みたいなものだけが解釈というわけではないですが)
これは、書いていることを素直に読むという文理ではなく、晴れのドライブが気持ちいいから晴れたらドライブって言ってるんだろうなという道理から、このように解釈している(意味を取り出している)わけです。直接的には書かれていないことであっても。
まぁ、規範というのも結局日本語なので、何が記号で何が規範かというのもはっきりパキッとは分かれないような面もありますが、一応このようにいえるのではと思います。
結び
今回は、法令解釈ということで、学理的解釈の分類を見てみました。
最後にまとめると、文理から意味を取るのが文理解釈、道理から意味を取るのが論理解釈、このように文理や道理の考察で解釈しようとするのが学理的解釈、という感じです。
なお、法令解釈の種類の全体像については、以下の関連記事にくわしく書いています。
-

-
法令解釈の基本|法解釈の種類-法規的解釈と学理的解釈
続きを見る
[注記]
本記事を含む一連の勉強記事は、過去の自分に向けて、①自分の独学や経験の記録を見せる、②感覚的な理解を伝えることを優先する、③細かく正確な理解は書物に譲る、ということをコンセプトにした読みものです。ベテランの方が見てなるほどと思うようなことは書かれていないほか、業務上必要であるときなど、正確な内容については別途ご確認ください。また、法改正をはじめとした最新の情報を反映しているとは限りませんので、ご注意ください。
法制執務に関するその他の記事(≫Read More)
参考文献
※注:「法令読解の基礎知識」には第一次改訂版【Amazonページ】があります
当サイトではアフィリエイトプログラムを利用して商品・サービスを記載しています