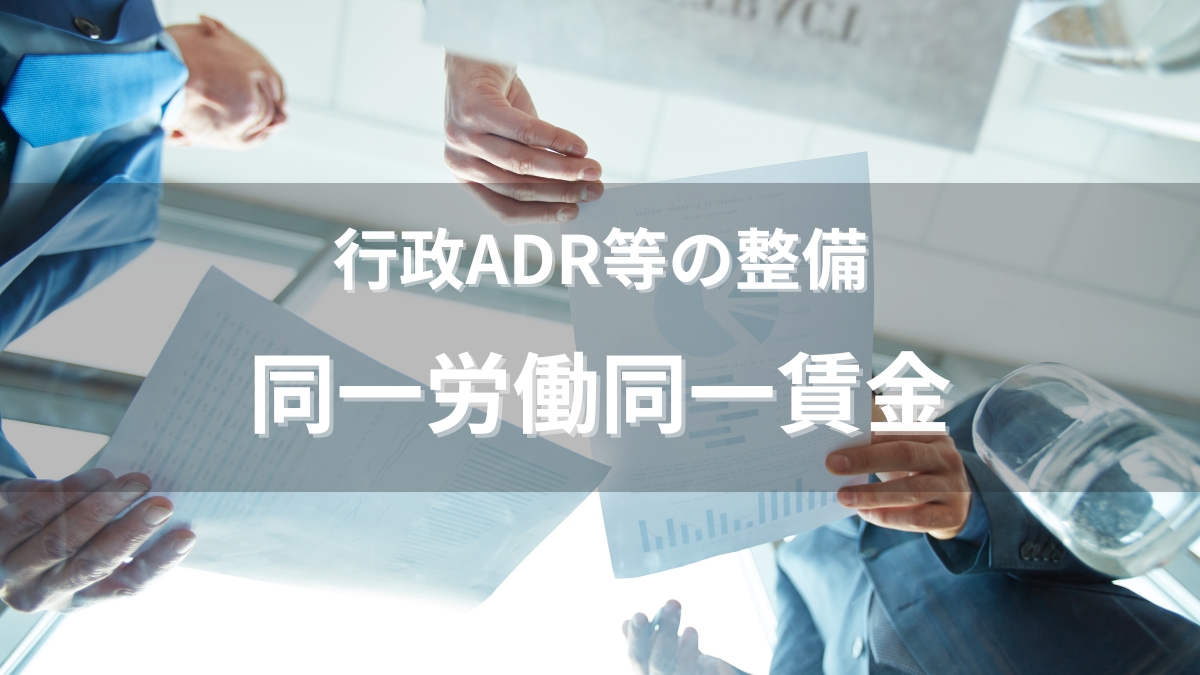今回は、非正規訴訟ということで、ハマキョウレックス事件と長澤運輸事件の最高裁判決について見てみたいと思います。
最近、非正規訴訟について一連の最高裁判決が出てニュースでも取り上げられていますが、この2件の最高裁判決がいわゆる先例になっています。
ではさっそく。なお、引用部分の太字、下線、改行などは管理人によるものです。
メモ
このカテゴリーでは、インハウスとしての法務経験からピックアップした、管理人の独学や経験の記録を綴っています。
ネット上の読み物としてざっくばらんに書いており、感覚的な理解を掴むことを目指していますが、書籍などを理解する際の一助になれば幸いです。
改正前の労働契約法20条
判決を見る前に、いったい何の話をした判決だったのか?ということについて、少しだけ前置きをしたいと思います。
この2件の最高裁判決は、同一労働同一賃金に関する法改正(いわゆる働き方改革関連法(平成30年法律第71号))の前の、労働契約法20条の解釈に関するものになります。
-

-
同一労働同一賃金①|働き方改革関連法と均等待遇・均衡待遇
続きを見る
この労契法20条は、上記法改正によって削除されていますが(→内容的にはパート・有期労働法8条に移行)、本記事の最高裁判決が解釈しているのはこの条文になりますので、内容を確認してみます。
▽改正前・労働契約法20条
(期間の定めがあることによる不合理な労働条件の禁止)
第二十条 有期労働契約を締結している労働者の労働契約の内容である労働条件が、期間の定めがあることにより同一の使用者と期間の定めのない労働契約を締結している労働者の労働契約の内容である労働条件と相違する場合においては、当該労働条件の相違は、労働者の業務の内容及び当該業務に伴う責任の程度(以下この条において「職務の内容」という。)、当該職務の内容及び配置の変更の範囲その他の事情を考慮して、不合理と認められるものであってはならない。
分節すると、
⑴有期契約労働者の労働条件が、
⑵期間の定めがあることにより無期契約労働者の労働条件と相違する場合においては、
⑶当該労働条件の相違は、
①労働者の業務の内容及び当該業務に伴う責任の程度(=「職務の内容」)
②当該職務の内容及び配置の変更の範囲(=「職務の内容・配置の変更範囲」)
③その他の事情
を考慮して、
⑷不合理と認められるものであってはならない。
のようになっています。
これは、均等待遇・均衡待遇の区別でいうと、均衡待遇に相当する内容の規定になります。
この「均等」とか「均衡」が何なのかわかりにくいですが(言葉が似ているので)、ざっくりいうと、
- 就業の実態が同じ場合=「均等待遇」(イコールにせよ)
- 就業の実態が異なる場合=「均衡待遇」(イコールじゃなくていいけどバランスはとれ)
という意味です。
均衡待遇は、就業の実態が異なる場合はバランスのとれた待遇の相違は許容するもので、就業の実態については、
- 労働者の業務の内容及び当該業務に伴う責任の程度(=「職務の内容」と略される)
- 当該職務の内容及び配置の変更の範囲(=「職務の内容・配置の変更範囲」と略される)
- その他の事情
という、3つの観点から判断されることになっています(条文の文言どおり)。
そして、裁判では、個別の待遇ごとに趣旨を認定したうえで、①~③の観点から見た就業の実態の違いから、待遇の相違が説明できるかどうかが問われることになります。
上記の労契法20条は、改正により内容的にはパート・有期労働法8条に移行していますが、改正は本記事の最高裁判決を色濃く反映したものとなっており、判決で示されている解釈はパート・有期労働法8条の解釈にも引き継がれると考えられています。ですので、引き続き重要な判例といえます。
改正後の内容については、以下の関連記事にくわしく書いています。
ハマキョウレックス事件最高裁判決
事案の概要
ではまず、ハマキョウレックス事件最高裁判決(最判平成30年6月1日(民集72巻2号88頁))から見てみます。
原告はトラックの乗務員(運転手)で、被告はハマキョウレックスという物流と運送の会社になります。
事案の概要は以下のとおりです。
事案の概要
有期労働者(契約社員)である原告が、正社員との間で、無事故手当、作業手当、給食手当、住宅手当、皆勤手当、通勤手当、家族手当、賞与、定期昇給及び退職金(併せて「本件賃金等」)に相違があることは労働契約法20条に違反している等と主張して、被告であるハマキョウレックスに対して、以下のとおり請求した事案。
⑴ 地位の確認請求
労働契約に基づき、被上告人が上告人に対し、本件賃金等に関し、正社員と同一の権利を有する地位にあることの確認を求める。
⑵ 差額賃金請求又は損害賠償請求(①がダメなら②)
① 主位的請求
労働契約に基づき、平成21年10月1日から平成27年11月30日までの間に正社員に支給された無事故手当、作業手当、給食手当、住宅手当、皆勤手当及び通勤手当(「本件諸手当」)と、同期間に原告に支給された本件諸手当との差額の支払を求める。
② 予備的請求
不法行為に基づき、上記差額に相当する額の損害賠償を求める。
主な判旨
「期間の定めがあることにより」の意義
これは、改正前の労働契約法20条が「期間の定めがあることにより…(正社員の)労働条件と相違する場合」と定めていることの意味を判示した部分になります。
該当部分を引用すると、以下のとおりです。条文の文言どおりという感じかなと。
労働条件が相違しているというだけでは適用できないが、労働条件の相違と期間の定めの有無との強い関連性までは要らない(”関連して生じた”ものであれば足る)、ということです。
▽最判平成30年6月1日(民集72巻2号88頁)(ハマキョウレックス事件)|裁判例検索(裁判所HP)
「ア 労働契約法20条は、有期契約労働者と無期契約労働者の労働条件が期間の定めがあることにより相違していることを前提としているから、両者の労働条件が相違しているというだけで同条を適用することはできない。一方、期間の定めがあることと労働条件が相違していることとの関連性の程度は、労働条件の相違が不合理と認められるものに当たるか否かの判断に当たって考慮すれば足りるものということができる。
そうすると、同条にいう「期間の定めがあることにより」とは、有期契約労働者と無期契約労働者との労働条件の相違が期間の定めの有無に関連して生じたものであることをいうものと解するのが相当である。」
「不合理と認められるもの」の意義
これは、改正前の労働契約法20条の「不合理と認められるものであってはならない。」と書かれている部分になります。
ここの意味については、文字どおりの意味では?何の争いがあるの?という気もするかもしれませんが、これが
「不合理であってはいけない」
という意味なのか、
「合理的でなければならない」
という意味なのかが争われました。
どちらと解するかで、合理とも不合理ともつかぬもの(つまりグレーゾーン)がどうなるのかが違ってくるわけです。
結論としては、文字どおり、「クロ」であってはならない、という意味だとされました。
(⇔原告は、「シロ」でなければならない、という意味に解すべきだと主張していた)
つまり、明確に「クロ」といえる場合でなければ、「不合理と認められるもの」にはあたらないということです。
▽最判平成30年6月1日(民集72巻2号88頁)(ハマキョウレックス事件)|裁判例検索(裁判所HP)
「イ 次に、労働契約法20条は、有期契約労働者と無期契約労働者との労働条件の相違が、職務の内容等を考慮して不合理と認められるものであってはならないとしているところ、所論は、同条にいう「不合理と認められるもの」とは合理的でないものと同義であると解すべき旨をいう。しかしながら、同条が「不合理と認められるものであってはならない」と規定していることに照らせば、同条は飽くまでも労働条件の相違が不合理と評価されるか否かを問題とするものと解することが文理に沿うものといえる。また、同条は、職務の内容等が異なる場合であっても、その違いを考慮して両者の労働条件が均衡のとれたものであることを求める規定であるところ、両者の労働条件が均衡のとれたものであるか否かの判断に当たっては、労使間の交渉や使用者の経営判断を尊重すべき面があることも否定し難い。
したがって、同条にいう「不合理と認められるもの」とは、有期契約労働者と無期契約労働者との労働条件の相違が不合理であると評価することができるものであることをいうと解するのが相当である。」
「不合理」であると判断された場合の労働条件への影響(=労働契約法20条違反の効果)
では、「不合理」と判断された場合には、労働条件は結局どうなるのでしょうか?
これについては、
- 労働条件の相違を設ける部分は無効となるが(=強行的効力はある)、
- 自動的に比較対象の正社員の労働条件と同一になるものではない(=直律的効力はない)、
とされました。
▽最判平成30年6月1日(民集72巻2号88頁)(ハマキョウレックス事件)|裁判例検索(裁判所HP)
「イ 労働契約法20条が有期契約労働者と無期契約労働者との労働条件の相違は「不合理と認められるものであってはならない」と規定していることや、その趣旨が有期契約労働者の公正な処遇を図ることにあること等に照らせば、同条の規定は私法上の効力を有するものと解するのが相当であり、有期労働契約のうち同条に違反する労働条件の相違を設ける部分は無効となるものと解される。
もっとも、同条は、有期契約労働者について無期契約労働者との職務の内容等の違いに応じた均衡のとれた処遇を求める規定であり、文言上も、両者の労働条件の相違が同条に違反する場合に、当該有期契約労働者の労働条件が比較の対象である無期契約労働者の労働条件と同一のものとなる旨を定めていない。
そうすると、有期契約労働者と無期契約労働者との労働条件の相違が同条に違反する場合であっても、同条の効力により当該有期契約労働者の労働条件が比較の対象である無期契約労働者の労働条件と同一のものとなるものではないと解するのが相当である。」
ではどうするのか?違法なのに救済されないのか?というと、賃金請求としてではなく、差額の損害を被ったということで、不法行為に基づく損害賠償請求として差額の請求を認めるという構成をとりました。
具体的な結論
というわけで、判決は、不法行為に基づく損害賠償請求権の有無を判断するという文脈のなかで、違法性(労働契約法20条違反の有無)の判定をしています。
判断の構造・順序としては、
- 労働条件の相違は「期間の定めがあること」により相違したものといえるか
↓ Yes - 「職務の内容」or「職務の内容・配置の変更範囲」or「その他の事情」に違いはあるか
↓ Yes - 待遇差の不合理性の有無について判定
=個別の待遇ごとに趣旨を認定した上で、「職務の内容」「職務の内容・配置の変更範囲」「その他の事情」の違いと関連性があるかを判断
という感じになります(管理人の理解の仕方)。
これらの判断構造・順序を事案にあてはめると、以下のようになっています(なお、控訴審での判断については含んでいません)。
判断構造と結論|ハマキョウレックス事件最高裁判決
- 労働条件の相違は「期間の定めがあること」により相違したものといえるか
- 結論:肯定
- 判決文:
「本件諸手当に係る労働条件の相違は、契約社員と正社員とでそれぞれ異なる就業規則が適用されることにより生じているものであることに鑑みれば、当該相違は期間の定めの有無に関連して生じたものであるということができる。したがって、契約社員と正社員の本件諸手当に係る労働条件は、同条にいう期間の定めがあることにより相違している場合に当たるということができる。」
- 「職務の内容」or「職務の内容・配置の変更範囲」or「その他の事情」に違いはあるか
- 結論:「職務の内容」に違いはないが、「職務の内容・配置の変更範囲」(=広域異動の可能性と、将来的に中核人材として登用する可能性)に違いはある
- 判決文:
「(ア) 本件では、契約社員である被上告人の労働条件と、被上告人と同じく上告人の彦根支店においてトラック運転手(乗務員)として勤務している正社員の労働条件との相違が労働契約法20条に違反するか否かが争われているところ、前記第1の2(6)の事実関係等に照らせば、両者の職務の内容に違いはないが、職務の内容及び配置の変更の範囲に関しては、正社員は、出向を含む全国規模の広域異動の可能性があるほか、等級役職制度が設けられており、職務遂行能力に見合う等級役職への格付けを通じて、将来、上告人の中核を担う人材として登用される可能性があるのに対し、契約社員は、就業場所の変更や出向は予定されておらず、将来、そのような人材として登用されることも予定されていないという違いがあるということができる。」
- 待遇差の不合理性の有無についての判定
- 住宅手当について
- 結論:
→住宅手当の趣旨:従業員の住宅に要する費用を補助する趣旨で支給されるもの
→就業場所の変更の可能性という違いと関連性がある
⇒待遇差は不合理とはいえない - 判決文:
「(イ) 上告人においては、正社員に対してのみ所定の住宅手当を支給することとされている。この住宅手当は、従業員の住宅に要する費用を補助する趣旨で支給されるものと解されるところ、契約社員については就業場所の変更が予定されていないのに対し、正社員については、転居を伴う配転が予定されているため、契約社員と比較して住宅に要する費用が多額となり得る。
したがって、正社員に対して上記の住宅手当を支給する一方で、契約社員に対してこれを支給しないという労働条件の相違は、不合理であると評価することができるものとはいえないから、労働契約法20条にいう不合理と認められるものに当たらないと解するのが相当である。」
- 結論:
- 皆勤手当について
- 結論
→運送業務を円滑に進めるには実際に出勤するトラック運転手を一定数確保する必要があることから、皆勤を奨励する趣旨で支給されるもの(=出勤者の確保)
→「職務の内容」は本件では相違がない。「職務の内容・配置の変更範囲」についての相違はあるが、出勤者の確保の必要性というのは、これらの相違とは関連性がない
⇒待遇差は不合理 - 判決文:
「(ウ) 上告人においては、正社員である乗務員に対してのみ、所定の皆勤手当を支給することとされている。この皆勤手当は、上告人が運送業務を円滑に進めるには実際に出勤するトラック運転手を一定数確保する必要があることから、皆勤を奨励する趣旨で支給されるものであると解されるところ、上告人の乗務員については、契約社員と正社員の職務の内容は異ならないから、出勤する者を確保することの必要性については、職務の内容によって両者の間に差異が生ずるものではない。また、上記の必要性は、当該労働者が将来転勤や出向をする可能性や、上告人の中核を担う人材として登用される可能性の有無といった事情により異なるとはいえない。そして、本件労働契約及び本件契約社員就業規則によれば、契約社員については、上告人の業績と本人の勤務成績を考慮して昇給することがあるとされているが、昇給しないことが原則である上、皆勤の事実を考慮して昇給が行われたとの事情もうかがわれない。
したがって、上告人の乗務員のうち正社員に対して上記の皆勤手当を支給する一方で、契約社員に対してこれを支給しないという労働条件の相違は、不合理であると評価することができるものであるから、労働契約法20条にいう不合理と認められるものに当たると解するのが相当である。」
- 結論
- 住宅手当について
長澤運輸事件最高裁判決
事案の概要
続いて、長澤運輸事件最高裁判決(最判平成30年6月1日(民集72巻2号202頁))を見てみます。
原告はバラセメントタンク車(バラ車)の乗務員(運転手)で、定年退職後の再雇用者(いわゆる嘱託社員)です。被告は長澤運輸というセメント、液化ガス、食品等の輸送事業を営む運送会社になります。
事案の概要は以下のとおりです。
事案の概要
定年退職後にいわゆる嘱託社員(有期労働者)として就労している原告らが、正社員との間に、ⅰ~ⅳのような労働契約法20条に違反する労働条件の相違があると主張して、被告である長澤運輸に対し、以下のとおり請求した事案。
- 嘱託乗務員に対し、能率給及び職務給が支給されず、歩合給が支給されること
- 嘱託乗務員に対し、精勤手当、住宅手当、家族手当及び役付手当が支給されないこと
- 嘱託乗務員の時間外手当が正社員の超勤手当よりも低く計算されること
- 嘱託乗務員に対して賞与が支給されないこと
⑴ 地位の確認請求(主位的請求)
正社員に関する就業規則等が適用される労働契約上の地位にあることの確認を求める。
⑵ 差額賃金請求(主位的請求)
労働契約に基づき、上記就業規則等により支給されるべき賃金と実際に支給された賃金との差額及びこれに対する遅延損害金の支払を求める。
⑶ 損害賠償請求(予備的請求)
不法行為に基づき、上記差額に相当する額の損害賠償金及びこれに対する遅延損害金の支払を求める
主な判旨
「その他の事情」の意義
これは、原告が有期契約労働者が定年退職後に再雇用された者であることは「その他の事情」にあたるか、という形で争われた争点です。
条文上は、”職務の内容、職務内容・配置の変更範囲、その他の事情…”という順番で出てくるのですが、判旨は、「その他の事情」の解釈としては、その前に出てくる”職務の内容”や”職務内容・配置の変更範囲”に関連する事情に限定されることはない、ということを言っています。
その上で、有期契約労働者が定年退職後に再雇用された者であることは、「その他の事情」にあたるとして、待遇差の不合理性を判断する際の考慮要素にしてOKである、としました。
▽最判平成30年6月1日(民集72巻2号202頁)(長澤運輸事件)|裁判例検索(裁判所HP)
「イ 被上告人における嘱託乗務員及び正社員は、その業務の内容及び当該業務に伴う責任の程度に違いはなく、業務の都合により配置転換等を命じられることがある点でも違いはないから、両者は、職務の内容並びに当該職務の内容及び配置の変更の範囲(以下、併せて「職務内容及び変更範囲」という。)において相違はないということができる。
しかしながら、労働者の賃金に関する労働条件は、労働者の職務内容及び変更範囲により一義的に定まるものではなく、使用者は、雇用及び人事に関する経営判断の観点から、労働者の職務内容及び変更範囲にとどまらない様々な事情を考慮して、労働者の賃金に関する労働条件を検討するものということができる。また、労働者の賃金に関する労働条件の在り方については、基本的には、団体交渉等による労使自治に委ねられるべき部分が大きいということもできる。そして、労働契約法20条は、有期契約労働者と無期契約労働者との労働条件の相違が不合理と認められるものであるか否かを判断する際に考慮する事情として、「その他の事情」を挙げているところ、その内容を職務内容及び変更範囲に関連する事情に限定すべき理由は見当たらない。
したがって、有期契約労働者と無期契約労働者との労働条件の相違が不合理と認められるものであるか否かを判断する際に考慮されることとなる事情は、労働者の職務内容及び変更範囲並びにこれらに関連する事情に限定されるものではないというべきである。」
個々の賃金項目に係る労働条件の相違が不合理か否かについての判断の方法
本判決は、不合理性の有無は、待遇のそれぞれについて個別に判断するとしています。
▽最判平成30年6月1日(民集72巻2号202頁)(長澤運輸事件)|裁判例検索(裁判所HP)
「⑷ 本件においては、被上告人における嘱託乗務員と正社員との本件各賃金項目に係る労働条件の相違が問題となるところ、労働者の賃金が複数の賃金項目から構成されている場合、個々の賃金項目に係る賃金は、通常、賃金項目ごとに、その趣旨を異にするものであるということができる。そして、有期契約労働者と無期契約労働者との賃金項目に係る労働条件の相違が不合理と認められるものであるか否かを判断するに当たっては、当該賃金項目の趣旨により、その考慮すべき事情や考慮の仕方も異なり得るというべきである。
そうすると、有期契約労働者と無期契約労働者との個々の賃金項目に係る労働条件の相違が不合理と認められるものであるか否かを判断するに当たっては、両者の賃金の総額を比較することのみによるのではなく、当該賃金項目の趣旨を個別に考慮すべきものと解するのが相当である。
なお、ある賃金項目の有無及び内容が、他の賃金項目の有無及び内容を踏まえて決定される場合もあり得るところ、そのような事情も、有期契約労働者と無期契約労働者との個々の賃金項目に係る労働条件の相違が不合理と認められるものであるか否かを判断するに当たり考慮されることになるものと解される。」
非正規訴訟に関するニュースを見ていると、”最高裁は待遇ごとに個別に判断するという判断枠組みをとっている”みたいな表現がチラホラ目に入るかと思いますが、それは主にこの長澤運輸最高裁判決のことを言っています。
具体的な結論
以上のような判断構造・順序を事案にあてはめると、以下のようになっています(なお、控訴審での判断については含んでいません)。
判断構造と結論|長澤運輸事件最高裁判決
- 労働条件の相違は「期間の定めがあること」により相違したものといえるか
- 結論:肯定
- 判決文:
「 被上告人の嘱託乗務員と正社員との本件各賃金項目に係る労働条件の相違は、嘱託乗務員の賃金に関する労働条件が、正社員に適用される賃金規定等ではなく、嘱託社員規則に基づく嘱託社員労働契約によって定められることにより生じているものであるから、当該相違は期間の定めの有無に関連して生じたものであるということができる。したがって、嘱託乗務員と正社員の本件各賃金項目に係る労働条件は、同条にいう期間の定めがあることにより相違している場合に当たる。」
- 「職務の内容」or「職務の内容・配置の変更範囲」or「その他の事情」に違いはあるか
- 結論:「職務の内容」「職務の内容・配置の変更範囲」に違いはない。しかし、有期契約労働者が定年退職後に再雇用された者であることは「その他の事情」の違いにあたる
- 判決文:
「被上告人における嘱託乗務員及び正社員は、その業務の内容及び当該業務に伴う責任の程度に違いはなく、業務の都合により配置転換等を命じられることがある点でも違いはないから、両者は、職務の内容並びに当該職務の内容及び配置の変更の範囲(以下、併せて「職務内容及び変更範囲」という。)において相違はないということができる。」
「ウ 被上告人における嘱託乗務員は、被上告人を定年退職した後に、有期労働契約により再雇用された者である。
定年制は、使用者が、その雇用する労働者の長期雇用や年功的処遇を前提としながら、人事の刷新等により組織運営の適正化を図るとともに、賃金コストを一定限度に抑制するための制度ということができるところ、定年制の下における無期契約労働者の賃金体系は、当該労働者を定年退職するまで長期間雇用することを前提に定められたものであることが少なくないと解される。これに対し、使用者が定年退職者を有期労働契約により再雇用する場合、当該者を長期間雇用することは通常予定されていない。また、定年退職後に再雇用される有期契約労働者は、定年退職するまでの間、無期契約労働者として賃金の支給を受けてきた者であり、一定の要件を満たせば老齢厚生年金の支給を受けることも予定されている。そして、このような事情は、定年退職後に再雇用される有期契約労働者の賃金体系の在り方を検討するに当たって、その基礎になるものであるということができる。
そうすると、有期契約労働者が定年退職後に再雇用された者であることは、当該有期契約労働者と無期契約労働者との労働条件の相違が不合理と認められるものであるか否かの判断において、労働契約法20条にいう「その他の事情」として考慮されることとなる事情に当たると解するのが相当である。」
- 待遇差の不合理性の有無についての判定
- 嘱託乗務員に対し、能率給及び職務給が支給されず、歩合給が支給されること
- 結論:待遇差は不合理とはいえない
- 判決文:
「ア 嘱託乗務員に対して能率給及び職務給が支給されないこと等について
被上告人は、正社員に対し、基本給、能率給及び職務給を支給しているが、嘱託乗務員に対しては、基本賃金及び歩合給を支給し、能率給及び職務給を支給していない。基本給及び基本賃金は、労務の成果である乗務員の稼働額にかかわらず、従業員に対して固定的に支給される賃金であるところ、上告人らの基本賃金の額は、いずれも定年退職時における基本給の額を上回っている。また、能率給及び歩合給は、労務の成果に対する賃金であるところ、その額は、いずれも職種に応じた係数を乗務員の月稼働額に乗ずる方法によって計算するものとされ、嘱託乗務員の歩合給に係る係数は、正社員の能率給に係る係数の約2倍から約3倍に設定されている。そして、被上告人は、本件組合との団体交渉を経て、嘱託乗務員の基本賃金を増額し、歩合給に係る係数の一部を嘱託乗務員に有利に変更している。このような賃金体系の定め方に鑑みれば、被上告人は、嘱託乗務員について、正社員と異なる賃金体系を採用するに当たり、職種に応じて額が定められる職務給を支給しない代わりに、基本賃金の額を定年退職時の基本給の水準以上とすることによって収入の安定に配慮するとともに、歩合給に係る係数を能率給よりも高く設定することによって労務の成果が賃金に反映されやすくなるように工夫しているということができる。そうである以上、嘱託乗務員に対して能率給及び職務給が支給されないこと等による労働条件の相違が不合理と認められるものであるか否かの判断に当たっては、嘱託乗務員の基本賃金及び歩合給が、正社員の基本給、能率給及び職務給に対応するものであることを考慮する必要があるというべきである。そして、第1審判決別紙5及び6に基づいて、本件賃金につき基本賃金及び歩合給を合計した金額並びに本件試算賃金につき基本給、能率給及び職務給を合計した金額を上告人ごとに計算すると、前者の金額は後者の金額より少ないが、その差は上告人X1につき約10%、上告人X2につき約12%、上告人X3につき約2%にとどまっている。
さらに、嘱託乗務員は定年退職後に再雇用された者であり、一定の要件を満たせば老齢厚生年金の支給を受けることができる上、被上告人は、本件組合との団体交渉を経て、老齢厚生年金の報酬比例部分の支給が開始されるまでの間、嘱託乗務員に対して2万円の調整給を支給することとしている。
これらの事情を総合考慮すると、嘱託乗務員と正社員との職務内容及び変更範囲が同一であるといった事情を踏まえても、正社員に対して能率給及び職務給を支給する一方で、嘱託乗務員に対して能率給及び職務給を支給せずに歩合給を支給するという労働条件の相違は、不合理であると評価することができるものとはいえないから、労働契約法20条にいう不合理と認められるものに当たらないと解するのが相当である。」
- 嘱託乗務員に対し、精勤手当、住宅手当、家族手当及び役付手当が支給されないこと
- 結論:
⇒精勤手当の待遇差は不合理
⇒住宅手当及び家族手当の待遇差は不合理とはいえない
⇒役付手当の待遇差は不合理とはいえない - 判決文:
「イ 嘱託乗務員に対して精勤手当が支給されないことについて
被上告人における精勤手当は、その支給要件及び内容に照らせば、従業員に対して休日以外は1日も欠かさずに出勤することを奨励する趣旨で支給されるものであるということができる。そして、被上告人の嘱託乗務員と正社員との職務の内容が同一である以上、両者の間で、その皆勤を奨励する必要性に相違はないというべきである。なお、嘱託乗務員の歩合給に係る係数が正社員の能率給に係る係数よりも有利に設定されていることには、被上告人が嘱託乗務員に対して労務の成果である稼働額を増やすことを奨励する趣旨が含まれているとみることもできるが、精勤手当は、従業員の皆勤という事実に基づいて支給されるものであるから、歩合給及び能率給に係る係数が異なることをもって、嘱託乗務員に精勤手当を支給しないことが不合理でないということはできない。
したがって、正社員に対して精勤手当を支給する一方で、嘱託乗務員に対してこれを支給しないという労働条件の相違は、不合理であると評価することができるものであるから、労働契約法20条にいう不合理と認められるものに当たると解するのが相当である。
ウ 嘱託乗務員に対して住宅手当及び家族手当が支給されないことについて
被上告人における住宅手当及び家族手当は、その支給要件及び内容に照らせば、前者は従業員の住宅費の負担に対する補助として、後者は従業員の家族を扶養するための生活費に対する補助として、それぞれ支給されるものであるということができる。上記各手当は、いずれも労働者の提供する労務を金銭的に評価して支給されるものではなく、従業員に対する福利厚生及び生活保障の趣旨で支給されるものであるから、使用者がそのような賃金項目の要否や内容を検討するに当たっては、上記の趣旨に照らして、労働者の生活に関する諸事情を考慮することになるものと解される。被上告人における正社員には、嘱託乗務員と異なり、幅広い世代の労働者が存在し得るところ、そのような正社員について住宅費及び家族を扶養するための生活費を補助することには相応の理由があるということができる。他方において、嘱託乗務員は、正社員として勤続した後に定年退職した者であり、老齢厚生年金の支給を受けることが予定され、その報酬比例部分の支給が開始されるまでは被上告人から調整給を支給されることとなっているものである。
これらの事情を総合考慮すると、嘱託乗務員と正社員との職務内容及び変更範囲が同一であるといった事情を踏まえても、正社員に対して住宅手当及び家族手当を支給する一方で、嘱託乗務員に対してこれらを支給しないという労働条件の相違は、不合理であると評価することができるものとはいえないから、労働契約法20条にいう不合理と認められるものに当たらないと解するのが相当である。
エ 嘱託乗務員に対して役付手当が支給されないことについて
上告人らは、嘱託乗務員に対して役付手当が支給されないことが不合理である理由として、役付手当が年功給、勤続給的性格のものである旨主張しているところ、被上告人における役付手当は、その支給要件及び内容に照らせば、正社員の中から指定された役付者であることに対して支給されるものであるということができ、上告人らの主張するような性格のものということはできない。したがって、正社員に対して役付手当を支給する一方で、嘱託乗務員に対してこれを支給しないという労働条件の相違は、労働契約法20条にいう不合理と認められるものに当たるということはできない。」
- 結論:
- 嘱託乗務員の時間外手当が正社員の超勤手当よりも低く計算されること
- 結論:待遇差は不合理
- 判決文:
「オ 嘱託乗務員の時間外手当と正社員の超勤手当の相違について
正社員の超勤手当及び嘱託乗務員の時間外手当は、いずれも従業員の時間外労働等に対して労働基準法所定の割増賃金を支払う趣旨で支給されるものであるといえる。被上告人は、正社員と嘱託乗務員の賃金体系を区別して定めているところ、割増賃金の算定に当たり、割増率その他の計算方法を両者で区別していることはうかがわれない。しかしながら、前記イで述べたとおり、嘱託乗務員に精勤手当を支給しないことは、不合理であると評価することができるものに当たり、正社員の超勤手当の計算の基礎に精勤手当が含まれるにもかかわらず、嘱託乗務員の時間外手当の計算の基礎には精勤手当が含まれないという労働条件の相違は、不合理であると評価することができるものであるから、労働契約法20条にいう不合理と認められるものに当たると解するのが相当である。」
- 嘱託乗務員に対して賞与が支給されないこと
- 結論:待遇差は不合理とはいえない
- 判決文:
「カ 嘱託乗務員に対して賞与が支給されないことについて
賞与は、月例賃金とは別に支給される一時金であり、労務の対価の後払い、功労報償、生活費の補助、労働者の意欲向上等といった多様な趣旨を含み得るものである。嘱託乗務員は、定年退職後に再雇用された者であり、定年退職に当たり退職金の支給を受けるほか、老齢厚生年金の支給を受けることが予定され、その報酬比例部分の支給が開始されるまでの間は被上告人から調整給の支給を受けることも予定されている。また、本件再雇用者採用条件によれば、嘱託乗務員の賃金(年収)は定年退職前の79%程度となることが想定されるものであり、嘱託乗務員の賃金体系は、前記アで述べたとおり、嘱託乗務員の収入の安定に配慮しながら、労務の成果が賃金に反映されやすくなるように工夫した内容になっている。
これらの事情を総合考慮すると、嘱託乗務員と正社員との職務内容及び変更範囲が同一であり、正社員に対する賞与が基本給の5か月分とされているとの事情を踏まえても、正社員に対して賞与を支給する一方で、嘱託乗務員に対してこれを支給しないという労働条件の相違は、不合理であると評価することができるものとはいえないから、労働契約法20条にいう不合理と認められるものに当たらないと解するのが相当である。」
- 嘱託乗務員に対し、能率給及び職務給が支給されず、歩合給が支給されること
結び
今回は、非正規訴訟ということで、ハマキョウレックス事件と長澤運輸事件の最高裁判決について見てみました。
[注記]
本記事を含む一連の勉強記事は、過去の自分に向けて、①自分の独学や経験の記録を見せる、②感覚的な理解を伝えることを優先する、③細かく正確な理解は書物に譲る、ということをコンセプトにした読みものです。ベテランの方が見てなるほどと思うようなことは書かれていないほか、業務上必要であるときなど、正確な内容については別途ご確認ください。また、法改正をはじめとした最新の情報を反映しているとは限りませんので、ご注意ください。
同一労働同一賃金に関するその他の記事(≫Read More)
主要法令等・参考文献
主要法令等
- 働き方改革関連法(「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律」(平成30年法律第71号))(≫法律情報)|厚労省HP(≫掲載ページ)
- 労働契約法
- パート・有期労働法(「短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律」)
- パート・有期労働指針(「事業主が講ずべき短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する措置等についての指針」 (平成19年厚生労働省告示第326号))|厚労省HP(≫掲載ページ)
- 労働者派遣法(「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律」)
- 労働者派遣法施行規則(「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則」)
- 派遣元指針(「派遣元事業主が講ずべき措置に関する指針」)|厚労省HP(≫掲載ページ)
- 派遣先指針(「派遣先が講ずべき措置に関する指針」)|厚労省HP(≫掲載ページ)
- 派遣業務取扱要領(「労働者派遣事業関係業務取扱要領」)|厚労省HP
- 同一労働同一賃金ガイドライン(「短時間・有期雇用労働者及び派遣労働者に対する不合理な待遇の禁止等に関する指針」(平成30年厚生労働省告示第430号))|厚労省HP(≫掲載ページ)
- 改正法施行通達(「短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律の施行について」(基発0130第1号・職発0130第6号・雇均発0130第1号・開発0130第1号))|厚労省HP(≫掲載ページ)
参考ページ
- 「働き方改革」の実現に向けて|厚労省HP
- 同一労働同一賃金特集ページ|厚労省HP ※パート・有期がメイン
- 派遣労働者の同一労働同一賃金について|厚労省HP
- 同一労働同一賃金ガイドライン|厚労省HP