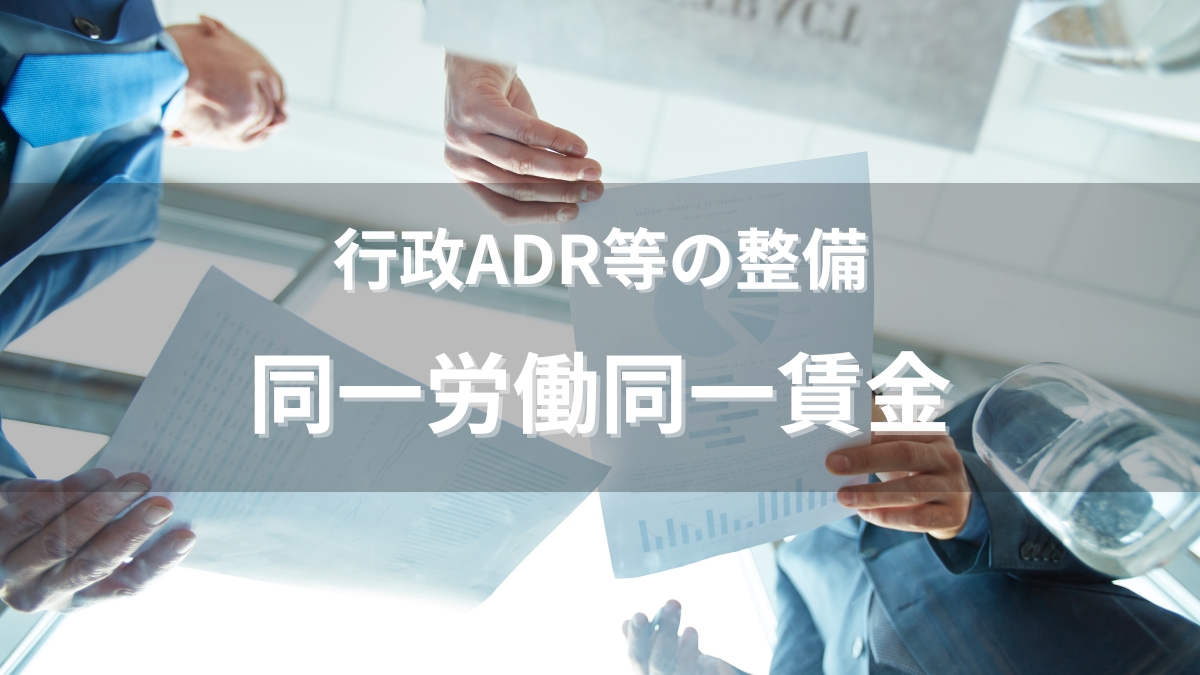今回は、同一労働同一賃金ということで、均等待遇・均衡待遇の基本的な考え方について見てみたいと思います。
改正法である働き方改革関連法と併せて見てみます。
ではさっそく。なお、引用部分の太字、下線、改行などは管理人によるものです。
メモ
このカテゴリーでは、インハウスとしての法務経験からピックアップした、管理人の独学や経験の記録を綴っています。
ネット上の読み物としてざっくばらんに書いており、感覚的な理解を掴むことを目指していますが、書籍などを理解する際の一助になれば幸いです。
働き方改革関連法について
同一労働同一賃金は、働き方改革関連法の項目の中のひとつになります。
なお、法改正で突然出てきたように見えますが、同一労働同一賃金(=Equal pay for equal work)という概念自体は労働法の基本理念として以前からあります
働き方改革関連法の正式名称は、「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律」(平成30年法律第71号)といいます。
「働き方改革」の実現に向けて|厚労省HP
このように改正法というのは、
・改正しようとする方針や内容に沿って(=改正事項)
・いろんな法律を改正して整備する(=改正対象法令)
という感じですので、以下ではその順番でまとめてみます。
改正事項
まず、働き方改革関連法はどんな内容で改正しようとしたのか?(=改正事項)というと、全体の骨子は以下のようになっています。
要するに、「公正な待遇の確保」(3⃣の部分)に関する改正事項は、
①不合理な待遇差の解消
②待遇に関する説明義務の強化
③行政ADR等の整備
という3本柱になっており、「同一労働同一賃金」は①の部分のことになります。
改正法の概要説明資料から該当部分を抜粋すると、以下のように記載されています。
▽「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律(平成30年法律第71号)の概要」5頁|厚労省HP(≫掲載ページ)
1 不合理な待遇差を解消するための規定の整備
○ 短時間・有期雇用労働者に関する同一企業内における正規雇用労働者との不合理な待遇の禁止に関し、個々の待遇ごとに、当該待遇の性質・目的に照らして適切と認められる事情を考慮して判断されるべき旨を明確化。
(有期雇用労働者を法の対象に含めることに伴い、題名を改正(「短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律」))
○ 有期雇用労働者について、正規雇用労働者と①職務内容、②職務内容・配置の変更範囲が同一である場合の均等待遇の確保を義務化。
○ 派遣労働者について、①派遣先の労働者との均等・均衡待遇、②一定の要件(同種業務の一般の労働者の平均的な賃金と同等以上の賃金であること等)を満たす労使協定による待遇のいずれかを確保することを義務化。
○ また、これらの事項に関するガイドラインの根拠規定を整備。
2 労働者に対する待遇に関する説明義務の強化
○ 短時間労働者・有期雇用労働者・派遣労働者について、正規雇用労働者との待遇差の内容・理由等に関する説明を義務化。
3 行政による履行確保措置及び裁判外紛争解決手続(行政ADR)の整備
○ 1の義務や2の説明義務について、行政による履行確保措置及び行政ADRを整備。
当ブログでは、「公正な待遇の確保」の3本柱に関して、以下の関連記事にまとめています。
改正対象法令(改正前後の比較)
次に、①~③についてどんな法律が改正されたのか?(=改正対象法令)というと、主に見るべきものは、労働契約法、パート労働法、労働者派遣法になります。
①の「不合理な待遇差の解消」=同一労働同一賃金に関して、改正前後の法令を整理してみると、以下のようになります。
ここ(元々はどんな内容でそれがどう変わったのか)が、ごちゃごちゃしていてわかりにくいところかと思います
改正前後の比較|同一労働同一賃金について
| 非正規雇用の類型 | 同一労働同一賃金 | 改正前 | 改正後 |
|---|---|---|---|
| パート労働法 | 均等待遇 | パート労働法9条 | ➢均等待遇:パート・有期労働法9条 ➢均衡待遇:パート・有期労働法8条 |
| 均衡待遇 | パート労働法8条 | ||
| 有期労働者 | 均等待遇 | なし | |
| 均衡待遇 | 労働契約法20条 | ||
| 派遣労働者 | 均等待遇 | なし | ➢派遣先均等・均衡方式(労働者派遣法30条の3) ➢労使協定方式(労働者派遣法30条の4) |
| 均衡待遇 | 労働者派遣法30条の2(※配慮義務のみ) |
※有期雇用労働者を法の対象に含めることに伴い、法律の名称も変更されています
パート労働法(「短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律」)
↓
パート・有期労働法(「短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律」)
施行日
なお、施行日は以下のとおりです。
- パート・有期労働法:2020年4月1日(中小企業は2021年4月1日)
- 労働者派遣法:2020年4月1日
同一労働同一賃金の基本的な考え方
均等待遇・均衡待遇
同一労働同一賃金(を含む「公正な待遇の確保」の全体)については、厚労省HPに特集ページがあります。
同一労働同一賃金の基本的な考え方は、ここでは、「均等待遇」「均衡待遇」であるとされています。
リーフレット(「雇用形態に関わらない公正な待遇の確保」【省令・指針反映版】)の該当部分を抜粋すると、以下のように記載されています。
▽リーフレット【省令・指針反映版】1-⑴・⑵
1 不合理な待遇差の禁止
同一企業内において、正規雇用労働者と非正規雇用労働者の間で、基本給や賞与などあらゆる待遇について不合理な待遇差を設けることが禁止されます。
裁判の際に判断基準となる「均衡待遇規定」「均等待遇規定」を法律に整備します。
(1)パートタイム労働者・有期雇用労働者
「均衡待遇規定」の内容(不合理な待遇差の禁止)
①職務内容※、②職務内容・配置の変更範囲、③その他の事情の内容を考慮して不合理な待遇差を禁止
「均等待遇規定」の内容(差別的取扱いの禁止)
①職務内容※ 、②職務内容・配置の変更範囲が同じ場合は、差別的取扱い禁止
※ 職務内容とは、業務の内容+責任の程度をいいます。
(2)派遣労働者
★ 派遣労働者の待遇差に関する規定の整備にあたっては、「派遣先均等・均衡方式」と「労使協定方式」の選択制になります。
<考え方>
● 派遣労働者の就業場所は派遣先であり、待遇に関する派遣労働者の納得感を考慮する上で、派遣先の労働者との均等・均衡は重要な観点です。
● しかし、派遣先の賃金水準と職務の難易度が常に整合的とは言えないため、結果として、派遣労働者の段階的・体系的なキャリアアップ支援と不整合な事態を招くこともあり得ます。
● こうした状況を踏まえ、以下の2つの方式の選択制とします。
1)派遣先の労働者との均等・均衡待遇
2)一定の要件を満たす労使協定による待遇
この「均等」とか「均衡」が何なのかわかりにくいですが(言葉が似ているので)、
- 就業の実態が同じ場合=「均等待遇」(イコールにせよ)、
- 就業の実態が異なる場合=「均衡待遇」(イコールじゃなくていいけどバランスはとれ)、
という意味です。
改正法施行通達(「短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律の施行について」)の関連部分を参考までに引用すると、以下のように記載されています。
▽改正法施行通達 第1-4-⑴-ニ
ニ 通常の労働者との均衡のとれた待遇の確保等
法は、短時間・有期雇用労働者について、就業の実態等を考慮して雇用管理の改善等に関する措置等を講ずることにより、通常の労働者との均衡のとれた待遇を確保することを目指しているが、これは、一般に短時間・有期雇用労働者の待遇が通常の労働者と比較して働きや貢献に見合ったものとなっておらず低くなりがちであるという状況を前提として、通常の労働者との均衡(バランス)をとることを目指した雇用管理の改善を進めていくという考え方であること。
通常の労働者と短時間・有期雇用労働者の「均衡のとれた待遇」は、就業の実態に応じたものとなるが、その就業の実態が同じ場合には、「均等な待遇」を意味する。
他方、通常の労働者と短時間・有期雇用労働者との間で、就業の実態が異なる場合、その「均衡のとれた待遇」とはどのようなものであるかについては、一義的に決まりにくい上、待遇と言ってもその種類(賃金、教育訓練、福利厚生施設等)や性質・目的(職務の内容との関連性等)は一様ではない。
「就業の実態」の判断
では、「就業の実態」はどうやって判断するのか?というと。
均等待遇でも均衡待遇でも、就業の実態を判断するにあたってメインとなる切り口は2つであり、
- 職務の内容・責任の程度(職務内容と略される)
- 職務の内容・責任の程度または配置が変更される範囲(職務内容・配置の変更範囲と略される)
となっています。
この2つは、均等待遇の判断においては”要件”ですが、均衡待遇の判断においては要件扱いではなく”考慮要素”となっており、また「その他の事情」も考慮要素に入れてよいことになっています。
つまり、同一労働同一賃金というのは、
- ①②が同じなら、均等の待遇にせよ【=均等待遇】
- ①②やその他の事情が違うなら、均等の待遇にしなくてもいいが、不合理な相違はないようにせよ(均衡のとれた待遇にせよ)【=均衡待遇】
ということです(管理人的な理解の仕方)。
改正法施行通達の該当部分を参考までに引用すると、以下のような記載になっています。
▽改正法施行通達 第1-4-⑵-イ
⑵ 均衡のとれた待遇の確保の図り方について
イ 基本的考え方
短時間・有期雇用労働者についての、通常の労働者との均衡のとれた待遇の確保に当たっては、短時間・有期雇用労働者の就業の実態等を考慮して措置を講じていくこととなるが、「就業の実態」を表す要素のうちから「職務の内容」及び「職務の内容及び配置の変更の範囲(有無を含む。)」の2つを、法第8条において通常の労働者との待遇の相違の不合理性を判断する際の考慮要素として例示するとともに、法第9条等において適用要件としている。これは、現在の我が国の雇用システムにおいては、一般に、通常の労働者の賃金をはじめとする待遇の多くがこれらの要素に基づいて決定されることが合理的であると考えられている一方で、短時間・有期雇用労働者については、これらが通常の労働者と全く同じ、又は一部同じであっても、所定労働時間が短い労働者であるということ、あるいは期間の定めがある労働契約を締結している労働者であるということのみを理由として待遇が低く抑えられている場合があることから、通常の労働者との均衡のとれた待遇の確保を図る際に、短時間・有期雇用労働者の就業の実態をとらえるメルクマールとして、これらの要素を特に取り上げるものであること。
法8条や法9条(※ここでの「法」はパート・有期労働法を指しています)が具体的にどんなものかについては、また次の記事で見ていきたいと思います。
結び
今回は、同一労働同一賃金ということで、働き方改革関連法と、同一労働同一賃金の基本的な考え方について見てみました。
-

-
同一労働同一賃金②|パート・有期労働者の場合(均等待遇・均衡待遇)
続きを見る
[注記]
本記事を含む一連の勉強記事は、過去の自分に向けて、①自分の独学や経験の記録を見せる、②感覚的な理解を伝えることを優先する、③細かく正確な理解は書物に譲る、ということをコンセプトにした読みものです。ベテランの方が見てなるほどと思うようなことは書かれていないほか、業務上必要であるときなど、正確な内容については別途ご確認ください。また、法改正をはじめとした最新の情報を反映しているとは限りませんので、ご注意ください。
同一労働同一賃金に関するその他の記事(≫Read More)
主要法令等・参考文献
主要法令等
- 働き方改革関連法(「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律」(平成30年法律第71号))(≫法律情報)|厚労省HP(≫掲載ページ)
- 労働契約法
- パート・有期労働法(「短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律」)
- パート・有期労働指針(「事業主が講ずべき短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する措置等についての指針」 (平成19年厚生労働省告示第326号))|厚労省HP(≫掲載ページ)
- 労働者派遣法(「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律」)
- 労働者派遣法施行規則(「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則」)
- 派遣元指針(「派遣元事業主が講ずべき措置に関する指針」)|厚労省HP(≫掲載ページ)
- 派遣先指針(「派遣先が講ずべき措置に関する指針」)|厚労省HP(≫掲載ページ)
- 派遣業務取扱要領(「労働者派遣事業関係業務取扱要領」)|厚労省HP
- 同一労働同一賃金ガイドライン(「短時間・有期雇用労働者及び派遣労働者に対する不合理な待遇の禁止等に関する指針」(平成30年厚生労働省告示第430号))|厚労省HP(≫掲載ページ)
- 改正法施行通達(「短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律の施行について」(基発0130第1号・職発0130第6号・雇均発0130第1号・開発0130第1号))|厚労省HP(≫掲載ページ)
参考ページ
- 「働き方改革」の実現に向けて|厚労省HP
- 同一労働同一賃金特集ページ|厚労省HP ※パート・有期がメイン
- 派遣労働者の同一労働同一賃金について|厚労省HP
- 同一労働同一賃金ガイドライン|厚労省HP