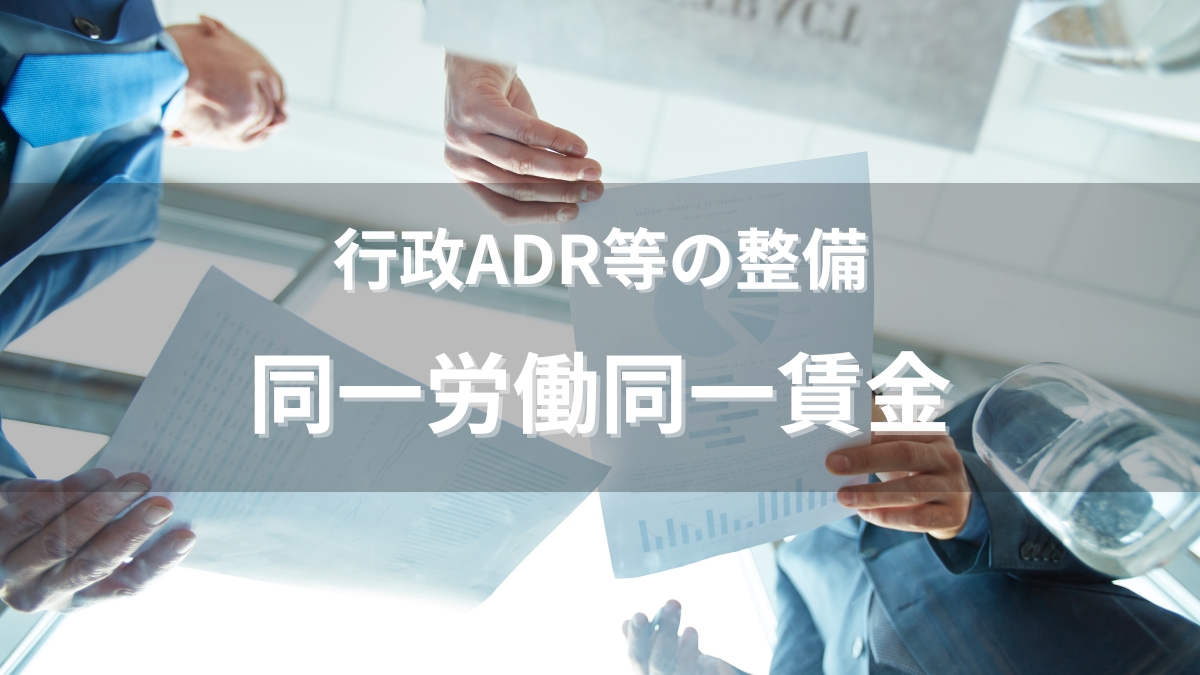今回は、同一労働同一賃金ということで、派遣労働者の場合の「同一労働同一賃金」の内容について見てみたいと思います。
ではさっそく。なお、引用部分の太字、下線、改行などは管理人によるものです。
メモ
このカテゴリーでは、インハウスとしての法務経験からピックアップした、管理人の独学や経験の記録を綴っています。
ネット上の読み物としてざっくばらんに書いており、感覚的な理解を掴むことを目指していますが、書籍などを理解する際の一助になれば幸いです。
改正前後の法令比較
いわゆる働き方改革関連法(「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律」平成30年法律第71号)で同一労働同一賃金が整備されたわけですが、派遣労働者の同一労働同一賃金について改正前後の法令を比較すると、以下のようになっています。
改正前後の比較|同一労働同一賃金(派遣の場合)
| 非正規雇用の類型 | 同一労働同一賃金 | 改正前 | 改正後 |
|---|---|---|---|
| 派遣労働者 | 均等待遇 | なし | ➢派遣先均等・均衡方式(労働者派遣法30条の3) ➢労使協定方式(労働者派遣法30条の4) |
| 均衡待遇 | 労働者派遣法30条の3(※配慮義務のみ) |
ポイントの1つ目は、改正前の労働者派遣法30条の3は均衡待遇に相当する規定であり、均等待遇に関する規定はなかったのが、改正後の同条は2項で均等待遇を、1項で均衡待遇を定めている点です。
ポイントの2つ目は、派遣労働者の場合は、労使協定方式との選択制とされている点です。
つまり、派遣労働者については、
- 派遣先の労働者の待遇との均等・均衡を図る派遣先均等・均衡方式(労働者派遣法30条の3)
- 派遣元事業主との間で一定の要件を満たす労使協定を締結し同協定に基づき待遇を決定する労使協定方式(労働者派遣法30条の4)
のいずれかの方法により待遇を決定する必要があります。
つまり、待遇決定方式が2種類あるということです。
なぜそのようにしたのかについては、以下のような説明がなされています。
▽「派遣労働者の≪同一労働同一賃金≫の概要(平成30年労働者派遣法改正)」Ⅰ-1|厚労省HP(≫掲載ページ)
1 我が国が目指す「派遣労働者の同一労働同一賃金」
基本的な考え方
派遣労働者の就業場所は派遣先であり、待遇に関する派遣労働者の納得感を考慮するため、派遣先の労働者との均等(=差別的な取扱いをしないこと)、均衡(=不合理な待遇差を禁止すること)は重要な観点です。
しかし、この場合、派遣先が変わるごとに賃金水準が変わり、派遣労働者の所得が不安定になることが想定されます。また、一般に賃金水準は大企業であるほど高く、小規模の企業であるほど低い傾向にありますが、派遣労働者が担う職務の難易度は、同種の業務であっても、大企業ほど高度で小規模の企業ほど容易とは必ずしも言えないため、結果として、派遣労働者個人の段階的・体系的なキャリアアップ支援と不整合な事態を招くこともあり得ます。
こうした状況を踏まえ、改正により、派遣労働者の待遇について、派遣元事業主には、以下のいずれかを確保することが義務化されます。
【派遣先均等・均衡方式】派遣先の通常の労働者との均等・均衡待遇
【労使協定方式】一定の要件を満たす労使協定による待遇
この選択制がとられているあたり、パート・有期労働者の場合とはルールの構造が違っているので、留意が必要かと思います。厚労省HPも、派遣労働者の同一労働同一賃金については別の特集ページが組まれています。
改正後の法令等
派遣労働者の同一労働同一賃金に関する改正後の主要な法令等は、以下のようになっています。
| 法令 | 告示等 | 行政解釈 (通達、Q&A等) | 解説 (マニュアル等) |
|---|---|---|---|
| 労働者派遣法(「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律」)等 | ➢派遣元指針(「派遣元事業者が講ずべき措置に関する指針」(H30告427)) ➢派遣先指針(「派遣先が講ずべき措置に関する指針」(H30告428)) ➢同一労働同一賃金ガイドライン(「短時間・有期雇用労働者及び派遣労働者に対する不合理な待遇の禁止等に関する指針」(H30告430)) | ➢改正省令通達(「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備及び経過措置に関する省令等の公布について」) ➢派遣先均等・均衡方式に関するQ&A ➢労使協定方式に関するQ&A ➢労働者派遣事業関係業務取扱要領 | ➢平成30年労働者派遣法改正の概要<同一労働同一賃金> ➢不合理な待遇差解消のための点検・検討マニュアル~改正労働者派遣法の対応に向けて~(労働者派遣業界編) |
(※)一部タイトルは溶込み後のものに変更
(※)派遣元指針、派遣先指針、同一労働同一賃金ガイドラインは、労働者派遣法47条の12を受けて策定された指針(告示)
派遣先均等・均衡方式
これは、派遣先労働者との均等・均衡方式のことです(※派遣元ではない点に注意)。
均等・均衡の基本的な考え方は、パート・有期労働法のもの(法9条の「均等待遇」と法8条の「均衡待遇」)と同じです。
-

-
同一労働同一賃金②|パート・有期労働者の場合(均等待遇・均衡待遇)
続きを見る
均等待遇(法30条の3第2項)
均等待遇は、法30条の3第2項に定められています。
つまり、派遣労働者と派遣先の通常の労働者との間で、①職務の内容、②職務の内容・配置の変更の範囲が同じ場合は、派遣労働者であることを理由とした差別的取扱いは禁止されています。
なお、同じ取扱いのもとで、能力、経験等の違いにより差がつくのは差支えないとされています。
▽労働者派遣法30条の3第2項
2 派遣元事業主は、職務の内容が派遣先に雇用される通常の労働者と同一の派遣労働者であつて、当該労働者派遣契約及び当該派遣先における慣行その他の事情からみて、当該派遣先における派遣就業が終了するまでの全期間において、その職務の内容及び配置が当該派遣先との雇用関係が終了するまでの全期間における当該通常の労働者の職務の内容及び配置の変更の範囲と同一の範囲で変更されることが見込まれるものについては、正当な理由がなく、基本給、賞与その他の待遇のそれぞれについて、当該待遇に対応する当該通常の労働者の待遇に比して不利なものとしてはならない。
均衡待遇(法30条の3第1項)
均衡待遇は、1項に定められています。
つまり、派遣労働者と派遣先の通常の労働者との間で、①職務の内容、②職務の内容・配置の変更の範囲、③その他の事情を考慮して、不合理な待遇差を設けることは禁止されています。
「その他の事情」は、「職務の内容」「職務の内容・配置の変更の範囲」以外の事情のことで、個々の状況に合わせて、その都度検討されます。成果、能力、経験、合理的な労使の慣行、労使交渉の経緯などが想定されています。
▽労働者派遣法30条の3第1項
(不合理な待遇の禁止等)
第三十条の三 派遣元事業主は、その雇用する派遣労働者の基本給、賞与その他の待遇のそれぞれについて、当該待遇に対応する派遣先に雇用される通常の労働者の待遇との間において、当該派遣労働者及び通常の労働者の職務の内容、当該職務の内容及び配置の変更の範囲その他の事情のうち、当該待遇の性質及び当該待遇を行う目的に照らして適切と認められるものを考慮して、不合理と認められる相違を設けてはならない。
職務の内容等を勘案した賃金の決定義務(派遣元の努力義務)
派遣元事業主は、派遣先に雇用される通常の労働者との均衡を考慮しつつ、その雇用する派遣労働者の職務の内容、職務の成果、意欲、能力又は経験その他の就業の実態に関する事項を勘案して、賃金決定するように努めなければならないとされています。
均衡待遇方式によるときの努力義務となっています(※以下の下線部で、均等待遇方式と、労使協定方式による場合は除かれている)。
▽労働者派遣法30条の5
(職務の内容等を勘案した賃金の決定)
第三十条の五 派遣元事業主は、派遣先に雇用される通常の労働者との均衡を考慮しつつ、その雇用する派遣労働者(第三十条の三第二項の派遣労働者及び前条第一項の協定で定めるところによる待遇とされる派遣労働者(以下「協定対象派遣労働者」という。)を除く。)の職務の内容、職務の成果、意欲、能力又は経験その他の就業の実態に関する事項を勘案し、その賃金(通勤手当その他の厚生労働省令で定めるものを除く。)を決定するように努めなければならない。
労使協定方式
これは、労使協定により一定水準を満たす待遇決定方式です。
派遣元事業主が、労働者の過半数で組織する労働組合又は労働者の過半数代表者と一定の要件を満たす労使協定を締結し、当該協定に基づいて待遇を決定するものです(ただし、①派遣先の教育訓練、②派遣先の福利厚生の2点は除く)。
適法にこの労使協定が締結された場合は、法30条の3の適用が除外されます(以下の太字部分参照)。
ただし、①派遣先の教育訓練、及び②派遣先の福利厚生の待遇については、労使協定方式による場合であっても、労使協定の対象とはならないため、派遣元事業主は、派遣先の通常の労働者との均等・均衡を確保する必要があります。
▽労働者派遣法30条の4第1項
第三十条の四 派遣元事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、その雇用する派遣労働者の待遇(第四十条第二項の教育訓練、同条第三項の福利厚生施設その他の厚生労働省令で定めるものに係るものを除く。以下この項において同じ。)について、次に掲げる事項を定めたときは、前条の規定は、第一号に掲げる範囲に属する派遣労働者の待遇については適用しない。ただし、第二号、第四号若しくは第五号に掲げる事項であつて当該協定で定めたものを遵守していない場合又は第三号に関する当該協定の定めによる公正な評価に取り組んでいない場合は、この限りでない。
一~六 (略)
過半数代表者の選出
労働組合がない場合、労使協定は過半数代表者と締結することになりますが、法30条の4でいう「過半数代表者」は、
- 労働基準法第41条第2号に規定する管理監督者でないこと
- 労使協定を締結する者を選出することを明らかにして実施される投票、挙手等の民主的な方法による手続により選出された者であって、派遣元事業主の意向に基づき選出されたものでないこと
のいずれにも該当する者(①に該当する者がいないときは②に該当する者)とされています。
▽労働者派遣法施行規則25条の6
(法第三十条の四第一項の過半数代表者)
第二十五条の六 法第三十条の四第一項の労働者の過半数を代表する者(以下この条において「過半数代表者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。ただし、第一号に該当する者がいない場合にあつては、過半数代表者は第二号に該当する者とする。
一 労働基準法第四十一条第二号に規定する監督又は管理の地位にある者でないこと。
二 法第三十条の四第一項の協定をする者を選出することを明らかにして実施される投票、挙手等の民主的な方法による手続により選出された者であつて、派遣元事業主の意向に基づき選出されたものでないこと。
労使協定に定めるべき事項
では、労使協定にはどんな事項を定めればいいのでしょうか?
これについては、法30条の4第1項の1~6号に列記されています(以下の表のとおり)。条文が読みにくいですが、要するに、2号が「賃金」の決定方法、4号が「賃金以外の待遇」の決定方法です。
なお、4号で言及されている「賃金以外の待遇」に関して、派遣先の教育訓練と派遣先の福利厚生の2つは労使協定の対象から除かれています(←法30条の4の柱書で、「待遇」の文言から除かれている)ので、これらについては派遣先均等・均衡方式によらざるを得ないことになります。
| 号 | 労使協定に定めるべき内容 |
|---|---|
| 1号 | 労使協定の対象となる派遣労働者の範囲 |
| 2号 | 賃金の決定方法 ⇒次のア及びイを満たす決定方法をとる必要がある ア 派遣労働者が従事する業務と同種の業務に従事する一般労働者の平均的な賃金の額と同等以上の賃金額となること (※)派遣先の事業所その他派遣就業の場所の所在地を含む地域において派遣労働者が従事する業務と同種の業務に従事する一般の労働者であって、当該派遣労働者と同程度の能力及び経験を有する者の平均的な賃金の額。職種ごとの賃金、能力・経験、地域別の賃金差をもとに決定される(職種ごとの賃金等については、毎年6~7月に通知で示される予定) イ 派遣労働者の職務の内容、成果、意欲、能力又は経験等の向上があった場合に賃金が改善されること (※)職務の内容に密接に関連して支払われる賃金以外の賃金(例えば、通勤手当、家族手当、住宅手当、別居手当、子女教育手当)を除く |
| 3号 | 派遣労働者の職務の内容、成果、意欲、能力又は経験等を公正に評価して賃金を決定すること |
| 4号 | 賃金(及び労使協定の対象とならない派遣先の教育訓練と派遣先の福利厚生)以外の待遇の決定方法 ⇒派遣元事業主に雇用される通常の労働者(派遣労働者を除く)との間で不合理な相違がないものに限る |
| 5号 | 派遣労働者に対して段階的・計画的な教育訓練を実施すること |
| 6号 | その他の事項 ・ 有効期間(2年以内が望ましい) ・ 労使協定の対象となる派遣労働者の範囲を派遣労働者の一部に限定する場合は、その理由 ・ 特段の事情がない限り、一の労働契約の期間中に派遣先の変更を理由として、協定の対象となる派遣労働者であるか否かを変えようとしないこと |
条文も確認してみます。
▽労働者派遣法30条の4第1項各号
第三十条の四
(略)
一 その待遇が当該協定で定めるところによることとされる派遣労働者の範囲
二 前号に掲げる範囲に属する派遣労働者の賃金の決定の方法(次のイ及びロ(通勤手当その他の厚生労働省令で定めるものにあつては、イ)に該当するものに限る。)
イ 派遣労働者が従事する業務と同種の業務に従事する一般の労働者の平均的な賃金の額として厚生労働省令で定めるものと同等以上の賃金の額となるものであること。
ロ 派遣労働者の職務の内容、職務の成果、意欲、能力又は経験その他の就業の実態に関する事項の向上があつた場合に賃金が改善されるものであること。
三 派遣元事業主は、前号に掲げる賃金の決定の方法により賃金を決定するに当たつては、派遣労働者の職務の内容、職務の成果、意欲、能力又は経験その他の就業の実態に関する事項を公正に評価し、その賃金を決定すること。
四 第一号に掲げる範囲に属する派遣労働者の待遇(賃金を除く。以下この号において同じ。)の決定の方法(派遣労働者の待遇のそれぞれについて、当該待遇に対応する派遣元事業主に雇用される通常の労働者(派遣労働者を除く。)の待遇との間において、当該派遣労働者及び通常の労働者の職務の内容、当該職務の内容及び配置の変更の範囲その他の事情のうち、当該待遇の性質及び当該待遇を行う目的に照らして適切と認められるものを考慮して、不合理と認められる相違が生じることとならないものに限る。)
五 派遣元事業主は、第一号に掲げる範囲に属する派遣労働者に対して第三十条の二第一項の規定による教育訓練を実施すること。
六 前各号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事項
労使協定の内容の周知
派遣元事業主は、労使協定を締結したときは、
- 書面の交付
- 労働者が希望した場合のファクシミリ・電子メール等
(※)「電子メール等」は出力することにより書面を作成することができるものに限られる - 電子計算機に備えられたファイル、磁気ディスクその他これらに準ずる物に記録し、かつ、労働者が当該記録の内容を常時確認できるようにすること
(※) 例えば、派遣労働者にログイン・パスワードを発行し、イントラネット等で常時確認できる方法が考えられる - 常時派遣元事業主の各事業所の見やすい場所に掲示し、又は備え付けること(協定の概要について、書面の交付等によりあわせて周知する場合に限る。)
のいずれかの方法により、その内容を雇用する労働者に周知しなければなりません。
条文も確認してみます。
▽労働者派遣法30条の4第2項
2 前項の協定を締結した派遣元事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、当該協定をその雇用する労働者に周知しなければならない。
▽労働者派遣法施行規則25条の11
(法第三十条の四第二項の周知の方法)
第二十五条の十一 法第三十条の四第二項の周知は、次のいずれかの方法により行わなければならない。
一 書面の交付の方法
二 次のいずれかの方法によることを当該労働者が希望した場合における当該方法
イ ファクシミリを利用してする送信の方法
ロ 電子メール等の送信の方法
三 電子計算機に備えられたファイル、磁気ディスクその他これらに準ずる物に記録し、かつ、労働者が当該記録の内容を常時確認できる方法
四 常時当該派遣元事業主の各事業所の見やすい場所に掲示し、又は備え付ける方法(法第三十条の四第一項の協定の概要について、第一号又は第二号の方法により併せて周知する場合に限る。)
派遣先が講ずべき措置
待遇情報の提供義務
ここまで見てみたように、派遣先均等・均衡方式又は労使協定方式という2種類の選択制の待遇決定方式が新設・義務化されたわけですが、これらとあわせて、派遣先になろうとする事業主に対し、派遣先労働者の待遇に関する派遣元への情報提供義務が新設・義務化されました。
つまり、派遣先は、派遣元に対して、「比較対象労働者」の「待遇情報」の提供をしなければなりません。
待遇情報
提供すべき「待遇情報」は、以下のとおりです。
- 派遣先均等・均衡方式の場合
- 比較対象労働者の職務の内容、職務の内容及び配置の変更の範囲並びに雇用形態
- 比較対象労働者を選定した理由
- 比較対象労働者の待遇のそれぞれの内容(昇給、賞与その他の主な待遇がない場合には、その旨を含む。)
- 比較対象労働者の待遇のそれぞれの性質及び当該待遇を行う目的
- 比較対象労働者の待遇のそれぞれを決定するに当たって考慮した事項
- 労使協定方式の場合
- 派遣労働者と同種の業務に従事する派遣先の労働者に対して、業務の遂行に必要な能力を付与するために実施する教育訓練(法第40条第2項の教育訓練)
- 給食施設、休憩室、更衣室(法第40条第3項の福利厚生施設)
提供方法は、書面、ファクシミリ、電子メール等によることとされています。
▽労働者派遣法26条7項
7 労働者派遣の役務の提供を受けようとする者は、第一項の規定により労働者派遣契約を締結するに当たつては、あらかじめ、派遣元事業主に対し、厚生労働省令で定めるところにより、当該労働者派遣に係る派遣労働者が従事する業務ごとに、比較対象労働者の賃金その他の待遇に関する情報その他の厚生労働省令で定める情報を提供しなければならない。
▽労働者派遣法施行規則24条の3、24条の4
(法第二十六条第七項の情報の提供の方法等)
第二十四条の三 法第二十六条第七項の情報の提供は、同項の規定により提供すべき事項に係る書面の交付等により行わなければならない。
2 派遣元事業主は前項の規定による情報の提供に係る書面等を、派遣先は当該書面等の写しを、当該労働者派遣契約に基づく労働者派遣が終了した日から起算して三年を経過する日まで保存しなければならない。
(法第二十六条第七項の厚生労働省令で定める情報)
第二十四条の四 法第二十六条第七項の厚生労働省令で定める情報は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める情報とする。
一 労働者派遣契約に、当該労働者派遣契約に基づく労働者派遣に係る派遣労働者を協定対象派遣労働者に限定しないことを定める場合 次のイからホまでに掲げる情報
イ 比較対象労働者(法第二十六条第八項に規定する比較対象労働者をいう。以下同じ。)の職務の内容(同項に規定する職務の内容をいう。以下同じ。)、当該職務の内容及び配置の変更の範囲並びに雇用形態
ロ 当該比較対象労働者を選定した理由
ハ 当該比較対象労働者の待遇のそれぞれの内容(昇給、賞与その他の主な待遇がない場合には、その旨を含む。)
ニ 当該比較対象労働者の待遇のそれぞれの性質及び当該待遇を行う目的
ホ 当該比較対象労働者の待遇のそれぞれについて、職務の内容、当該職務の内容及び配置の変更の範囲その他の事情のうち、当該待遇に係る決定をするに当たつて考慮したもの
二 労働者派遣契約に、当該労働者派遣契約に基づく労働者派遣に係る派遣労働者を協定対象派遣労働者に限定することを定める場合 次のイ及びロに掲げる情報
イ 法第四十条第二項の教育訓練の内容(当該教育訓練がない場合には、その旨)
ロ 第三十二条の三各号に掲げる福利厚生施設の内容(当該福利厚生施設がない場合には、その旨)
比較対象労働者
では、「比較対象労働者」とはどのようなものなのでしょうか?
これについては、派遣先が、次の①~⑥の優先順位により「比較対象労働者」を選定することになっています。
「比較対象労働者」の選定順位
- 「職務の内容」と「職務の内容及び配置の変更の範囲」が同じ通常の労働者
- 「職務の内容」が同じ通常の労働者
- 「業務の内容」又は「責任の程度」が同じ通常の労働者
- 「職務の内容及び配置の変更の範囲」が同じ通常の労働者
- ①~④に相当するパート・有期雇用労働者(短時間・有期雇用労働法等に基づき、派遣先の通常の労働者との間で均衡待遇が確保されていることが必要)
- 派遣労働者と同一の職務に従事させるために新たに通常の労働者を雇い入れたと仮定した場合における当該労働者(※「仮想の通常の労働者」と呼ばれる)
条文も確認してみます。
▽労働者派遣法26条8項
8 前項の「比較対象労働者」とは、当該労働者派遣の役務の提供を受けようとする者に雇用される通常の労働者であつて、その業務の内容及び当該業務に伴う責任の程度(以下「職務の内容」という。)並びに当該職務の内容及び配置の変更の範囲が、当該労働者派遣に係る派遣労働者と同一であると見込まれるものその他の当該派遣労働者と待遇を比較すべき労働者として厚生労働省令で定めるものをいう。
▽労働者派遣法施行規則24条の5
(法第二十六条第八項の厚生労働省令で定める者)
第二十四条の五 法第二十六条第八項の厚生労働省令で定める者は、次のとおりとする。
一 職務の内容並びに当該職務の内容及び配置の変更の範囲が派遣労働者と同一であると見込まれる通常の労働者
二 前号に該当する労働者がいない場合にあつては、職務の内容が派遣労働者と同一であると見込まれる通常の労働者
三 前二号に該当する労働者がいない場合にあつては、前二号に掲げる者に準ずる労働者
③以下は業務取扱要領(「労働者派遣事業関係業務取扱要領」)に示されていますが、特に⑥はみだりに使われると骨抜きになってしまうので、注意すべき細かい解釈が書き込まれています。
▽業務取扱要領 第5-2-⑶-ハ
ハ 比較対象労働者の内容
(イ) 比較対象労働者とは、労働者派遣の役務の提供を受けようとする者に雇用される通常の労働者であって、その業務の内容及び当該業務に伴う責任の程度(以下「職務の内容」という。)並びに当該職務の内容及び配置の変更の範囲が、当該労働者派遣に係る派遣労働者と同一であると見込まれるものその他の当該派遣労働者と待遇を比較すべき労働者であり、具体的には、次に掲げる労働者である(法第26条第8項、則第24条の5)。
なお、比較対象労働者の選定に際しては、派遣労働者が就業する場所にとどまらず、労働者派遣の役務の提供を受けようとする者の事業所全体の労働者が対象となることに留意が必要である。
- 職務の内容並びに当該職務の内容及び配置の変更の範囲が派遣労働者と同一であると見込まれる通常の労働者
- ①に該当する労働者がいない場合にあっては、職務の内容が派遣労働者と同一であると見込まれる通常の労働者
- ①及び②に該当する労働者がいない場合にあっては、業務の内容又は責任の程度のいずれかが派遣労働者と同一であると見込まれる通常の労働者
- ①~③に該当する労働者がいない場合にあっては、職務の内容及び配置の変更の範囲が派遣労働者と同一であると見込まれる通常の労働者
- ①~④に該当する労働者がいない場合にあっては、①から④までに相当する短時間・有期雇用労働者(短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成5年法律第76号。以下「短時間・有期雇用労働法」という。)第2条第3項に規定する「短時間・有期雇用労働者」をいう。)
当該短時間・有期雇用労働者の待遇については、労働者派遣の役務の提供を受けようとする者が雇用する通常の労働者の待遇との間で、短時間・有期雇用労働法第8条に基づき、不合理と認められる相違を設けてはならない。 - ①~⑤に該当する労働者がいない場合にあっては、派遣労働者と同一の職務の内容で業務に従事させるために新たに通常の労働者を雇い入れたと仮定した場合における当該通常の労働者(以下「仮想の通常の労働者」という。)
仮想の通常の労働者の待遇は、実際に雇い入れた場合の待遇であることを証する一定の根拠に基づき決定されていることが必要である。「一定の根拠」とは、例えば、これまで適用実績はないが、仮に雇い入れるとすれば適用される待遇が示されている就業規則であって、労働基準監督署に届け出ている就業規則、労働基準監督署には届け出ていないがモデル就業規則に基づき作成している就業規則等が考えられ、労働者派遣の役務の提供を受けようとする者が明示的に説明できることが必要である。
また、仮想の通常の労働者は、労働者派遣の役務の提供を受けようとする者に雇用される通常の労働者との間で適切な待遇が確保されている必要がある。「適切な待遇が確保されている」とは、労働者派遣の役務の提供を受けようとする者が、仮想の通常の労働者の待遇について、実際に雇用する通常の労働者との間で「職務の内容」、「職務の内容及び配置の変更の範囲」等も考慮しつつ、客観的・具体的な実態に照らして不合理でないことについて派遣元事業主に説明できる状態であることをいう。
なお、仮想の通常の労働者については、その時点では実在しない労働者を指すが、例えば、過去1年以内に雇用していた者や現存する就業規則等に基づき設定され、適用実績のある労働者の標準的なモデルがある場合は、当該者が①から⑤までに該当する可能性があることに留意すること。
派遣料金に関する配慮義務
派遣先は、派遣元との派遣料金の交渉にあたり、派遣料金に関して配慮すべき義務が定められています。
つまり、派遣元が、その選択した待遇方式(派遣先均等・均衡方式又は労使協定方式)による待遇を遵守できるよう配慮せよ、ということです。
もっとくだけた言い方をすれば、値切り過ぎるなということです(管理人の理解)
▽労働者派遣法26条11項
11 労働者派遣の役務の提供を受けようとする者及び派遣先は、当該労働者派遣に関する料金の額について、派遣元事業主が、第三十条の四第一項の協定に係る労働者派遣以外の労働者派遣にあつては第三十条の三の規定、同項の協定に係る労働者派遣にあつては同項第二号から第五号までに掲げる事項に関する協定の定めを遵守することができるものとなるように配慮しなければならない。
派遣元が講ずべき措置
待遇決定方式の情報提供
派遣元事業主は、派遣労働者の数/派遣先の数/いわゆるマージン率/教育訓練に関する事項等に加えて、
- 労使協定を締結しているか否か
- 労使協定を締結している場合には、
- 労使協定の対象となる派遣労働者の範囲
- 労使協定の有効期間の終期
に関し、関係者(派遣労働者、派遣先等)に情報提供しなければなりません。
これらの事項に関する情報提供にあたっては、常時インターネットの利用により、広く関係者、とりわけ派遣労働者に必要な情報を提供することが原則となっています(厚生労働省の「人材サービス総合サイト」に掲載することも可能)。
条文等も確認してみます。
▽労働者派遣法23条5項
5 派遣元事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、労働者派遣事業を行う事業所ごとの当該事業に係る派遣労働者の数、労働者派遣の役務の提供を受けた者の数、労働者派遣に関する料金の額の平均額から派遣労働者の賃金の額の平均額を控除した額を当該労働者派遣に関する料金の額の平均額で除して得た割合として厚生労働省令で定めるところにより算定した割合、教育訓練に関する事項その他当該労働者派遣事業の業務に関しあらかじめ関係者に対して知らせることが適当であるものとして厚生労働省令で定める事項に関し情報の提供を行わなければならない。
▽労働者派遣法施行規則18条の2第3項
(情報提供の方法等)
第十八条の二
3 法第二十三条第五項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 労働者派遣に関する料金の額の平均額
二 派遣労働者の賃金の額の平均額
三 法第三十条の四第一項の協定を締結しているか否かの別
四 法第三十条の四第一項の協定を締結している場合にあつては、協定対象派遣労働者(法第三十条の五に規定する協定対象派遣労働者をいう。以下同じ。)の範囲及び当該協定の有効期間の終期
五 その他労働者派遣事業の業務に関し参考となると認められる事項
▽派遣元指針 第2-16
16 情報の提供
派遣元事業主は、派遣労働者及び派遣先が良質な派遣元事業主を適切に選択できるよう、労働者派遣の実績、労働者派遣に関する料金の額の平均額から派遣労働者の賃金の額の平均額を控除した額を当該労働者派遣に関する料金の額の平均額で除して得た割合(以下この16において「マージン率」という。)、教育訓練に関する事項、労働者派遣法第30条の4第1項の協定を締結しているか否かの別並びに当該協定を締結している場合における協定対象派遣労働者の範囲及び当該協定の有効期間の終期(以下この16において「協定の締結の有無等」という。)等に関する情報を事業所への書類の備付け、インターネットの利用その他の適切な方法により提供すること。特に、マージン率及び協定の締結の有無等の情報提供に当たっては、常時インターネットの利用により広く関係者とりわけ派遣労働者に必要な情報を提供することを原則とすること。また、労働者派遣の期間の区分ごとの雇用安定措置を講じた人数等の実績及び教育訓練計画については、インターネットの利用その他の適切な方法により関係者に対し情報提供することが望ましいこと。
▽業務取扱要領 第4-4-⑶
(3)情報提供の方法等
イ 情報提供の方法は、事業所への書類の備付け、インターネットの利用その他の適切な方法により行うこととする(則第18条の2第1項)。なお、派遣元指針により、マージン率及び(2)のヘの事項の情報提供に当たっては、常時インターネットの利用により広く関係者、とりわけ派遣労働者に必要な情報を提供することを原則とすることとされているので留意すること。
「その他の適切な方法」としては、例えば、パンフレットの作成や人材サービス総合サイトの活用等が考えられるが、情報提供の趣旨に鑑みて適切な方法によることが必要である。なお、人材サービス総合サイトについては、上記のインターネットの利用が原則とされていることにかんがみ、自社でホームページを有していない場合等については積極的に活用することが望ましい。
結び
今回は、同一労働同一賃金ということで、派遣労働者の場合の「同一労働同一賃金」(=派遣先均等・均衡方式 or 労使協定方式)の内容について見てみました。
-

-
同一労働同一賃金④|待遇に関する説明義務の強化
続きを見る
[注記]
本記事を含む一連の勉強記事は、過去の自分に向けて、①自分の独学や経験の記録を見せる、②感覚的な理解を伝えることを優先する、③細かく正確な理解は書物に譲る、ということをコンセプトにした読みものです。ベテランの方が見てなるほどと思うようなことは書かれていないほか、業務上必要であるときなど、正確な内容については別途ご確認ください。また、法改正をはじめとした最新の情報を反映しているとは限りませんので、ご注意ください。
同一労働同一賃金に関するその他の記事(≫Read More)
主要法令等・参考文献
主要法令等
- 働き方改革関連法(「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律」(平成30年法律第71号))(≫法律情報)|厚労省HP(≫掲載ページ)
- 労働契約法
- パート・有期労働法(「短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律」)
- パート・有期労働指針(「事業主が講ずべき短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する措置等についての指針」 (平成19年厚生労働省告示第326号))|厚労省HP(≫掲載ページ)
- 労働者派遣法(「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律」)
- 労働者派遣法施行規則(「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則」)
- 派遣元指針(「派遣元事業主が講ずべき措置に関する指針」)|厚労省HP(≫掲載ページ)
- 派遣先指針(「派遣先が講ずべき措置に関する指針」)|厚労省HP(≫掲載ページ)
- 派遣業務取扱要領(「労働者派遣事業関係業務取扱要領」)|厚労省HP
- 同一労働同一賃金ガイドライン(「短時間・有期雇用労働者及び派遣労働者に対する不合理な待遇の禁止等に関する指針」(平成30年厚生労働省告示第430号))|厚労省HP(≫掲載ページ)
- 改正法施行通達(「短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律の施行について」(基発0130第1号・職発0130第6号・雇均発0130第1号・開発0130第1号))|厚労省HP(≫掲載ページ)
参考ページ
- 「働き方改革」の実現に向けて|厚労省HP
- 同一労働同一賃金特集ページ|厚労省HP ※パート・有期がメイン
- 派遣労働者の同一労働同一賃金について|厚労省HP
- 同一労働同一賃金ガイドライン|厚労省HP