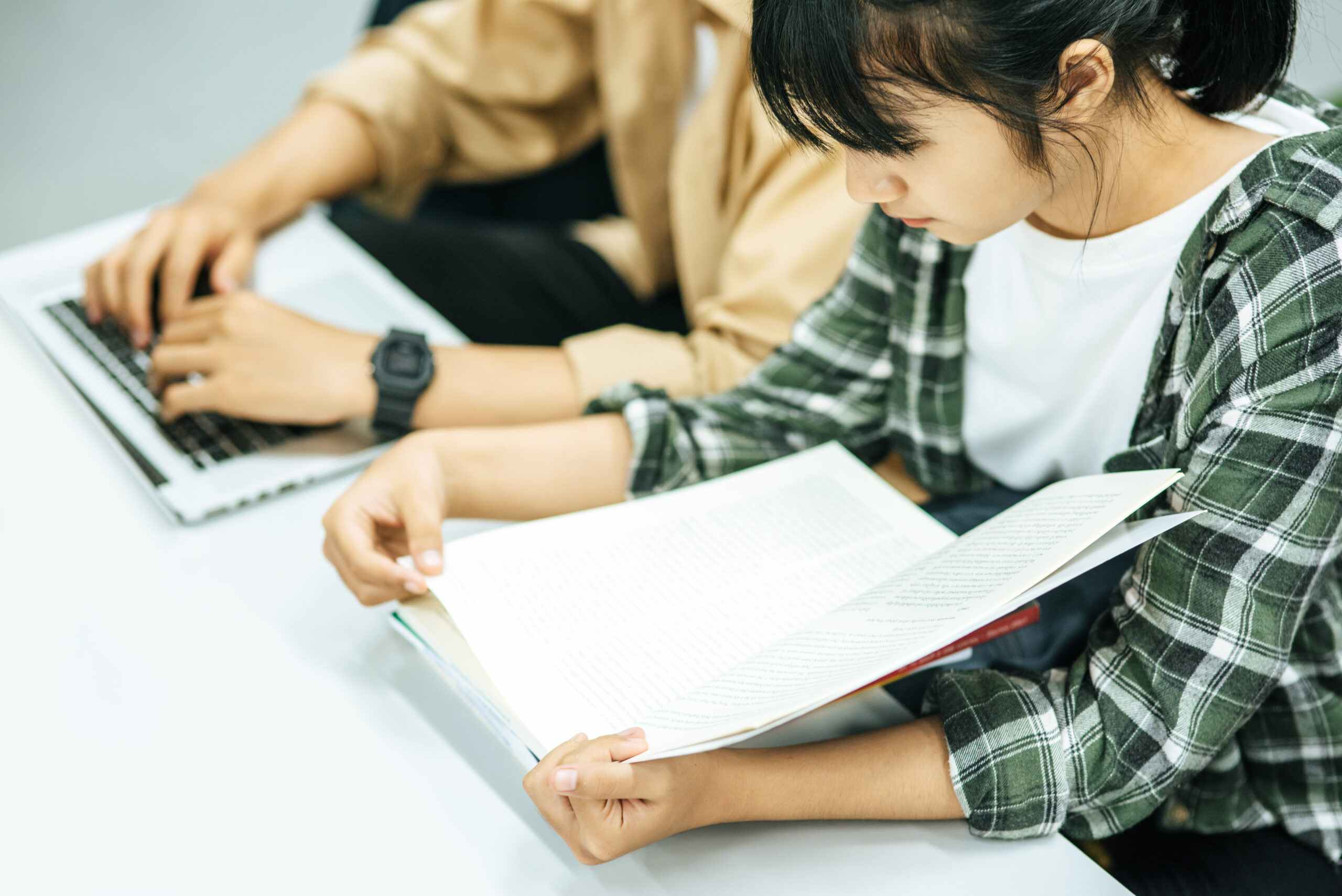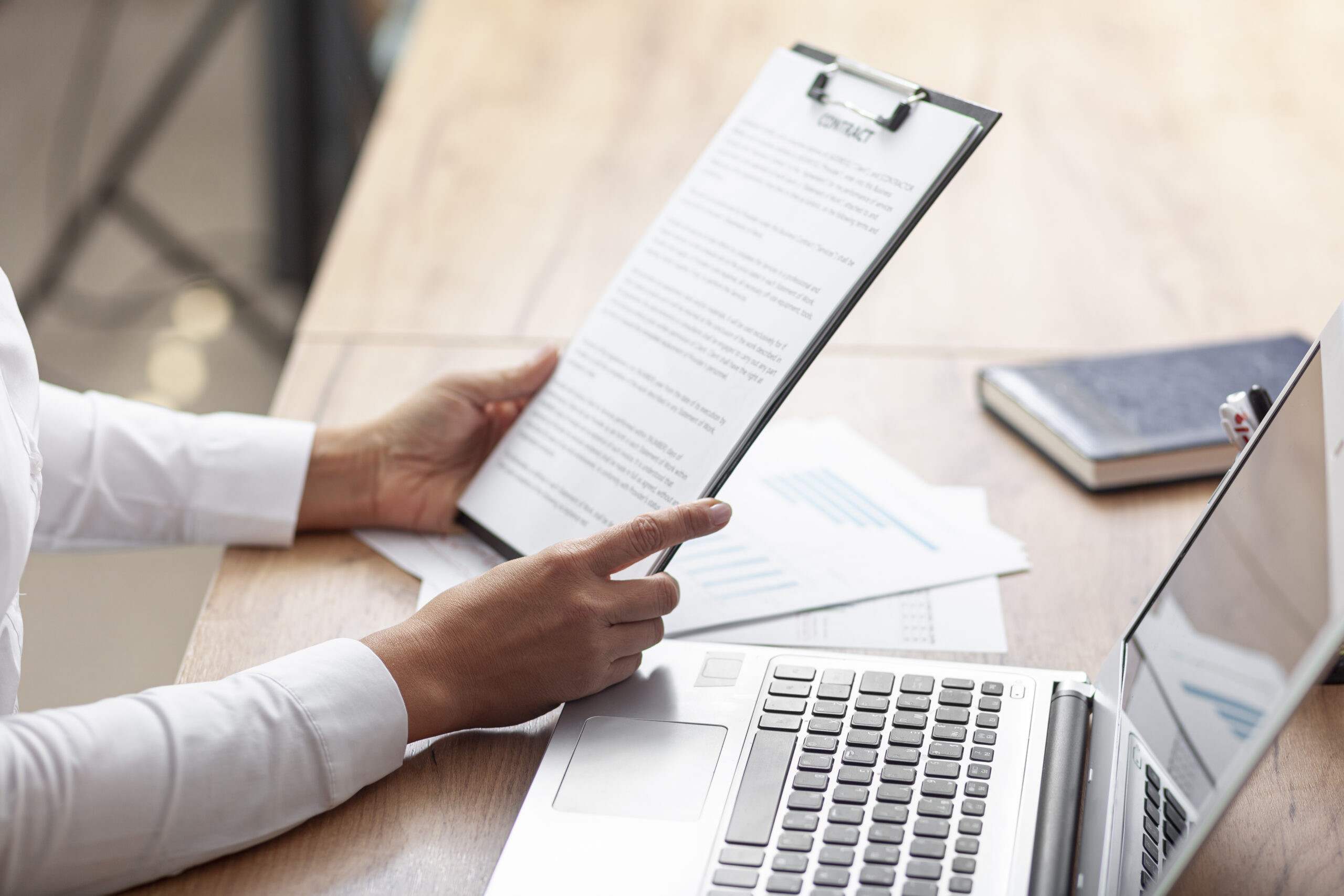今回は、法令作成ということで、条文の文章構造について見てみたいと思います。
法令作成には一定の決まった型みたいなものがありますが、当ブログでは、契約書などを読み書きするときにも役立ちそうなものをピックアップしています。
ではさっそく。なお、引用部分の太字、下線、改行などは管理人によるものです。
メモ
このカテゴリーでは、インハウスとしての法務経験からピックアップした、管理人の独学や経験の記録を綴っています。
ネット上の読み物としてざっくばらんに書いており、感覚的な理解を掴むことを目指していますが、書籍などを理解する際の一助になれば幸いです。
主語
主語は、条文では権利義務の主体を表しますので、文章の基本構造として重要になります。
基本形
主語の基本形は、
〇〇は、
という形です。
つまり、主語には、
- 「は」を用いる
- 読点(「、」)を打つ
というのが基本ルールです。
主語の省略
普通の文章と同様に、主語が省略されることもあります。
▽地方自治法89条1項
第八十九条 普通地方公共団体に、その議事機関として、当該普通地方公共団体の住民が選挙した議員をもつて組織される議会を置く。
省略される理由も普通の文章と同様で、その動作を行ったのが誰あるいは何であるかが重要でないとか、書かなくても意味が通じる、といったことです。
主語の位置
主語の位置は、冒頭に置くのが基本です(※もちろん、実際にはそうでない場合も多くありますが)。
主語は冒頭に置く
Sは、Vすることができる。
★「S」は主語、「V」は述語(以下同じ)
また、条件文が入るときでも、冒頭に置くのが基本です。
条件文が入るとき
Sは、ホニャララのときは、Vしなければならない。
ただ、条件文が長いときなどには、主語を後ろに置くこともあります。
条件文が長いとき
ホニャララホニャララホニャララのときは、Sは、Vしなければならない。
これは、条件文が長いときまで主語を冒頭に置くと、「Sは、ホニャララホニャララホニャララホニャララのときは、Vしなければならない」みたいになって、読みにくいからです。しかし、このような形になっていることもあります。
条件文の主語
条件文にも主語・述語があるとき、通常は、主たる文の主語では「は」を用い、条件文の主語では「が」を用います。
また、条件文の方では、読点(「、」)を打ちません。
つまり、
S1は、S2がV2するときは、V1しなければならない。
★「S1」は主たる文の主語、「S2」は条件文の主語(以下同じ)
みたいな表現になります(条件文の主語では「が」を用い、読点を打たない)。
▽民法233条1項
(竹木の枝の切除及び根の切取り)
第二百三十三条 土地の所有者は、隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。
S2=S1の場合
条件文の主語が冒頭の主語(=主たる文の主語)と同じ場合、条件文の主語は省略されます。
つまり、
S1は、V2するときは、V1しなければならない。
みたいな表現になります。
▽個人情報保護法43条1項
(匿名加工情報の作成等)
第四十三条 個人情報取扱事業者は、匿名加工情報(匿名加工情報データベース等を構成するものに限る。以下この章及び第六章において同じ。)を作成するときは、特定の個人を識別すること及びその作成に用いる個人情報を復元することができないようにするために必要なものとして個人情報保護委員会規則で定める基準に従い、当該個人情報を加工しなければならない。
S2がS1の先にくる場合
条件文が先にきて、主たる文の主語が後ろにくることも、やはりあります(先ほど見たように、条件文が長い場合)。
つまり、
S2がV2するときは、S1は、V1しなければならない。
みたいな表現になります。
▽民法415条1項
(債務不履行による損害賠償)
第四百十五条 債務者がその債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるときは、債権者は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、…(略)…。
述語
主語に対して、述語は、いわずもがなですが条文の末尾にきます。
述語や文末表現には、その条文で定めようとする内容に応じてさまざまなものがありますが、特に法律効果(権利義務の発生・変更・消滅等)と結びついたものは重要になります。
権利義務を示す表現で典型的なのは、以下のようなものです。
| 分類 | 述語 | 意味 |
|---|---|---|
| 権利をあらわす表現 | 「することができる」 | 法律上の権利や能力などがあることを示す |
| 「することができない」 | 法律上の権利や能力などがないことを示す | |
| 義務をあらわす表現 | 「しなければならない」 | 作為義務(命令)を示す |
| 「してはならない」 | 不作為義務(禁止)を示す | |
| その他義務をあらわす表現 | 「する」・「しない」(動詞の終止形) | その内容の規範を創設する(作為・不作為の義務を定める場合もある) |
| 「するものとする」 | ソフトなニュアンスでの義務付けを示す |
目的語の倒置
法令では、意味上の主語(本来の主語)が省略されたうえで、本来は目的語であるものが主語にくる形になっていることがよくあります(目的語の倒置)。契約書でもよくある形です。
▽民法94条1項
(虚偽表示)
第九十四条 相手方と通じてした虚偽の意思表示は、無効とする。
▽民法3条の2
第三条の二 法律行為の当事者が意思表示をした時に意思能力を有しなかったときは、その法律行為は、無効とする。
また、もちろん、本来の主語がそのまま存在する場合もあります。
▽民法224条
(境界標の設置及び保存の費用)
第二百二十四条 境界標の設置及び保存の費用は、相隣者が等しい割合で負担する。ただし、測量の費用は、その土地の広狭に応じて分担する。
★「相隣者は、境界標の設置及び保存の費用を等しい割合で負担する」が普通の形だが、境界標の設置と保存の費用がこの条文のテーマであることが伝わりやすいように、目的語を倒置している
これらは、その条文で言いたい内容との関係で、「SがOをVする」と淡々と書くよりも、目的語を主語にもってきて強調した方が内容が伝わりやすいからです(目的語をその文の主題=テーマにするという意図)。
英語であれば受動態を用いて記述されるような内容ですが、法令では、能動態で記述されます。
「これを」の使用
本来の目的語を主語にしたあと、元の位置にも形式的な目的語として「これを」という文言を残している場合があります。
「日本国民たる要件は、法律でこれを定める」(憲法10条)のような用例で、漢文口調で語感をよくするものですが、省略しても意味は通じるものなので、最近はあまり使われなくなったとされています。
とはいえ、ちょこちょこと見かけることはあります。
▽民法448条1項
(保証人の負担と主たる債務の目的又は態様)
第四百四十八条 保証人の負担が債務の目的又は態様において主たる債務より重いときは、これを主たる債務の限度に減縮する。
▽民法459条の2第3項
3 第一項の求償権は、主たる債務の弁済期以後でなければ、これを行使することができない。
結論だけを書く
通常、条文には結論(こういう決めごとになったという結果)だけを書き、経緯や意図や趣旨のようなものは書きません。法令でもそうですし、契約書でもそうです。
これは、いろいろ無駄なことを書くと、意味内容にブレが生じる原因になる(解釈に疑義が出る)可能性があるからです。
契約書でも、条文には権利義務を表そうとするものが多いですが、そのときは要件と効果を端的に記述します。
契約書でも経緯や意図は普通書きませんが、もし書くシチュエーションがあったときは「鑑み」(これも法令用語のひとつ)などを使うのが便利ではないかと思います(管理人の私見)
なお、前文や目的規定では、経緯や意図のようなものを書くのがむしろ普通です。結論だけを書くというのは、これら以外の普通の本文の話です。
結び
今回は、法令作成ということで、条文の文章構造について見てみました。
実際に条文を眺めてみるとすぐ見て取れるように、現実の法令や契約書の文章には、上記のようなパターンやその他の組み合わせで無数のものがあります。
なので、あまり型にはめようとしても無理な面もありますが、基本的なパターン(主語、述語、目的語の倒置、条件文の主語・述語や主たる文との位置関係、といったあたり)をいくつか押さえておくと、多少読み書きしやすくなるように思います。
[注記]
本記事を含む一連の勉強記事は、過去の自分に向けて、①自分の独学や経験の記録を見せる、②感覚的な理解を伝えることを優先する、③細かく正確な理解は書物に譲る、ということをコンセプトにした読みものです。ベテランの方が見てなるほどと思うようなことは書かれていないほか、業務上必要であるときなど、正確な内容については別途ご確認ください。また、法改正をはじめとした最新の情報を反映しているとは限りませんので、ご注意ください。
法制執務に関するその他の記事(≫Read More)
参考文献
参考文献image
※注:「法令読解の基礎知識」には第一次改訂版【Amazonページ】があります
当サイトではアフィリエイトプログラムを利用して商品・サービスを記載しています