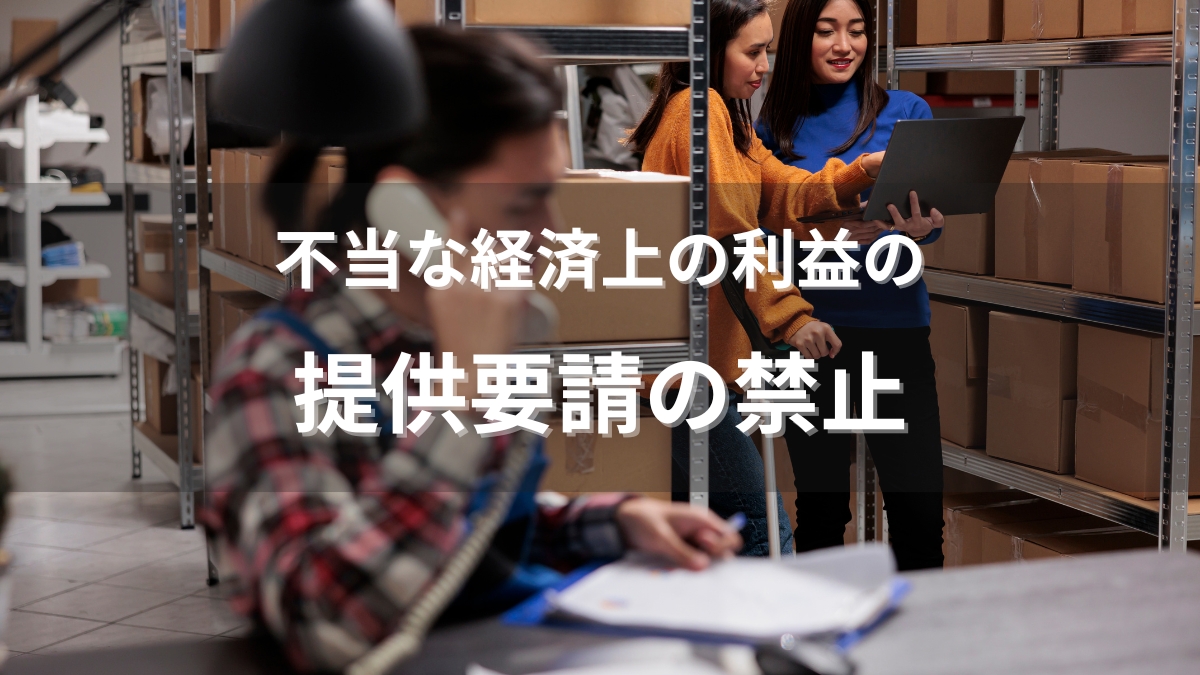今回は、業務委託契約ということで、知的財産権の帰属に関する条項を見てみたいと思います。
業務委託契約で成果物を受け取っても、その知的財産権が自動的に委託者に移転するわけではありません。著作権や特許の帰属を明確にしておかないと、思わぬトラブルにつながる可能性があります。本記事では、契約書で押さえるべき注意点を整理します。
ではさっそく。なお、引用部分の太字、下線、改行などは管理人によるものです。
メモ
このカテゴリーでは、インハウスとしての法務経験からピックアップした、管理人の独学や経験の記録を綴っています。
ネット上の読み物としてざっくばらんに書いており、感覚的な理解を掴むことを目指していますが、書籍などを理解する際の一助になれば幸いです。
知的財産権の帰属
業務委託の成果物に関するIPは、
- 特許権等の産業財産権
- 著作権
- 営業秘密・ノウハウ
など多層的ですが(※③はIPそのものではないです)、以下では、主として①②を見た後、やや応用的な論点として③を見てみます。
法律上の原則
知的財産権は、原則として発明・創作をした者に権利が発生するため、報酬を支払っただけで自動的に権利が移るわけではありません。
しかし、委託者は通常、委託による成果物を使用する必要がありますので、知的財産権の帰属に関する条項を設けて、その権限(権利移転or使用許諾)を明らかにしておくわけです。
知的財産権の帰属に関する条項
知的財産権の帰属に関する条項のポイントを、いくつか挙げてみます。
成果物の内容は明確か(何が成果物か)
まず対象として、成果物の内容が何であるのか、定義が明確になっているかを確認します。これはそもそもの前提という感じです。
譲渡方式か許諾方式か
次に、譲渡方式(=権利移転)か許諾方式(=使用許諾)かを決める必要があります。
契約の目的にもよりますが(例えばコンテンツ制作やシステム開発などでは委託者に成果物を権利帰属させないと普通は困る)、大ざっぱにいえば、委託者が強い場合には譲渡方式、受託者が強い場合には許諾方式になるといえます。
譲渡方式による場合(=権利を移転させる場合)は、知的財産の譲渡に関する条項は必須となります。譲渡される知的財産権の範囲、移転の時期、対価などを明らかにします。
許諾方式による場合(=受託者が権利を保持する場合)も、その旨を確認しつつ、使用許諾の範囲を決めるような条項を設けておくことが多いかと思います。
許諾に際しては、他のライセンス契約一般と同様ですが、何を(対象)、どの範囲で(時期・場所)、いくらで(対価)、許諾のタイプ(専用許諾か通常許諾か)などを明確にしておくことが重要です。
(譲渡の場合)著作権法27条・28条の特掲
著作権の譲渡については、翻案権(著作権法27条)と二次的著作物の利用に関する原著作者の権利(同法28条)を譲渡する場合には明確な記載が必要で、契約に特段の表示がないときは譲渡されなかったと推定されます(同法61条2項)。
そのため、知的財産権の帰属に関する条項では、「著作権法第27条及び第28条に定める権利を含む」と明記するのが通例です(いわゆる特掲事項)。
▽著作権法60条2項
2 著作権を譲渡する契約において、第二十七条又は第二十八条に規定する権利が譲渡の目的として特掲されていないときは、これらの権利は、譲渡した者に留保されたものと推定する。
(譲渡の場合)著作者人格権の不行使特約
著作者人格権は、著作財産権と違い、一身専属権であるため譲渡ができません(著作権法59条)。そのため実務上は、行使しない旨の合意(不行使特約)を入れることで運用されています。
ただし、公序良俗(民法90条)に反するなどとして効力が否定される可能性は残りますので、これで完全に担保できるものではないことも一応知っておく必要があります(とはいえ他に良い方法もないので、普通は不行使特約を入れる)。
▽著作権法59条
(著作者人格権の一身専属性)
第五十九条 著作者人格権は、著作者の一身に専属し、譲渡することができない。
権利侵害がない旨の表明保証
以上のほか、受託者が第三者の権利を侵害していない旨の表明保証(レプワラ)と、侵害が判明した場合の対応(契約不適合、損害賠償、代替作成・買替え、弁護士費用等)を定める場合もあります。
システム開発の場合では、OSS(オープンソース)利用の有無の開示させることなどもポイントになるかと思います。
下請法との関係
業務委託の内容が製造委託や情報成果物作成委託などである場合、つまり下請法の適用があり得る場合は、知的財産権の帰属に関する条項にもいくつかの留意が必要です。
下請法は一定の要件(資本金区分と取引内容)を満たす場合に適用され、発注者である親事業者に、発注書面(3条書面)の交付義務や、いくつかの禁止行為を課します。そのため、知的財産権の譲渡を給付の内容に含める場合には、3条書面への明記と譲渡対価の扱いを適切に行う必要があります。
下請法運用基準を使って関係箇所を概観すると、以下のとおりです。
知的財産権の帰属と下請法の関係
| 分類 | 義務と禁止行為 | 運用基準の関係箇所 |
|---|---|---|
| 親事業者の義務 | 発注書面の交付義務 (法3条1項) | 「また、主に、情報成果物作成委託に係る作成過程を通じて、情報成果物に関し、下請事業者の知的財産権が発生する場合において、親事業者は、情報成果物を提供させるとともに、作成の目的たる使用の範囲を超えて知的財産権を自らに譲渡・許諾させることを『下請事業者の給付の内容』とすることがある。この場合は、親事業者は、3条書面に記載する『下請事業者の給付の内容』の一部として、下請事業者が作成した情報成果物に係る知的財産権の譲渡・許諾の範囲を明確に記載する必要がある。」(運用基準第3-1-⑶) |
| 親事業者の禁止行為 | 買いたたきの禁止 (法4条1項5号) | 「給付の内容に知的財産権が含まれているにもかかわらず、当該知的財産権の対価を考慮せず、一方的に通常の対価より低い下請代金の額を定めること。」(運用基準第4-5-⑵-ク) |
| 不当な経済上の利益の提供要請の禁止 (法4条2項3号) | 「情報成果物等の作成に関し、下請事業者の知的財産権が発生する場合において、親事業者が、委託した情報成果物等に加えて、無償で、作成の目的たる使用の範囲を超えて当該知的財産権を親事業者に譲渡・許諾させることは、法第4条第2項第3号に該当する。」(運用基準第3-7-⑷) 違反行為事例7-9「親事業者は、テレビ番組の制作を委託している下請事業者との契約により、下請事業者に発生した番組の知的財産権を譲渡させていたところ、それに加えて、番組で使用しなかった映像素材の知的財産権を無償で譲渡させた。」(運用基準第3-7-⑷) |
つまり、そもそも給付の内容に含めていなかった場合には「発注書面の交付義務」や「不当な経済上の利益の提供要請の禁止」に触れる場合があります。また、含めている場合でも、あまりに対価のバランスを欠く場合には「買いたたきの禁止」に触れる場合があるということです。
アイデア・ノウハウの流用の抑止
さて、やや応用的な論点として、業務の遂行中に生じたアイデアやノウハウを受託者が第三者との他案件に流用することを抑止できるかについて考えてみたいと思います(あまり正面から論じた文献・資料を見たことはなく、管理人の私見です)。
アイデアやノウハウ自体は知的財産権そのものではないため、これを含めたい場合には別途記載しておく必要があると考えられます。この点につき、「ノウハウ等」として知的財産権の帰属に関する条項で、譲渡や権利保持の対象に含めて書いておくことも多いかと思います。
これに関しては内容や範囲は明らかでないものの、業務の遂行過程で得られた知見を指し、例えば製造委託の場合には何らかの製造ノウハウ(しかし知的財産権未満のもの)を想定していると思えば、さほど違和感なく受け入れられるように思います。
他方、著作物(情報成果物)の場合に、アイデアに係る部分、つまり著作権法では保護されない部分(「マージ理論」とか「思想・表現二分論」と呼ばれ、アイデアは著作権法で保護されないとされる)をどれほど含められるのかは、あまり明確でないように思われます。
というよりどちらかというと、ここで記載する「ノウハウ等」にアイデアを含めることはおそらく想定されていないような気がします
この点、どこまでアイデアレベル(例えばコンテンツ制作でいえばバラエティ番組のフォーマットに相当するようなもの)につき他案件での流用を抑止できるかは明確ではありませんが(下請法をはじめとした独禁法系の抵触にも関係がないとは思えない)、委託者側として牽制作用を期待するのであれば、何らかの表現を知的財産権の帰属に関する条項に記載しておくことが考えられます。少なくとも、何も書いていなければ何も取り決めしていないことになりますので。
あるいは見方を変えて、秘密保持条項におけるいち記載としてあまり大げさにならないよう盛り込むといった方法もあるかもしれません。
結び
業務委託契約ということで、知的財産権の帰属に関する条項を見てみました。
[注記]
本記事を含む一連の勉強記事は、過去の自分に向けて、①自分の独学や経験の記録を見せる、②感覚的な理解を伝えることを優先する、③細かく正確な理解は書物に譲る、ということをコンセプトにした読みものです。ベテランの方が見てなるほどと思うようなことは書かれていないほか、業務上必要であるときなど、正確な内容については別途ご確認ください。また、法改正をはじめとした最新の情報を反映しているとは限りませんので、ご注意ください。
業務委託契約書に関するその他の記事(≫Read More)
参考文献
当サイトではアフィリエイトプログラムを利用して商品・サービスを記載しています
参考文献image