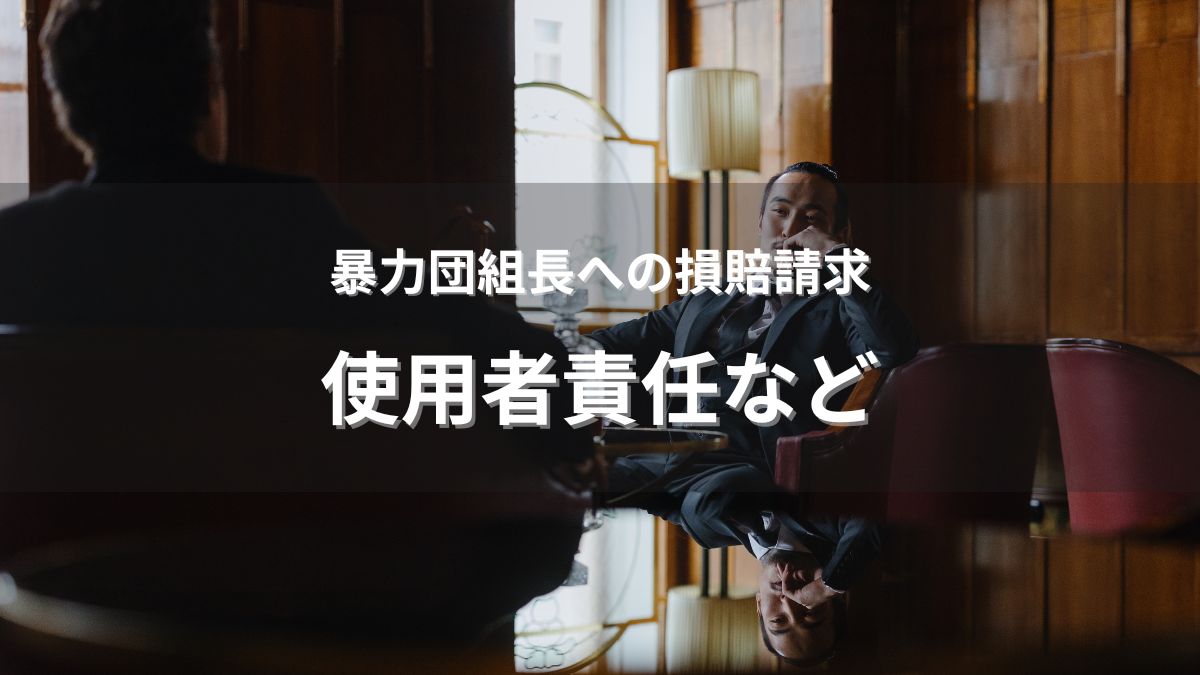今回は、暴力団対策法ということで、規制の仕組み(全体像)について見てみたいと思います。
正式名称は「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」といいます。よく「暴対法」と略されますので、本記事ではこれで表記したいと思います。
ではさっそく。なお、引用部分の太字、下線、改行などは管理人によるものです。
暴対法の目的と全体像
暴対法は、暴力団員の行う「暴力的要求行為」等に対して必要な規制を行い、対立抗争等による市民生活への危険を防止することを目的とする法律です(法1条)。
1991年(平成3年)に成立・公布され、全国の都道府県公安委員会が運用の要として位置づけられています。
▽暴対法1条
(目的)
第一条 この法律は、暴力団員の行う暴力的要求行為等について必要な規制を行い、及び暴力団の対立抗争等による市民生活に対する危険を防止するために必要な措置を講ずるとともに、暴力団員の活動による被害の予防等に資するための民間の公益的団体の活動を促進する措置等を講ずることにより、市民生活の安全と平穏の確保を図り、もって国民の自由と権利を保護することを目的とする。
全体としては、目的・定義・指定制度・禁止行為・命令と罰則、といった構造で組み立てられており、行為規制と行政的措置を通じて市民の平穏を守るという仕組みになっています。
この法律の特徴は、「指定暴力団」制度と、個々の暴力団員に対する行為規制です。指定暴力団に所属する構成員が、その組織の威力を示して不当な要求を行った場合、公安委員会は個別の行為者に対し中止命令や再発防止命令を発出し、違反すれば刑事罰が科されます。地域や情勢により、より厳格な運用(特定危険指定暴力団等)も用意されています。
ここでは大きく、
- 暴力団など規制対象の定義
- 暴対法による禁止行為
- 違反に対する措置(行政措置と刑事罰)
の3つに分けて、暴対法を概観します。
01|暴力団など規制対象の定義
暴対法は、規制の対象となる組織や個人を定めることで、その後の禁止行為規制や行政措置の射程を画しています。
暴力団
暴力団とは、その構成員が団体として、暴力的不法行為等を行うことを目的として結合した団体を指します(法2条2号)。法人格の有無を問わず、実態として継続的に活動する集団を広く含みます。
つまり、”不法行為を目的に組織された団体”というのが暴力団の基本的な概念です。
▽暴対法2条2号
二 暴力団 その団体の構成員(その団体の構成団体の構成員を含む。)が集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長するおそれがある団体をいう。
「暴力的不法行為等」とは?
この定義におけるキーワードは、「暴力的不法行為等」です。
暴力的不法行為等とは、暴対法別表に掲げる犯罪行為のうち、国家公安委員会規則で定めるものをいいます(法2条1号)。
この別表/規則では、殺人・傷害・放火・爆発等の重大犯罪や業務妨害・恐喝など、暴力的手段による犯罪行為のほか、賭博開帳図利、ノミ行為、風営法違反など、暴力団が典型的に行うその他の犯罪行為が掲げられています。
つまり、「暴力的不法行為等」とは、単に”暴力的な振る舞い”を指す一般語ではなく、法令上特定された犯罪類型を指す技術的な用語であり、暴力団の定義(その構成員が集団的・常習的にこれらを行うおそれがある団体)を規定するための基礎になっています。
▽暴対法2条1号(※【 】は管理人注)
一 暴力的不法行為等 別表に掲げる罪のうち国家公安委員会規則【=暴対法規則1条】で定めるものに当たる違法な行為をいう。
▽暴対法別表(第二条関係)
クリックで開きます
一 爆発物取締罰則(明治十七年太政官布告第三十二号)に規定する罪
二 刑法(明治四十年法律第四十五号)第二編第五章、第七章、第二十二章、第二十三章、第二十六章、第二十七章、第三十一章から第三十三章まで、第三十五章から第三十七章まで及び第四十章に規定する罪
三 暴力行為等処罰に関する法律(大正十五年法律第六十号)に規定する罪
四 盗犯等の防止及び処分に関する法律(昭和五年法律第九号)に規定する罪
五 労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第十三章に規定する罪
六 職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第五章に規定する罪
七 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第八章に規定する罪
八 金融商品取引法第八章に規定する罪
九 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第七章に規定する罪
十 大麻草の栽培の規制に関する法律(昭和二十三年法律第百二十四号)第六章に規定する罪
十一 船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第六章に規定する罪
十二 競馬法(昭和二十三年法律第百五十八号)第五章に規定する罪
十三 自転車競技法(昭和二十三年法律第二百九号)第六章に規定する罪
十四 建設業法第八章に規定する罪
十五 弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)第十章に規定する罪
十六 火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号)第五章に規定する罪
十七 小型自動車競走法(昭和二十五年法律第二百八号)第七章に規定する罪
十八 毒物及び劇物取締法(昭和二十五年法律第三百三号)に規定する罪
十九 港湾運送事業法(昭和二十六年法律第百六十一号)第五章に規定する罪
二十 投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第五編に規定する罪
二十一 モーターボート競走法(昭和二十六年法律第二百四十二号)第七章に規定する罪
二十二 覚醒剤取締法(昭和二十六年法律第二百五十二号)第八章に規定する罪
二十三 旅券法(昭和二十六年法律第二百六十七号)に規定する罪
二十四 出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第九章に規定する罪
二十五 宅地建物取引業法第八章に規定する罪
二十六 酒税法(昭和二十八年法律第六号)第九章に規定する罪
二十七 麻薬及び向精神薬取締法(昭和二十八年法律第十四号)第七章に規定する罪
二十八 武器等製造法(昭和二十八年法律第百四十五号)第五章に規定する罪
二十九 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和二十九年法律第百九十五号)に規定する罪
三十 売春防止法(昭和三十一年法律第百十八号)第二章に規定する罪
三十一 銃砲刀剣類所持等取締法(昭和三十三年法律第六号)第五章に規定する罪
三十二 割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)第五章に規定する罪
三十三 著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)第八章に規定する罪
三十四 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第五章に規定する罪
三十五 火炎びんの使用等の処罰に関する法律(昭和四十七年法律第十七号)に規定する罪
三十六 建設労働者の雇用の改善等に関する法律(昭和五十一年法律第三十三号)第八章に規定する罪
三十七 銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第九章に規定する罪
三十八 貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)第五章に規定する罪
三十九 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)第六章に規定する罪
四十 港湾労働法(昭和六十三年法律第四十号)第七章に規定する罪
四十一 国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律(平成三年法律第九十四号)第三章に規定する罪
四十二 不動産特定共同事業法(平成六年法律第七十七号)第十章に規定する罪
四十三 保険業法(平成七年法律第百五号)第六編に規定する罪
四十四 資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第五編に規定する罪
四十五 債権管理回収業に関する特別措置法(平成十年法律第百二十六号)第六章に規定する罪
四十六 児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(平成十一年法律第五十二号)第二章に規定する罪
四十七 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号)第二章に規定する罪
四十八 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号)第七章に規定する罪
四十九 著作権等管理事業法(平成十二年法律第百三十一号)第七章に規定する罪
五十 高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成十三年法律第二十六号)第八章に規定する罪
五十一 使用済自動車の再資源化等に関する法律(平成十四年法律第八十七号)第八章に規定する罪
五十二 インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律(平成十五年法律第八十三号)第六章に規定する罪
五十三 裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(平成十六年法律第百五十一号)第五章に規定する罪
五十四 信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第七章に規定する罪
五十五 会社法第八編に規定する罪
五十六 探偵業の業務の適正化に関する法律(平成十八年法律第六十号)に規定する罪
五十七 犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成十九年法律第二十二号)に規定する罪
五十八 電子記録債権法(平成十九年法律第百二号)第五章に規定する罪
五十九 資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第八章に規定する罪
六十 性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律(令和五年法律第六十七号)第二章に規定する罪
▽暴対法規則1条
クリックで開きます
(暴力的不法行為等)
第一条 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(以下「法」という。)第二条第一号の国家公安委員会規則で定める罪は、次のとおりとする。
一 爆発物取締罰則(明治十七年太政官布告第三十二号)第一条から第三条までに規定する罪
二 刑法(明治四十年法律第四十五号)第九十五条、第九十六条の二から第九十六条の四まで、第九十六条の五(第九十六条の二から第九十六条の四までに係る部分に限る。)、第九十六条の六第一項、第百三条、第百四条、第百五条の二、第百七十五条、第百七十七条第一項若しくは第三項、第百七十九条第二項、第百八十条(第百七十七条第一項及び第三項並びに第百七十九条第二項に係る部分に限る。以下この号において同じ。)、第百八十一条第二項(第百七十七条第一項及び第三項、第百七十九条第二項並びに第百八十条に係る部分に限る。)、第百八十二条第三項、第百八十五条から第百八十七条まで、第百九十九条、第二百一条、第二百三条(第百九十九条に係る部分に限る。)、第二百四条、第二百五条、第二百八条、第二百八条の二、第二百二十条から第二百二十三条まで、第二百二十五条から第二百二十六条の三まで、第二百二十七条第一項(第二百二十五条及び第二百二十六条から第二百二十六条の三までに係る部分に限る。以下この号において同じ。)から第四項まで、第二百二十八条(第二百二十五条、第二百二十五条の二第一項、第二百二十六条から第二百二十六条の三まで並びに第二百二十七条第一項から第三項まで及び第四項前段に係る部分に限る。)、第二百二十八条の三、第二百三十四条、第二百三十五条の二から第二百三十七条まで、第二百四十条(第二百三十六条に係る部分に限る。以下この号において同じ。)、第二百四十一条第一項(第二百三十六条に係る部分に限る。)若しくは第三項(第二百三十六条に係る部分に限る。以下この号において同じ。)、第二百四十三条(第二百三十五条の二、第二百三十六条、第二百四十条及び第二百四十一条第三項に係る部分に限る。)、第二百四十六条(第六十条の規定が適用される場合に限る。以下この号において同じ。)、第二百四十六条の二(第六十条の規定が適用される場合に限る。以下この号において同じ。)、第二百四十九条、第二百五十条(第二百四十六条、第二百四十六条の二及び第二百四十九条に係る部分に限る。)又は第二百五十八条から第二百六十一条までに規定する罪
三 暴力行為等処罰に関する法律(大正十五年法律第六十号)に規定する罪
四 盗犯等の防止及び処分に関する法律(昭和五年法律第九号)第二条(刑法第二百三十六条及び第二百四十三条(第二百三十六条に係る部分に限る。以下この号において同じ。)に係る部分に限る。)、第三条(刑法第二百三十六条及び第二百四十三条に係る部分に限る。)又は第四条(刑法第二百三十六条に係る部分に限る。)に規定する罪
五 労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第百十七条又は第百十八条第一項(第六条及び第五十六条に係る部分に限る。)に規定する罪
六 職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第六十三条、第六十四条第一号、第一号の二(第三十条第一項、第三十二条の六第二項(第三十三条第四項において準用する場合を含む。)及び第三十三条第一項に係る部分に限る。)、第四号、第五号若しくは第十号又は第六十六条第一号若しくは第三号に規定する罪
七 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第六十条第一項又は第二項(第三十四条第一項第四号の二、第五号、第七号及び第九号に係る部分に限る。)に規定する罪
八 金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第百九十七条の二第十号の四、第十号の五若しくは第十号の八から第十号の十まで、第百九十八条第一項第一号、第三号、第三号の三若しくは第四号から第七号まで、第百九十八条の四、第百九十八条の五第二号の二(第五十七条の二十第一項に係る部分に限る。)、第百九十八条の六第一号(第二十九条の二第一項から第三項まで、第五十九条の二第一項及び第三項、第六十条の二第一項及び第三項、第六十六条の二、第六十六条の二十八、第六十六条の五十一、第八十一条、第百二条の十五、第百六条の十一、第百五十五条の二、第百五十六条の三、第百五十六条の二十の三、第百五十六条の二十の十七、第百五十六条の二十四第二項から第四項まで並びに第百五十六条の四十に係る部分に限る。)若しくは第十一号の五、第二百条第十二号の三、第十三号若しくは第十七号(第百六条の三第一項及び第四項、第百六条の十七第一項及び第三項並びに第百五十六条の五の五第一項及び第四項に係る部分に限る。)、第二百五条第九号、第十三号(第百六条の三第三項(第百六条の十第四項及び第百六条の十七第四項において準用する場合を含む。)及び第百五十六条の五の五第三項に係る部分に限る。)若しくは第十六号、第二百五条の二の三第一項第一号(第三十一条第一項、第五十七条の十四、第六十条の五第一項、第六十三条第八項(第六十三条の三第二項において準用する場合を含む。)、第六十三条の九第七項(第六十三条の十一第二項において準用する場合を含む。)、第六十六条の五第一項、第六十六条の三十一第一項、第六十六条の五十四第一項及び第百五十六条の五十五第一項に係る部分に限る。)、第二号(第三十一条の三及び第六十六条の六に係る部分に限る。)若しくは第四号(第三十六条の二第三項及び第六十六条の八第三項に係る部分に限る。)又は第二百六条第一項第二号(第百四十九条第二項前段(第百五十三条の四において準用する場合を含む。)及び第百五十五条の七に係る部分に限る。)、第七号(第百五十六条の十三に係る部分に限る。)、第九号(第百五十六条の二十の十一及び第百五十六条の二十の二十一第二項に係る部分に限る。)若しくは第十号(第百五十六条の二十八第三項に係る部分に限る。)に規定する罪
九 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第四十九条第五号若しくは第六号、第五十条第一号若しくは第二号、第五十一条第一項第四号(第二十二条第一項第三号及び第四号(第三十一条の二十三及び第三十二条第三項において準用する場合を含む。)に係る部分に限る。)、第五号(第二十八条第十二項第三号に係る部分に限る。)、第六号、第八号(第三十一条の十三第二項第三号及び第四号に係る部分に限る。)、第九号若しくは第十号又は第五十三条第一号に規定する罪
十 大麻草の栽培の規制に関する法律(昭和二十三年法律第百二十四号)第二十四条、第二十四条の三又は第二十四条の四に規定する罪
十一 船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第百十二条第一号、第二号(第三十四条第一項、第五十五条第一項及び第六十条第二項に係る部分に限る。)若しくは第五号又は第百十四条第二号若しくは第三号(第六十一条第一項に係る部分に限る。)に規定する罪
十二 競馬法(昭和二十三年法律第百五十八号)第三十条第三号又は第三十四条に規定する罪
十三 自転車競技法(昭和二十三年法律第二百九号)第五十六条第二号又は第五十八条第三号に規定する罪
十四 建設業法(昭和二十四年法律第百号)第四十七条第一項第一号若しくは第三号又は第五十条第一項第一号、第二号(第十一条第一項及び第三項(第十七条において準用する場合を含む。)に係る部分に限る。)若しくは第三号に規定する罪
十五 弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)第七十七条第三号又は第四号に規定する罪
十六 火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号)第五十八条第一号から第四号まで又は第五十九条第二号(第二十一条に係る部分に限る。)、第四号若しくは第五号に規定する罪
十七 小型自動車競走法(昭和二十五年法律第二百八号)第六十一条第二号又は第六十三条第三号に規定する罪
十八 毒物及び劇物取締法(昭和二十五年法律第三百三号)第二十四条第一号(第三条に係る部分に限る。)に規定する罪
十九 港湾運送事業法(昭和二十六年法律第百六十一号)第三十四条第一号に規定する罪
二十 投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第二百四十五条第三号又は第二百四十六条第一号(第百九十一条第一項に係る部分に限る。)若しくは第八号に規定する罪
二十一 モーターボート競走法(昭和二十六年法律第二百四十二号)第六十五条第二号又は第六十八条第三号に規定する罪
二十二 覚醒剤取締法(昭和二十六年法律第二百五十二号)第四十一条、第四十一条の二、第四十一条の三第一項第一号、第三号若しくは第四号、第二項(同条第一項第一号、第三号及び第四号に係る部分に限る。)若しくは第三項(同条第一項第一号、第三号及び第四号並びに第二項(同条第一項第一号、第三号及び第四号に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)、第四十一条の四第一項第三号から第五号まで、第二項(同条第一項第三号から第五号までに係る部分に限る。)若しくは第三項(同条第一項第三号から第五号まで及び第二項(同条第一項第三号から第五号までに係る部分に限る。)に係る部分に限る。)、第四十一条の六、第四十一条の七、第四十一条の九から第四十一条の十一まで又は第四十一条の十三に規定する罪
二十三 旅券法(昭和二十六年法律第二百六十七号)第二十三条第一項第一号、第二項(同条第一項第一号に係る部分に限る。以下この号において同じ。)又は第三項(同条第一項第一号及び第二項に係る部分に限る。)に規定する罪
二十四 出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第七十四条から第七十四条の六まで、第七十四条の六の二第一項第一号若しくは第二号若しくは第二項、第七十四条の六の三(第七十四条の六の二第一項第一号及び第二号並びに第二項に係る部分に限る。)又は第七十四条の八に規定する罪
二十五 宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)第七十九条第一号若しくは第二号、第八十二条第一号、第二号(第十二条第二項に係る部分に限る。)若しくは第三号又は第八十三条第一項第一号(第九条及び第五十三条(第六十三条の三第二項において準用する場合を含む。)に係る部分に限る。)に規定する罪
二十六 酒税法(昭和二十八年法律第六号)第五十四条第一項若しくは第二項又は第五十六条第一項第一号、第五号若しくは第七号に規定する罪
二十七 麻薬及び向精神薬取締法(昭和二十八年法律第十四号)第六十四条から第六十六条まで、第六十六条の二(第二十七条第一項及び第五項に係る部分に限る。)、第六十六条の三から第六十八条の二まで、第六十九条の二、第六十九条の四、第六十九条の五、第七十条第十四号又は第七十二条第四号に規定する罪
二十八 武器等製造法(昭和二十八年法律第百四十五号)第三十一条、第三十一条の二又は第三十一条の三第一号若しくは第四号に規定する罪
二十九 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和二十九年法律第百九十五号)第五条に規定する罪
三十 売春防止法(昭和三十一年法律第百十八号)第六条、第七条第二項若しくは第三項(同条第二項に係る部分に限る。)、第八条第一項(第七条第二項に係る部分に限る。)又は第十条から第十三条までに規定する罪
三十一 銃砲刀剣類所持等取締法(昭和三十三年法律第六号)第三十一条から第三十一条の四まで、第三十一条の七から第三十一条の九まで、第三十一条の十一第一項第一号若しくは第二号若しくは第二項、第三十一条の十二、第三十一条の十三、第三十一条の十五、第三十一条の十六第一項第一号から第三号まで若しくは第二項、第三十一条の十七、第三十一条の十八第一項若しくは第二項第二号、第三十二条第一号、第三号、第四号若しくは第七号又は第三十五条第二号(第二十二条の二第一項及び第二十二条の四に係る部分に限る。)に規定する罪
三十二 割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)第四十九条第二号、第三号若しくは第六号又は第五十三条の二第一号(第三十三条の三第一項、第三十五条の二の十三第一項、第三十五条の三の二十八第一項及び第三十五条の十七の六第一項に係る部分に限る。)に規定する罪
三十三 著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)第百十九条第二項第三号に規定する罪
三十四 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第二十五条第一項第一号、第二号、第八号、第九号、第十三号若しくは第十四号若しくは第二項(同条第一項第十四号に係る部分に限る。)、第二十六条第三号、第四号若しくは第六号(第二十五条第一項第十四号に係る部分に限る。)、第二十九条第一号(第七条の二第四項(第十四条の二第三項及び第十四条の五第三項において読み替えて準用する場合を含む。)及び第九条第六項(第十五条の二の六第三項において読み替えて準用する場合を含む。)に係る部分に限る。)又は第三十条第二号(第七条の二第三項(第十四条の二第三項及び第十四条の五第三項において準用する場合を含む。)、第九条第三項(第十五条の二の六第三項において準用する場合を含む。)及び第九条の七第二項(第十五条の四において準用する場合を含む。)に係る部分に限る。)に規定する罪
三十五 火炎びんの使用等の処罰に関する法律(昭和四十七年法律第十七号)第二条又は第三条に規定する罪
三十六 建設労働者の雇用の改善等に関する法律(昭和五十一年法律第三十三号)第四十九条第一号又は第五十一条第四号若しくは第六号に規定する罪
三十七 銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第六十一条第一号、第六十二条の二第一号又は第六十三条の三第二号(第五十二条の七十八第一項に係る部分に限る。)に規定する罪
三十八 貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)第四十七条第一号若しくは第二号、第四十七条の三第一項第一号、第二号(第十一条第二項に係る部分に限る。)若しくは第三号、第四十八条第一項第一号の三(第二十四条第二項、第二十四条の二第二項、第二十四条の三第二項、第二十四条の四第二項及び第二十四条の五第二項において準用する第十二条の七に係る部分に限る。)、第三号の三(第二十四条第二項、第二十四条の二第二項、第二十四条の三第二項、第二十四条の四第二項及び第二十四条の五第二項において準用する第十六条の三第一項に係る部分に限る。)、第四号の二、第五号(第二十四条第二項、第二十四条の二第二項、第二十四条の三第二項、第二十四条の四第二項及び第二十四条の五第二項において準用する第二十条第三項に係る部分に限る。)、第五号の二、第五号の三若しくは第九号の八、第四十九条第七号、第五十条第一項第一号(第八条第一項に係る部分に限る。)若しくは第二号又は第五十条の二第六号(第四十一条の五十五第一項に係る部分に限る。)に規定する罪
三十九 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)第五十九条第一号(第四条第一項に係る部分に限る。)から第三号まで又は第六十一条第一号若しくは第二号(第十一条第一項に係る部分に限る。)に規定する罪
四十 港湾労働法(昭和六十三年法律第四十号)第四十八条第一号又は第五十一条第二号(第十八条第二項において準用する第十二条第二項に規定する申請書及び第十八条第二項において準用する第十二条第三項に規定する書類に係る部分を除く。)若しくは第三号(第十九条第一項に係る部分に限る。)に規定する罪
四十一 国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律(平成三年法律第九十四号。以下この号及び第四十七号並びに第十三条の二第十二号において「麻薬特例法」という。)第三章に規定する罪のうち、次に掲げる罪
イ 麻薬特例法第五条に規定する罪のうち、次に掲げる行為に係る罪
(1) 大麻草の栽培の規制に関する法律第二十四条に規定する罪に当たる行為をすること。
(2) 覚醒剤取締法第四十一条又は第四十一条の二に規定する罪に当たる行為をすること。
(3) 麻薬及び向精神薬取締法第六十四条、第六十四条の二、第六十五条、第六十六条、第六十六条の三又は第六十六条の四に規定する罪に当たる行為をすること。
ロ 麻薬特例法第六条又は第七条に規定する罪
ハ 麻薬特例法第八条第一項に規定する罪のうち、次に掲げる罪に係る罪
(1) イ又はホに掲げる罪
(2) 覚醒剤取締法第四十一条に規定する罪
(3) 麻薬及び向精神薬取締法第六十四条、第六十五条又は第六十六条の三に規定する罪
ニ 麻薬特例法第八条第二項に規定する罪のうち、次に掲げる罪に係る罪
(1) イ又はホに掲げる罪
(2) 覚醒剤取締法第四十一条の二に規定する罪
(3) 麻薬及び向精神薬取締法第六十四条の二、第六十六条又は第六十六条の四に規定する罪
ホ 麻薬特例法第九条に規定する罪のうち、次に掲げる罪に係る罪
(1) イ又はロに掲げる罪
(2) 大麻草の栽培の規制に関する法律第二十四条、第二十四条の三又は第二十四条の四に規定する罪
(3) 覚醒剤取締法第四十一条、第四十一条の二、第四十一条の六、第四十一条の九又は第四十一条の十一に規定する罪
(4) 麻薬及び向精神薬取締法第六十四条、第六十四条の二、第六十五条、第六十六条、第六十六条の三から第六十八条の二まで、第六十九条の二、第六十九条の四又は第六十九条の五に規定する罪
四十二 不動産特定共同事業法(平成六年法律第七十七号)第七十七条第一号、第二号若しくは第五号から第七号まで、第八十二条第一号若しくは第五号又は第八十四条第一号(第五十八条第四項に係る部分を除く。)若しくは第三号に規定する罪
四十三 保険業法(平成七年法律第百五号)第三百十五条第六号、第三百十五条の二第四号から第六号(第二百七十二条の三十五第五項に係る部分に限る。)まで、第三百十六条の三第一号、第三百十七条の二第三号、第三百十九条第九号又は第三百二十条第九号(第三百八条の十八第一項に係る部分に限る。)に規定する罪
四十四 資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二百九十四条第一号(第四条第一項に係る部分に限る。)、第三号若しくは第十二号(第四条第二項から第四項まで(これらの規定を第十一条第五項において準用する場合を除く。)及び第九条第二項(第二百二十七条第二項において準用する場合を除く。)に係る部分に限る。)又は第二百九十五条第二号(第二百九条第二項(第二百八十六条第一項において準用する場合を含む。)において準用する第二百十九条の規定による命令に係る部分を除く。)に規定する罪
四十五 債権管理回収業に関する特別措置法(平成十年法律第百二十六号)第三十三条第一号若しくは第二号、第三十四条第一号若しくは第三号又は第三十五条第一号、第二号、第五号、第六号若しくは第八号に規定する罪
四十六 児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(平成十一年法律第五十二号)第五条、第六条、第七条第二項から第八項まで又は第八条に規定する罪
四十七 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号。以下この号において「組織的犯罪処罰法」という。)第二章に規定する罪のうち、次に掲げる罪
イ 組織的犯罪処罰法第三条第一項に規定する罪のうち、同項第二号から第十号まで又は第十二号から第十五号までに規定する罪に当たる行為に係る罪
ロ 組織的犯罪処罰法第三条第二項に規定する罪のうち、同条第一項第二号から第四号まで、第七号から第十号まで、第十二号、第十四号又は第十五号に規定する罪に係る罪
ハ 組織的犯罪処罰法第四条に規定する罪のうち、組織的犯罪処罰法第三条第一項第七号、第九号、第十号(刑法第二百二十五条の二第一項に係る部分に限る。)、第十三号又は第十四号に規定する罪に係る罪
ニ 組織的犯罪処罰法第六条に規定する罪
ホ 組織的犯罪処罰法第六条の二第一項又は第二項に規定する罪のうち、次に掲げる罪に当たる行為に係る罪
(1) 爆発物取締罰則第三条に規定する罪
(2) 刑法第百七十七条第一項若しくは第三項、第二百四条、第二百二十五条、第二百二十六条、第二百二十六条の二第一項、第四項若しくは第五項、第二百二十六条の三、第二百二十七条第一項(第二百二十五条及び第二百二十六条から第二百二十六条の三までに係る部分に限る。)、第三項若しくは第四項、第二百三十五条の二、第二百三十六条又は第二百四十六条の二に規定する罪
(3) 労働基準法第百十七条に規定する罪
(4) 職業安定法第六十三条に規定する罪
(5) 児童福祉法第六十条第一項に規定する罪
(6) 金融商品取引法第百九十七条の二第十号の四、第十号の五若しくは第十号の八から第十号の十までに規定する罪
(7) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第四十九条第五号又は第六号に規定する罪
(8) 大麻草の栽培の規制に関する法律第二十四条第一項に規定する罪
(9) 競馬法第三十条第三号に規定する罪
(10) 自転車競技法第五十六条第二号に規定する罪
(11) 小型自動車競走法第六十一条第二号に規定する罪
(12) モーターボート競走法第六十五条第二号に規定する罪
(13) 覚醒剤取締法第四十一条第一項、第四十一条の二第一項若しくは第二項、第四十一条の三第一項第一号、第三号若しくは第四号若しくは第二項(同条第一項第一号、第三号及び第四号に係る部分に限る。)又は第四十一条の四第一項第三号から第五号までに規定する罪
(14) 旅券法第二十三条第一項第一号に規定する罪
(15) 出入国管理及び難民認定法第七十四条第一項、第七十四条の二第二項、第七十四条の四第一項、第七十四条の六の二第二項又は第七十四条の八第二項に規定する罪
(16) 麻薬及び向精神薬取締法第六十四条第一項、第六十四条の二第一項若しくは第二項、第六十四条の三第一項若しくは第二項、第六十五条第一項若しくは第二項、第六十六条第一項、第六十六条の二第一項(第二十七条第一項及び第五項に係る部分に限る。)、第六十六条の三第一項又は第六十六条の四第二項に規定する罪
(17) 武器等製造法第三十一条第一項、第三十一条の二第一項又は第三十一条の三第四号(猟銃の製造に係る部分に限る。)に規定する罪
(18) 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律第五条に規定する罪
(19) 売春防止法第八条第一項(第七条第二項に係る部分に限る。)、第十一条第二項、第十二条又は第十三条に規定する罪
(20) 銃砲刀剣類所持等取締法第三十一条第一項(拳銃等の発射に係るものを除く。)、第二項若しくは第三項、第三十一条の二第一項、第三十一条の三第一項(拳銃等の所持に係るものを除く。)、第二項(拳銃等の所持に係るものを除く。)、第三項若しくは第四項、第三十一条の四第一項若しくは第二項、第三十一条の七第一項、第三十一条の八、第三十一条の九第一項、第三十一条の十一第一項第一号若しくは第二号又は第三十一条の十三に規定する罪
(21) 著作権法第百十九条第二項第三号に規定する罪
(22) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第二十五条第一項第一号、第二号、第八号、第九号、第十三号又は第十四号に規定する罪
(23) 火炎びんの使用等の処罰に関する法律第二条第一項に規定する罪
(24) 貸金業法第四十七条第一号又は第二号に規定する罪
(25) 麻薬特例法第六条第一項又は第七条に規定する罪
(26) 児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律第五条第一項、第六条第一項又は第七条第六項から第八項までに規定する罪
(27) 組織的犯罪処罰法第三条第一項(同項第二号から第十号まで及び第十二号から第十五号までに係る部分に限る。)若しくは第二項(同条第一項第二号から第四号まで、第七号から第十号まで、第十二号、第十四号及び第十五号に係る部分に限る。)、第七条(同条第一項第一号から第三号までに係る部分に限る。)、第七条の二第二項、第九条第一項から第三項まで、第十条第一項又は第十一条に規定する罪
(28) 会社法(平成十七年法律第八十六号)第九百七十条第四項に規定する罪
(29) 性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律(令和五年法律第六十七号)第三条第二項又は第五条第一項若しくは第二項に規定する罪
ヘ 組織的犯罪処罰法第七条、第七条の二又は第九条から第十一条までに規定する罪
四十八 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号)第百四十条第一号、第百四十一条第一号、第百四十二条第一号、第百四十八条第五号、第百四十九条第一号(第十六条第三項第一号に係る部分に限る。)又は第百五十一条第一号、第三号若しくは第六号(第六十七条第一項に係る部分に限る。)に規定する罪
四十九 著作権等管理事業法(平成十二年法律第百三十一号)第二十九条第一号若しくは第二号又は第三十二条第一号に規定する罪
五十 高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成十三年法律第二十六号)第八十条第一号、第二号(第九条第一項及び第十一条第三項に係る部分に限る。)又は第三号(第十四条に係る部分に限る。)に規定する罪
五十一 使用済自動車の再資源化等に関する法律(平成十四年法律第八十七号)第百三十八条第四号若しくは第五号又は第百四十条第二号(第六十三条第一項及び第七十一条第一項に係る部分に限る。)に規定する罪
五十二 インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律(平成十五年法律第八十三号)第三十一条(第十四条第二項に係る部分に限る。)、第三十二条第一号又は第三十四条第一号若しくは第二号に規定する罪
五十三 裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(平成十六年法律第百五十一号)第三十二条第一項(第五条に係る部分に限る。)又は第三項第一号(第八条に係る部分に限る。)若しくは第二号に規定する罪
五十四 信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第九十一条第一号から第三号まで若しくは第七号から第九号まで、第九十三条第一号、第二号、第九号から第十二号まで、第二十二号、第二十三号、第二十七号若しくは第三十二号、第九十四条第五号、第九十六条第二号又は第九十七条第一号、第三号、第六号、第九号(第七十一条第一項に係る部分に限る。)、第十一号若しくは第十四号に規定する罪
五十五 会社法第九百七十条第二項から第四項までに規定する罪
五十六 探偵業の業務の適正化に関する法律(平成十八年法律第六十号)第十七条(第十五条第二項に係る部分に限る。)、第十八条第一号又は第十九条第一号若しくは第二号に規定する罪
五十七 犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成十九年法律第二十二号)第二十八条に規定する罪
五十八 電子記録債権法(平成十九年法律第百二号)第九十五条第一号又は第九十七条第二号に規定する罪
五十九 資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第百七条第二号(第三十七条、第四十一条第一項、第六十二条の三、第六十二条の七第一項及び第六十三条の二に係る部分に限る。)、第六号、第八号、第九号、第十二号、第十四号、第十五号若しくは第十七号から第十九号まで、第百九条第十一号若しくは第十二号、第百十二条第二号(第三十八条第一項(第四十一条第二項において準用する場合を含む。)及び第二項(第四十一条第二項において準用する場合を含む。)、第六十二条の四第一項(第六十二条の七第二項において準用する場合を含む。)及び第二項(第六十二条の七第二項において準用する場合を含む。)並びに第六十三条の三第一項及び第二項に係る部分に限る。)又は第百十四条第一号(第四十一条第三項及び第四項、第六十二条の七第三項及び第四項並びに第六十三条の六第一項及び第二項に係る部分に限る。)若しくは第七号(第六十三条の三十三第二項及び第七十七条に係る部分に限る。)に規定する罪
六十 性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律第二条から第六条までに規定する罪
暴力団員
暴力団員とは、暴力団の構成員を意味します(法2条6号)。組織に所属し、その威力を背景に活動する個人であり、暴対法上の禁止行為や中止命令の直接の対象になります。
「暴力団」が組織単位の概念であるのに対し、「暴力団員」はその所属個人を指すと理解すると整理しやすいです。
▽暴対法2条6号
六 暴力団員 暴力団の構成員をいう。
指定暴力団
指定暴力団とは、暴力団のうち、特に規模や組織性が大きく社会的影響が深刻なものについて、都道府県公安委員会が「指定」(法3条以下)した団体を指します(法2条3号)。
指定を受けると、その団体の構成員(=指定暴力団員)は、暴力的要求行為の禁止規制や中止命令の対象となります。
「暴力団」という広いカテゴリーの中から、実際に規制対象として抽出された団体が「指定暴力団」です。
▽暴対法2条3号
三 指定暴力団 次条の規定により指定された暴力団をいう。
指定要件について
指定の要件は法3条に規定されており、簡単にいうと、
- その暴力団の実質的な目的が、組員に対して資金獲得活動を行うために自己の威力を利用させ、組員がその威力を利用することを容認する点にあること(1号)
- その暴力団の幹部、または全組員のなかに、政令の定める一定比率以上の犯罪経歴保有者(暴力的不法行為または暴対法に定める罪を犯してから所定期間を経過しない者)が存在すること(2号)
- その暴力団が、代表者の統制下に構成員相互の間に序列が定められ、階層的に構成されていること(3号)
となっています。
▽暴対法3条
(指定)
第三条 都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)は、暴力団が次の各号のいずれにも該当すると認めるときは、当該暴力団を、その暴力団員が集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長するおそれが大きい暴力団として指定するものとする。
一~三 (略)
指定を受けることにより、当該暴力団は暴対法の規制対象となります。指定は官報に公示されます(法7条)。
指定暴力団は、警察庁の資料や各地の暴追センターHP等で確認することができます(本記事公開日現在は25団体)。
指定暴力団連合
複数の指定暴力団が結合して形成された団体を指し(法2条4号)、公安委員会が「指定暴力団連合」として指定します(法4条)。
暴力団は相互に対立関係にあることも多い一方、必要に応じて連合体を形成することがあります。そのため、その連合体にも規制を及ぼす仕組みです。
▽暴対法2条4号
四 指定暴力団連合 第四条の規定により指定された暴力団をいう。
▽暴対法4条
第四条 公安委員会は、暴力団(指定暴力団を除く。)が次の各号のいずれにも該当すると認めるときは、当該暴力団を指定暴力団の連合体として指定するものとする。
一・二 (略)
指定暴力団等
実際の条文の中では、「指定暴力団等」という用語が頻繁に出てきます。
これは、指定暴力団+指定暴力団連合という意味ですが(法2条5号)、結果として、「指定に基づき規制された団体」を包括的に指すことになります。
つまり、実際に公安委員会が指定して規制を及ぼす対象をひとまとめに表現する便宜的な用語といえます。
▽暴対法2条5号
五 指定暴力団等 指定暴力団又は指定暴力団連合をいう。
まとめ
ここまでをまとめると、以下のようになります。
暴力団など規制対象の定義(まとめ)
- 暴力団 … 不法行為を目的とした組織
┗ 暴力団員 … その組織に所属する個人
- 指定暴力団 … 暴力団のうち公安委員会が指定したもの
- 指定暴力団連合 … 複数の指定暴力団が結合した団体
- 指定暴力団等 … 指定暴力団+指定暴力団連合を包括する呼称
┗ 指定暴力団員 … 指定暴力団等に所属する個人(※法9条1項参照)
このように、暴対法は、団体(暴力団)、個人(暴力団員)、指定による規制(指定暴力団+指定暴力団連合)を整理し、包括的な「指定暴力団等」という用語で束ねる構造になっています。
02|暴対法による禁止行為
暴対法は、暴力団員による不当要求行為、いわゆる民事介入暴力への規制を中心に、さまざまな規制を設けています。
「民事介入暴力」という言葉に法律上の定義はありませんが、一般的には、暴力団員が一般市民の日常生活や経済活動に介入し、暴力団の威力を背景に行う不当要求行為などをいいます
禁止行為の中心は「暴力的要求行為」で、概ねこれが民事介入暴力と呼ばれるものにあたると考えてよいです。
暴力的要求行為とは
暴力的要求行為とは、平たく言えば、暴力団が持つ威力(組織的な力や社会的威圧感)を背景に、指定暴力団員が行う不当要求行為のことです。必ずしも実際に暴行を加える必要はありません。
定義としては、法9条に違反する行為とされています(法2条7号)。
▽暴対法2条7号
七 暴力的要求行為 第九条の規定に違反する行為をいう。
そして、法9条では、1号から27号まで多様な行為類型が禁止の対象となっています。
▽暴対法9条
(暴力的要求行為の禁止)
第九条 指定暴力団等の暴力団員(以下「指定暴力団員」という。)は、その者の所属する指定暴力団等又はその系列上位指定暴力団等(当該指定暴力団等と上方連結(指定暴力団等が他の指定暴力団等の構成団体となり、又は指定暴力団等の代表者等が他の指定暴力団等の暴力団員となっている関係をいう。)をすることにより順次関連している各指定暴力団等をいう。以下同じ。)の威力を示して次に掲げる行為をしてはならない。
一~二十七 (略)
典型例としては、みかじめ料・寄付金等の不当要求、下請受注や資材納入の強要、事故示談への不当介入、弱みにつけ込んだ口止め料要求などが挙げられます。
【補足】暴力的要求行為「等」
また、一般市民が指定暴力団員によるこれらの暴力的要求行為を利用することも禁じられています(法10条)。
これらをまとめると、暴力的要求行為等としては、
- 指定暴力団員による暴力的要求行為(法9条各号)
- 指定暴力団員に対する暴力的要求行為の要求・依頼・教唆(法10条1項)
- 上記①の援助(法10条2項)
があるといえます。
▽暴対法10条
(暴力的要求行為の要求等の禁止)
第十条 何人も、指定暴力団員に対し、暴力的要求行為をすることを要求し、依頼し、又は唆してはならない。
2 何人も、指定暴力団員が暴力的要求行為をしている現場に立ち会い、当該暴力的要求行為をすることを助けてはならない。
暴力的要求行為の類型(27の行為)
暴力的要求行為の類型を簡単に見ておくと、以下のとおりです。27の類型があります(法9条1号~27号)。
| 号 | 行為類型 | 備考 |
|---|
| ① | 口止め料を要求する行為 | |
| ② | 金品等の贈与を要求する行為 | |
| ③ | 下請参入等を要求する行為 | |
| ④ | 縄張り内の営業者に対してみかじめ料を要求する行為 | みかじめ料:縄張り内で営業を営むことを容認する対償としての金品等 |
| ⑤ | 縄張り内の営業者に対して用心棒代等を要求する行為 | 日常業務用の物品購入、興行の入場券・パーティ券等の購入、用心棒料など |
| ⑥ | 利息制限法違反の債権等を取り立てる行為 | |
| ⑦ | 不当な方法で債権を取り立てる行為 | |
| ⑧ | 債務の免除や支払猶予を要求する行為 | |
| ⑨ | 不当な貸付および手形の割引を要求する行為 | |
| ⑩ | 不当な信用取引を要求する行為 | |
| ⑪ | 不当な株式の買取等を要求する行為 | |
| ⑫ | 預貯金の受入れを要求する行為 | |
| ⑬ | 不当な地上げ行為 | |
| ⑭ | 土地・家屋の明渡し料等を不当に要求する行為 | |
| ⑮ | 宅建業者に対して宅地等の売買等を要求する行為 | 宅建業者以外の者に対する請求、宅建業者に対する賃貸の要求は除外されている |
| ⑯ | 宅地等の売買等を不当に要求する行為 | 上記は「みだりに」を要件として本号で規定 |
| ⑰ | 建設工事を要求する行為 | |
| ⑱ | 施設利用を要求する行為 | |
| ⑲ | 交通事故等の示談に介入し、損害賠償を要求する行為 | |
| ⑳ | 不当なクレーム等により損害賠償等を要求する行為 | |
| ㉑ | (行政庁に対して)許認可をすること等を要求する行為 | 要件該当しないのに許認可等をすることor要件該当するのに不利益処分をしないことを要求 |
| ㉒ | (行政庁に対して)許認可をしないこと等を要求する権利 | 要件該当するのに許認可等をしないことor要件該当しないのに不利益処分をすることを要求 |
| ㉓ | (国等に対して)国等が行う売買等の契約の入札に参加させることを要求する行為 | 入札参加資格を持たずまたは指名基準に適合しないにもかかわらず、入札参加させるよう要求 |
| ㉔ | (国等に対して)国等が行う売買等の契約の入札に参加させないことを要求する行為 | 入札参加資格を持ちまたは指名基準に適合するにもかかわらず、入札参加させないよう要求 |
| ㉕ | (人に対して)入札への不参加等を要求する行為 | |
| ㉖ | (国等に対して)売買等の契約の相手方とすること又はしないことを要求する行為 | |
| ㉗ | (国等に対して)売買等の契約の相手方に対する指導等の要求 | 自己または関係者に下請業務を発注し、物品やサービスを購入するよう指導・助言することを要求 |
以下の警視庁のページでは、イラスト形式の説明でこれらをわかりやすく確認することができます。
参考:「暴力的不法行為等」とは別の概念
なお、暴力団の定義のところで「暴力的不法行為等」という用語が出てきましたが、「暴力的要求行為」はこれとは別の概念です。
目的・対象が異なり、暴力的不法行為等が”法で定める犯罪類型の総称”であるのに対し、暴力的要求行為は”特定の類型に整理された不当要求等の行為群”であり、別条項で個別に定められています。
<要点>
- 暴力的不法行為等 = 法令(別表+規則)で特定された犯罪類型を指す用語
- 暴力的要求行為 = 法9条で列挙された、指定暴力団員が威力を示して行う具体的要求類型(民事介入暴力の類型)
暴対法における禁止行為には他にもさまざまなものがありますが、本記事では割愛します。
03|違反に対する措置等
暴対法はこれら禁止行為の実効性を確保するために、行政上の命令と刑事罰を設けています。
違反があった場合、まずは都道府県公安委員会による命令などの行政措置が取られ、それでも従わない場合には刑事罰が科される仕組みになっています。
行政措置
中止命令
公安委員会は、暴対法による禁止行為が行われた場合に、その行為をやめるように命ずることができます。この命令は、暴力団員等が不当な要求を継続して行うこと等を防ぐための最も基本的な措置です。
禁止行為の諸規定の後ろに続いて規定されていることが多く、暴力的要求行為の禁止を例にとると、法11条1項に定めがあります。
▽暴対法11条1項
(暴力的要求行為等に対する措置)
第十一条 公安委員会は、指定暴力団員が暴力的要求行為をしており、その相手方の生活の平穏又は業務の遂行の平穏が害されていると認める場合には、当該指定暴力団員に対し、当該暴力的要求行為を中止することを命じ、又は当該暴力的要求行為が中止されることを確保するために必要な事項を命ずることができる。
再発防止命令
暴力的要求行為が行われた後、再度同様の行為が行われるおそれがあると認められる場合には、公安委員会は、暴力団員等に対して将来に向けた再発防止措置をとるよう命じることができます。
つまり、禁止行為が完了してしまった場合は、中止命令はできず、再発防止命令の問題となります
例えば、特定の場所や相手方に接近しないことなど、行為の再発を防ぐための具体的措置が命じられます。
これも、暴力的要求行為の禁止を例にとると、法11条2項に定めがあります。
▽暴対法11条2項
2 公安委員会は、指定暴力団員が暴力的要求行為をした場合において、当該指定暴力団員が更に反復して当該暴力的要求行為と類似の暴力的要求行為をするおそれがあると認めるときは、当該指定暴力団員に対し、一年を超えない範囲内で期間を定めて、暴力的要求行為が行われることを防止するために必要な事項を命ずることができる。
その他の命令
その他の命令として、
- 損害賠償等の妨害を防止するための命令(法30条の4)
- 暴力行為の賞揚等を禁止する旨の命令(法30条の5)
- 事務所の使用方法を制限する旨の命令(法15条1項・2項)
等々がありますが、本記事では割愛します。
刑事罰
暴対法は、これらの命令に従わない暴力団員に対して、刑事罰を科すことで実効性を担保しています(法46条~48条ほか)。
ここでも暴力的要求行為の禁止を例に見てみると、中止命令・再発防止命令違反に対しては、拘禁3年以下もしくは罰金500万円以下、またはその併科となっています(法46条1号)。
▽暴対法46条(※【 】は管理人注)
第四十六条 次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の拘禁刑若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 第十一条の規定による命令【=暴力的要求行為の中止命令・再発防止命令】に違反した者
ニ・三 (略)
民事責任-指定暴力団の代表者等の損害賠償責任
また、暴対法では、指定暴力団の構成員が暴力的要求行為などを行い第三者に損害を与えた場合に、その構成員本人だけでなく、暴力団の代表者等も、民法上の使用者責任に準じて損害賠償責任を負う旨が定められています(法31条、31条の2)。
関連記事
-
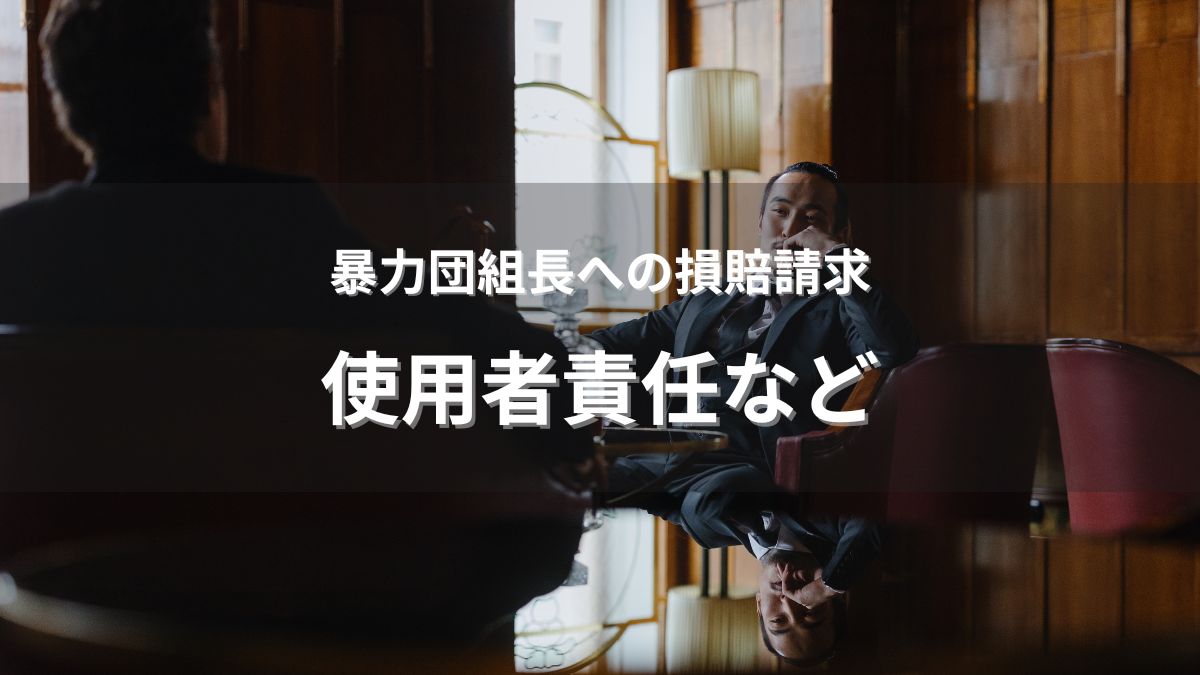
-
暴力団組長に対する損害賠償請求(使用者責任・指定暴力団代表者責任など)
続きを見る
これは、暴力団の組織的な活動実態を踏まえ、単に行為者本人を責任追及しても被害者救済が十分に図れない場合があることから、組織の代表者等にも賠償責任を負わせる仕組みです。
具体的には、
- 指定暴力団の代表者(組長など)
- 代表者に準ずる地位にある幹部
などが対象となり、構成員の違法行為によって発生した被害に対し、被害者は暴力団代表者等に直接損害賠償を請求することが可能です。
この規定は、①被害者の救済をより実効的に確保するとともに、②暴力団の組織的活動の抑止にも資するものと位置づけられています。
▽暴対法31条~31条の3(第5章)
(対立抗争等に係る損害賠償責任)
第三十一条 指定暴力団の代表者等は、当該指定暴力団と他の指定暴力団との間に対立が生じ、これにより当該指定暴力団の指定暴力団員による暴力行為(凶器を使用するものに限る。以下この条において同じ。)が発生した場合において、当該暴力行為により他人の生命、身体又は財産を侵害したときは、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
2 一の指定暴力団に所属する指定暴力団員の集団の相互間に対立が生じ、これにより当該対立に係る集団に所属する指定暴力団員による暴力行為が発生した場合において、当該暴力行為により他人の生命、身体又は財産を侵害したときも、前項と同様とする。
(威力利用資金獲得行為に係る損害賠償責任)
第三十一条の二 指定暴力団の代表者等は、当該指定暴力団の指定暴力団員が威力利用資金獲得行為(当該指定暴力団の威力を利用して生計の維持、財産の形成若しくは事業の遂行のための資金を得、又は当該資金を得るために必要な地位を得る行為をいう。以下この条において同じ。)を行うについて他人の生命、身体又は財産を侵害したときは、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
一~ニ (略)
(民法の適用)
第三十一条の三 指定暴力団の代表者等の損害賠償の責任については、前二条の規定によるほか、民法(明治二十九年法律第八十九号)の規定による。
結び
今回は、暴対法ということで、規制の仕組み(全体像)について見てみました。
[注記]
本記事を含む一連の勉強記事は、過去の自分に向けて、①自分の独学や経験の記録を見せる、②感覚的な理解を伝えることを優先する、③細かく正確な理解は書物に譲る、ということをコンセプトにした読みものです。ベテランの方が見てなるほどと思うようなことは書かれていないほか、業務上必要であるときなど、正確な内容については別途ご確認ください。また、法改正をはじめとした最新の情報を反映しているとは限りませんので、ご注意ください。

犯罪被害/民暴に関するその他の記事(≫Read More)
主要法令等