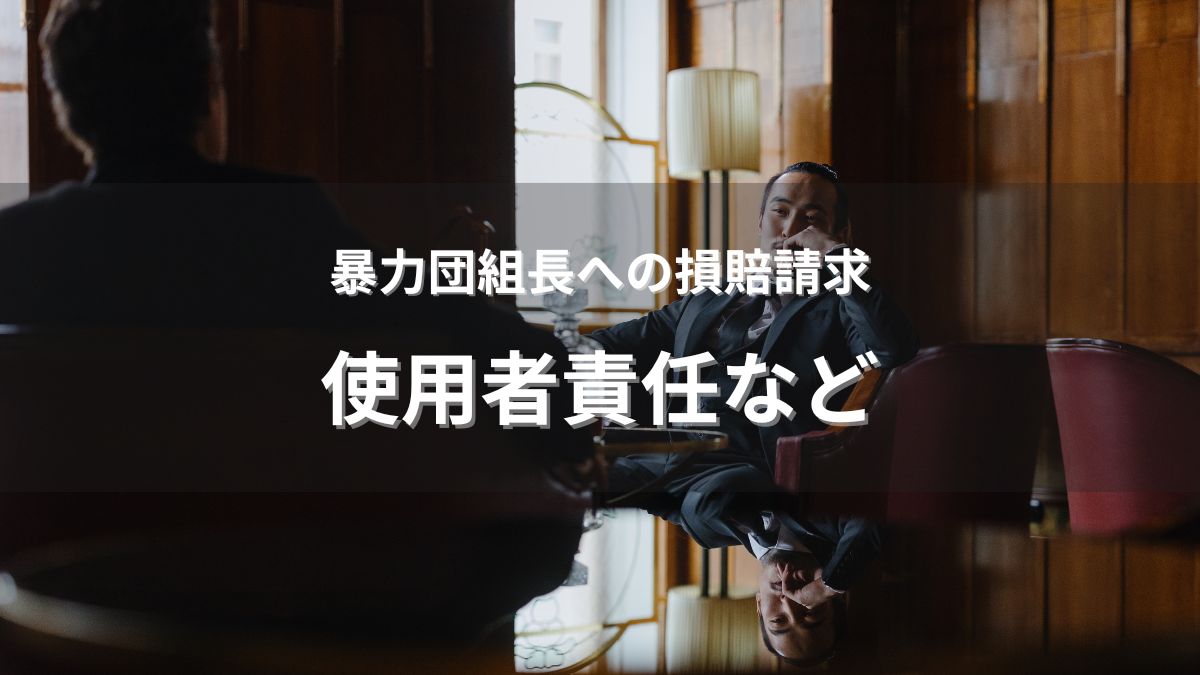今回は、民暴事件ということで、暴力団組長に対する損害賠償請求について見てみたいと思います。
暴力団による事件で被害を受けた場合に、加害者本人だけでなくその背後にいる組長に対して損害賠償を請求できるのかは、被害回復にとって重要です。法制度上は、民法上の使用者責任や共同不法行為責任が考えられるほか、暴力団対策法で代表者等の責任という特別な規定が定められています。
本記事では、それぞれの法的根拠を整理し、両者の違いや使い分けを解説しています。なお、引用部分の太字、下線、改行などは管理人によるものです。
暴力団組長に対する損害賠償請求
暴力団組長に対する損害賠償請求の法的根拠としては、
- 使用者責任(民法715条)
- 共同不法行為責任(民法719条)
- 指定暴力団の代表者等の責任(暴対法31条、31条の2)
の3つが考えられます。
結論からいうと、暴対法上の責任は「指定暴力団」などの要件を満たす場面で、代表者等に責任を問いやすくするよう特別に定められたもので、民法ルートより被害者側に有利なことが多い一方、指定や「威力利用資金獲得行為」等の要件の立証が前提になります。
民法ルートでは適用範囲が広い反面、指揮監督関係や関与の程度など、事実認定のハードルが相対的に高くなりがちです。
以下、順に内容を見てみます。
01|使用者責任
使用者責任とは、他人を使用して事業を営む者が、その被用者の不法行為について負う賠償責任です。その「事業の執行について」なされた行為である必要があります。
使用者責任の成立要件は、
- 使用関係があること(使用関係)
- 被用者に不法行為責任があること(被用者の不法行為)
- 被用者の不法行為が事業の執行につきなされたこと(事業執行性)
- 使用者に免責事由がないこと(免責事由の不存在)
★免責事由=選任・監督上の無過失(相当注意)または因果関係の不存在
となっています。立証責任が転換された過失責任である(④参照)という点につき、”中間責任”と呼ばれることもあります。
暴力団事案では、
- 加害行為を行った暴力団組員と組長との間に指揮監督関係があるといえるか(使用関係)
- 当該行為が組の資金獲得活動(いわゆるシノギ)等という事業の執行にあたるか(事業執行性)
が中心論点となります。
▽民法715条(※【 】は管理人注)
(使用者等の責任)
第七百十五条 ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、使用者が被用者の選任及びその事業の監督について相当の注意をしたとき、又は相当の注意をしても損害が生ずべきであったときは、この限りでない。
2 使用者に代わって事業を監督する者【=代理監督者】も、前項の責任を負う。
3 前二項の規定は、使用者又は監督者から被用者に対する求償権の行使を妨げない。
なお、代理監督者の責任(2項)も、組長ではなく組織幹部に責任を問う場合の法的構成として使われる場合があります(組長が収監されているケースなど)。代理監督者といえるためには、現実に被用者の具体的な選任・監督にあたっていることが必要とされます。
02|共同不法行為責任
共同不法行為は、複数人が共同して他人に損害を生じさせたとき(1項)、または誰が直接の加害者か特定できないが共同関係があるときに(2項)、各人が連帯して損害賠償責任を負う仕組みです。
条文上、教唆・幇助者も共同不法行為者と同視して責任を負うことが明示されています。
暴力団事案では、組長が犯行計画を指示・黙認した、資金分配・役割分担の仕組みを作ったといったような、共謀して不法行為を行ったと評価できる場合、つまり指揮・関与の具体性に着目して共同不法行為責任を追及することが考えられます。
使用者責任のように事業執行性の要件を要しない反面、共謀・教唆・幇助など関与の事実の立証が要点になります。
▽民法719条
(共同不法行為者の責任)
第七百十九条 数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えたときは、各自が連帯してその損害を賠償する責任を負う。共同行為者のうちいずれの者がその損害を加えたかを知ることができないときも、同様とする。
2 行為者を教唆した者及び幇助した者は、共同行為者とみなして、前項の規定を適用する。
03|指定暴力団の代表者等の責任
暴対法は、指定暴力団の代表者等に対し、民法一般の不法行為よりも強い帰責構造を用意しています。
この暴対法上の損害賠償責任については、①被害者救済と、②暴力団活動の抑止という2点が制度趣旨として位置づけられています。
以下の2つの条文(暴対法31条・31条の2)が柱となっています。
対立抗争等に係る損害賠償責任(暴対法31条)
指定暴力団相互の対立抗争で、組員らが凶器を用いた暴力行為等により人の生命・身体・財産に害を生じさせた場合、その指定暴力団の代表者等が損害賠償責任を負うとする規定です(1項。2項では指定暴力団内部の対立抗争の場合も)。
対立抗争という状況と結果(生命・身体・財産への害)の発生を踏まえて、代表者等に責任を広く認める趣旨で、民法のような事業執行性や具体的な指示関係の証明を必要としません。
▽暴対法31条
(対立抗争等に係る損害賠償責任)
第三十一条 指定暴力団の代表者等は、当該指定暴力団と他の指定暴力団との間に対立が生じ、これにより当該指定暴力団の指定暴力団員による暴力行為(凶器を使用するものに限る。以下この条において同じ。)が発生した場合において、当該暴力行為により他人の生命、身体又は財産を侵害したときは、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
2 一の指定暴力団に所属する指定暴力団員の集団の相互間に対立が生じ、これにより当該対立に係る集団に所属する指定暴力団員による暴力行為が発生した場合において、当該暴力行為により他人の生命、身体又は財産を侵害したときも、前項と同様とする。
威力利用資金獲得行為に係る損害賠償責任(暴対法31条の2)
指定暴力団員が団体の威力を利用して資金を得るために、他人の生命・身体・財産を侵害した場合(典型例はみかじめ料、違法な取立てなど)、指定暴力団の代表者等が損害賠償責任を負います。
条文上は限定的な免責事由(例:組や代表者等に利益帰属がない場合、外部者の関与による特殊事情等)が掲げられているものの、基本的には過失の有無に左右されにくい内容になっているといえます。
▽暴対法31条の2
(威力利用資金獲得行為に係る損害賠償責任)
第三十一条の二 指定暴力団の代表者等は、当該指定暴力団の指定暴力団員が威力利用資金獲得行為(当該指定暴力団の威力を利用して生計の維持、財産の形成若しくは事業の遂行のための資金を得、又は当該資金を得るために必要な地位を得る行為をいう。以下この条において同じ。)を行うについて他人の生命、身体又は財産を侵害したときは、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
一 当該代表者等が当該代表者等以外の当該指定暴力団の指定暴力団員が行う威力利用資金獲得行為により直接又は間接にその生計の維持、財産の形成若しくは事業の遂行のための資金を得、又は当該資金を得るために必要な地位を得ることがないとき。
二 当該威力利用資金獲得行為が、当該指定暴力団の指定暴力団員以外の者が専ら自己の利益を図る目的で当該指定暴力団員に対し強要したことによって行われたものであり、かつ、当該威力利用資金獲得行為が行われたことにつき当該代表者等に過失がないとき。
暴対法と民法の違い
法制度上は、暴対法に基づく責任と民法に基づく責任は併存しており、この点は暴対法31条の3で明示されています。
▽暴対法31条の3
(民法の適用)
第三十一条の三 指定暴力団の代表者等の損害賠償の責任については、前二条の規定によるほか、民法(明治二十九年法律第八十九号)の規定による。
他方、実際上の違いについていうと、暴対法は「指定暴力団」を対象に、代表者等に責任を課す特別の定めであり、民法ルートよりも被害者救済に有効な場合が多いといえます。一方で、暴対法が適用できない場合や、適用要件が争われる場合には、民法715条・719条の主張を検討することになります。
暴対法は特別の定めとして被害回復の実効性を高める設計となっていますが、適用要件を外した局面でも民法ルートがあるという、この二段構えが、組長責任追及の基本イメージといえます。
もう少し具体的に使い分けの視点を見てみると、例えば以下のようになります。
対象の限定 vs 広汎な適用
暴対法は「指定暴力団」の構成員が関与する一定類型(対立抗争/威力利用資金獲得行為の場面)に絞って、代表者等の責任を強化しています。
指定暴力団の指定がない団体や上記の場面以外の状況には直接は使えません。その場合は民法715条・719条での追及が基本線です。
立証の重点(行為類型 vs 組織関係)
暴対法では、「対立抗争」か「威力利用資金獲得行為」かという行為類型と結果の立証が主眼で、代表者等の個別過失や具体的指示の立証まで通常は求めません。
これに対し民法715条は、使用関係と事業執行性の外形(組織の資金獲得活動としての密接関連性)を、719条は共謀・教唆・幇助等の具体的関与を、いずれも事実に即して積み上げる必要があります。
結び
今回は、民暴事件ということで、暴力団組長に対する損害賠償請求について見てみました。
[注記]
本記事を含む一連の勉強記事は、過去の自分に向けて、①自分の独学や経験の記録を見せる、②感覚的な理解を伝えることを優先する、③細かく正確な理解は書物に譲る、ということをコンセプトにした読みものです。ベテランの方が見てなるほどと思うようなことは書かれていないほか、業務上必要であるときなど、正確な内容については別途ご確認ください。また、法改正をはじめとした最新の情報を反映しているとは限りませんので、ご注意ください。
主要法令等