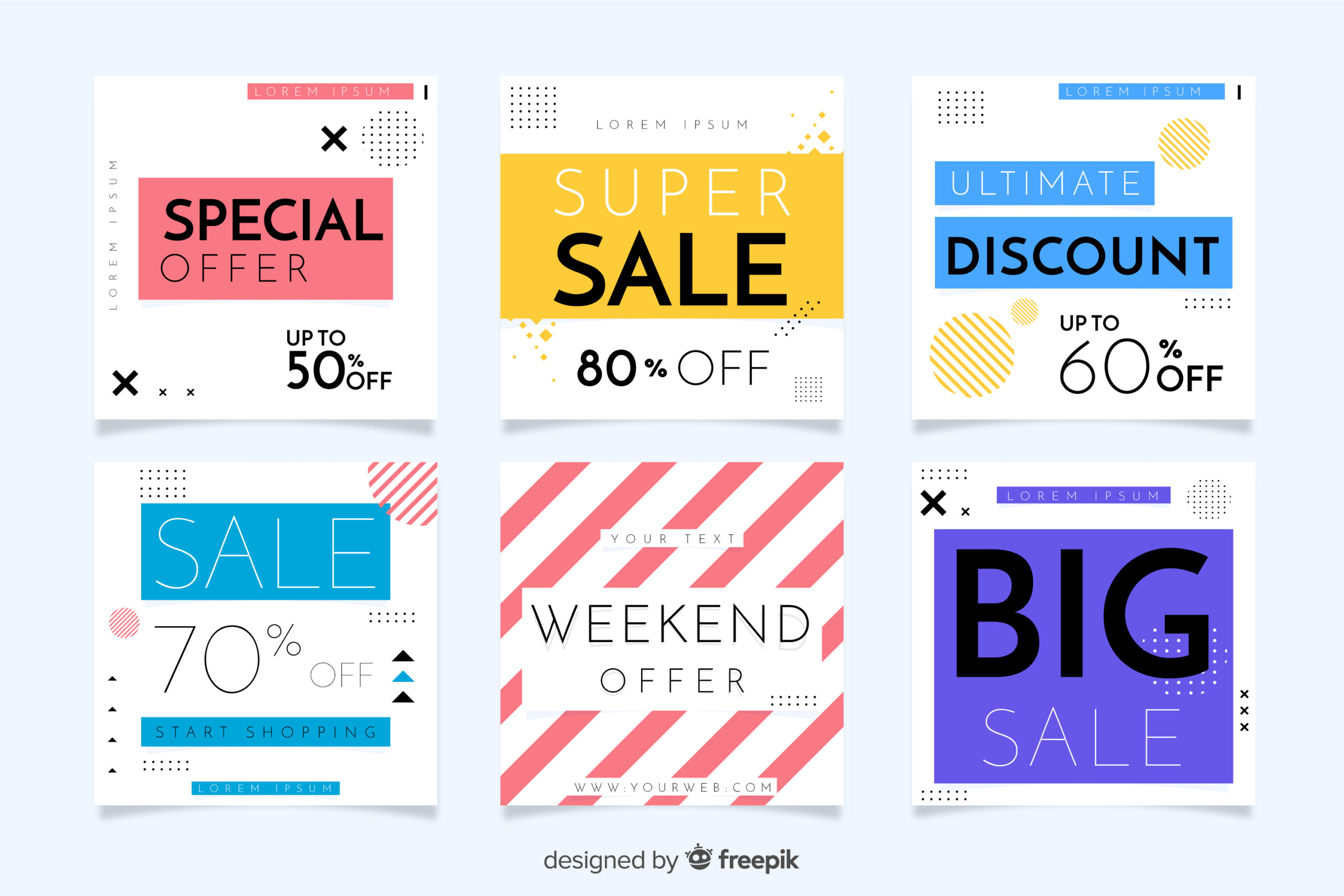今回は、景品表示法を勉強しようということで、違反に対する措置等について見てみたいと思います。
ではさっそく。なお、引用部分の太字、下線、改行などは管理人によるものです。
メモ
このカテゴリーでは、インハウスとしての法務経験からピックアップした、管理人の独学や経験の記録を綴っています。
ネット上の読み物としてざっくばらんに書いており、感覚的な理解を掴むことを目指していますが、書籍などを理解する際の一助になれば幸いです。
違反に対する措置等(全体像)
景品表示法に違反したときに、事業者にはどのような措置がとられる可能性があるのか?というのが気になるところですが、その全体像は以下のとおりです。
措置命令と課徴金納付命令はニュースなどでも比較的よく見かけるかと思いますが、それ以外もあります(事実行為も含む)。
違反に対する措置
| 分類 | 違反に対する措置 | 内容 |
|---|---|---|
| 行政上の措置 | 措置命令 | 違反行為の差止めや再発防止などを命じる行政処分 |
| 課徴金納付命令 | 違反行為によって得た利益に相当する金額を国に納付させる行政処分 | |
| 確約手続 | 事業者が作成した是正計画を認定する行政処分 | |
| 行政指導 | (措置命令までいかなくても)一定の是正措置をとるよう指導する事実行為 | |
| 公表 | 措置命令や課徴金納付命令、行政指導を行ったことを公表する事実行為 | |
| 刑事罰 | 違反者個人/違反企業/違反企業代表者 | 措置命令にも違反した場合などには刑事罰の定めがある(直罰規定もある) |
| 民事責任 | 適格消費者団体による差止請求 | 優良誤認/有利誤認表示に対する、①停止、②予防、③これらに必要な措置の請求(民事上の請求権) |
| 業界団体による自主規制 | 公正取引協議会等による措置 | 公正競争規約(景品規約と表示規約からなる)に違反した加入事業者に対して、業界団体である公正取引協議会等が行う処分 |
もちろん、あらゆる違反行為について上記のメニュー全てが適用されるということではなく、あくまでもこういうラインナップがあるという意味です。
消費者庁HPにも、行政上の措置に関する解説ページがあります。
以下、順に見てみます。
行政上の措置
措置命令
措置命令というのはひと言でいうと、「こういう措置をとりなさい」という命令のことです(法7条1項)。
そして、どういう措置をとりなさいと言われるのかというと、
- 違反行為の差止め:
”違反行為をやめなさい”という命令 - 再発防止に必要な事項:
”再発防止策を策定し実施しなさい”とか、”暫くの間は事前に広告を提出しなさい”といった命令 - これらの実施に関する公示:
不当表示により一般消費者に与えた誤認の排除(そのための新聞広告等による公示) - その他必要な事項
といったものがあります。
条文も確認してみます。
▽法7条1項(※【 】は管理人注)
第七条 内閣総理大臣は、第四条の規定による制限若しくは禁止【=景品規制】又は第五条の規定【=表示規制(不当表示の禁止)】に違反する行為があるときは、当該事業者に対し、その行為の差止め若しくはその行為が再び行われることを防止するために必要な事項又はこれらの実施に関連する公示その他必要な事項を命ずることができる。…(略)…
都道府県への権限委任(平成26年6月法改正)
なお、地域的にきめ細かく迅速な規制ができるよう、調査や措置命令は都道府県知事にも権限があり、実際に運用されています。
平成26年6月法改正で導入されました。
条文としては、法38条11項・施行令23条1項により、権限が付与されています。
▽法38条1項・11項
(権限の委任等)
第三十八条 内閣総理大臣は、この法律による権限(政令で定めるものを除く。)を消費者庁長官に委任する。
11 第一項の規定により消費者庁長官に委任された権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。
▽施行令23条1項(※【 】は管理人注、「…」は適宜省略)
(都道府県が処理する事務)
第二十三条 法第三十八条第一項の規定により消費者庁長官に委任された権限に属する事務のうち、法第七条第一項【=措置命令】及び第二項【=不実証広告規制における合理的根拠提出要求】並びに第二十五条第一項【=調査】の規定による権限に属する事務(同項の規定による権限に属する事務にあっては、法第七条第一項の規定による命令を行うため必要があると認める場合におけるものに限る。)は、不当な景品類の提供又は表示がされた場所又は地域を含む都道府県の区域を管轄する都道府県知事が行うこととする。ただし、二以上の都道府県の区域にわたり一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあり、消費者庁長官…(略)…がその事態に適正かつ効率的に対処するため特に必要があると認めるとき、又は都道府県知事から要請があったときは、消費者庁長官が自らその事務を行うことを妨げない。
上記に定められているように、消費者庁と都道府県との役割分担としては、調査の対象が複数の都道府県にわたるときや都道府県から要請があったとき等は消費者庁、主に1都道府県内だけの場合にはその都道府県、というのが基本となっています(ただ、複数の都道府県にわたるときでも、複数の都道府県が合同で行うこともある)。
例えば、東京都による措置命令の例としては以下のようなものがあります。
課徴金納付命令
課徴金納付命令は、要するに違反に対する金銭的ペナルティであり、平成26年11月法改正(平成28年4月1日施行)から導入されました(法8条)。
違反事業者に経済的不利益を課すものですが、消費者の被害回復の促進という観点も趣旨に含んでいます。
課徴金納付命令は、景品規制の違反に対しては適用されません。表示規制の違反に対してのみであり、かつ、優良誤認表示と有利誤認表示に対してのみとなっています(その他の不当表示は対象外)。
| 違反行為 | 課徴金対象行為 | |
| 景品規制(法4条。景品類の制限及び禁止) | × | |
| 表示規制(法5条。不当表示の禁止) | ①優良誤認表示(1号) | 〇 |
| ②有利誤認表示(2号) | 〇 | |
| ③その他の不当表示(3号) | × | |
その他の不当表示が対象外であることについては、以下の条文の括弧書きの中に書かれています(「同条第三号に該当する表示に係るものを除く。」との部分)。
ペナルティについては、かいつまんでいうと、課徴金対象行為にかかる商品・役務の「売上額×3%」が賦課金額となります。
▽法8条1項
(課徴金納付命令)
第八条 事業者が、第五条の規定【=表示規制(不当表示の禁止)】に違反する行為(同条第三号に該当する表示に係るものを除く。以下「課徴金対象行為」という。)をしたときは、内閣総理大臣は、当該事業者に対し、当該課徴金対象行為に係る課徴金対象期間に取引をした当該課徴金対象行為に係る商品又は役務の政令で定める方法により算定した売上額に百分の三を乗じて得た額に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命じなければならない。ただし、当該事業者が当該課徴金対象行為をした期間を通じて当該課徴金対象行為に係る表示が次の各号のいずれかに該当することを知らず、かつ、知らないことにつき相当の注意を怠つた者でないと認められるとき、又はその額が百五十万円未満であるときは、その納付を命ずることができない。
一 商品又は役務の品質、規格その他の内容について、実際のものよりも著しく優良であること又は事実に相違して当該事業者と同種若しくは類似の商品若しくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも著しく優良であることを示す表示
二 商品又は役務の価格その他の取引条件について、実際のものよりも取引の相手方に著しく有利であること又は事実に相違して当該事業者と同種若しくは類似の商品若しくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも取引の相手方に著しく有利であることを示す表示
「命じなければならない」とされているように、優良誤認表示/有利誤認表示の違反行為がある限りは課徴金の賦課が義務づけられており、命令を出すかどうかについて裁量の余地はありません。ただし、違反事業者が相当の注意を怠った者ではないときや課徴金の算定額が150万円未満となるときは、課徴金の納付は命じられないとされています(ただし書参照)。
当該改正については、詳しい解説が消費者庁HPに掲載されています。
減額制度
また、課徴金には以下のような減額制度があります。
自主報告による課徴金額の減額(法9条)
まず、違反行為を自主的に報告したときに課徴金額の2分の1を減額する、という規定があります(法9条)。
ただ、調査を受けて、課徴金納付命令があるべきことを予知して報告したときは減額されないことになっています(ただし書)。自主的に申告したとは言い難いからです。
▽法9条
(課徴金対象行為に該当する事実の報告による課徴金の額の減額)
第九条 前条第一項(同条第五項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この節において同じ。)の場合において、内閣総理大臣は、当該事業者が課徴金対象行為に該当する事実を内閣府令で定めるところにより内閣総理大臣に報告したときは、同条第一項の規定により計算した課徴金の額に百分の五十を乗じて得た額を当該課徴金の額から減額するものとする。ただし、その報告が、当該課徴金対象行為についての調査があつたことにより当該課徴金対象行為について課徴金納付命令があるべきことを予知してされたものであるときは、この限りでない。
なお、令和5年規則改正によって自主報告の提出方法が変更され、ファクシミリによる提出は認められなくなっています。
自主返金の実施による課徴金額の減額等(法10条)
また、消費者への返金措置を実施したときに課徴金額から返金相当額を減額する、という規定もあります(法10条)。
返金措置に関する計画(「実施予定返金措置計画」)を作成し、認定を受ける必要があります。
▽法10条1項・10項(※「…」は管理人が適宜省略)
(返金措置の実施による課徴金の額の減額等)
第十条 第十五条第一項の規定による通知を受けた者は、第八条第二項に規定する課徴金対象期間において当該商品又は役務の取引を行つた一般消費者であつて政令で定めるところにより特定されているものからの申出があつた場合に、当該申出をした一般消費者の取引に係る商品又は役務の政令で定める方法により算定した購入額に百分の三を乗じて得た額以上の金銭…を交付する措置…を実施しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、その実施しようとする返金措置(以下この条において「実施予定返金措置」という。)に関する計画(以下この条において「実施予定返金措置計画」という。)を作成し、これを第十五条第一項に規定する弁明書の提出期限までに内閣総理大臣に提出して、その認定を受けることができる。
10 内閣総理大臣は、第一項の認定をしたときは、第八条第一項の規定にかかわらず、次条第一項に規定する報告の期限までの間は、認定事業者に対し、課徴金の納付を命ずることができない。ただし、第八項の規定により認定を取り消した場合には、この限りでない。
返金合計額が課徴金額以上となった場合は課徴金の納付を命じないほか(「当該額は、零とする」。法11条2項後段)、減額の結果、課徴金額が1万円未満となる場合も、課徴金の納付は命じられません(法11条3項)。
▽法11条2項・3項
2 内閣総理大臣は、第八条第一項の場合において、前項の規定による報告に基づき、前条第一項の認定後に実施された返金措置が認定実施予定返金措置計画に適合して実施されたと認めるときは、当該返金措置(当該認定実施予定返金措置計画に同条第三項に規定する事項が記載されている場合又は同条第四項の規定による報告がされている場合にあつては、当該記載又は報告に係る返金措置を含む。)において交付された金銭の額として内閣府令で定めるところにより計算した額を第八条第一項若しくは第四項又は第九条の規定により計算した課徴金の額から減額するものとする。この場合において、当該内閣府令で定めるところにより計算した額を当該課徴金の額から減額した額が零を下回るときは、当該額は、零とする。
3 内閣総理大臣は、前項の規定により計算した課徴金の額が一万円未満となつたときは、第八条第一項の規定にかかわらず、認定事業者に対し、課徴金の納付を命じないものとする。この場合において、内閣総理大臣は、速やかに、当該認定事業者に対し、文書をもつてその旨を通知するものとする。
返金措置については、認定されたものの一覧が消費者庁のHPに掲載されています。
認定された返金措置一覧|消費者庁HP
確約手続
確約手続は、景表法違反の疑いについて、内閣総理大臣(消費者庁長官)と事業者との間の合意により自主的に解決するための手続です。令和5年法改正により導入されました(景表法第2章第6節)。
内閣総理大臣(消費者庁長官)からの通知を受けた事業者は、違反の疑いの理由となった行為とその影響を是正するために必要な措置等を記載した確約計画を作成し、内閣総理大臣(消費者庁長官)に提出して、その認定を申請することができます。
計画が認定されると、措置命令や課徴金納付命令が行われないこととなります。
▽法27条1項・3項
(是正措置計画に係る認定の申請等)
第二十七条 前条の規定による通知を受けた者は、疑いの理由となつた行為及びその影響を是正するために必要な措置を自ら策定し、実施しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、その実施しようとする措置(以下この条及び第二十九条第一項第一号において「是正措置」という。)に関する計画(以下この条及び同号において「是正措置計画」という。)を作成し、これを当該通知を受けた日から六十日以内に内閣総理大臣に提出して、その認定を申請することができる。
3 内閣総理大臣は、第一項の規定による認定の申請があつた場合において、その是正措置計画が次の各号のいずれにも適合すると認めるときは、その認定をするものとする。
一 是正措置が疑いの理由となつた行為及びその影響を是正するために十分なものであること。
二 是正措置が確実に実施されると見込まれるものであること。
▽法28条(※【 】は管理人注)
(是正措置計画に係る認定の効果)
第二十八条 第七条第一項【=措置命令】及び第八条第一項【=課徴金納付命令】の規定は、内閣総理大臣が前条第三項の認定(同条第八項の変更の認定を含む。次条において同じ。)をした場合における当該認定に係る疑いの理由となつた行為については、適用しない。ただし、次条第一項の規定による当該認定の取消しがあつた場合は、この限りでない。
なお、確約計画は、対象行為終了前の場合は「是正措置計画」、対象行為終了後の場合は「影響是正措置計画」と呼ばれており、前者は法26条~29条、後者は法30条~33条に規定されています
確約手続に関する主な法令等は、以下のようになっています。
当該改正については、消費者庁HPに以下の解説資料があります(※掲載ページでは動画での説明もされています)。
法令関係の参考リンクとしては、以下のようなものがあります。
▽BUSINESS LAWYERSのXアカウント
10/1に令和5年改正景表法が施行されました。実務対応の詳細は、以下の解説記事をご参照ください。
— BUSINESS LAWYERS 編集部 (@bl_desk) October 1, 2024
【記事改訂】令和5年景表法改正法の概説と実務への影響 https://t.co/sFKhttY6a9
【記事改訂】2024年10月1日施行!景表法に導入された確約手続の概要 https://t.co/WwyTIt6miL
行政指導
これは、(措置命令までいかなくても)一定の是正措置をとるよう指導する事実行為のことです。
消費者庁や都道府県等は、景表法違反のおそれのある行為がみられた場合には、事業者に対して是正措置をとるよう指導を行うなどしています。
都道府県等によるものとして、例えば以下のようなページがあります。
公表
法的措置である措置命令や課徴金納付命令については、公表されます。
確約手続も、「景品表示法の規定に違反することを認定したものではないことを付記する」とはされるものの、認定自体は公表されます。
▽確約手続運用基準 9
9 確約計画の認定に関する公表
確約計画の認定をした後、消費者庁は、確約手続に係る法運用の透明性及び事業者の予見可能性を確保する観点から、認定確約計画の概要、当該認定に係る違反被疑行為の概要、確約認定を受けた事業者名その他必要な事項を公表する。また、公表に当たっては、景品表示法の規定に違反することを認定したものではないことを付記する。
なお、消費者庁が確約認定申請を却下した場合若しくは認定確約計画の認定を取り消した場合又は申請者が確約認定申請を取り下げた場合については、その後、確約手続通知を行う前の調査を再開することとなるため、原則として、いずれも公表しない。
行政指導を行う場合は、事案の内容は公表されることがありますが、指導を受けた事業者名や具体的な商品名等は公表されていません。
刑事罰
行為者に対する刑罰
措置命令が出されたにもかかわらずこれに違反した場合は、刑事罰(2年以下の懲役or300万円以下の罰金またはこれらの併科)があります(法46条)。
▽法46条
第四十六条 措置命令に違反したときは、当該違反行為をした者は、二年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
2 前項の罪を犯した者には、情状により、懲役及び罰金を併科することができる。
法的な調査権限に基づく調査(法25条1項)、つまり、報告命令/提出命令/立入検査/質問調査に従わなかった場合にも、刑事罰(1年以下の懲役or300万円以下の罰金)があります(法47条)。
つまり、これらの調査は罰則によって間接的に履行を担保するものになっている(間接強制権限)ということです。
▽法47条
第四十七条 第二十五条第一項の規定による報告若しくは物件の提出をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の物件の提出をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、当該違反行為をした者は、一年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
また、令和5年法改正により、優良誤認表示・有利誤認表示に対し、直罰(100万円以下の罰金)の規定が設けられています(法48条)。
直罰というのは、先ほど見たような
「違反」→「措置命令」→(措置命令にも違反したら)「刑罰」
という流れのように、違反と刑罰の間に入っている措置命令のような”クッション”がないということです。つまり、違反があったら即、刑罰を科すことができるということです。
▽法48条(※【 】は管理人注)
第四十八条 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、百万円以下の罰金に処する。
【1号:優良誤認表示】
一 自己の供給する商品又は役務の取引における当該商品又は役務の品質、規格その他の内容について、実際のもの又は当該事業者と同種若しくは類似の商品若しくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも著しく優良であると一般消費者を誤認させるような表示をしたとき。
【2号:有利誤認表示】
二 自己の供給する商品又は役務の取引における当該商品又は役務の価格その他の取引条件について、実際のもの又は当該事業者と同種若しくは類似の商品若しくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも取引の相手方に著しく有利であると一般消費者を誤認させるような表示をしたとき。
両罰規定・三罰規定
刑事罰は、行為者つまり自然人に対して科されるのが原則であり(刑事法の基本的な考え方)、上記で見た罰則は、いずれも行為者(たとえば役員、従業員等の個人)について定められたものになります。
ですが、結局、法人などの事業活動に関して景表法違反の行為が行われるわけですので、法人が刑事責任を負わなくて済むというのは社会的に許容されるものではないですし、法的にいっても法益侵害に関与しているといえます。
そのため、事業者である法人に対しても刑事罰を科す仕組みになっており(事業者たる個人も同様)、これを両罰規定といいます。なお、法人は肉体がないので、必然的に自由刑はありません(罰金刑のみ)。
つまり、違反した行為者だけでなく、法人または事業者たる個人にも刑罰があります(法49条)。
内容としては、
- 措置命令違反については3億円以下の罰金
- 調査拒否・妨害等については300万円以下の罰金
- 優良誤認・有利誤認表示への直罰については100万円以下の罰金
となっています。
▽法49条(※【 】は管理人注)
第四十九条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、当該各号に定める罰金刑を科する。
一 第四十六条第一項【=措置命令違反】 三億円以下の罰金刑
二 前二条【=調査拒否・妨害等/直罰】 各本条の罰金刑
さらに、措置命令違反については、事業者たる法人の代表者についても一定の要件を満たせば刑事罰(300万円以下の罰金)が科されるようになっており、これを三罰規定といいます(法50条。法51条については割愛)。
▽法50条(※【 】は管理人注)
第五十条 第四十六条第一項の違反【=措置命令違反】があつた場合においては、その違反の計画を知り、その防止に必要な措置を講ぜず、又はその違反行為を知り、その是正に必要な措置を講じなかつた当該法人(当該法人で事業者団体に該当するものを除く。)の代表者に対しても、同項の罰金刑を科する。
適格消費者団体による差止請求
平成20年の消費者契約法等の改正(平成21年4月1日施行)から、消費者契約法に基づく適格消費者団体による差止請求も認められています(法34条)。
適格消費者団体とは、消費者庁長官の認定を受けた法人で、不特定かつ多数の消費者の利益を擁護するために、景品表示法や特定商取引法などの法律に基づいて、不当な表示や広告などを行っている事業者に対して、差止請求権を行使することができる団体です。
対象となる行為は、課徴金納付命令と同じく、表示規制のうちの優良誤認表示と有利誤認表示の違反行為のみとなっています。
行政機関によるエンフォースメントとはまた別のところから、不当表示の排除・防止を強化しようとするものであり(不特定かつ多数の一般消費者に被害をもたらす表示)、行政処分とはまた別の、民事ルールとしての差止請求権です。
具体的には、①停止、②予防、③これらに必要な措置を請求することができます。
▽景表法34条1項(※【 】は管理人注)
(差止請求権等)
第三十四条 消費者契約法(平成十二年法律第六十一号)第二条第四項に規定する適格消費者団体(以下「適格消費者団体」という。)は、事業者が、不特定かつ多数の一般消費者に対して次の各号に掲げる行為を現に行い又は行うおそれがあるときは、当該事業者に対し、当該行為の停止若しくは予防又は当該行為が当該各号に規定する表示をしたものである旨の周知その他の当該行為の停止若しくは予防に必要な措置をとることを請求することができる。
【1号:優良誤認表示】
一 商品又は役務の品質、規格その他の内容について、実際のもの又は当該事業者と同種若しくは類似の商品若しくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも著しく優良であると誤認される表示をすること。
【2号:有利誤認表示】
二 商品又は役務の価格その他の取引条件について、実際のもの又は当該事業者と同種若しくは類似の商品若しくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも取引の相手方に著しく有利であると誤認される表示をすること。
適格消費者団体による差止請求については、以下のリンクなどから詳しく見ることができます。
公正取引協議会等による措置
公正競争規約への違反がある場合、規約の運用機関である公正取引協議会は、調査を行い、違反のあった加入事業者に対して必要な措置(警告、違約金、除名処分etc)をとります。
公正取引協議会には、以下のような団体があります。
公正競争規約は、事業者団体が策定して、消費者庁長官と公正取引委員会の認定によって成立する業界の自主ルールのことです(要するに、景品規制と表示規制に関する、業界別の自主規制)。
▽法36条1項
(協定又は規約)
第三十六条 事業者又は事業者団体は、内閣府令で定めるところにより、景品類又は表示に関する事項について、内閣総理大臣及び公正取引委員会の認定を受けて、不当な顧客の誘引を防止し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択及び事業者間の公正な競争を確保するための協定又は規約を締結し、又は設定することができる。これを変更しようとするときも、同様とする。
公正競争規約の内容は、それぞれの公正取引協議会HPで見ることができるほか、全国公正取引協議会連合会HPで一覧を見ることができます。
結び
今回は、景品表示法を勉強しようということで、違反に対する措置等について見てみました。
次の記事では、行政上の措置の手続面について書いています。
-
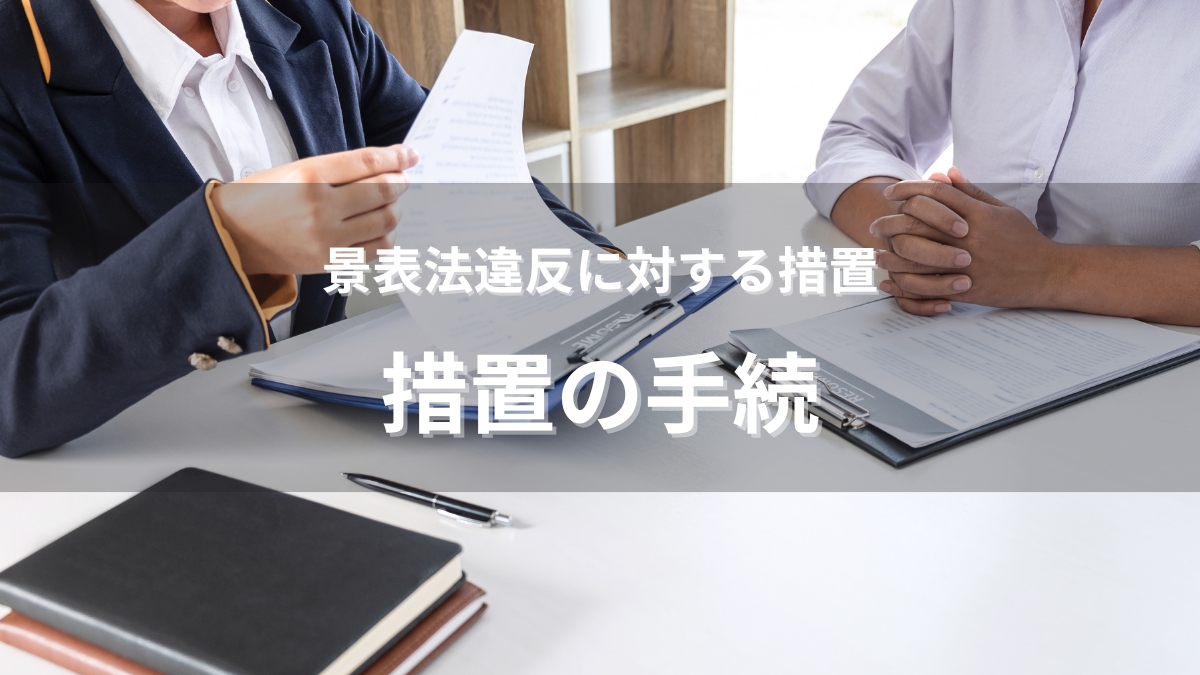
-
景品表示法を勉強しよう|違反に対する措置の手続
続きを見る
[注記]
本記事を含む一連の勉強記事は、過去の自分に向けて、①自分の独学や経験の記録を見せる、②感覚的な理解を伝えることを優先する、③細かく正確な理解は書物に譲る、ということをコンセプトにした読みものです。ベテランの方が見てなるほどと思うようなことは書かれていないほか、業務上必要であるときなど、正確な内容については別途ご確認ください。また、法改正をはじめとした最新の情報を反映しているとは限りませんので、ご注意ください。
景品表示法に関するその他の記事(≫Read More)
主要法令等・参考文献
主要法令等
参考文献
- エッセンス景品表示法(古川昌平)
- 景品表示法〔第6版〕(西川康一)
- 実務解説 景品表示法〔第2版〕(波光巌、鈴木恭蔵)
- 景品表示法の法律相談〔改定版〕(加藤公司、伊藤憲二、内田清人、石井崇、薮内俊輔)
- よくわかる景品表示法と公正競争規約〔令和6年12月改訂〕(消費者庁)|消費者庁HP(≫掲載ページ)
- 事例でわかる景品表示法〔令和6年12月改訂〕(消費者庁)|消費者庁HP(≫掲載ページ)
- 違反事例集(「景品表示法における違反事例集」)|消費者庁HP(≫掲載ページ)
当サイトではアフィリエイトプログラムを利用して商品・サービスを記載しています